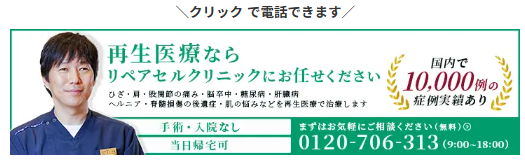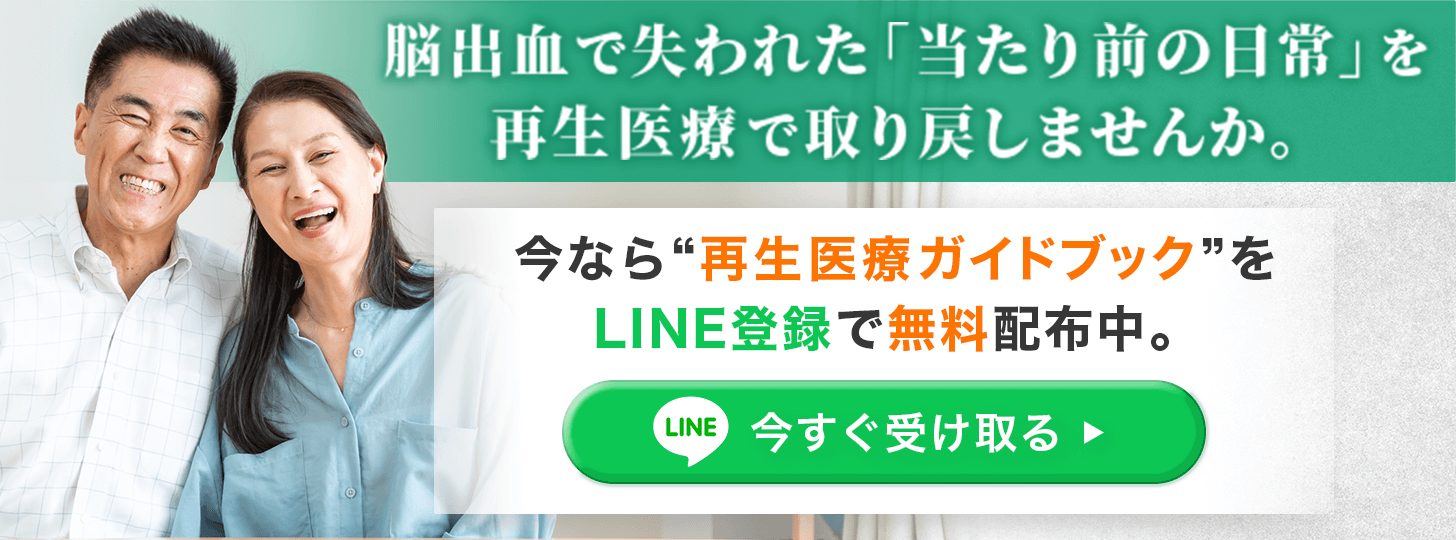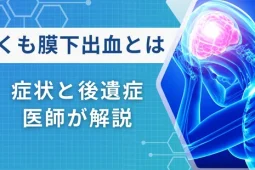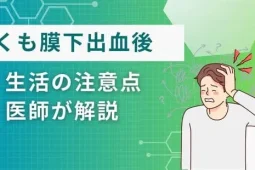- 脳卒中
- 頭部
- くも膜下出血
くも膜下出血は後遺症なしでも再発する?再発率や生存率、前兆を紹介

くも膜下出血は、重い後遺症が出る方や亡くなってしまう方も少なくない一方で、後遺症が軽く済む場合もあります。
しかし「後遺症がなくても再発しないか不安」という方もいるのではないでしょうか。
本記事では、くも膜下出血の再発率や、再発の前兆について詳しく解説しています。
くも膜下出血の再発を防ぐためのポイントも紹介しているので、再発しないか不安な日々を過ごしている方は、ぜひ参考にしてください。
\再発予防につながる再生医療とは/
再生医療とは、機能障害や機能不全になった脳細胞に対して、体が持つ再生能力を利用して損なわれた機能を再生させる医療技術のことです。
従来の治療では難しかった脳血管障害の再発予防や後遺症治療にも注目されています。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- くも膜下出血が再発しないか不安を抱えている
- 現在の治療やリハビリを継続した方がいいのかわからない
- 大きな手術や長期間の入院をせずに治療できる方法を探している
再生医療では、今まで元に戻らないとされていた損傷した脳細胞の改善が期待できるため、くも膜下出血の再発予防や後遺症改善につながる可能性があります。
詳しい治療法については、再生医療を専門とする当院リペアセルクリニックにお問い合わせください。
目次
くも膜下出血は後遺症がなくても再発のリスクがある
くも膜下出血の原因となるのは、脳の血管にできたコブ「脳動脈瘤」の破裂です。
血管には壁が薄く弱い部分があり、強い血流を受けると膨らんでコブができることがあります。このコブに高い血圧がかかるなどして破裂してしまうと、くも膜下出血が起きます。
くも膜下出血が起きると、運動麻痺・感覚障害・高次脳機能障害など後遺症が出ることも多いです。また、適切な治療が行われ後遺症がなくても、後から同じ場所や別の場所に再び脳動脈瘤ができてしまうことは珍しくありません。
再発しないように気をつけることが、くも膜下出血を経験した方にとって重要なテーマになります。
くも膜下出血が再発しないか不安な方は、先端医療である再生医療をご検討ください。
再生医療では、今まで元に戻らないとされていた損傷した脳細胞の改善が期待できるため、くも膜下出血の再発予防や後遺症改善につながる可能性があります。
当院リペアセルクリニックでは、専門の医師・スタッフによる無料のカウンセリングも実施しており、再生医療についてわかりやすくご説明いたします。
再生医療について詳しく知りたい方は、一度当院までご相談ください。
くも膜下出血の概要については以下の記事で詳しく紹介しているので、あわせてご覧ください。
くも膜下出血の再発率|1カ月以内に20~30%が再発
くも膜下出血の再発率の高さを数字で見てみましょう。
くも膜下出血は、発症から1カ月までの初期に最も再発しやすいのが特徴です。具体的には、最初の1カ月で20〜30%の方が再発するとの報告があります。(文献1)別の報告では、発症初日の再発率が3〜4%、以降4週間は1日あたり1〜2%です。(文献1)
発症から3カ月目以降の再発率は、1年あたり3%との報告があります。(文献1)少なく感じるかもしれませんが、1万人の患者様がいれば約300人が再発する計算となり、決して低い数字ではありません。
くも膜下出血の再発の前兆
くも膜下出血が再発する前兆・初期症状の代表例は目の症状と頭痛です。
これらの症状をもとに、脳動脈瘤が破裂する前に受診できれば、早期の治療で再発を防げる可能性があります。また、再発のごく初期で気付ければ、治療が成功する可能性も高まります。
くも膜下出血を経験した方は再発の前兆を知っておき、常日ごろから注意する意識が大切です。
再発の前兆①動眼神経麻痺
くも膜下出血の再発の前兆または初期症状として、以下のような目の症状が代表的です。
- 両目でモノを見るとモノが二つに見える
- 視力の低下
- 視野が欠ける
これらの症状は、大きくなった脳動脈瘤が目につながる神経を圧迫するために起こります。
モノが二つに見える症状は、眼球の運動やまぶたの開閉を担当する「動眼神経」の麻痺が原因です。片方の瞼が開かなくなる症状も併発します。
視力が低下したり視野が欠けたりする症状は、目で見たものを脳に伝える「視神経」への圧迫が原因です。
以上のような目の異常に気付いたら、脳動脈瘤が大きくなっている可能性があります。脳動脈瘤が破裂してしまうと、くも膜下出血の再発につながる可能性があるため、速やかに脳外科や脳神経外科を受診してください。
再発の前兆②頭痛
注意すべき二つ目の症状は「頭痛」です。頭痛を感じた場合は、すでに少量の出血が生じている可能性が高いため、早急に治療すべきとの意識を持ってください。
頭痛に関して知っておきたいポイントは、以下の2点です。
- 痛みの程度はさまざまである(軽くても要注意)
- 視野の乱れとともに起きることもある
とくに軽い頭痛の場合、くも膜下出血の再発の前兆とは考えずに見過ごしてしまうことも多いです。痛みが軽くても、異常を感じたら念のため病院へ向かいましょう。
受診する際には、くも膜下出血の経験があることを必ず医師に伝えてください。伝えないと、単なる風邪などと診断されてしまうケースがあるからです。
ほかにも気になる症状があれば、「いつもと違う」「初めての痛み」などと、症状の内容を詳しく医師に伝えるよう努めてください。
くも膜下出血の再発を防ぐには生活習慣の改善と定期検査が大切
くも膜下出血の再発予防には、生活習慣の改善と定期的な検査が大切です。それぞれ説明します。
生活習慣の改善
日常生活で注意すべきポイントは以下のとおりです。
- 処方薬は主治医・薬剤師の指示通りに服用する
- 定期的に血圧を測る
- ストレスを溜めず規則正しい生活を送る
- 過度な飲酒を控える・禁煙をする
- 塩分の取りすぎに注意してバランスの良い食事を心がける
くも膜下出血の危険因子は過度な飲酒、高血圧、喫煙です。(文献1)糖尿病も脳卒中全般のリスクとなるため、コントロールが欠かせません。(文献2)飲酒は適量に抑え、喫煙習慣のある方は禁煙しましょう。
高圧薬や糖尿病薬などを処方されていれば、指示通りに服用してください。ストレス管理や減塩も高血圧のコントロールに有用です。自宅で血圧を測り、血圧手帳に記録しておけば、医師が体の状態を判断する助けとなります。
生活上の注意点は、以下の記事で詳しく紹介しているので、あわせてご覧ください。
定期的な検査
くも膜下出血の再発防止には、定期的に検査を受けることも非常に重要です。脳動脈瘤を検査で発見できれば、破裂してしまう前に処置できるからです。
くも膜下出血を発症して10年くらい経過してから、治療した脳動脈瘤が再び大きくなったり、新しい脳動脈瘤ができて破裂したりする可能性もあります。一度検査して問題なかったからと油断せずに、定期的に検査を受けましょう。
くも膜下出血になると長生きできない?5年後の生存率
くも膜下出血を発症してから5年後の生存率は、55%前後といわれています。(文献3)生存率が低い要因の一つは、発症30日以内に、くも膜下出血自体で亡くなる方が多いことです。(文献1)発症初期の死亡率は、発症時の重症度や、どれだけ早く治療を開始できたかに左右されます。(文献1)
最初の30日を乗り越えたら、その後は再出血の有無が大きな要素となります。(文献1)生活習慣を整え、定期的に検査を受けて再出血の予防につなげましょう。
万が一再発してしまった場合も、もし早めに気づければ、治療が間に合う可能性が高まります。本記事で紹介した再発の前兆を覚えておき、体に異変を感じたらためらわずに受診しましょう。
くも膜下出血を発症し後遺症が出たが3年で改善した事例
ここでは、くも膜下出血の後遺症がある患者様に再生医療を行った事例を紹介します。
患者様は50代の女性です。当院「リペアセルクリニック」を受診したとき、くも膜下出血を発症してから3年が経過しており、後遺症として左半身麻痺が残っていました。日常生活で大きな不自由はないものの、ときどき足がもつれて転びそうになる、左手が思うように動かせない、ときどき呂律が回らなくなる、といった症状がありました。
幹細胞を点滴する再生医療を行ったところ、治療後3週間ほどで以下の変化が見られています。
- 足の踏ん張りが効くようになり、転倒しなくなった
- 左上肢の力がつき、左腕で背中を洗えるようになった
- 左手の力がつき、左手でボールを握れるようになった
今まで不自由だった動作ができるようになり、毎日の生活が楽になったとのことです。
この症例については以下の記事で詳しくご覧ください。
くも膜下出血は後遺症なしでも再発のリスクあり!油断せず予防に努めよう
くも膜下出血は再発率が非常に高い病気です。たとえ後遺症がなくても、再発防止を意識して生活しましょう。
とくに節度ある飲酒、高血圧の管理、禁煙がポイントです。定期的な検査も欠かさず受けましょう。
再発の前兆となる症状は、目の異常と頭痛です。このほかにも体の異常を感じたら、すぐに脳外科や脳神経外科などを受診してください。早期に対処すれば再発を防げる可能性が高まります。
くも膜下出血の後遺症でお困りの方は、再生医療が役立つかもしれません。日常生活に大きな支障がない症状でも、再生医療で改善する可能性があります。
興味があれば、お気軽に当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
参考文献
(文献1)
日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2009 Ⅳ.クモ膜下出血」2009年
https://www.jsnt.gr.jp/guideline/img/nou2009_04.pdf(最終アクセス:2025年2月22日)
(文献2)
四條克倫.「脳卒中ガイドライン2021(改訂2023)」『日大医学雑誌』82(6), pp.325-322, 2023年
https://www.jstage.jst.go.jp/article/numa/82/6/82_325/_pdf/-char/ja(最終アクセス:2025年2月22日)
(文献3)
今井明ほか.「脳卒中患者の生命予後と死因の 5 年間にわたる観察研究:栃木県の調査結果とアメリカの報告との比較」『脳卒中』32(6), pp.572-578, 2010年
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jstroke/32/6/32_6_572/_pdf(最終アクセス:2025年2月22日)