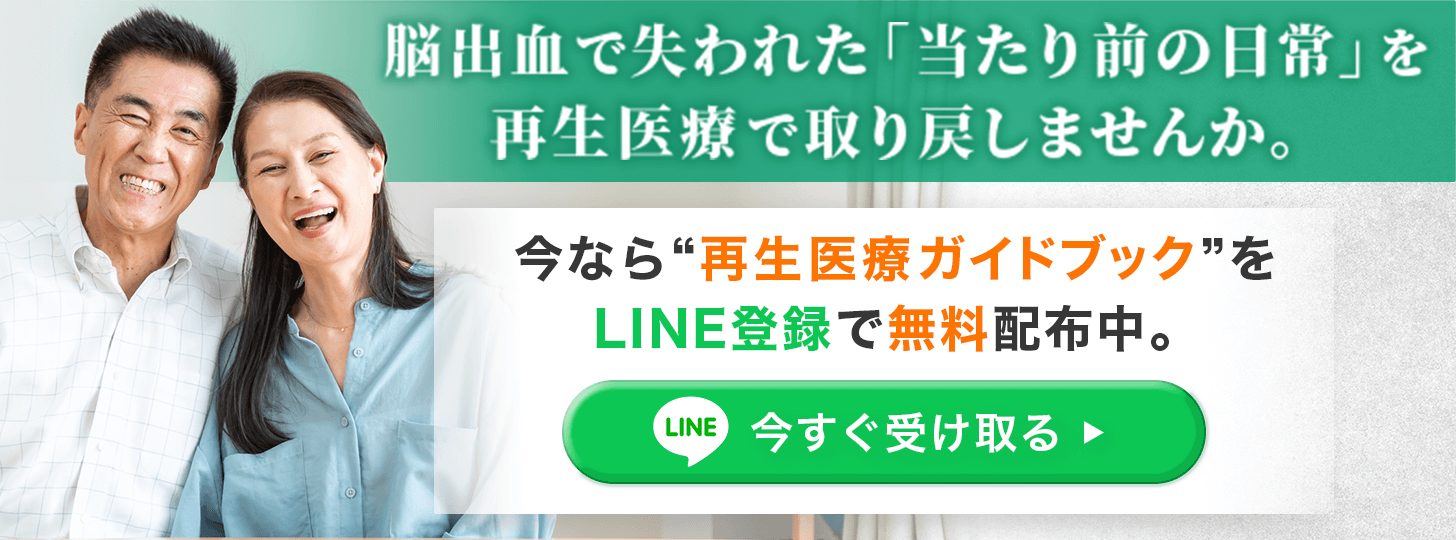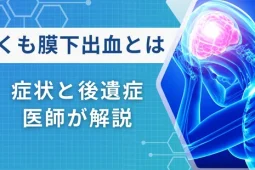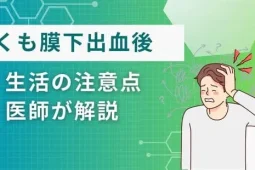- 脳卒中
- 頭部
- くも膜下出血
くも膜下出血の退院後に気をつけることは?生活の注意点について解説【医師監修】
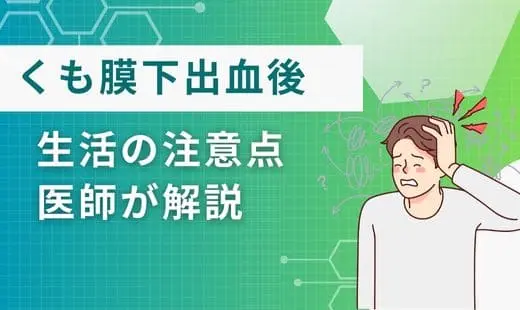
くも膜下出血発症後は後遺症があることも少なくありません、以前のような日常生活を送れるのか、退院後の生活に不安は絶えないですよね。
くも膜下出血の退院後は、リハビリを定期的に行うことが大切です。普段の食事や入浴などはリハビリの一環となるため、自発的に行いましょう。
本記事では、くも膜下出血で退院後に気を付ける点や後遺症について詳しく解説します。くも膜下出血の再発を防いで日常生活を取り戻すヒントとなれれば幸いです。
当院「リペアセルクリニック」では、再生医療による脳卒中の治療を行っております。気になる方はメール相談もしくはオンラインカウンセリングにてお気軽にご相談ください。
目次
くも膜下出血の退院後の生活で気をつけるべきこと7選【再発予防】
くも膜下出血再発予防のため、退院後に気をつけるべきことは以下の7つです。
- 体調の変化があったら医師の指示に従う
- 処方薬は主治医・薬剤師の指示通りに服用する
- 定期的に血圧を測る
- ストレスを溜めず規則正しい生活を送る
- 過度な飲酒を控える・禁煙をする
- 塩分の取りすぎに注意してバランスの良い食事を心がける
- 身の回りのことはできる限り自分で行う
退院後は上記を意識しながら日常生活を送りましょう。
体調の変化があったら主治医の指示に従う
身体のしびれやろれつが回らないなど、いつもと違う体調の変化があれば、くも膜下出血の可能性があります。早めに主治医へ相談しましょう。
くも膜下出血は発症から処置までのスピードが遅れると、その後の死亡率に影響します。自己判断で受診せず様子をみることは当面控えるようにしてください。
また、主治医以外の意見を聞きたい場合は、セカンドオピニオンもひとつの手です。ただし、体調変化があれば、すぐに受診しましょう。
当院「リペアセルクリニック」では、再生医療による脳卒中の治療を行っております。気になる方はメール相談もしくはオンラインカウンセリングにてお気軽にご相談ください。
くも膜下出血の再発については、以下の記事でも詳しく解説しています。
処方薬は主治医・薬剤師の指示通りに服用する
降圧薬や糖尿病薬など、処方された薬がある場合は指示通りに服用しましょう。
くも膜下出血の一因として、高血圧症や糖尿病といったほかの病気が考えられます。(文献1)
処方薬を正しく服用しないと血圧や血糖値はもちろんのこと、くも膜下出血の再発のリスクにつながります。
ただし、副作用がみられる場合は自己判断で辞めず、医師や薬剤師に相談してください。
定期的に血圧を測る
高血圧症によるくも膜下出血の再発を防ぐためには、日頃から定期的に血圧を測定し、記録しておきましょう。
血圧に急激な変化があったときに、主治医が適切な治療の判断をしやすくなります。
また、病院と自宅で血圧の数値が異なるケースもあります。(文献2)そのため、自宅でも血圧測定が大切です。
家庭用の測定器は、薬局や家電製品などで手軽に購入ができます。また、毎日の血圧は血圧手帳に記載し、定期受診の際に主治医へ見せるようにしましょう。
ストレスを溜めず規則正しい生活を送る
ストレスや不規則な生活は血圧に影響する可能性があります。ストレスによりくも膜下出血の一因である高血圧のリスクが2倍に上がるという報告もあるのです。(文献2)
そのため、自分なりのストレス発散方法を持っておくことが大切です。また、起床時間や就寝時間は毎日同じ時間に設定し、規則正しい生活を送りましょう。
再発リスクを減らす予防法は、以下の記事でも詳しく解説しています。
過度な飲酒を控える・禁煙をする
飲酒や喫煙も血圧を上昇させるため、くも膜下出血のリスクがあります。飲酒・喫煙も可能な限り退院後は控えましょう。
また、飲酒量が多いほど、くも膜下出血のリスクが上がるという報告もあります。(文献2)
普段から飲酒の習慣がある方は休肝日を設け、適度な飲酒量に調整するよう心がけてみてください。
喫煙は血圧上昇につながるため禁煙しましょう。自分だけで禁煙が難しい場合は、禁煙外来へ受診する方法もあります。
塩分の取りすぎに注意してバランスの良い食事を心がける
塩分の過剰摂取に注意した栄養バランスの良い食事も、くも膜下出血の再発予防につながります。
塩分の取りすぎは血圧を上げすぎてしまいます。以下のような点を意識して、減塩に取り組んでみてください。
- 食事量を腹八分目にとどめる
- 調味料を減塩タイプに切り替える
また、便秘気味の人は排便の際に、血圧が上がってしまうリスクがあります。こまめな水分補給や食物繊維が豊富な食べ物の摂取にて便秘解消を心がけてみてください。
生活習慣の見直しのみで便秘が改善しない場合は我慢せず、便秘薬の服用もひとつの手です。
身の回りのことはできる限り自分で行う
くも膜下出血で退院後は、日常生活に必要な運動機能を低下させないようにする必要があります。食事や入浴など日常生活の行動がリハビリになるため、無理のない範囲で積極的に自分で行いましょう。
また、軽めの運動も効果的です。歩行困難をきたしていない場合は、定期的な散歩やストレッチを日々の日課に取り入れてみてください。
デイサービスなどの施設で定期的にリハビリへ通うのも、くも膜下出血の再発予防に効果的でしょう。
くも膜下出血で退院後の生活はリハビリが重要
日常生活の行動のみならず、病院での定期的なリハビリも大切です。病院でリハビリをするよう指示のある方は、定期的な受診を欠かさないようにしましょう。
また、リハビリの内容は発症後の経過期間によって変わります。
| 目的 | リハビリ方法 | |
|---|---|---|
| 急性期リハビリ (治療後~14 日程度) |
寝たきり状態の予防 | 座ったままできる運動 (膝伸ばし運動や肩の上げ下げ運動など) |
| 回復期リハビリ | 日常生活の基本的な動作を行える | 歩行訓練や手芸、嚥下(えんげ)訓練など |
| 維持期リハビリ(デイサービス) | 回復期で得た機能を維持する | 軽い運動(散歩やストレッチなど) |
退院後に行うのは「回復期リハビリ」または「維持期リハビリ」です。主治医の指示に従い、自分の症状に合ったリハビリを行いましょう。
くも膜下出血のリハビリについては以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
くも膜下出血の退院後にみられる6つの後遺症
くも膜下出血の退院後も、以下6つの後遺症がみられる可能性があります。
- 手足が動かしにくい
- 触覚が鈍くなる
- 食べ物が飲み込みにくくなる
- 視野が狭くなる
- うまく話せない
- 最近の出来事を思い出せない
出血部位や出血量、合併症の有無などによって重症度は変わります。軽度の場合は発症前と同じ生活が可能となる一方で、重度では日常生活に大きな支障をきたすリスクがあります。
くも膜下出血の詳細は以下の記事でも解説していますので、参考にしてください。
くも膜下出血の退院後も定期的な治療で再発を予防しよう
くも膜下出血の退院後には、定期的なリハビリや血圧管理、生活習慣を整えることが大切です。退院後も定期受診は欠かさず、体調変化があればすぐに受診するようにしましょう。
当院「リペアセルクリニック」では、元々人体にある幹細胞を利用した再生医療による治療を行っております。気になる方はメール相談もしくはオンラインカウンセリングにてお気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
再生医療による脳卒中の治療について気になる方は、下記のぺージをご覧ください。
くも膜下出血の退院後によくあるQ&A
くも膜下出血で退院後の仕事復帰はできる?
社会復帰できる確率は半分以下と言われています。
社会復帰ができても、くも膜下出血の発症から数カ月かかる可能性もあるでしょう。その後の経過は重症度によって異なるため、早期発見が大切です。
軽症のうちに治療を行うと、仕事復帰できる可能性は高まります。
くも膜下出血の生存率は?
5年生存は、およそ55%程度と報告があります。(文献3)ただし、意識不明な状態で緊急搬送された人よりも、軽度の段階で自ら受診した人の方が生存率が高い傾向があるため、早期発見が大切です。
くも膜下出血後の食事で避けた方が良い食べ物は?
くも膜下出血後に避けた方が良い食べ物は、以下の成分が多く含まれた食べ物です。
| 多量摂取を避けた方が良い成分 | 食品例 | リスク |
|---|---|---|
| 塩分 |
|
血圧上昇 |
| 飽和脂肪酸・トランス脂肪酸 |
|
動脈硬化 |
| 糖質(炭水化物) |
|
動脈硬化 |
常に摂取しており完全に控えるのが難しい場合は、食べる頻度を減らすことからはじめましょう。
|
参考文献一覧 文献1
文献2 |