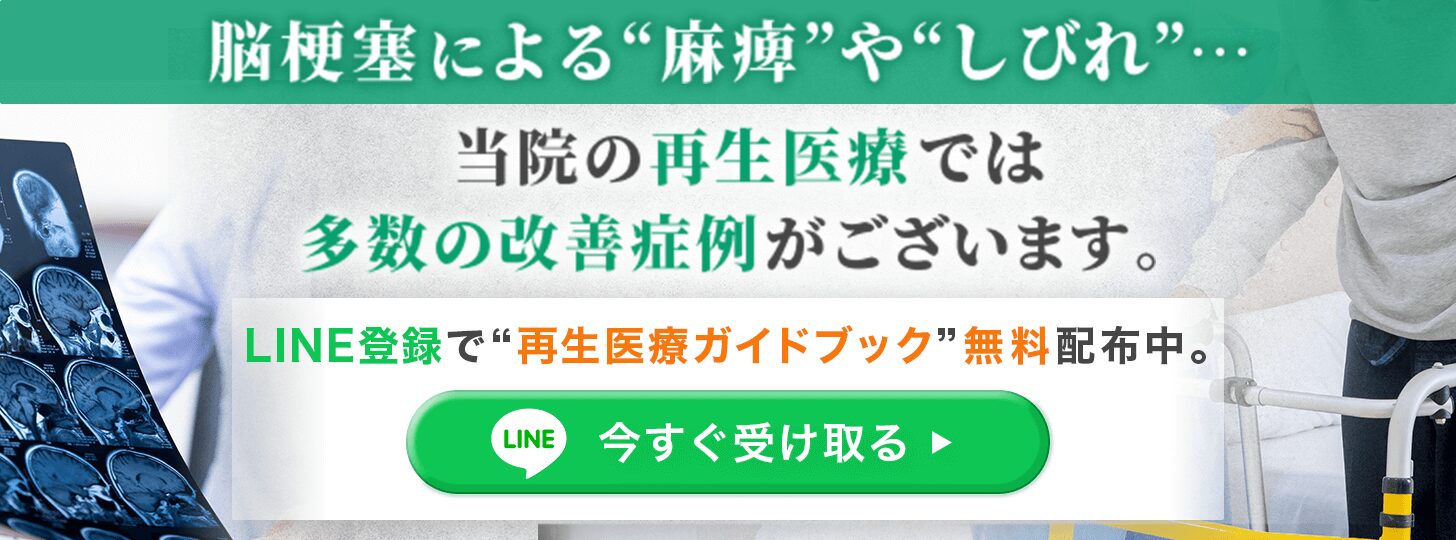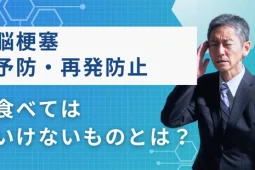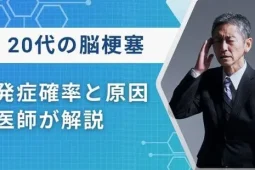- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
脳梗塞になりやすい人の特徴は?前兆や後遺症も解説

この記事を読んでいる方の中には、「自分は脳梗塞のリスクが高いのではないか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、脳梗塞は誰にでも起こる可能性がある病気です。特に、高血圧や糖尿病がある方、喫煙習慣のある方、不整脈のある方は要注意です。
しかし、適切な予防策を取ることで、脳梗塞のリスクは下げられる可能性があります。本記事では、脳梗塞になりやすい人の特徴や、脳梗塞のリスクを下げる方法などを詳しく説明します。この記事を読むことで、適切な予防策が取れるようになり、健康に関するリスクを軽減できるでしょう。
目次
脳梗塞になりやすい人の特徴6選
脳梗塞とは、脳の血管が詰まって血流が低下して、脳に障害が起こる病気です。
高齢者が寝たきりになる原因の多くを占め、初期段階での早期治療や発症予防が非常に重要といわれています。
脳梗塞になりやすい人の特徴は、以下のとおりです。
- 高血圧の人
- 糖尿病の人
- 不整脈(心房細動)がある人
- 脂質異常症の人
- 生活習慣の乱れやストレスがある人
- 妊婦や経口避妊薬の服用をしている人【女性】
本章の内容をもとに、自分が脳梗塞になりやすいのかを考えてみましょう。
脳梗塞の症状や原因など、包括的な解説は「脳梗塞とは|症状・原因・治療法を現役医師が解説」をご覧ください。
高血圧の人
脳梗塞の原因疾患でもっとも多いものは、「高血圧」です。(文献1)
一般的には病院や健診施設などで測定した血圧が、最高血圧(収縮期血圧)140mmHg以上、あるいは最低血圧(拡張期血圧)90mmHg以上であれば、「高血圧症」と診断されます。(家庭内血圧 135/85mmHg以上)
脳梗塞を防ぐためにどの程度血圧を下げるかは、年齢や持病の状況によって異なります。
具体的な目標値は、以下のとおりです。
|
降圧目標 |
該当者 |
|---|---|
|
130/80mmHg未満 |
|
|
140/90mmHg未満 |
|
糖尿病や重度の腎機能障害の人は脳梗塞になりやすいため、血圧の目標値がより厳しく定められています。
糖尿病の人
近年、糖尿病の増加に伴って「アテローム血栓性脳梗塞」の発症数が増えています。
血糖値が高い状態が続くと、血液中に多量に存在する糖分が血管の壁を傷つけ、動脈硬化が悪化します。
その結果、脳梗塞や心筋梗塞などの病気の発症リスクが高くなるのです。(文献2)
不整脈(心房細動)がある人
「心房細動」と呼ばれる不整脈がある場合、心房内に血栓ができるリスクが高まります。できた血栓が血流に乗って全身へ飛ぶ恐れがあり、飛んだ血栓が脳で詰まると「脳梗塞」になるためです。
この心臓由来の血栓による脳梗塞を、「心原性脳塞栓症」と呼びます。心原性脳塞栓症は、ほかの脳梗塞よりも大きな血管が詰まるため、命に関わるケースもあります。
脂質異常症の人
脂質異常症の人は、血液中のコレステロールが高い状態です。そのため、血管を詰まらせる「血栓」ができやすく、脳梗塞になるリスクも高いため注意が必要です。
脂質異常症から脳梗塞にいたる流れを、以下に紹介します。
- 血管中に脂質(コレステロール)が高い状態が続く
- 血管の壁に「プラーク」と呼ばれる塊ができ、詰まりやすくなる
- できたプラークが何かをきっかけに壊れる
- 破れた部分を修復するために「血小板」という血液を固める物質が集まり、血栓ができる
- 血栓が脳の血管に詰まり、脳梗塞が起こる
脂質異常症そのものには自覚症状が無いケースが多いため、治療の必要性を感じない人もいます。しかし、放置すると結果的に脳梗塞をはじめとする大きな病気につながるのです。
生活習慣の乱れやストレスがある人
以下のような生活習慣の乱れは、脳梗塞のリスクを上昇させます。(文献3)
- 喫煙
- 肥満
- 運動不足
- 食生活の乱れ
- お酒の飲みすぎ
- 塩分の取りすぎ
- ストレスの多い生活
複数の要因が重なると、より脳梗塞の発症リスクは高まります。
妊婦や経口避妊薬の服用をしている人【女性】
妊娠中の人や女性ホルモン剤を服用している一部の人は、血栓ができやすくなることがあります。
とくに、45歳未満で前兆のある片頭痛がある人は経口避妊薬の服用によって脳梗塞のリスクが上昇するという報告があります。(文献1)
そのため、前兆のある片頭痛を持病に持つ女性は、経口避妊薬を飲むことはできません。
また、女性は、血管や骨の健康を保つ女性ホルモン「エストロゲン」が閉経により減少すると、脳梗塞になりやすくなるともいわれています。
当院「リペアセルクリニック」では、脳梗塞後の後遺症軽減や再発予防に、再生医療(幹細胞治療)をおこなっています。ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けています。どうぞ気軽にお問い合わせください。
また、脳梗塞の前兆については、以下の記事で詳しく説明しています。あわせてご覧いただければ幸いです。
\無料オンライン診断実施中!/
脳梗塞の発症を予防する3つの対策
脳梗塞の発症を予防する対策は、以下の3つです。
- 生活習慣病を治療して動脈硬化を防ぐ
- 生活習慣をととのえる
- 不整脈を治療する
本章の内容を参考に、脳梗塞のリスクを軽減させましょう。
1.生活習慣病を治療して動脈硬化を防ぐ
生活習慣病である「高血圧」「糖尿病」「脂質異常症」の治療は、脳梗塞の発症リスクを低下させます。取り入れやすい対策法を順番に説明します。
高血圧
高血圧を治療すれば血圧が下がり、血管への負担が軽減します。その結果、脳梗塞リスクの減少が期待できます。生活上の注意を守りながら、処方された薬を正しく服用しましょう。
高血圧の治療に使われる薬の例は、以下のとおりです。(文献1)
- カルシウム拮抗薬
- 利尿薬
- アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬
- アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)
また、血圧を下げるためには「規則正しい食生活」「適度な運動」などの生活習慣の改善が重要です。できることから少しずつ心がけましょう。
糖尿病
糖尿病のコントロールが悪いと脳梗塞の原因となる「動脈硬化」になりやすくなります。そのため、糖尿病の治療も、脳梗塞の予防に効果があります。。
糖尿病治療の基本は「食事療法」「運動療法」「薬物療法」の3つです。具体的な指導内容は、糖尿病の状態や残された腎臓の機能などによって異なるため、医師の指示に従いましょう。(文献4)
脂質異常症
脳梗塞のリスクを下げるには、血中のLDLコレステロール値を適正に保つことも大切です。
LDLコレステロールは、脳梗塞のなかでも「アテローム血栓性脳梗塞」のリスクに関わるといわれています。
脂質異常症の治療は、生活習慣の改善に加えて以下の薬がよく使われます。
- スタチン系
- エゼチミブ
スタチン系の薬で十分な効果が得られない場合、エゼチミブと併用するケースもあります。(文献1)
2.生活習慣をととのえる
生活習慣の乱れは高血圧、糖尿病、脂質異常症など多くの生活習慣病の発症・悪化に関わります。
取り入れたい生活習慣は、以下のとおりです。(文献5)(文献6)
- 肥満を解消する
- 適度な運動をする
- 十分な睡眠をとる
- 脂質や塩分を控える
- たばこをやめる(禁煙)
- お酒の飲みすぎは避ける
- 魚を積極的に取り入れる
また、脱水も脳梗塞のリスクを上げるため、運動や入浴、サウナなど、汗を多くかいた後は水分をこまめにとることも心がけたいポイントです。
できることから少しずつ始めてみましょう。
脳梗塞の予防につながる生活習慣は、以下の記事でも詳しく説明しています。
3.不整脈を治療する
不整脈のうち「心房細動」があると、毎年約5%の方に脳梗塞が発症すると指摘されています。
日常生活で動悸・息切れなどの自覚症状が出現した際は、心臓専門の医療機関で詳しく調べてもらいましょう。
\無料オンライン診断実施中!/
脳梗塞の再発を予防する方法
最近、脳ドックを受診する方が増えて「無症候性脳梗塞(隠れ脳梗塞)」が見つかるケースが増えています。この隠れ脳梗塞が発見されたのち、数年以内に3割の人が再び脳梗塞の発作を起こすともいわれています。
「脳梗塞は再発する危険性がある」と考えておきましょう。
脳梗塞を発症した方は、血栓ができないように再発を予防する薬を飲む必要があります。起きた脳梗塞の種類と、代表的な再発予防薬は以下のとおりです。
|
起きた脳梗塞の種類 |
代表的な再発予防薬 |
|---|---|
|
「ラクナ梗塞」や「アテローム血栓症」 |
抗血小板薬(少量のアスピリン、シロスタゾールなど) |
|
心臓が原因で起こる「脳塞栓」 |
抗凝固薬(ワーファリン、リバーロキサバンなど) |
再発防止で大切なのは、症状が悪化していない・調子が良いなどの場合も、自己判断で薬をやめないことです。基本的には脳梗塞の再発予防薬は、継続する必要があります。
また、再発防止薬を飲んでいる人は、出血しやすい状態です。あざが治らない、鼻血が止まらない、便に血が混じるなどの場合はすぐに受診してください。
また、薬の効果に影響するため、ワーファリンを服用している人は納豆や青汁などを食べてはいけません。
薬の継続についてや副作用に関する不安がある場合は、当院「リペアセルクリニック」でも相談を受け付けております。「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で気軽にご連絡ください。
脳梗塞を含む脳卒中の再発予防については、以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。
まとめ|脳梗塞になりやすい基礎疾患は早めに治療しよう
脳梗塞になりやすい人は、高血圧や糖尿病、脂質異常症など、動脈硬化になりやすい要素があります。脳梗塞の発症や再発を予防するために、高血圧や糖尿病を罹患している場合には疾病の治療を行い、日頃の生活習慣を見直してみましょう。
当院「リペアセルクリニック」では、脳梗塞後の治療として再生医療(幹細胞)をおこなっています。再生医療は、脳梗塞によってダメージを受けた脳細胞の修復や麻痺の改善、リハビリ効果の向上などに効果が期待できます。
再生医療へのご質問・ご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けております。気になる点がありましたら、どうぞ気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
脳梗塞になりやすい人に関するよくあるQ&A
脳梗塞になりやすい性格は?
ストレスをためやすい人は、脳梗塞のリスクを高める以下の病気が悪化しやすく、脳梗塞になりやすい可能性があります。(文献7)(文献8)
- 高血圧
- 糖尿病
また、「脳梗塞の発症には、労働時間や労働によるストレスが関与している可能性がある」という研究報告もあります。適度な運動や休息をとり、ストレスをやわらげるようにしてみてください。(文献3)
ストレスは若年性脳梗塞の原因になりますか?
若年性脳梗塞とは、50歳以下の若い人に起こる脳梗塞です。通常の脳梗塞と同様に、動脈硬化がひとつのリスクといわれています。
そのため、動脈硬化を悪化させるストレスは、若年性脳梗塞のリスクを上昇させる可能性が考えられるでしょう。
当院「リペアセルクリニック」では、若年性脳梗塞後の治療にも再生医療(幹細胞治療)をおこなっています。気になる症状がある方は「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」まで気軽にご連絡ください。
若年性脳梗塞については、以下の記事で詳しく説明しています。
脳梗塞になりやすい食べ物はありますか?
以下の食品を摂りすぎると、脳梗塞になりやすくなる可能性があります。
|
食品 |
理由 |
|---|---|
|
動物性脂肪・トランス脂肪酸が含まれる食品 |
コレステロールを増やしたり血行を悪くしたりするから |
|
加工食品 |
添加物や保存料、トランス脂肪酸を多く含むから |
|
塩蔵品 |
塩分が多く、動脈硬化や高血圧の原因となるから |
|
アルコール |
摂りすぎると動脈硬化のリスクが上がるから おつまみとして塩分や脂肪が多い食品が過剰になりやすいから |
|
高GI炭水化物 |
血糖値を急激に上げたり血管内に炎症をもたらしたりするから |
毎日の積み重ねが身体をつくるため、摂りすぎには注意しましょう。
脳梗塞の予防・再発防止に関係する食事については以下の記事で詳しく紹介しています。
脳梗塞の後遺症はどんな症状ですか?
脳梗塞は、約半数の人に後遺症が出るといわれています。どのような後遺症が出るかは、ダメージを受けた部位によって異なります。
|
ダメージを受けた脳の部位 |
後遺症の例 |
|---|---|
|
前頭葉 |
人格や性格が変化する |
|
頭頂葉 |
体が動かなくなる(麻痺) |
|
後頭葉 |
視野の半分が欠ける |
|
側頭葉 |
学習、記憶障害が起こる |
どの後遺症の場合も、継続的なリハビリが大切となります。
脳梗塞の治療や後遺症については、以下の記事もぜひ参考にしてください。
参考文献
(文献1)
日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会「脳卒中治療ガイドライン 2021〔改訂2025〕」
(文献2)
国立国際医療研究センター糖尿病情報センター「糖尿病の慢性合併症について知っておきましょう」
(文献3)
三重大学「ストレス関連疾患の発症に寄与する勤務状況の因子とその影響に関する研究」
(文献4)
国立国際医療研究センター糖尿病情報センター「糖尿病の治療ってどんなものがあるの?」
(文献5)
文部科学省「健康啓発教材2021高校生用07」
(文献6)
国立がん研究センター「肥満度と病型別脳梗塞の発症リスクとの関連について」