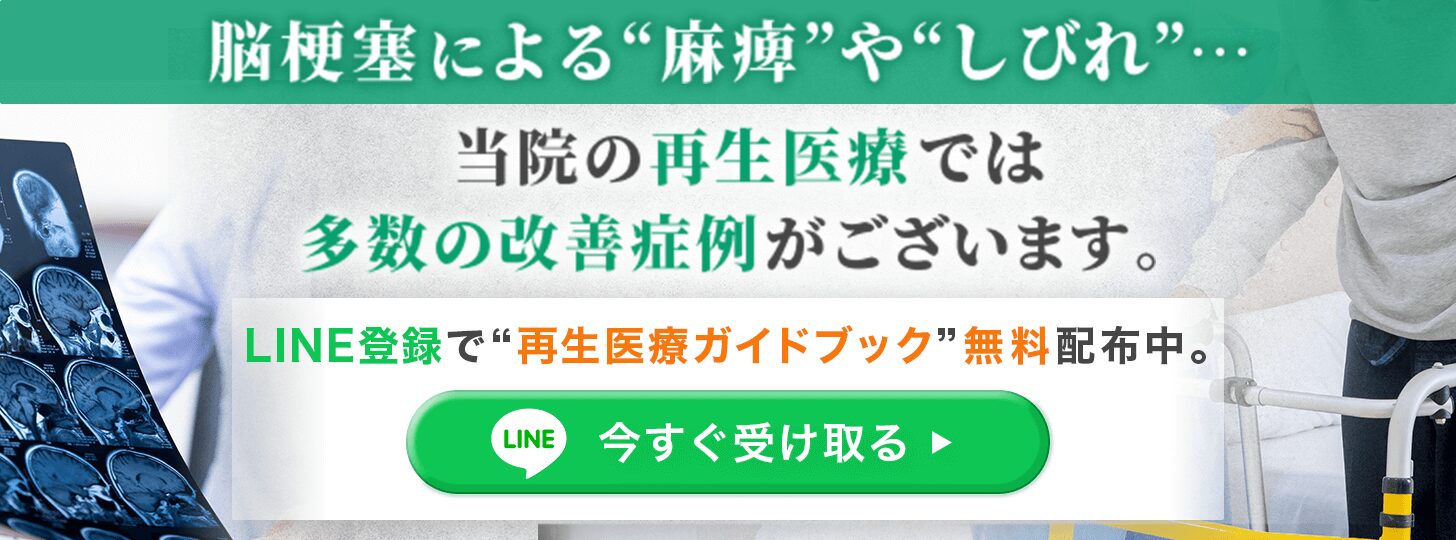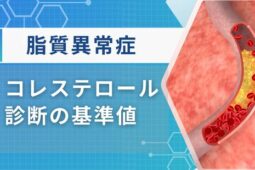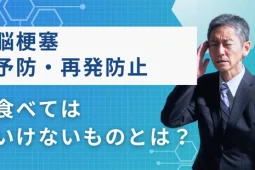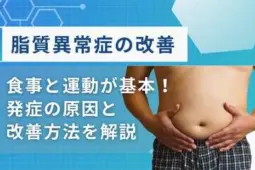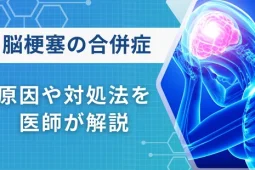- 脳卒中
- 頭部
- 脳梗塞
【医師監修】脳梗塞の再発率|繰り返す原因・予防・再発しなかった人の割合を解説
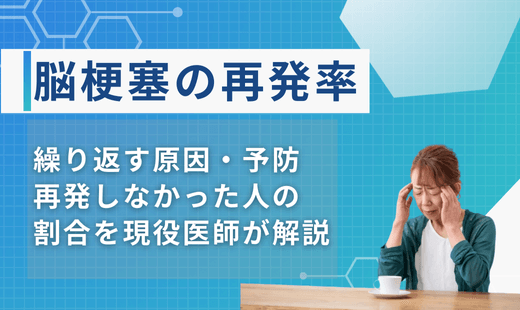
「脳梗塞の再発が怖い」
「脳梗塞を繰り返す原因を知りたい」
一度脳梗塞を経験すると、再発のリスクが年を追うごとに高まります。実際、発症後1年で約10%、5年で約35%、10年では約50%の方が再発を経験したと報告されています。
日常生活で不安や心細さを感じるのは自然なことです。脳梗塞は再発率の高い疾患であり、そのリスクを理解し、退院後に適切に対処することが長期的な予後管理に極めて重要です。
本記事では、脳梗塞の再発率を現役医師が解説します。
- 脳梗塞を再発しなかった人の割合
- 脳梗塞の再発死亡率
- 脳梗塞の再発サイン
- 脳梗塞を繰り返す原因
- 脳梗塞の再発を予防する方法
記事の最後には、脳梗塞の再発に関するよくある質問をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
脳梗塞の再発が不安な方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
脳梗塞の再発率
| 種類 | 詳細 |
|---|---|
| 脳梗塞 | 全体の1年再発率10%、10年再発率49.7% |
| ラクナ梗塞 | 細い血管の閉塞による1年再発率7.2%、10年再発率46.8% |
| アテローム血栓性脳梗塞 | 動脈硬化関連の1年再発率14.8%、10年再発率46.9% |
| 心原性脳塞栓症 | 心臓由来の血栓による1年再発率19.6%、10年再発率75.2% |
脳梗塞は再発しやすく、危険性はタイプによって異なります。再発は生活の質を大きく左右するため、退院後の予防が重要です。
生活習慣の改善や薬剤の服用に加え、自身の脳梗塞の種類を理解し、適切に対策することが再発防止につながります。
脳梗塞
脳梗塞は再発の可能性が高い疾患で、10年再発率は49.7%と報告されており、発症者のおよそ半数が再発を経験することになります。脳卒中全体の10年再発率は51.3%、くも膜下出血は70.0%、脳出血は55.6%と、いずれも高い値を示しています。(文献1)
脳梗塞に限ると、1年再発率は10.0%であり、10人に1人が1年以内に再発している計算になります。
脳卒中は日本人の死因第4位で、中でも脳梗塞は全体の57.0%を占める最も多い病型です。(文献1)
再発によって重症化や死亡に至る例も少なくなく、そのリスクは軽視できません。
とくに、再発は発症直後から1年以内に集中しており、海外の研究では発症後最初の30日間に最も高い再発率が認められたとの報告もあります(文献3)
発症後は、症状のわずかな変化にも注意を払い、異常を自覚した場合には、速やかに医療機関を受診することが重要です。
以下の記事では、脳梗塞について詳しく解説しています。
ラクナ梗塞
ラクナ梗塞は、高血圧などで損傷した脳深部の細い血管が血栓で詰まり発症し、症状は軽いことが多いものの、再発を繰り返すとパーキンソン症候群や認知症の原因となる疾患です。
再発率は1年で7.2%、10年で46.8%と報告されており、長期的には高いリスクを伴います。(文献2)
そのため、継続的な予防と適切な管理が不可欠です。
以下の記事では、ラクナ脳梗塞について詳しく解説しています。
アテローム血栓性脳梗塞
アテローム血栓性脳梗塞は、頸動脈などの太い血管に動脈硬化(アテローム硬化)が生じることで発症します。血管内に形成された血栓がはがれて脳へ流入し梗塞を起こすのが特徴です。発症時は軽症でも徐々に進行する例が少なくありません。
再発率は1年で14.8%、10年で46.9%と報告されています。(文献2)
動脈硬化は高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病により進行しやすく、頸動脈だけでなく冠動脈や下肢動脈にも生じます。そのため、心筋梗塞や下肢閉塞性動脈硬化症を併発することもあり、全身的な管理が求められます。
以下の記事では、アテローム血栓性脳梗塞について詳しく解説しています。
心原性脳塞栓症
心原性脳塞栓症は、心臓内に生じた血栓が血流に乗って脳の動脈に到達し、血管を閉塞することで発症する脳梗塞です。主な原因は心房細動をはじめとする不整脈や心臓弁膜症などで、心臓内の血流が滞り血栓が形成されやすくなります。
このタイプの脳梗塞は突然発症し、重篤な症状を呈することが多いのが特徴です。再発率も高く、1年で19.6%、10年で75.2%に達すると報告されています。(文献2)
再発時も重症化しやすいため、抗凝固薬を用いた適切な治療と継続的な管理が再発予防に不可欠です。
以下の記事では、心原性脳梗塞について詳しく解説しています。
脳梗塞を再発しなかった人の割合
| 種類 | 1年再発率 | 1年再発しなかった割合 | 10年再発率 | 10年再発しなかった場合 |
|---|---|---|---|---|
| ラクナ梗塞(細い血管が詰まるタイプ) | 約7.2% | 約92.8% | 約46.8% | 約53.2% |
| アテローム血栓性脳梗塞(太い血管が詰まるタイプ) | 約14.8% | 約85.2% | 約46.9% | 約53.1% |
| 心原性脳塞栓症(心臓でできた血栓が脳に飛ぶタイプ) | 約19.6% | 約80.4% | 約75.2% | 約24.8% |
| 脳梗塞全体 | 約10.0% | 約87.2% | 約49.7% | 約50.3% |
(文献2)
脳梗塞は再発しやすい病気ですが、再発しなかった方の割合を知ることも重要です。日本の研究では、脳梗塞全体で1年以内に約87.2%、約50.3%が再発していません。ラクナ梗塞やアテローム血栓性脳梗塞では10年後も半数以上が再発せずに過ごしていますが、心原性脳塞栓症では約25%にとどまり、再発率がとくに高いと報告されています。(文献2)
脳梗塞の種類によって再発リスクは大きく異なります。再発しなかった人が多い背景には、生活習慣の改善や薬の継続といった日々の予防が欠かせません。再発を予防するための取り組みは、長期的な健康維持と生活の質の向上につながる重要な要素です。
脳梗塞の再発死亡率
脳梗塞は再発後1年以内の死亡率が約10%と報告されています。
高血圧・糖尿病・脂質異常症の管理、禁煙・節酒・運動・食生活改善など生活習慣の見直しが重要です。抗血栓薬や降圧薬は医師の指示に従って継続し、服薬アドヒアランス(処方薬を忘れず、正しい方法で飲み続けること)を守ることが再発予防につながります。
定期的な受診と検査で血圧や血糖、脂質、心房細動、頸動脈プラークを確認し、異常を早期に発見することが必要です。
心房細動や心不全を合併した場合は死亡リスクが高まるため、神経内科と循環器内科の連携が重要です。さらに、一過性脳虚血発作(TIA)などの前兆があれば速やかに
医療機関を受診することが予後改善に直結します。
脳梗塞の再発サイン
| 再発のサイン | 詳細 |
|---|---|
| 片側のしびれ・麻痺、バランスの異常 | 身体の半分のしびれや脱力、力が入らない状態、歩行時のふらつき |
| 言語・視覚に関わる異常 | 言葉が出にくい、ろれつが回らない、視界の異常や急な視野欠損 |
| めまい・頭痛・意識変容などの緊急サイン | 突然の激しいめまい、今までにない強い頭痛、意識がもうろうとする状態 |
脳梗塞は再発しやすく、早期にサインを見極めることが予後を左右します。片側のしびれや麻痺、歩行時のふらつきといった運動障害、言葉が出にくい、ろれつが回らない、視界の異常などの言語・視覚障害は重要な警告です。
さらに、突然の激しいめまいや強い頭痛、意識がもうろうとする状態は緊急のサインであり、速やかな受診が必要です。
以下の記事では、脳梗塞のサインについて詳しく解説しています。
【関連記事】
片側のしびれ・麻痺、バランスの異常
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 脳の損傷と半身症状 | 脳の損傷した側とは反対の身体半分にしびれや麻痺が現れる現象 |
| バランス異常の原因 | 麻痺側をかばうことで重心が偏り、姿勢や歩行にふらつきが生じる状態 |
| 一過性脳虚血発作(TIA) | 数分〜1時間以内に現れ回復する脳梗塞に似た症状で、再発前の警告サイン |
| 早期対策と注意点 | 症状が突然現れた場合、短時間でも早期受診 |
脳梗塞では、脳の損傷部位と反対側の手足にしびれや麻痺が生じます。右脳の障害では左半身、左脳の障害では右半身に症状が出るのが典型です。
麻痺側をかばうことで重心が偏り、歩行時のふらつきや不安定さが起こることもあります。これらの症状は脳梗塞だけでなく、再発の前には、一過性脳虚血発作(TIA)がみられることがあります。症状は数分から1時間以内に回復する場合もありますが、これは重大な警告サインです。症状が短時間であっても軽視せず、速やかに受診することが再発予防と健康維持につながります。
以下の記事では、手足に違和感が出るアッヘンバッハ症候群と脳梗塞の関係性について詳しく解説しています。
言語・視覚に関わる異常
言語は左脳の前頭葉や側頭葉、視覚は後頭葉が担います。脳梗塞でこれらが障害されると血流が途絶え、言語障害や視覚異常が生じます。
言語では言葉が出にくい、ろれつが回らない、話が理解しにくいといった症状、視覚では視野の欠損や片目の見えにくさ、物が二重に見えるといった症状が突然現れることがあり、これらは再発の重要なサインです。数分で改善しても一過性脳虚血発作(TIA)の可能性があるため、速やかな受診が必要です。
以下の記事では、閃輝暗点について詳しく解説しています。
めまい・頭痛・意識変容などの緊急サイン
| 再発の前兆 | 詳細 |
|---|---|
| めまい・ふらつき・バランスの乱れ | 小脳や脳幹の血流障害による平衡感覚の低下、突然のめまいやふらつき |
| 激しい頭痛と嘔吐、意識変化 | 脳内圧力上昇や出血性脳梗塞に伴う後頭部の強い頭痛、嘔吐、意識のもうろう状態 |
| 意識レベルの低下・混乱した状態 | 認知機能・意識維持領域への血流障害による突然の混乱、意識障害や失神に近い状態 |
小脳や脳幹は体のバランスを保つ重要な部位であり、血流が途絶えると突然のめまいやふらつきが生じます。これらの症状は疲労や薬の副作用と誤解されやすいため注意が必要です。
また、出血性脳梗塞や頭蓋内圧の急激な上昇では、強い頭痛、吐き気、意識混濁が短時間で出現することがあります。
さらに、認知機能や意識維持に関わる領域が障害されると、混乱や意識低下、失神に近い状態を引き起こす場合があります。これらはいずれも脳梗塞再発の緊急サインであり、症状が突然現れた場合は速やかな医療機関への受診が不可欠です。
以下の記事では、頭痛について詳しく解説しています。
【関連記事】
こめかみの痛みは脳梗塞のサイン?頭痛の原因や受診すべき目安を医師が解説
頭が痛いときの対処法を解説!原因やタイプ別の治療法についても紹介【医師監修】
脳梗塞を繰り返す原因
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 生活習慣病と動脈硬化 | 高血圧や糖尿病、脂質異常症による血管の損傷と動脈硬化の進行 |
| 心血管疾患と血栓リスク | 心房細動など心疾患による血栓形成と脳血管への血栓飛来による血管閉塞 |
| 不健康な生活習慣とストレス | 喫煙、過度な飲酒、運動不足、塩分過多、不規則な食生活、慢性的なストレス状態 |
脳梗塞の再発は、高血圧や糖尿病による動脈硬化や心房細動による血栓形成、不健康な生活習慣が原因で起こります。
喫煙や過度な飲酒、運動不足やストレスも再発リスクを高めるため、適切な管理が再発予防につながります。
生活習慣病と動脈硬化
脳梗塞は脳の血管が詰まり血流が途絶する疾患であり、原因のひとつが動脈硬化です。動脈硬化とは、血管壁に脂肪やコレステロールが蓄積して血管が狭く硬くなる状態を指し、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病により進行します。
生活習慣病は血管を損傷させ血栓形成を促進し、脳梗塞のリスクを高めます。再発予防には薬物治療に加え、血圧や血糖の適切な管理、食生活の改善、適度な運動、禁煙が重要です。さらに、定期的な検査による早期発見と治療が動脈硬化の進行抑制と再発防止に直結します。
以下の記事では、脂質異常症の診断基準について詳しく解説しています。
心血管疾患と血栓リスク
心血管疾患は脳梗塞再発の大きな要因です。心房細動などの不整脈、心臓弁膜症、心筋梗塞、拡張型心筋症では心臓内の血流がよどみ、血栓が形成されやすくなります。心臓でできた血栓が脳血管に流れて閉塞を起こすと、心原性脳塞栓症が発症します。
とくに心房細動は無症状で進行することも多く、定期的な心電図検査や、動悸・息切れといった症状がある場合の早期受診が重要です。再発予防には、基礎疾患の適切な治療に加え、抗凝固薬による血栓予防と定期的な心臓検査が不可欠です。
以下の記事では、不整脈になりやすい人の特徴を詳しく解説しています。
不健康な生活習慣とストレス
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 血管を傷つける生活習慣 | 喫煙、高塩分、脂肪や過度の飲酒、運動不足による血圧やコレステロールの悪化 |
| 慢性的なストレス | 長期間のストレスによるコルチゾール増加、高血圧、血糖異常、炎症状態の持続 |
| 生活習慣とストレスの複合リスク | 複数の治療可能なリスク要因の重なりによる再発リスク上昇、不健康生活と強いストレスの悪循環 |
不健康な生活習慣や慢性的なストレスは脳梗塞の再発リスクを高めます。喫煙や過度の飲酒、偏った食事、運動不足は動脈硬化を進め、ストレスは血圧や血糖を乱し血管に負担をかけます。
再発予防には禁煙、減塩、適度な運動、ストレス管理、そして医師の指導に基づく治療の継続が欠かせません。
以下の記事では、脳梗塞の予防・再発防止のために食べてはいけないものを詳しく解説しています。
脳梗塞の再発を予防する方法
| 再発を予防する方法 | 詳細 |
|---|---|
| 生活習慣・リスク因子の管理 | 血圧、血糖、脂質異常症のコントロール、禁煙、減塩、適度な運動、体重管理 |
| 適切な薬物療法と医療フォローの継続 | 原因に応じた抗血栓薬の服用、定期的な診察や血液検査、検査機器による血管状態の確認 |
| 質の良い睡眠とリハビリの継続 | 睡眠時無呼吸症候群の検査・対策、十分な睡眠環境の整備、理学療法士による継続リハビリ |
脳梗塞の再発予防には、生活習慣の改善と医療的管理を組み合わせた多角的なアプローチが求められます。血圧・血糖・脂質の適切なコントロールに加え、禁煙、減塩、適度な運動、体重管理などの日常的な生活習慣の調整が基本です。
さらに、原因に応じた抗血栓薬の継続服用や、定期的な診察・血液検査、画像検査による血管状態の把握が再発リスクの低減に直結します。
加えて、睡眠時無呼吸症候群への対応や良質な睡眠環境の整備、医師による継続的なリハビリも重要です。これらを包括的に実践し、医療機関と連携しながら継続的に取り組むことが、脳梗塞再発を防ぐために不可欠です。
生活習慣・リスク因子の管理
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 脳梗塞の再発リスク | 動脈硬化や血栓形成を促進する高血圧、糖尿病、脂質異常症などのリスク因子 |
| 生活習慣の改善と管理 | 血圧・血糖のコントロール、塩分や脂肪を控えた食事、禁煙、適度な運動、節度ある飲酒 |
| 定期検査と薬物療法の継続 | 医師の指示に従い薬を服用、定期的な検査で血管や内臓の状態を確認 |
脳梗塞は脳の血管が詰まることで発症し、一度起こると再発のリスクが高まります。その背景には、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病が関与し、血管を傷つけて動脈硬化や血栓形成を進行させる点が挙げられます。
再発を防ぐためには、血圧や血糖の適切な管理に加え、減塩・低脂肪を意識した食生活、禁煙、適度な運動、節度ある飲酒といった生活習慣の改善が欠かせません。
さらに、医師の指示に基づいた薬物療法を継続し、定期的な検査で血管や全身の状態を確認することも重要です。こうした継続的かつ総合的な健康管理が、脳梗塞の再発予防につながります。
以下の記事では、脂質異常症改善について詳しく解説しています。
適切な薬物療法と医療フォローの継続
脳梗塞の再発予防には、薬物療法と医療フォローの継続が重要です。抗血小板薬は血栓形成を抑え、抗凝固薬は血液凝固を調整して血管内の血栓を防ぎます。
病態に応じた使い分けにより再発リスクの低減が期待されます。さらに、高血圧や糖尿病、脂質異常症に対する治療も動脈硬化抑制に欠かせません。服薬は患者自身の判断で中断すべきではなく、医師の指示に基づいて継続することが求められます。
以下の記事では、脳梗塞に使われるメコバラミン(メチコバール)について詳しく解説しています。
質の良い睡眠とリハビリの継続
睡眠障害は脳梗塞の再発リスクを高め、日中の眠気はリハビリへの集中を妨げて回復を遅らせます。リハビリは身体機能の回復や生活の自立に直結し、神経回路の再構築に不可欠ですが、無理のない範囲で続けることが重要です。
家族や医師の支援はリハビリ継続を後押しします。再発予防には睡眠環境の整備や必要に応じた検査・治療、医師の指導によるリハビリの継続が欠かせません。
脳梗塞の再発に不安を抱えている方は当院へお気軽にご相談ください
脳梗塞の再発予防には生活習慣の改善や薬物療法、リハビリの継続など多方面での取り組みが必要であり、一人で抱えるには大きな負担となります。再発への不安や生活上の工夫、治療の継続に悩む方も少なくありません。
脳梗塞の再発についてお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。当院では、患者様とご家族を支える体制を整え、睡眠・食事・運動習慣の改善などに関するお悩みに丁寧に対応しています。患者様一人ひとりに合った再発予防策を共に考え、継続して取り組めるよう支援いたします。
脳梗塞に対する再生医療について、以下の記事では右脳梗塞の後遺症により左手が思うように動かなくなった50代女性の症例を紹介しています。再生医療に関する治療内容や症状経過について興味がある方は、ぜひ一度ご覧ください。
ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。
\無料オンライン診断実施中!/
脳梗塞の再発に関するよくある質問
脳梗塞は他の病気と合併症になることはありますか?
脳梗塞は高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病や、心房細動などの心疾患、睡眠時無呼吸症候群と合併しやすく、再発リスクを高めます。
また、誤嚥性肺炎、出血、脳血管性認知症、サルコペニア、脳卒中後てんかん、うつ病、摂食嚥下障害などの合併症を伴うこともあります。これらは脳や身体機能の障害や治療の影響で生じるため、基礎疾患の管理と合併症への早期対応が重要です。
以下の記事では、脳梗塞の合併症について詳しく解説しています。
振動(ブルブル)マシンは脳梗塞を再発させる原因になりますか?
振動マシン(WBV)が脳梗塞の再発を直接引き起こす医学的根拠は現時点で示されていません。
ただし、脳梗塞の既往がある方や血管が脆弱な方、心疾患を合併する方では、強い振動が身体に負担となる可能性があります。
利用を検討する場合は、体調や既往歴を踏まえ、必ず主治医に相談し、医学的な観点から使用の可否を判断することが推奨されます。
以下の記事では、振動(ブルブル)マシンと脳梗塞の関係性について詳しく解説しています。
参考文献
Ten year recurrence after first ever stroke in a Japanese community: the Hisayama study|PubMed