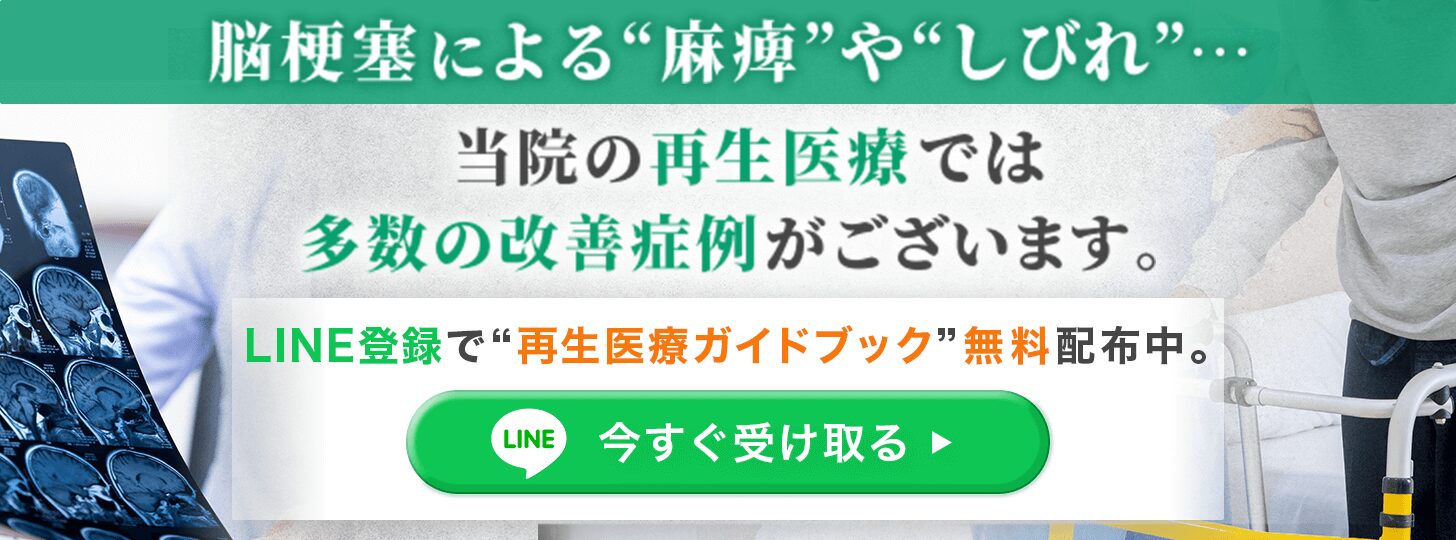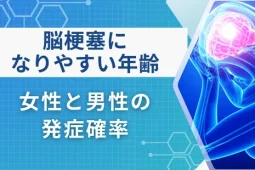- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
20代でも脳梗塞になる!確率と原因を詳しく解説【医師監修】
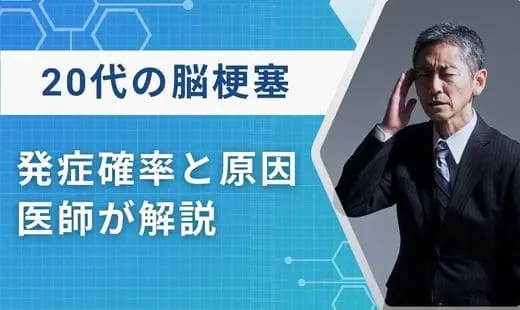
「脳梗塞は20代や30代でも発症するの?」「若いうちから脳梗塞の予防を考えるべき?」と疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。
結論からいえば、脳梗塞は20代や30代など若い人であっても起こりうる病気で、若年性脳梗塞と呼ばれることもあります。
20代・30代の若いうちから生活習慣を整え、脳梗塞の予防に努めることが大切です。
本記事では、20代の脳梗塞のリスクや予防方法について詳しく解説します。本記事を参考に、20代から脳梗塞の予防に努めましょう。
また、当院「リペアセルクリニック」では、脳梗塞の後遺症改善や再発予防として再生医療を行っています。気になる方は、当院の「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にご相談ください。
目次
20代・30代で脳梗塞になる確率は1%
脳梗塞は高齢者に多い病気ではあるものの、20代や30代でも1%の確率で発症する可能性があります。
現に、30代の脳血管患者(脳梗塞含む)は約1,000人もいるとの報告もあります。(文献1)
若年層の脳梗塞の発症は珍しいことではありません。
早期に発見できず治療が遅れると、その後の後遺症や生活へ大きな悪影響を及ぼすことも考えられます。
そのため、日常から健康に気を配ることが大切です。
「まだ20代だから大丈夫」と侮らずに、今からできる脳梗塞の予防策を実践してみてください。
脳梗塞とは「脳血管の詰まり」による脳障害
脳梗塞とは、脳にある血管が詰まることで脳への血流が途絶え、脳機能に障害が起こる病気です。
2025年1月現在、日本人の多くの死因である疾患として注目されています。
脳梗塞のタイプは大きく分けて以下の3つです。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| ラクナ梗塞 | 脳血管の中でも細い血管が詰まる脳梗塞。 無症状の場合があるものの、重要なカ所の血管が詰まると重篤になることがある。 |
| アテローム性脳梗塞 | コレステロールの塊が脳血管の中に蓄積することで生じる脳梗塞。 |
| 心原性脳梗塞 | 足や心臓など、脳以外のカ所が原因で引き起こされる脳梗塞。 |
これらの脳梗塞はいずれも血管が詰まることで発症するものの、原因が異なります。
原因や脳梗塞の範囲によって、対策方法や治療方法が異なるため、医師の指示のもとで適切な治療を受けることが大切です。
脳梗塞の症状や原因など、包括的な解説は「脳梗塞とは|症状・原因・治療法を現役医師が解説」をご覧ください。
【すぐに受診しよう】脳梗塞における3つの前兆
脳梗塞の初期症状は、主に以下の3つです。
- 顔が動かない
- 片腕が動かない
- 会話ができない
脳梗塞の後遺症は、いかに早期に発見し、迅速な治療ができるかでその後の後遺症が変わります。
本章を参考に、初期症状を事前に理解して早期に脳梗塞を疑いましょう。
1. 顔が動かない
脳梗塞の前兆として、以下のように顔面の一方に麻痺があらわれる場合があります。
- 顔の半分が下がる
- 笑顔が上手につくれない
- 片目が開きにくいまたは閉じにくい
顔面神経に近い血管が詰まることで、神経の働きが阻止されて顔面麻痺があらわれる可能性があります。
鏡をみると顔の動きに違和感があり、周囲の人に指摘されたりした場合は迷わず脳神経外科へ受診しましょう。
2. 片腕が動かない
片腕が動かなくなる症状も、脳梗塞の前兆の一つとして知られています。
具体的な症状は以下のとおりです。
- 両手を同時にあげても、片方だけ下がる
- 物を持つ動作がぎこちない
- 片腕の感覚がないまたは薄い
片腕に違和感がある場合、両腕を上げてみて片腕が垂れてこないかどうかを確認してみましょう。
3. 会話できない
以下のような言語障害も、脳梗塞の前兆です。
- いつも通り言葉が出てこない
- ろれつが回らない
- 他の人の言葉が理解できない
言語障害は自分自身で気づくこともあるものの、身近な人が会話していて異常に気がつく場合もあります。
自覚症状はもちろんのこと、他の人に言語障害の症状が見られる場合は迅速に受診を促すようにしましょう
今回解説したような前兆に早めに気がつき、すぐに処置を行うことで後遺症の悪化を防げる可能性があります。
脳梗塞の前兆についてより詳しく知りたい方は、以下のコラムを参考にしていただければ幸いです。
20代で脳梗塞になる7つの原因
20代で脳梗塞が起こる原因は、主に7つあります。
- 脂肪分や塩分の高い食品の摂取
- ストレス
- 運動不足やデスクワーク
- タバコ
- 遺伝
- 妊娠
- 女性ホルモン剤の副作用
原因に対して今からでも予防が可能です。
本章の内容が該当する方は、脳梗塞を予防するために対策をしましょう。
1.脂肪分や塩分の高い食品の摂取
20代で脳梗塞のリスクを高める大きな一因が「脂肪分・塩分の多い食品の過剰摂取」です。
2025年1月現在では、食生活の欧米化が進み、ファストフードやスナック菓子など不健康な食生活が常態化している方も多いかもしれません。
脂肪分や塩分が高い食品の一例として、以下があります。
| 脂肪分が多い食品 |
|
| 塩分が高い食品 |
|
豊富な栄養素を含んだ食事にすると、脳梗塞のリスク低減が期待できます。
今回紹介したような食品を日常的に食べている方は、頻度や量を控えましょう。
2.ストレス
ストレスも脳梗塞のリスクを増加させる一因です。
過度なストレスは交感神経を刺激し、ストレスホルモンの分泌を促します。
その結果血圧が上昇し、脳梗塞のリスクを高めてしまいます。
とくに20代や30代は仕事や学業、人間関係などでストレスを感じやすい年代です。
日頃からストレスを感じている方は、以下のようなストレス発散方法を生活に取り入れてみてください。
- 新しい趣味をはじめる
- 好きな音楽を聞く
- 自然に触れる
ストレスを管理することが、結果的に脳梗塞の予防につながります。
3.運動不足やデスクワーク
運動不足や長時間座り続ける生活は、血流を悪化させ血管内で血の塊が作りやすくなる一因です。
デスクワークなどで座りっぱなしの状態を続けると、脳梗塞リスクを高めてしまいます。
適度な運動の習慣を取り入れるのはもちろんのこと、座りっぱなしを防ぐために「こまめに立つ」方法も脳梗塞防止に効果的です。
日常的に座りっぱなしの状態が続いている方は、1時間に1回程度は立つようにしましょう。
4.喫煙
喫煙は血管に悪影響を与える代表的な習慣です。
タバコに含まれる有害物質には血管を収縮させ、血圧を上げる作用があります。
その結果、血管が硬くなる「動脈硬化」を悪化させ脳梗塞のリスクも大幅に高まることも否定できません。
若い世代であっても、喫煙習慣を続けると脳梗塞になるリスクを高めます。
必要に応じて禁煙外来の受診も検討し、早めに禁煙できるよう心がけましょう。
5.遺伝
遺伝は20代での脳梗塞発生リスクを高める原因の一つです。
とくに「親や兄弟など近親者で脳梗塞にかかった人がいる」場合、遺伝的な体質によりリスクが上昇するとの報告もあります。
遺伝による原因を取り除くのは困難であるため、生活習慣の改善や定期的な検査で早期発見を心がけることが大切です。
また、脳血管障害の一つ「もやもや病」も、遺伝が一因であるとされています。
もやもや病について詳しく知りたい方は、以下のコラムを参考にしていただければ幸いです。
6.妊娠
妊娠により脳梗塞のリスクが上がる場合があります。
とくに妊娠高血圧症候群は脳血管への負担を増すため、脳梗塞のリスクが上がると言われているのです。
また、妊娠中は出産に備えて血液が固まりやすくなるよう体質が変わります。
そのため、妊娠高血圧症にかかっていなくても注意が必要です。
妊娠中は血圧管理や定期的な検診で、脳梗塞の予防になるため、出産を控えている方は心がけてみてください。
妊娠高血圧症について詳しく知りたい方は、以下のコラムを参考にしていただければ幸いです。
7.女性ホルモン剤の副作用
女性ホルモン剤の使用も脳梗塞のリスクを増加させる要因です。
女性ホルモン剤の服用で稀に血栓症が副作用としてあらわれる可能性があるため、脳梗塞につながる可能性があります。
血栓症が報告されている女性ホルモン剤は、以下のような目的で使用されるケースが多いです。
- PMS(月経前症候群)
- 月経困難症
- 避妊
不安な方は、薬の使用前に医師から副作用について相談してみましょう。
20代の脳梗塞を予防する4つの方法
20代からできる脳梗塞の予防として、以下の4つがあります。
- バランスの取れた食事をする
- 定期的に運動する
- 禁煙する
- 定期的に検査を受ける
若年層から脳梗塞を予防するためには、生活習慣を見直し、脳血管に負担をかけないことが重要です。
本章を参考に、脳梗塞のリスクを減らしましょう。
1.バランスの取れた食事をする
若年性脳梗塞を予防するためには、食生活の改善にて動脈硬化を防ぐことが大切です。
食生活が乱れていると感じる方は、以下のような工夫で食事を見直してみましょう。
- 野菜や果物、魚を積極的に取り入れる
- スープやみそ汁の塩分を減らし、具材を多く入れる
- インスタント食品のような加工食品を食べる頻度を減らす
20代や30代は仕事や育児で忙しく、食生活が乱れがちです。
塩分や脂質の摂りすぎに注意した食生活で、脳梗塞の予防に努めてみてください。
2.定期的に運動する
運動不足は血流を悪化させ、血の塊を作りやすくして脳梗塞のリスクが上がります。
ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を定期的に行うと、脳梗塞の予防につながるでしょう。
毎日無理なく続けられる運動を取り入れることが大切です。
また、デスクワークが中心の生活を送っている場合は、1時間に1回程度こまめに立ち上がり、ストレッチを行うことで血流の改善が期待できます。
デスクワークの方は、座りっぱなしの状態を防ぐように意識してみてください。
3.禁煙
喫煙は血管を収縮させ、動脈硬化を進行させる原因になります。
そのため、喫煙している人は早めの段階で禁煙することが重要です。
自力での禁煙が難しい場合、専門機関で治療が行える「禁煙外来」の活用も選択肢のひとつです。
以下の条件すべてに当てはまる場合、禁煙外来を利用できます。(文献2)
- ニコチン依存症と診断されている
- すぐの禁煙を希望している
- 禁煙治療について説明を受けて文書により同意している
無理をせずに、専門医の力を借りて禁煙を心がけましょう。
4.定期的に検査を受ける
高血圧や糖尿病、高コレステロール血症は自覚症状がほとんどないことが多いため、脳梗塞の発見が遅れる可能性があります。
定期的な健康診断で脳梗塞を早期に発見・治療すると、脳梗塞の悪化の防止が期待できます。
「無症状だから大丈夫」と侮らず、早期に脳梗塞の原因となる芽を見つけて対策をしましょう。
まとめ|20代でも脳梗塞リスクはある!生活習慣の改善で予防しましょう
本記事では、若年層、20代でも起こりうる脳梗塞について解説しました。
20代は高齢者に比べて脳梗塞にかかる可能性は低いものの、ストレスや食生活の乱れにより突然発症する可能性も否定できません。
そして、後遺症を残してしまうことも考えられます。
普段の生活習慣を改めた上で、医療機関での検診を活用し、若い頃から脳梗塞にならないように気をつけていきましょう。
当院「リペアセルクリニック」では、脳梗塞の後遺症改善や再発予防として再生医療を行っています。
気になる方は、当院の「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
20代の脳梗塞についてよくある質問
20代で脳梗塞になったあとの再発率はどのくらいですか?
20代で脳梗塞を発症した場合の再発率は極めて少ないといわれています。
ただし、全体の脳梗塞患者における10年間の再発率は約50%であるため、若い世代でも注意が必要です。(文献3)
とくに高血圧や高コレステロール血症などの持病がある場合は、定期的な検査と治療を怠らないようにしましょう。
当院「リペアセルクリニック」で行っている脳梗塞の後遺症改善や再発予防について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
20代でも脳の検査をした方が良いですか?
家族に脳梗塞の往来歴がある方や、喫煙習慣がある方は定期的な検査をおすすめします。
また、高血圧や糖尿病など生活習慣病がある場合も同様に、定期的な検査で脳梗塞の早期発見が期待できます。
若年層でも、脳梗塞のリスクは否定できません。
定期的な検査を怠らないようにしましょう。
20代で脳梗塞で死に至る可能性はどのくらいですか?
20代の脳梗塞による死亡率は約5%未満と報告されています。(文献4)
若年層での脳梗塞による死亡率は極めて低いものの、発症後の治療までの時間が予後を大きく左右します。
脳梗塞の初期症状があらわれた際には、迷わず医療機関を受診しましょう。