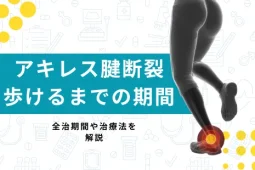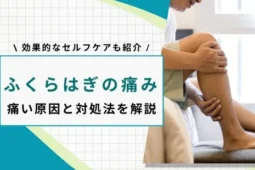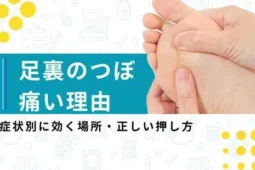- 足部、その他疾患
- 足部
【医師監修】アキレス腱断裂の保存療法|治癒過程・手術とどっちを選ぶべきかを解説

「アキレス腱断裂と診断されたが、リハビリで治したい」
「アキレス腱断裂と診断されたが、手術をすべきか悩んでいる」
アキレス腱断裂の治療では、「手術は避けたい」「できれば保存療法で治したい」と考える方が少なくありません。医師から「どちらの方法でも治せる」と説明を受けても、再断裂のリスクや回復期間、スポーツ復帰の時期などが気になり、治療法の選択に迷われる方は多いです。
保存療法(手術をしない治療)は、身体への負担が少ない利点がありますが、治癒までの期間がやや長くなる傾向があります。
手術療法は早期の回復が期待できますが、麻酔や手術に伴うリスクがあります。
それぞれに利点と注意点があるため、生活スタイルや回復後の目標に応じて、医師と相談して治療法を選択することが大切です。
本記事では、現役医師がアキレス腱断裂に対する保存療法の流れや注意点、手術との違いをわかりやすく解説します。記事の最後には、アキレス腱断裂の保存療法に関するよくある質問をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
アキレス腱断裂について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください
目次
アキレス腱断裂の保存療法とは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 治療内容 | 手術を行わず、腱の自然治癒力を利用する治療。足首をつま先が下を向く姿勢で固定し、腱の癒合を促す方法 |
| 適応となる人 | 断裂部が軽度で、断端間の距離が小さい皮下中央部断裂の場合。高齢者や手術リスクが高い方、手術を希望しない方。リハビリを継続可能な環境がある場合 |
| 適応でない場合 | アスリートや再断裂例、断端間の距離が広い症例、複雑な断裂は適応外 |
| 治療の進め方 | 医師の指導下でリハビリを段階的に導入する。装具の自己判断による中断は避ける。過度なストレッチは控える。腫れや違和感があれば早期受診、焦らず回復経過を見守ること |
アキレス腱断裂の保存療法は、手術を行わずにギプスや装具で足を固定し、腱が持つ自然な治る力で断裂部分をつなぐ治療法です。適切に行えば手術とほぼ同等の回復が期待できます。
治療初期は足首を底屈位で固定し、一定期間の後に可動域訓練や筋力回復のリハビリを段階的に行います。治療を成功させるには、固定の角度やリハビリを始める時期を守ることが大切です。
手術療法との違い
アキレス腱断裂の治療には、手術を行わず自然治癒力を活かす保存療法と、断裂した腱を直接縫合・修復する手術療法があります。手術療法は回復が早く、装具の装着期間は約6〜8週間、スポーツ復帰は3〜5カ月程度が目安です。
一方、保存療法は身体への負担が少ない反面、治癒に時間がかかり、回復までに約6カ月を要するケースが多くみられます。
アキレス腱断裂は活動的な成人に増加しており、治療法の選択は慎重な判断が必要です。再断裂率は外科的治療で約2.3%、非外科的治療で約3.9%と報告されています。(文献1)年齢や活動レベルに合わせた治療法の選択が不可欠です。
保存療法のメリット
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 手術に伴う身体的・心理的な負担が少ない | 皮膚切開や麻酔不要、術後感染や神経障害の回避、手術への不安軽減 |
| 高齢者や基礎疾患のある方でも実施しやすい | 手術リスクを避け、全身状態や持病がある方にも選択しやすい治療法 |
| 手術と同等の治療成績が期待できる | リハビリ技術や固定法の進歩により、手術と同様の機能回復が期待できる |
アキレス腱断裂の保存療法は、手術を行わずに腱の自然治癒力を活かして修復を促す治療法です。皮膚を切開せず麻酔も使用しないため、身体への負担が軽く、感染や神経障害といった手術特有の合併症を回避できます。そのため、高齢者や持病のある方にも選択しやすい治療法です。
近年は固定技術やリハビリの進歩により、手術を行わなくても良好な回復が期待でき、再断裂リスクも低減されています。(文献2)
手術に伴う身体的・心理的な負担が少ない
保存療法は、手術を行わず自然治癒力で回復を促す治療法で、身体的・心理的負担が少ない点が特徴です。切開や麻酔を行わないため、感染や術後の痛みといったリスクを避けられます。
手術への不安や傷跡の心配がなく、自宅療養や通院中心で治療を継続できます。日常生活との両立もしやすい治療法です。
高齢者や基礎疾患のある方でも実施しやすい
保存療法は、高齢者や基礎疾患のある方にも適した治療法です。手術を行わないため、麻酔や感染症といった合併症のリスクを避けられ、身体への負担を軽減できます。
切開や縫合が不要なため、体力が低下している方でも無理なく治療を続けられます。入院を必要とせず通院で治療できるため、自宅療養が可能で生活との両立もしやすい点も特徴です。
手術と同等の治療成績が期待できる
近年の研究では、保存療法でも適切な固定と早期リハビリを行うことで、手術と同等の治療成績が得られることが示されています。手術と非手術を比較した研究では、再手術率に差はあるものの、機能スコアや日常生活動作の回復度に有意な差は認められないとの報告があります。(文献3)
また、大規模データを用いた解析でも同様に、機能回復において手術と非手術で有意差がなかったとされています。(文献3)
さらに、2024年のFrontiers誌の報告では、手術群のほうが再断裂率はやや低いものの、活動復帰や機能面では両群に明確な差がない結果が示されました。(文献4)
BMC Musculoskeletal Disorders, 2025でも、非手術群でも十分な回復が得られたと報告されています。(文献5)
これらのエビデンスから、医師の管理下で適切に保存療法を進めれば、手術と同等の治癒率や機能回復を期待できることが示唆されています。
保存療法のデメリット
| デメリット | 詳細 |
|---|---|
| 再断裂や機能低下のリスクがある | 手術と比べて再断裂の可能性がやや高く、治癒過程で腱の強度が十分に戻らない場合がある治療。リハビリの進め方や固定管理が不十分な場合、機能低下を残すリスク |
| 回復に時間がかかる | 手術療法より治癒に時間を要し、装具装着やリハビリ期間が長くなる傾向。日常生活への復帰までに時間がかかる治療 |
| 復帰時期に個人差がある | 体質や年齢、リハビリの進行状況によって回復スピードに差が出やすい治療。スポーツ復帰までの期間にもばらつきがある特徴 |
保存療法は手術を行わない分、身体への負担が少ない一方で、いくつかの注意点があります。手術に比べて再断裂のリスクがやや高く、治癒の過程で腱の強度が十分に戻らない場合もあります。
回復には時間がかかり、装具の装着やリハビリ期間が長くなる傾向があり、年齢や体質によって回復や復帰時期に個人差が生じるのが特徴です。
再断裂や機能低下のリスクがある
保存療法は、手術を行わず腱の自然治癒力によって断裂部の癒合を促す治療法ですが、再断裂のリスクがやや高い点に注意が必要です。
2022年に行われた研究では、保存療法の再断裂率は6.2%、手術療法では0.6%と報告されており、一定の差があるとされています。(文献6)
また、保存療法では腱がやや伸びて治ることがあり、これにより筋力低下や関節の柔軟性の低下を生じる場合があります。
再断裂を防ぐためには、装具の正しい使用、段階的な荷重導入、医師の指導のもとリハビリが欠かせません。日常生活でも急な動作を避け、足への負担を慎重に管理することが求められます。
回復に時間がかかる
保存療法は、アキレス腱の自然治癒を促す方法であり、回復には比較的長い期間を要します。全治(完全回復)には6カ月以上かかるケースが多く、固定期間や装具装着の時間も長いため、筋力や柔軟性の回復にも時間がかかります。(文献7)
多くの症例で良好な回復が得られる一方、全力での動作やスポーツ復帰において機能回復に至らない例もみられます。
そのため、治療経過中は焦らず段階的にリハビリを進め、慎重な経過観察が必要です。手術療法ではリハビリを早期に開始できる傾向がありますが、いずれの治療法でも治癒までには時間を要する点は共通しています。
復帰時期に個人差がある
アキレス腱断裂の回復には個人差が大きく、治療法や身体の状態によって復帰時期は異なります。
保存療法では、完治までに6カ月以上かかることが多く、さらに時間を要する場合もあります。(文献7)
年齢や体力、リハビリへの取り組み方によって回復速度が変わるため、一律の期間で復帰を判断できません。
早期復帰を急ぐと再断裂の危険があるため、医師の指導に従い、自身の回復ペースで段階的にリハビリを進めることが大切です。
アキレス腱断裂の保存療法における治癒過程
| 治癒過程 | 詳細 |
|---|---|
| 受傷直後〜2週間|完全固定・非荷重期 | 足首を底屈位に固定し腱断端を密着させる期間。体重はかけず安静を保持 |
| 2〜6週間|固定継続・角度調整と保護荷重開始 | 底屈角度を段階的に緩め、軽い部分荷重開始。血流促進と組織癒合の促進 |
| 6〜12週間|部分荷重とリハビリ導入期 | 装具での部分荷重歩行開始。筋力・可動域訓練などリハビリ積極的に導入 |
| 3〜6カ月|日常生活復帰期・機能回復期 | 通常歩行が可能となり、日常生活動作の自立を目指す段階。機能改善の継続 |
| 6カ月以降|スポーツ復帰に向けた段階的訓練期 | ジョギングやスポーツ動作の段階的負荷訓練。再断裂防止の慎重な進行管理 |
アキレス腱断裂の保存療法では、受傷直後は腱の断端を安定させるためにギプスや装具で固定し、2〜6週間で角度を調整しながら徐々に荷重を開始します。
6〜12週間でリハビリを開始し、3〜6カ月で歩行と筋力を回復、6カ月以降は段階的トレーニングで再断裂防止と機能回復を目指します。各段階を医師の管理下で慎重に進めることが、良好な治癒において不可欠です。
以下の記事では、アキレス腱断裂に対するリハビリ方法を詳しく解説しています。
受傷直後〜2週間|完全固定・非荷重期
アキレス腱断裂の保存療法における受傷直後〜2週間の段階では、腱の自然治癒を促すための大切な期間です。
非手術・保存療法では、受傷後0〜2週間は足首を底屈位(つま先が下を向いた状態)で固定し、体重をかけない非荷重状態を維持するプロトコルが採用されています。(文献8)
この初期固定により、断裂した腱の断端同士が安定して接触し、修復が進みやすい環境が整います。一方、この時期に過度な動きや荷重を加えると、腱断端の離開や再断裂のリスクが高まるため、注意が必要です。
そのため、しっかりとした固定と非荷重が治癒の基本とされ、コロンビア大学整形外科の保存療法プロトコルでも受傷後0〜2週の完全固定・非荷重期間が標準的治療として推奨されています。(文献8)
2〜6週間|固定継続・角度調整と保護荷重開始
アキレス腱断裂の保存療法における2〜6週間の段階では、腱の癒合を維持しながら段階的に機能回復を進める時期です。
保存療法では、約6週間のギプス固定を基本とし、初期2週間は免荷(松葉杖)歩行、その後はギプスにヒールを付けて積極的歩行を行ったと報告されています。(文献9)
この期間は、装具の角度を調整しながら段階的に荷重を加えることで、腱の癒合を維持しつつ筋力低下や関節拘縮を防ぎ、腱修復と機能回復を促す重要な過程です。
6〜12週間|部分荷重とリハビリ導入期
アキレス腱断裂の保存療法における6〜12週間は「部分荷重とリハビリ導入期」とされ、歩行機能の回復と可動域の改善を目指します。
6〜8週目にはブーツを装着し松葉杖を併用して部分荷重を行い、8〜12週目には装具を軽くしてヒールリフト付きの靴へ移行し、活動範囲を段階的に広げます。(文献10)
痛みや腫れが落ち着けば、かかと上げや足首の屈伸運動、軽い筋力トレーニングを開始します。この時期は腱の膠原繊維が増加し抗張力が高まる生物学的回復期にあたるため、適度な荷重とリハビリによって機能回復を促し、再断裂リスクを抑える大切なプロセスです。
3〜6カ月|日常生活復帰期・機能回復期
アキレス腱断裂の保存療法における3〜6カ月は「日常生活復帰期・機能回復期」にあたります。この時期は通常の靴での歩行が可能となり、筋力強化やスポーツ復帰に向けた運動を段階的に行う段階です。
足関節の全可動域を使った抵抗運動や、片足立ち・バランスボードを用いた感覚訓練を通して、安定した動作とバランス能力を高めます。さらに、ジョギングや方向転換などのスポーツ特有の動きを取り入れることで、実践的な機能回復を目指します。(文献11)
腱の強度と柔軟性が十分に回復し、運動負荷を増やせる時期であり、再断裂を防ぎつつ活動レベルを高めるための中心的なフェーズです。
6カ月|スポーツ復帰に向けた段階的訓練期
アキレス腱断裂の保存療法における6カ月以降を日常生活復帰期・機能回復期以降のスポーツ復帰に向けた段階的訓練期とする理由は、この時期から高負荷運動(ジャンプ、スプリント、方向転換動作など)を段階的に導入できるためです。(文献12)
6カ月を過ぎると腱の強度と柔軟性が回復し、運動負荷を段階的に高めて競技動作を再現しながら筋力・バランス・俊敏性の強化を図ります。
こうした段階的訓練により、再断裂のリスクを抑えつつ、スポーツ復帰を実現できることが示されており、治癒過程の最終段階として重要視されています。
保存療法と手術療法のどっちを選ぶべきか
| 治療法 | 適用されるケース |
|---|---|
| 保存療法 | 手術リスクが高い方や活動量が少ない方に適した治療。断裂が軽度で自然癒合が見込める症例、手術を望まない方、リハビリ環境が整っている場合に選択される治療 |
| 手術療法 | 断裂の範囲が大きい、または複雑な断裂に適した治療。若年者や競技スポーツ選手で早期復帰を目指す場合、受傷から時間が経過して自然治癒が難しい症例に推奨される治療 |
保存療法は、断裂が軽度で手術リスクが高い方や、手術を望まず活動量が少ない方に適した治療です。一方、手術療法は断裂範囲が広い、または複雑な断裂、受傷から時間が経過して自然癒合が難しい場合に推奨されます。
若年者やスポーツ選手など、早期の競技復帰を目指す方にも手術が適しており、目的や身体状況に応じた治療選択が欠かせません。
以下の記事では、アキレス腱断裂後に歩けるまでどれくらいかかるかを詳しく解説しています。
保存療法が適用されるケース
| 保存療法が適用されるケース | 詳細 |
|---|---|
| 手術リスクが高い・活動量が少ない場合 | 高齢者や持病があり手術による合併症リスクが懸念される方、日常の身体活動が少ない方 |
| 断裂が軽度で保存療法でも癒合が見込める場合 | 断裂断端の間隔が小さく、皮下中央部に断裂がある状態 |
| 手術を望まない・適切なリハビリ環境が整っている場合 | 手術への抵抗感が強い方、医療機関で段階的リハビリを受けられる環境を有する方 |
保存療法は、手術を行わずに自然治癒を促す治療法であり、患者の全身状態や生活環境に応じて選択されます。高齢者や心疾患、糖尿病などで手術リスクが高い方、日常の活動量が少ない方に適しています。
また、断裂が軽度で腱の断端が近く、自然な癒合が期待できる場合にも有効です。さらに、手術を望まない方や通院・リハビリを継続できる環境が整っている方にとって、計画的に回復を目指せる治療法です。
手術リスクが高い・活動量が少ない場合
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 手術リスクの回避 | 麻酔合併症や感染症、創部トラブルのリスク回避。高齢者や基礎疾患がある方への治療手段 |
| 身体的負担の軽減 | 皮膚切開や縫合の侵襲なし。体力が落ちた高齢者や持病ある方も無理なく継続可能 |
| 活動レベルに応じた適応 | 運動量少なく日常生活中心の方に適し、治療負担やリハビリ期間の短縮につながる |
| 精神的負担の軽減 | 手術に対する恐怖や不安の軽減。非侵襲的で心理的な受け入れやすさ向上 |
(文献13)
高齢の方や糖尿病、心疾患、腎機能障害などの基礎疾患を持つ方は、麻酔や手術による合併症のリスクが高いため、保存療法が推奨されます。抗凝固薬(血液をサラサラにする薬剤)を服用している方も、出血リスクを考慮して手術を避ける傾向があります。
日常生活での活動量が少ない方や激しい運動を行わない方では、保存療法でも十分な回復が見込め、手術の早期回復よりもリスク回避を優先しましょう。
医師が全身状態や生活背景を総合的に評価し、手術による負担が大きいと判断した場合には、身体への影響を最小限に抑えられる保存療法を積極的に選択します。
断裂が軽度で保存療法でも癒合が見込める場合
断裂が軽度で腱の断端が近い場合は、保存療法でも良好な癒合が期待できます。部分断裂や断裂間隙が狭いケースでは、腱の自然治癒力によって固定のみで修復が進みやすいことが特徴です。
底屈位でのギプス固定や装具による安静管理で、血流や修復過程を妨げず安定した癒合環境を保てます。とくに高齢者や日常生活中心の方では身体への負担を抑えて無理なく回復でき、断裂の状態や生活背景に応じて医師と相談し治療法を選択します。
手術を望まない・適切なリハビリ環境が整っている場合
手術を望まない場合や、リハビリ環境が整っている場合には、保存療法が有効な選択肢となります。手術や麻酔に対する不安が強い方にとって、切開を伴わない保存療法は心理的負担が少なく、不安を軽減した状態で取り組める治療です。
医師の指導のもと、固定や荷重調整、段階的なリハビリを計画的に実施することで、手術と同等の機能回復が期待できます。また、手術を行わないため傷跡が残らず、軟部組織の柔軟性が保たれます。これにより可動域を維持しやすく、リハビリ効果の向上にもつながります。
なお、整形外科領域の臨床研究誌Orthopedic Reviewsでも、保存治療を選択する際は「患者の希望・期待・生活背景を考慮することが不可欠」と明示されており、個々の状態に合わせた治療選択が重要です。(文献14)
手術療法が適用されるケース
| 手術療法が適用されるケース | 詳細 |
|---|---|
| 断裂の程度が大きい場合や複雑な断裂 | 大きな断裂範囲や複雑で不安定な断裂状態 |
| 若年者や競技スポーツ選手で早期復帰を目指す方 | 早期の機能回復とスポーツ復帰を希望する方 |
| 受傷から時間が経過した場合 | 遅れた治療により自然癒合が難しくなった状況 |
手術療法は、断裂の程度が大きい場合や腱が複雑に損傷している場合に適した治療法です。腱の断端を直接縫合・修復し、強固な再接合を行うことで自然治癒が難しい症例にも対応できます。
若年者や競技スポーツ選手にとっては、再断裂リスクを抑えながら早期リハビリと復帰を目指せる点が利点です。また、受傷から時間が経過し腱が縮んだり瘢痕化している場合にも、腱移植や再建を含む外科的治療が必要となります。
以下の記事では、アキレス腱断裂でおこなう手術の流れについて詳しく解説しています。
断裂の程度が大きい場合や複雑な断裂
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 断端離開・ギャップが大きい場合 | 断裂した腱の端同士が離れており、自然にはくっつきにくい状態。保存療法では再断裂のリスクが高く、手術で直接縫合して確実に腱をつなぐ必要がある状態 |
| 複雑な断裂や骨付着部・裂離型断裂の場合 | 腱や骨の損傷範囲が広く、単純な固定では修復が困難な状態。縫合法や骨片固定などの外科的処置が必要となる症例 |
| 早期の機能回復・再断裂防止を目的とする場合 | 手術によって腱を正確に再建し、早期のリハビリ開始と再断裂防止を図る治療。スポーツ復帰や日常生活への早期復帰を希望する方に適した治療 |
(文献15)
断裂の程度が大きい場合や複雑な断裂では、腱の断端が大きく離れて自然な癒合が難しく、手術で直接縫合による再建が不可欠です。
とくに骨付着部の裂離や複雑損傷では縫合法・骨片固定などの外科的修復が必要で、腱を再建することで早期リハビリと再断裂予防が可能となり、早期復帰を目指す方に適します。
若年者や競技スポーツ選手で早期復帰を目指す方
若年者や競技スポーツ選手で早期復帰を目指す場合、手術療法が適用されます。これは、腱を直接縫合して強固に修復できるためです。
手術により再断裂リスクが低減し、保存療法に比べて筋力低下が少なく、ジャンプやダッシュ、方向転換などの高負荷動作にも対応しやすくなります。
複数研究をまとめたレビューでは、平均して6カ月でスポーツ復帰する例が多いと報告されており、機能回復と復帰時期の両面から手術選択が合理的とされています。(文献16)
競技復帰を目指す方にとって、確実な修復と計画的リハビリが欠かせません。
受傷から時間が経過した場合
アキレス腱断裂から時間が経過すると、腱の断端が硬くなり、周囲の筋肉も縮むことで自然な癒合が難しくなります。
その結果、腱同士の間が広がり、保存療法での回復が困難となる場合には、腱移植や腱移行術などの再建手術が必要になることがあります。
放置すると再断裂のリスクが高まり、足の可動域や筋力の回復が不十分になる恐れがあるため、早期の手術検討が必要です。手術後は早期からリハビリを行い、筋力や機能の回復を図ります。時間が経過した症例では、より高度な治療とリハビリが求められることもあります。
以下の記事では、アキレス腱が切れたときの対処法を詳しく解説しています。
保存療法で改善しないアキレス腱断裂は当院へご相談ください
アキレス腱断裂の治療には、手術療法と保存療法の2つの方法があります。どちらを選択するかは、患者の年齢、活動レベル、希望などを総合的に考慮して決定されます。
保存療法は手術や入院が不要で、費用を抑えられ、手術による合併症の心配がない点が利点です。しかし、固定期間が長くなる傾向があり、再断裂のリスクがあります。
一方、手術療法は再断裂率が低く、スポーツ復帰が比較的早いメリットがありますが、感染や神経障害など、手術に伴う合併症リスクもあります。治療法の選択にあたっては、それぞれの利点とリスクを理解した上で、医師と十分に相談しながら決めることが大切です。
アキレス腱断裂についてお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。当院では、アキレス腱断裂に対して、損傷した腱組織の修復を促す再生医療を取り入れています。従来の治療では再生が難しかった腱の損傷部位に直接アプローチし、組織の回復を促すことで、早期の機能回復を目指す治療法です。
ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。
\無料オンライン診断実施中!/
アキレス腱断裂の保存療法に関するよくある質問
治療法によってアキレス腱を再断裂する確率に違いはありますか?
再断裂率は外科的治療で約2.3%、非外科的治療で約3.9%と報告されており、非外科的治療の方が再断裂率はやや高い傾向です。(文献1)
手術は断裂した腱を直接縫合して強度を高めるのに対し、保存療法は自然治癒に頼るため回復に時間がかかり、再断裂のリスクがやや高くなります。どちらにもリスクがあるため、年齢や生活スタイル、活動レベルに応じて適切な治療法を選ぶことが大切です。
以下の記事では、アキレス腱断裂の予防方法を詳しく解説しています。
保存療法中にできること・避けるべきことは何ですか?
保存療法中は、上肢や体幹の運動で全身の筋力維持に努め、松葉杖を用いた非荷重歩行で患部への負担を避けます。
医師や理学療法士の指示に従い、痛みや腫れを確認しながら段階的にリハビリを進めることが大切です。固定中の無理な動作や自己判断での負荷増加や、喫煙・過度な飲酒は治癒を妨げるため避けましょう。
参考文献
(文献1)
Achilles Tendon Ruptures: Nonsurgical Versus Surgical Treatment|Arthroscopy
(文献2)
Achilles Tendon Ruptures: Nonsurgical Versus Surgical|PubMed
(文献3)
Operative Versus Nonoperative Treatment of Acute Achilles Tendon Rupture: A Propensity Score–Matched Analysis of a Large National Dataset|PMC PubMed Central
(文献4)
Surgical vs. nonoperative treatment for acute Achilles’ tendon rupture: a meta-analysis of randomized controlled trials|frontiersin
(文献5)
Outcomes of operative and nonoperative management of myotendinous Achilles tendon ruptures: a systematic review | BMC Part of Springer Nature
(文献6)
Nonoperative or Surgical Treatment of Acute Achilles’ Tendon Rupture | N Engl J Med
(文献7)
Achilles Tendon Ruptures | COLUMBIA ORTHOPEDICS
(文献8)
SLUCare Physician Group
(文献9)
当院でのアキレス腱断裂に対する保存療法の検討|CiNii Research
(文献10)
ACHILLES RUPTURE: NONOPERATIVE PROTOCOL|SOUTH BEND ORTHOPAEDICS
(文献11)
ACHILLES TENDON RUPTURE – NON-OPERATIVE TREATMENT REHABILITATION GUIDELINES|LONDON FOOT & ANKLE SURGERY Mr Andy Roche MSc FRCS (Tr&Orth)
(文献12)
Achilles Tendon Rupture|StatPearls [Internet]
(文献13)
Current Concepts in the Nonoperative Management of Achilles Tendon Pathologies: A Scoping Review|J Clin Med
(文献14)
National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information|J Clin Med
(文献15)
アキレス腱断裂に対する手術
(文献16)
Return to Play Post Achilles Tendon Rupture: A Systematic Review and Meta-Analysis of Rate and Measures of Return to Play|PMC PubMed Central