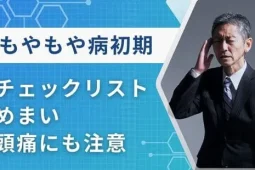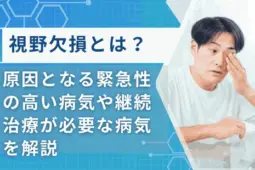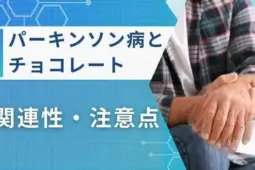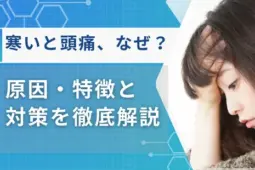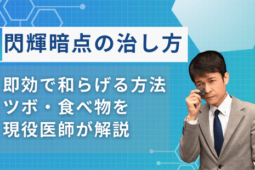- 頭部
- 頭部、その他疾患
【医師監修】もやもや病で気をつけることを状況別で解説
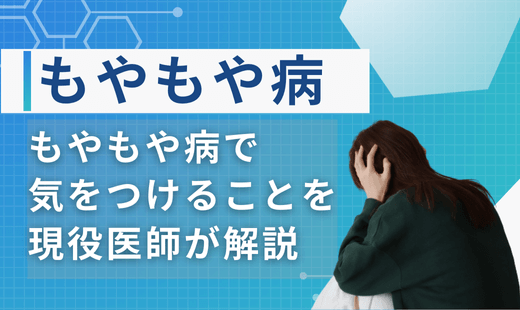
「もやもや病の悪化を防ぐには何を避けるべきか」
「日常生活でどこに注意すれば良いのか」
もやもや病は、厚生労働省が指定する難病で、脳の血管が徐々に狭くなり血流が不足することで、手足の麻痺やけいれんなどを引き起こす疾患です。正しい知識と適切な対策により、症状の進行を抑え、安定した日常生活を送ることが期待できます。
本記事では、もやもや病で気をつけるべきことを現役医師が詳しく解説します。記事の最後には、もやもや病に関するよくある質問をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
もやもや病について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
もやもや病で気をつけること|私生活
| 私生活で気をつけること | 詳細 |
|---|---|
| 異変を感じたらすぐに医療機関を受診する | 症状出現時の早期受診の徹底 |
| 生活習慣を見直す | 食事・睡眠・禁煙・節酒の維持 |
| 無理のない身体の使い方を意識する | 過度な運動・力仕事の回避 |
| ストレスに配慮する | 日常でのリラックス時間確保 |
| 体調管理を心がける | 発熱・疲労・気温変化に注意 |
もやもや病は脳の血流が不足し、さまざまな症状を引き起こす疾患です。そのため、日常生活では工夫や注意が必要です。頭痛やしびれなどの異変を感じた際は、早めに医療機関を受診しましょう。
食事や睡眠の質を整え、禁煙や節酒を心がけるなど、生活習慣を見直すことも欠かせません。また、無理な運動や力仕事を避けて体への負担を減らし、リラックスできる時間を意識して確保することも重要です。さらに、発熱や疲労、気温の変化に注意し、体調を整えることが症状の進行を防ぐ基盤となります。
以下の記事では、もやもや病の症状や治療法について詳しく解説しています。
異変を感じたらすぐに医療機関を受診する
もやもや病は脳の血流が不安定になる疾患で、突然のしびれや言葉のもつれ、視覚の異常などが発作のサインとして現れることがあります。症状が軽くても放置すると脳梗塞や脳出血に進行する危険があるため、早期に医療機関を受診することが重要です。
とくに片側のしびれや会話のしにくさは典型的な脳血管障害の兆候であり、受診の遅れは治療の選択肢を狭め、後遺症のリスクを高めます。普段と異なる違和感を覚えたときは、医療機関を受診しましょう。
生活習慣を見直す
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 血液の粘度や血流の安定 | 規則正しい水分補給・バランスの取れた食事 |
| 血管への負担軽減 | 禁煙・節酒・適量の飲酒 |
| 全身バランスの維持 | 適度な運動・十分な睡眠・ストレス管理 |
| 長期的な進行抑制 | 生活習慣改善による保存的な管理 |
生活習慣を見直すことは、もやもや病と診断された方が自分で取り組める大切なリスク管理です。水分補給や栄養状態の維持は血液が濃くなるのを防ぎ、脳梗塞や一過性虚血発作のリスクを下げる基盤になります。
禁煙や節酒は血管への直接的なダメージを防ぎ、過度な飲酒や喫煙による脳卒中のリスクを減らします。さらに、適度な運動や十分な睡眠、ストレス管理は心身のバランスを保ち、発作や症状の悪化を防ぎます。こうした取り組みの積み重ねが症状の進行を抑えることにつながるため、日常生活での意識的な改善が重要です。
以下の記事では、生活習慣改善について詳しく解説しています。
【関連記事】
脂質異常症改善のための正しい運動とお茶の選び方|生活習慣の見直しポイントを医師が解説
【医師監修】脂質異常症の診断基準|総コレステロールなど各数値の正常値と治療法を解説
無理のない身体の使い方を意識する
もやもや病は脳への血流が不足しやすく、手足の麻痺や言語障害、けいれんなどを引き起こす疾患です。そのため、日常生活では身体に無理のない使い方を意識することが重要です。
激しい運動や過度な力仕事は呼吸を乱し、脳血管の収縮を招く恐れがあります。長時間の無理な動作や過労も血圧の変動や過呼吸を招き、発作や再発の引き金になります。休憩を取り、ゆっくりと動作することが脳への血流不足を防ぐために有効です。
具体的には、急に立ち上がらず姿勢をゆっくり変える、重い荷物を無理に持たない、ウォーキングやストレッチなど軽い運動を取り入れることが推奨されます。
頭部に強い衝撃が加わるスポーツや激しい運動は避ける必要があります。体調の変化に注意し、無理のない範囲での活動が、症状の悪化や再発を防ぎ、安定した生活につながります。
ストレスに配慮する
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 血圧変動の負担軽減 | 交感神経刺激による血圧上昇抑制 |
| 過換気(過呼吸)リスクの回避 | 強いストレスによる早い呼吸回避 |
| 症状誘発要因の排除 | 血管緊張・血圧変動時の症状予防 |
| 精神的負担の軽減 | 生活の質向上・再発リスク低減 |
| 具体的な対策実施の重要性 | リラックス・休息・趣味の活用 |
ストレスへの配慮は、もやもや病の患者様が安定した日常生活を維持する上で極めて重要です。ストレスは血圧を急激に上昇させ、脳血流に過度な負担を与える要因となります。
とくに脳血管が狭窄している場合には、脳梗塞や脳出血の誘因となる可能性があり、注意が必要です。また、強い精神的緊張は呼吸を浅く速くする過換気を招き、脳血流の低下や症状の誘発につながることがあります。
これらのリスクを軽減するためには、日常生活の中で精神的負担を和らげ、リラックスできる環境や方法を取り入れることが大切です。自身に合ったストレス対処法を実践することで、症状の増悪や急変を予防し、生活の質の維持につながります。
以下の記事では、ストレスについて詳しく解説しています。
体調管理を心がける
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 疲労や睡眠不足の回避 | 免疫・循環機能の維持 |
| 水分補給と脱水予防 | 血液の濃度調整による血流改善 |
| 発熱や感染症の早期対処 | 体調悪化のリスク軽減 |
| 血圧管理の重要性 | 血圧変動の自己把握とコントロール |
| 体調変化の気づき習慣 | 微妙な症状の早期発見・受診促進 |
もやもや病は脳の血流が不足しやすく、体調のわずかな変化が症状の悪化や発作の引き金となる可能性があります。そのため、日常的な体調管理は極めて重要です。十分な休養と良質な睡眠を確保することで、血圧や呼吸の乱れを防ぎ、症状の安定につながります。
こまめな水分補給は脱水を予防し、血液の流れを保つことが脳梗塞のリスクを低減する上で重要です。発熱や感染症は血流に大きな影響を与えるため、体調不良を感じた際には早めに医療機関を受診しましょう。
また、気温の変化に注意しつつ血圧を測定するなど自己管理を習慣化するのも大切です。さらに、頭痛や倦怠感、手足の違和感といった小さな変化を記録しておくことで、早期に異常を把握しやすくなります。
もやもや病で気をつけること|仕事・人間関係
| 仕事・人間関係で気をつけること | 詳細 |
|---|---|
| 周囲への理解を得る | 疾患の状況や配慮事項の共有 |
| 無理のない働き方をする(精神的・身体的) | 負担軽減と休憩確保 |
| 急激な温度変化・過換気の回避 | 寒暖差対策と呼吸の過剰防止 |
| 人間関係のトラブル回避 | 適切なコミュニケーションと支援 |
もやもや病の患者様は、仕事や人間関係においていくつかの点に注意する必要があります。まず、疾患の状況や配慮すべき点を職場や周囲の人に共有し、理解を得ることが大切です。
精神的・身体的な負担を軽減し、無理のない働き方と十分な休憩を確保することが求められます。また、急激な温度変化には衣服で調整し、過換気を防ぐことも重要です。
さらに人間関係ではトラブルを避けるために適切にコミュニケーションを取り、必要に応じて周囲の支援を活用することが大切です。こうした配慮が症状の安定と生活の質の向上につながります。
周囲への理解を得る
| 重要性 | 詳細 |
|---|---|
| 疾患の特徴を伝え誤解を防止 | 体調変化や疲労の理解促進 |
| 仕事上の配慮を得やすくする | 休憩時間や業務内容の調整 |
| 支えと協力の輪づくり | 急な休みやサポート要請の円滑化 |
| 安定感と信頼感の向上 | 精神的負担軽減とコミュニケーション改善 |
もやもや病は外見からは判断しにくく、突然の体調変化や疲れやすさが現れることがあります。そのため、周囲に疾患の特徴や注意点を伝え、理解を得ることが重要です。
あらかじめ病状を共有しておくことで、急な症状が出た際にも誤解を避け、落ち着いた対応を受けられる可能性が高まります。また、疲労を感じやすい場合には休憩時間の確保や業務内容の調整が必要となりますが、職場の理解を得ることで配慮を依頼しやすくなります。
さらに、体調の波が大きいときには周囲の支援が欠かせません。協力を得やすい環境は心身の安定につながり、信頼関係の構築に役立ちます。仕事や人間関係を円滑に保つためには、主治医に相談し説明用資料の活用も有効です。
無理のない働き方をする(精神的・身体的)
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 身体的な無理を避ける | 休憩の確保・重い作業控える・通院を優先する |
| ストレスをためない環境づくり | 体調共有・業務調整・リラックス時間確保・支援の活用 |
| 柔軟な働き方の導入 | テレワーク・時差出勤・短時間勤務・コミュニケーション重視 |
| 体調変化の早期伝達と支援活用 | 疲労のサイン共有・限界認識・サポート制度活用 |
もやもや病の患者様が無理なく働き続けるには、身体と心の両面に配慮した働き方が必要です。疲れやすい体質を理解し、適度に休憩を取りながら長時間労働や重労働を避け、症状悪化の兆しがあれば早めに職場へ伝えましょう。
精神的な負担を減らすためには、体調や気持ちを共有し、過度な責任を抱え込まないことが大切です。リラックスできる時間を持ち、必要に応じて支援を活用するのも効果的です。
さらに、テレワークや短時間勤務など柔軟な働き方を取り入れ、体調変化を早めに共有して職場のサポート制度を活用することが、安定した就労につながります。
急激な温度変化・過換気の回避
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 過呼吸を起こす動作の回避 | 長時間の楽器演奏や激しい運動、大声の制限 |
| こまめな休憩と無理の回避 | 体調に応じた休息の確保 |
| 急激な寒暖差の環境での体調管理 | 身体を温かく保つこと |
| 精神的安定の維持 | 急な感情の高ぶりを避ける |
| 周囲へのリスク理解 | 過換気のリスク周知と支援依頼の促進 |
急激な温度変化は血管に負担をかけるため注意が必要です。夏場の屋外と冷房の効いた室内、冬場の暖房の部屋と寒い屋外の行き来では、羽織り物を用意するなど体温調節を心がけましょう。
また、過換気は脳の血管を収縮させる可能性があるため、興奮や緊張の場面では意識してゆっくり深呼吸を行い、防ぐことが大切です。
人間関係のトラブル回避
| 気をつけること | 詳細 |
| 疾患の適切な伝達 | 症状の特徴と体調の変動説明による誤解防止 |
| 感情のコントロール | 怒りや焦りの抑制による過換気防止 |
| 無理しすぎない | 体調に合わせた休息確保とストレス軽減 |
| 理解と助けの受け入れ | 早期相談と支援依頼によるトラブル予防 |
| コミュニケーション工夫 | 短時間対話やメール活用による負担軽減 |
| 周囲の理解促進と啓発支援 | 症状の理解に対する促進と説明資料共有による偏見軽減 |
もやもや病における人間関係のトラブルを避けるためには、疾患の特徴や体調の変動を周囲に適切に伝え、突然の体調不良や欠勤に対する誤解を防ぐことが重要です。
感情的になりすぎると過換気を起こしやすくなるため、できるだけ落ち着いた対応を心がけましょう。また、無理に仕事や付き合いを続けず、体調に応じて十分な休養を確保することが必要です。困難を感じた際には早めに相談し、周囲の支援を受け入れる姿勢を持つことでトラブルを未然に防止できます。
さらに、疲労が強い場合には面談時間を短縮したり、メールやメッセージを活用したりするなど、コミュニケーション方法を工夫することも有効です。周囲の理解を深めるためには、説明資料の活用や啓発活動を取り入れることが推奨され、偏見の軽減と良好な人間関係の構築につながります。
もやもや病で気をつけること|家族が発症した際の対応
| 家族が発症した際の対応 | 詳細 |
|---|---|
| もやもや病についての理解を深める | 疾患の特徴や遺伝的背景の把握 |
| ストレス・疲労をためない生活を一緒に作る | 規則正しい生活リズムと休息の確保 |
| 発作の兆候に気づけるようにする | 症状の変化や異常の早期発見 |
| 仕事・学校など周囲への説明と調整の支援 | 状況説明と環境調整の協力 |
| 自分自身(家族)のケアも忘れない | 介護負担の軽減と心身の健康維持 |
もやもや病には家族内で発症する例があり、遺伝的な素因が関与すると考えられています。家族が発症した場合は、まず疾患の特徴や背景を正しく理解することが重要です。
ストレスや疲労をためない生活リズムを一緒に整え、発作や症状の兆候に早く気づけるよう注意しましょう。さらに、仕事や学校などで周囲に説明し、環境を調整することで理解と協力を得やすくなり、生活の質の向上につながります。また、介護やサポートを担う家族自身の心身のケアも忘れず、支え合いながら疾患と向き合うことが大切です。
以下の記事では、もやもや病と遺伝の関係性について詳しく解説しています。
もやもや病についての理解を深める
もやもや病は脳の血管が狭くなり、血流が低下することで症状や体調の変動を起こしやすい指定難病です。家族がもやもや病について正しく理解することは、日常生活での支援や配慮を可能にし、患者自身の精神的・身体的負担を減らすために不可欠です。
正しい知識を共有することで誤解や不安を防ぎ、安定したコミュニケーションを保てます。患者様のできないことを責めず、支え合う姿勢を持つことは、生活の質を守り、家族の負担を軽くすることにつながります。
以下の記事では、家族がもやもや病を発症した際に起こりうることを詳しく解説しています。
【関連記事】
もやもや病になると性格が変化する?メカニズムや高次機能障害について医師が解説
ストレス・疲労をためない生活を一緒に作る
もやもや病の患者様にとって、ストレスや疲労の蓄積は症状悪化の要因となります。そのため、ご家族が生活環境を整え、無理のない生活リズムを作ることが大切です。
体調や生活のペースを尊重し、健康な人と同じ生活を無理に求めないようにしましょう。急激な温度変化や過換気を起こしやすい状況を避ける工夫も有効です。
日々の体調や疲労のサインを共有し、家族で支え合うことが精神的負担の軽減につながります。さらに、趣味やリラックスの時間を持ち、十分な休息を心掛けることも重要です。
必要に応じて医療機関やカウンセリングを利用することで、安定した生活を送りやすくなります。無理に「普通」を求めず、体調や環境に合わせて柔軟に支えることが、生活の質を守る上で大切です。
発作の兆候に気づけるようにする
| 重要性 | 詳細 |
|---|---|
| 迅速かつ適切な対応のための早期発見 | 発作の兆候を素早く見つけ、落ち着いて対応できる |
| 医療機関への速やかな受診促進 | 早期受診による重篤な合併症のリスク低減 |
| 症状状況の正確な把握と共有 | 発作頻度や状況を医師に伝え、適切な治療計画に役立てる |
| 生活の質と安定性の向上 | 生活の安定を維持 |
もやもや病は脳の血流が不足することで、しびれや脱力、言葉の障害、頭痛、けいれん、意識障害など多様な発作を引き起こします。とくに子どもでは激しい運動や過換気が誘因となりやすく、一時的に改善する場合もありますが、繰り返すことで脳梗塞へ進展する危険があります。
そのため、家族が発作の兆候を早期に察知することが極めて重要です。発作に気づくことで、冷静な対応や迅速な医療受診が可能となり、重篤化の防止につながります。また、症状の記録は診断と治療精度を高め、症状理解と体調観察は進行予防と生活安定に不可欠です。
以下の記事では、もやもや病の初期症状について詳しく解説しています。
仕事・学校など周囲への説明と調整の支援
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| もやもや病に関する理解を広げ誤解や偏見防止 | 周囲の特徴説明による休暇や配慮への理解促進 |
| 適切な環境や配慮の実現 | 勤務時間や学習環境の調整による無理のない生活サポート |
| トラブルやストレス軽減 | 誤解や摩擦の回避による環境の確保 |
| 支援の輪を広げやすくする | 具体的な支援方法の相談で協力体制の強化 |
| 本人の自己管理と生活質向上支援 | 周囲の理解により体調に応じた活動が可能となり、心身の安定と生活の質が向上 |
もやもや病の方が社会生活を続けるには、職場や学校に疾患の特性を理解してもらうことが重要です。勤務時間や学習環境の調整には、診断書や医師の意見書の活用が有効です。
家族が説明を担うことで本人の負担は軽減され、発作時の対応を共有しておけば周囲も落ち着いて行動できます。こうした取り組みにより、社会とのつながりを保ちながら体調に配慮した生活を続けやすくなり、家族が橋渡し役となることが求められます。
自分自身(家族)のケアも忘れない
もやもや病の家族ケアは長期にわたるため、支える側の心身の健康維持が不可欠です。疲労やストレスが蓄積すると冷静な対応が難しくなりますが、体調と心を整えることで適切なサポートが可能になります。
家族が健やかでいることは本人、家庭の安定にも直結します。趣味や休養、運動、睡眠を心がけ、信頼できる人や医師への相談などストレスケアを意識しましょう。また、医療機関や福祉サービスを活用することで負担を分散でき、持続的な支援につながります。
もやもや病に気をつけて異常があれば医療機関を受診しよう
もやもや病は、発作がなければ日常生活を普段通り送れることもあります。しかし、症状を放置すると脳梗塞や脳出血のリスクが高まります。
軽度のしびれや言葉のもつれ、視覚の異常といった違和感も軽視せず、早期に医療機関を受診することが重要です。
もやもや病によって引き起こされる脳出血の後遺症改善や再発予防を目的とした治療法として、再生医療という選択肢があります。
当院「リペアセルクリニック」では、幹細胞治療などの再生医療を用いて、脳の血流改善や症状の軽減を目指す治療を行っています。もやもや病に関連する脳出血に対する再生医療の治療例については、以下の症例記事をご覧ください。
ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。
\無料オンライン診断実施中!/
もやもや病に関するよくある質問
もやもや病は完治しますか?
もやもや病には現時点で根本的に完治させる方法はありません。しかし、薬物療法や血行再建術などの外科的治療により、脳の血流を補い症状の進行を抑えることができます。
適切な治療と生活管理を組み合わせることで、発作や脳卒中のリスクを減らし、日常生活を安定して続けることが期待できます。
以下の記事では、もやもや病の治療について詳しく解説しています。
【関連記事】
もやもや病の手術の難易度と成功率とは?入院期間や寿命への影響も医師が解説!
もやもや病の手術後に仕事復帰できるのはいつ?後遺症や退院後の働き方を医師が解説
もやもや病を発症すると寿命が短くなりますか?
もやもや病にかかったからといって、必ず寿命が短くなるわけではありません。もやもや病は、治療を行わず放置すると脳梗塞や脳出血のリスクが高まり、生命に関わる可能性があります。
一方で、血行再建術や薬物療法に加え、生活習慣の管理や定期的な受診を続けることで重症化を防ぎ、寿命への影響を最小限に抑えることができます。早期発見と適切な管理を行えば、健康な人と大きく変わらない生活を送れるケースも少なくありません。
もやもや病は国からの補助金などを貰うことは出来ますか?
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 指定難病としての位置づけ | 厚生労働省が認める「特定疾患(指定難病)」に含まれる |
| 医療費助成対象 | 国・都道府県による公費負担医療制度の対象 |
| 助成認定条件 | 重症度や軽症高額該当の基準を満たした場合、都道府県の審査を経て認定される |
| 小児慢性特定疾病制度の適用 | 18歳未満の患者に対し、小児慢性特定疾病医療費制度が適用される |
もやもや病は厚生労働省認定の指定難病で、公的な医療費助成の対象です。
重症度や高額医療の条件を満たせば、都道府県の審査を経て助成が受けられます。18歳未満は小児慢性特定疾病制度も適用され、医療費負担が軽減されます。申請は医師と相談し、手続きを行うことが重要です。