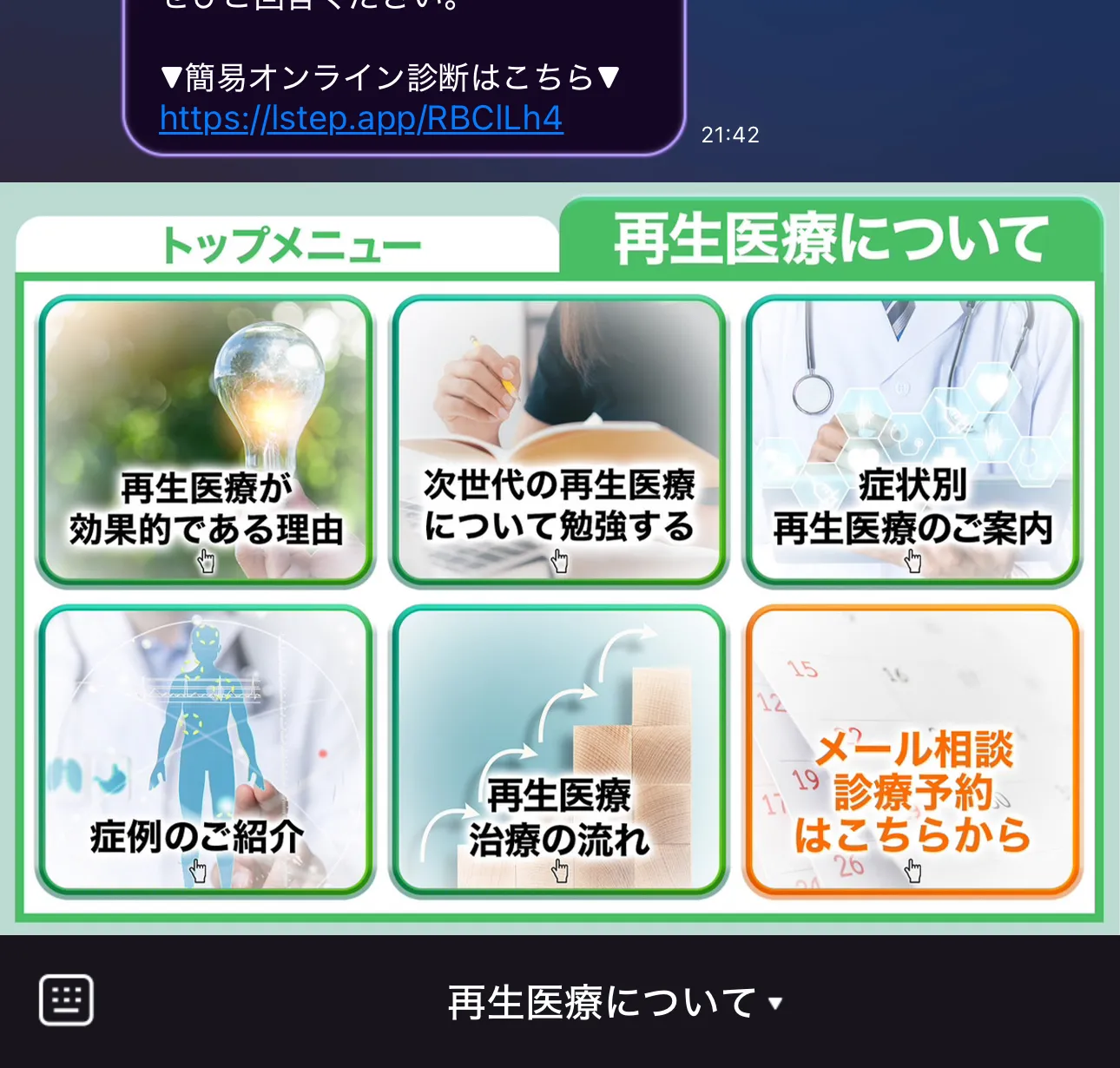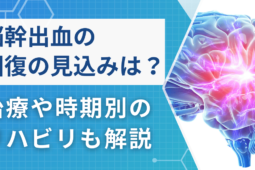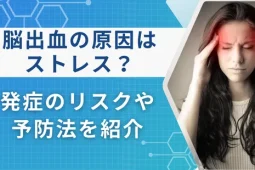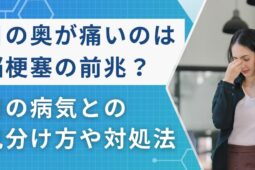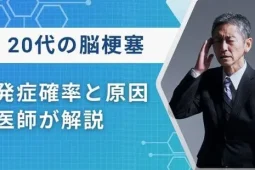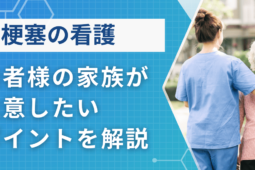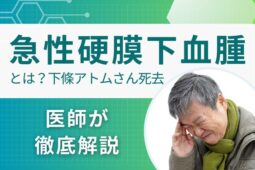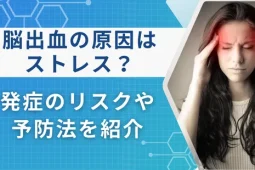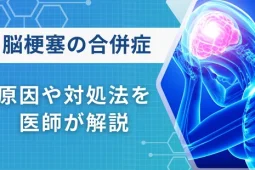- 脳卒中
- 脳出血
- 頭部
脳幹出血の原因は?今からできる予防策も解説【医師監修】
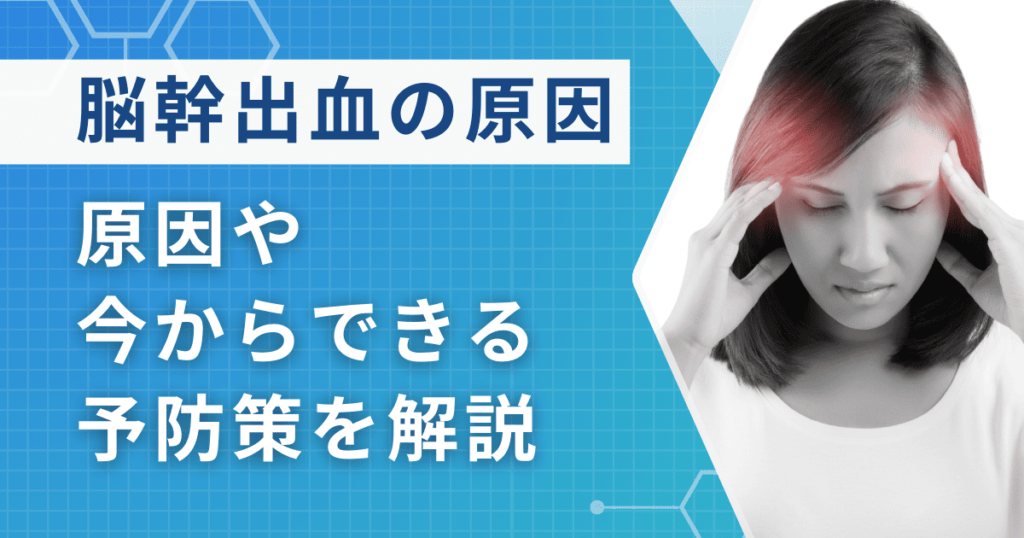
脳幹出血の原因は何?
脳幹出血にならないための予防策はある?
この記事を読んでいるあなたは、脳幹出血という病気に対して不安を抱いてるのではないでしょうか。
「今からできる予防法を知りたい」と思っている人もいるかもしれません。
結論、脳幹出血は動脈硬化が原因で起こるケースが多く、再発もしやすい病気です。しかし原因を知れば、適切な予防法を取れます。
本記事では、脳幹出血の原因や予防法について、詳しく解説します。記事を最後まで読めば、脳幹出血にならない方法がわかり、病気のリスクを軽減できるでしょう。
目次
脳幹出血とは「脳幹(中脳・橋・延髄)で起こる出血」のこと
「脳幹」は、小脳・橋(きょう)・延髄という脳の部分を合わせた部位です。「呼吸」「体温調節」「ホルモン分泌」など、人間が生きるために重要な働きをしています。
脳幹出血によってそれらの機能が損なわれると命に関わることもあるため、あらかじめ原因や予防法に関する知識をつけておくことが大切です。
本章では、脳幹の働きや脳幹出血について説明します。脳幹出血の治療や生存率については、以下の記事も参考にしてください。
脳幹は生命の維持に不可欠な働きをしている
「脳幹出血」とは、脳出血の一種です。具体的には、脳のうち「脳幹」という部位の血管が破れて出血することを指します。
脳幹は、「小脳」「橋(きょう)」「延髄」からできており、心臓や呼吸などの生命維持に大きく関わります。各部位の働きは以下のとおりです。
|
部位 |
働き |
|
小脳 |
・筋肉の緊張や姿勢をコントロールする ・注意・言語・感情などの精神機能をコントロールする |
|
橋(きょう) |
・中脳や大脳、延髄などをつないでいる ・呼吸調節に関係する |
|
延髄 |
・呼吸や心臓の動きをコントロールする ・咳、くしゃみ、発生、発汗などにも関係する |
脳内で出血すると血管からの酸素や栄養が供給されなくなり、脳はダメージを受けます。
また、脳内に血液があふれることで周りの脳細胞が圧迫される、出血により脳内の圧力が高まるなども、脳がダメージを受ける原因です。
出血により脳幹がダメージを受けると、意識不明の重体や寝たきり、ひどい場合は死に至るケースも珍しくありません。
脳幹出血は再発しやすい
脳幹出血を含む「脳出血」は、再発しやすい病気です。
具体的には、脳出血を10年以内に繰り返す確率(10年再発率)は55.6%というデータがあります。つまり、2人に1人の割合で、10年以内に脳出血の再発が起きています。(文献1)
出血によってダメージを受けた脳は、通常の医療技術による回復・修復は困難です。
また、脳出血を再発すると、初回はダメージを受けなかった部分もダメージを受けます。よって再出血時はさらに広い範囲の脳がダメージを受け、重い後遺症が出るケースもあります。
脳幹出血の主な原因は「高血圧による動脈硬化」
脳幹出血の主な原因は、「高血圧による動脈硬化」です。ただし、血圧に問題の無い人の場合、血管の奇形が原因のケースもあります。
本章の内容をもとに、脳幹出血の正しい基礎知識を身につけておきましょう。
脳幹出血後の回復については、以下の記事を参考にしてください。
動脈硬化は高血圧が原因で起こることが多い
脳幹出血を起こす「動脈硬化」は、主に高血圧によって起こると考えられています。
高血圧が動脈硬化を起こして脳幹出血に至る流れは以下のとおりです。
- 高血圧によって脳の血管に圧力がかかり続ける
- 動脈硬化が進み、血管がもろくなる
- 脳の血管が破れて出血が起こる
高血圧は「塩分の取りすぎ」「食生活の乱れ」「ストレス」「喫煙習慣」など、複数の要因が重なって起きるといわれています。(文献2)
「血圧が高くても体調は問題ない」と放置すると、脳出血につながる恐れもあるため、高血圧と診断された場合は医師の指導のもと早めに治療しましょう。
血管奇形が原因のケースもある
脳出血は、「脳動静脈奇形」という脳の血管奇形によって起こるケースもあります。脳動静脈奇形とは、脳の動脈と静脈をつなげる部分が「ナイダス」と呼ばれるとぐろを巻いたような固まり(奇形)になっている病気です。
奇形の部分は正常な血管よりも壁が薄いため破れやすく、20〜40代の若い人が脳出血になる原因の一つといわれています。
なお、奇形自体が痛みなどの症状を起こすことは、ほとんどありません。「脳出血」「頭痛」「てんかん発作」などの病気が出て見つかる、偶然受けた脳の検査で見つかるなどのケースが一般的です。
【今すぐできる】脳幹出血を予防する4つの方法
今すぐできる脳幹出血の予防方法は、以下の4つです。
- 減塩する
- 大量飲酒・喫煙を控える
- 肥満を解消する
- ストレスを溜めない
本章の内容をもとに脳幹出血の原因となる「高血圧」「動脈硬化」などのリスクを減らし、脳幹出血を予防しましょう。
減塩する
脳幹出血の大きな原因である「高血圧」の予防には「減塩」が有効です。
食塩摂取量の目標は、「健康日本21(第三次)」の目標値では7.0g未満、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」の目標量では、成人男性で7.5g未満、成人女性で6.5g未満とされています。(文献3)(文献4)
日本人は、食生活のなかで食塩の量が多くなりがちです。
以下に、厚生労働省が発信している減塩のコツを紹介します。ぜひ参考にして、毎日の食生活を見直してみてください。
|
1.漬物は控える |
自家製浅漬けにして少量に |
|---|---|
|
2.麺類の汁は残す |
全部残せば2~3gの減塩になる |
|
3.新鮮な食材を用いる |
食材の持ち味で薄味の調理 |
|
4.具だくさんの味噌汁にする |
同じ味付けで薄味の調理 |
|
5.むやみに調味料を使わない |
味付けを確かめて使う |
|
6.低ナトリウムの調味料を使う |
酢、ケチャップ、マヨネーズ、ドレッシングを上手に使う |
|
7.香辛料、香味野菜や果物の酸味を利用する |
こしょう、七味、ショウガ、柑橘類の酸味を組み合わせる |
|
8.外食や加工食品を控える |
目に見えない食塩が多く含まれている。塩干物にも注意する |
引用: e-ヘルスネット(厚生労働省)
大量飲酒・喫煙を控える
大量の飲酒は、脳出血はもちろんのこと、脳梗塞やくも膜下出血のリスクも上昇させます。お酒の飲みすぎは避けましょう。
1日あたりの飲酒量の目安を、以下に紹介します。
- ビール:中瓶1本500ml
- 清酒:1合180ml
- ウイスキー・ブランデー:ダブル60ml
また、たばこの煙に含まれる有害物質は動脈硬化を起こし、脳出血をはじめとする脳の病気のリスクを高めます。(文献5)
たとえば、たばこを吸う人は吸わない人に比べ、男性で1.3倍、女性で2.0倍脳卒中(脳出血・クモ膜下出血・脳梗塞)になりやすいというデータもあります。
お酒の飲みすぎとたばこは、どちらも控えるようにしましょう。
肥満を解消する
肥満の解消も、高血圧に伴なう動脈硬化や脳出血のリスク軽減に役立ちます。
具体的には以下の内容を試してみてください。
- 週に2~3回、20~30分程度の運動を行う(ウォーキング・息が上がらない程度のジョギング・サイクリング・水泳など)
- バランスの良い食生活を心がけ、高脂肪、高炭水化物の食事は避ける
ストレスを溜めない
過剰なストレスは血管の収縮を引き起こし、血圧を上昇させるため、脳出血の原因となります。
また、ストレスを溜めると、高血圧の原因になる暴飲暴食や過剰な飲酒、喫煙などにつながり、脳出血の間接的な原因になりかねません。(文献6)
ストレスを溜めないよう「生活習慣を整える」「困ったことがあれば誰かに相談する」などを、心がけてみてください。
脳出血とストレスの関係については、以下の記事も参考にしてください。
まとめ|生活習慣を見直して脳幹出血を未然に防ごう
本記事では、脳幹出血の概要や主な原因、予防策などを詳しく解説しました。
「脳幹出血」は脳出血の一種で、呼吸や言語機能に関連する「脳幹」から出血する病気です。最大のリスクは高血圧による動脈硬化ですが、血管の奇形によって起こる人もいます。
脳幹出血を防ぐには、高血圧にならないことが重要です。日頃から食生活や運動などに気を配ると良いでしょう。
当院「リペアセルクリニック」では、再生医療(幹細胞治療)による脳卒中の再生医療を実施しています。通常の保険診療では難しい壊れた脳細胞の再生も、再生医療なら可能です。
当院ではメール相談やオンラインカウンセリングも実施していますので、お気軽にお問い合わせください。
この記事が脳幹出血の基本的な知識を知るのに役立ち、効果的に予防できるきっかけになれば嬉しく思います。
脳幹出血についてよくある質問
脳幹出血を起こしても助かりますか。
少しでも早く治療を受けることが大切です。脳幹出血は、その部位の役割や特徴から、生命に直結する危険性もある病気です。ただ、早く治療を開始できれば、命が助かる可能性ももちろんあります。
日頃から、高血圧予防などの生活習慣改善に努め、健康診断などを受けて体調管理をしておくことがおすすめです。
脳幹出血は再発するとどうなりますか。
脳幹出血が再発すると、さらに重い後遺症が出ると考えられます。今までダメージが最小限に抑えられていた部分もダメージを受けると、より言語や呼吸の機能が低下するからです。場合によっては、命に関わるケースもあります。
再発を防ぐために、脳幹出血になったことのある人は、医師の指示にしたがってしっかりと血圧のコントロールを行いましょう。
参考文献一覧
文献1
Ten year recurrence after first ever stroke in a Japanese community: the Hisayama study J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005 Mar;76(3):368-72. doi: 10.1136/jnnp.2004.038166.
文献2
e-ヘルスネット(厚生労働省)
文献3
健康日本 21(第三次)推進のための説明資料 厚生労働省
文献4
日本人の食事摂取基準(2020 年版)厚生労働省
文献5
男女別、喫煙と脳卒中病型別発症との関係について 国立がん研究センター
文献6
舛形尚 ほか.高血圧外来患者の精神的ストレスと血圧コントロールの関係.日本病院総合診療医学会雑誌 2017:12(2)p13-17