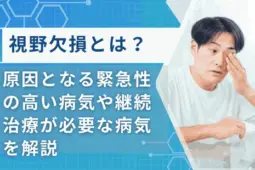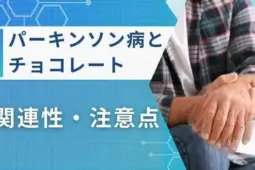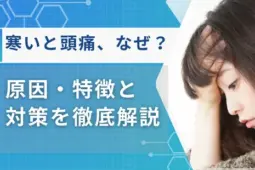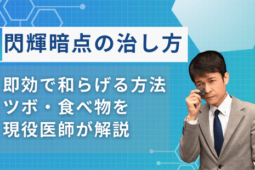- 頭部
- 頭部、その他疾患
小児もやもや病の症状|子どもと大人の違いや注意点を解説
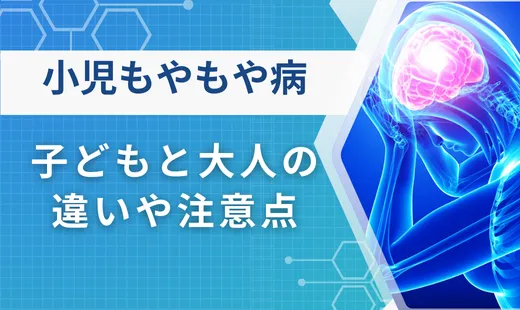
子どもがもやもや病と診断されて、困っている方もいるのではないでしょうか。
もやもや病は、脳の重要な血管である内頸動脈が細くなり、代わりに細い血管が多くなる病気です。大人と子どもでは、もやもや病の症状の出方やタイプ、そして注意点が異なります。
子どものもやもや病の症状や治療法などを知っておくと、今後病気に向き合っていく際に役に立ちます。本記事では、もやもや病の大人と子どもの違いや注意すべきポイントについて徹底解説していきましょう。
目次
もやもや病の症状|子どもと大人の違い
もやもや病は、脳の血管に生じる病気で、脳でも重要な血管である「内頸動脈」の終末部が徐々に細くなっていくのが特徴です。
脳に酸素や栄養を供給する脳血管は、血管が細くなるほど脳への血流が不足します。足りなくなった血流を補うため、内頚動脈の周囲に細い血管が網のように出現します。細い血管を脳血管撮影で映し出した際、煙のようにもやもやして見える点が、「もやもや病」の名前の由来です。
もやもや病の症状は大きく分けると、脳の血流不足である脳虚血と、発達した細い血管がちぎれて発生する脳出血が挙げられます。加えて、一時的な頭痛や言語障害などの症状が出るのも特徴です。
さらに子どもと大人とでは、症状の現れ方や注意点が異なります。
子どもの症状
子どものもやもや病は、小児もやもや病と呼ばれます。脳虚血症状がほとんどで脳出血はめったに例が見られません。
脳虚血症状では、手足の力が入らなかったりしびれたりするほか、言葉がうまく出ないなどの症状が急に起こります。
また、子どものもやもや病では、過呼吸(かこきゅう)によって脳虚血発作が誘発されやすい点も特徴的です。過呼吸は血中の二酸化炭素濃度を下げ、それにより脳血管が収縮して脳虚血発作が誘発されやすくなります。日常生活では、激しい運動や興奮状態など、呼吸が速くなる状況で注意が必要です。
一過性脳虚血発作は通常、数分から数時間で自然に回復します。ただし、これらの発作が繰り返されると脳梗塞につながる可能性があるため、軽視すべきではありません。
特に小さな子どもほど病気の進行が早い傾向があり、脳梗塞を発症するリスクが高いため、注意が必要です。
大人の症状
一方で大人のもやもや病では、脳の血流不足を補うために発達した細い血管が破れて起きる脳出血が多く見られます。
脳出血は、もやもや病による死亡や後遺症の最大の原因とされている症状です。後遺症が残った場合、脳機能の低下による高次脳機能障害や、運動障害によるマヒなどが発生するケースがあります。
また、成人のもやもや病では慢性的な頭痛を訴える患者様も多く、これも重要な症状の一つです。
もやもや病の検査
もやもや病かどうかを検査する方法は、MRI(磁気共鳴画像診断)・MRA(磁気共鳴血管造影)と脳血管造影検査(カテーテル検査)、脳血流検査の3つが代表的です。
MRI(磁気共鳴画像診断)・MRA(磁気共鳴血管造影)
MRIでは脳の断層画像を撮影し、脳梗塞や出血などの病変を確認します。
MRAでは脳血管の形態を非侵襲的に評価でき、内頚動脈終末部の狭窄や閉塞、もやもや血管の発達状況を確認できます。放射線被曝がなく、造影剤なしでも検査可能なため、小児や定期的な経過観察に適しています。
脳血管造影検査(カテーテル検査)
もやもや病の診断において重要な検査のひとつです。
足の付け根や手首から細いカテーテルを挿入し、造影剤を注入して脳血管を詳細に撮影します。
侵襲性(体への負担)があり、まれですが合併症のリスクがあるため、必要性を十分検討して実施されます。
脳血流検査
脳血流検査は、脳のどの部分にどれくらい血液が流れているかを調べる検査です。
特殊なカメラで撮影し、普通の状態と薬で血管を広げた状態の両方を調べることがあります。
この検査により、血管が血流を増やす能力を評価できます。この能力が弱い部分は将来脳梗塞のリスクが高まるため、手術が必要かどうかを判断する重要な材料になります。
症状が少ない方や手術効果の確認にも役立ちます。
小児での検査の注意点
小児では検査の協力が得られにくいため、年齢に応じた対応が必要です。
MRIやMRAでは、小さな子どもの場合、鎮静や全身麻酔を要することがあります。また、放射線被曝や造影剤使用についても配慮が必要です。
検査時の負担を最小限にするために、複数の検査をまとめて行ったり、年齢に応じた説明や準備を行うことが重要です。
もやもや病の治療
もやもや病の治療の目的は、脳梗塞や脳出血の防止です。
もやもや病を治療する方法に、薬による治療と、脳血流量を増やすためのバイパス手術があります。
薬による治療
薬による治療では、血液をサラサラにする抗血小板薬が用いられます。抗血小板薬は、血液が固まるのを防ぐとともに、血液の流れを円滑にする効果があるのが特徴です。
投薬により、一過性虚血発作を予防できます。ただし、効果が限定的であるため、次に紹介するバイパス手術が用いられるケースもあります。
バイパス手術
バイパス手術は、虚血型もやもや病の治療で、脳梗塞を予防する効果が認められています。
バイパス手術は、頭皮の血管を脳血管に直接つなぎ合わせる「直接バイパス術」と、頭皮の血管を周りの組織とともに脳の表面に接触させて、新たな血管の生成を促す「間接バイパス術」が主な方法です。加えて、両者の手法を組み合わせる「複合血行再建術」も用いられます。
大人の手術では直接バイパス術と複合血行再建術が、子どもの手術では間接バイパス術と複合血行再建術が行われます。
バイパス手術では、一過性脳虚血発作(TIA)や脳梗塞リスクなどの改善効果が報告されているのが現状です。(文献1)
小児もやもや病の注意点
子どもが小児もやもや病になった場合、脳虚血症状がたびたび見られるときは、激しい運動や楽器の演奏を控えさせる点に注意します。
激しい運動などをきっかけに、血流不足に陥るリスクがあるためです。そして、可能な限り早い段階で、子どもへの手術を主治医と相談する必要があります。
手術などの治療が終わった後は、子供の日常生活で必要以上の制限は不要です。ただ制限の要不要については、主治医との綿密な相談が大切です。
小児もやもや病になった子ども向けの就学支援
小児もやもや病の子どもは、たとえ脳梗塞などの症状がなくても、認知機能に関するさまざまな悩みを抱えることがあります。
特に計画立案や複数の課題の同時処理が難しいことがあり、学校生活に支障をきたすケースも見られます。
このような子どもたちの学校生活をサポートするため、厚生労働省の研究班による「医療関係者・教育関係者のためのもやもや病就学支援マニュアル」(2023年)が作成されました。(文献2)
このマニュアルを活用し、医療機関と教育機関が連携して支援を行う取り組みが進められています。
まとめ|もやもや病の症状は大人と子どもで異なる
もやもや病は子どもと大人で症状や注意すべき点、治療法が異なります。
いずれにしても脳梗塞や脳出血の症状が出る前に、適切な診断・治療を受けることが大切です。
また、脳卒中の後遺症に対しては、機能回復のためのリハビリテーションや再生医療による治療の選択肢があります。
再生医療をご検討方は、当院「リペアセルクリニック」でご相談ください。
もやもや病についてよくある質問
もやもや病は必ず手術しなければなりませんか?
症状が多発していない患者様であれば、すぐ手術をする必要はありません。
しかし、すでに脳虚血症状や脳血流検査での血流低下が認められる方などは、手術を勧めるのが一般的です。
また、子どもの場合は、将来の脳虚血や出血予防のために、手術による治療が広く考えられています。
以上に加えて、もやもや病の経験豊富な医師が的確な検査や年齢、患者様の状況を総合的に検討・判断していきます。
子どもの「もやもや病」の予後はどうなりますか?
子どものもやもや病は、症状のほとんどが脳虚血発作です。
このため、大きな脳梗塞が起こる前にバイパス手術を受けられれば、術後の脳梗塞の発症は少ないとされています。
また社会生活については、8割以上の子どもたちが通常の生活を送れる状況です。一方、2割弱は普通学級への就学困難や、卒業後の就職の困難が報告されています。
診断が遅れ、手術の時点で脳梗塞が起きた場合、その後の社会生活に支障が出てしまう可能性があります。そのため、早期の診断と適切なタイミングでのバイパス手術が非常に重要です。
もやもや病の検査費用はいくら?
もやもや病の検査費用は、検査の種類によって異なります。
種類別もやもや病の検査費用の相場(3割負担の場合)
- MRI・MRA検査:8,000円~2万5,000円程度
- CT検査:非造影は5,500円~8,000円程度/造影で7,500円~1万2,000円程度
ただし、具体的な金額は医療機関によって異なるため、詳しくは各医療機関にご確認ください。

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
参考文献
一般社団法人日本小児神経外科学会 「小児脳神経外科(もやもや病)」 一般社団法人日本小児神経外科学会公式サイト
http://jpn-spn.umin.jp/sick/d.html(最終チェック日 2025年3月20日)
京都大学医学部附属病院「もやもや病就学支援マニュアル」2023年.
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/department/division/pdf/moyamoya/moyamoya_web.pdf
(最終アクセス:2025年3月30日)