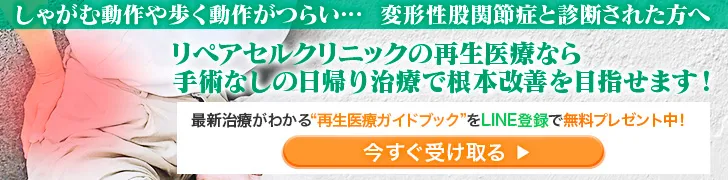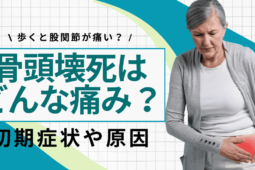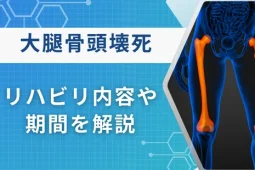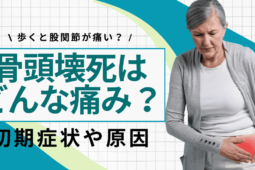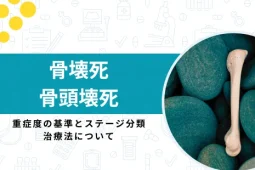- 再生治療
- 大腿骨骨頭壊死
- 股関節
大腿骨頭壊死の初期症状とは?発症後にやってはいけないことなどを現役医師が解説します!
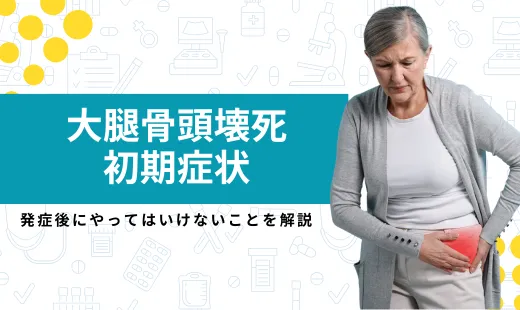
大腿骨頭壊死とは、股関節を構成している大腿骨頭の血流がなんらかの理由で途絶えてしまい、骨が壊死してしまう原因不明の難病です。
主に以下のような初期症状が見られた場合は、要注意です。
骨頭壊死による初期症状は、壊死した骨が潰れることで痛みとして現れるため、痛みを感じた時にはある程度進行している可能性が高いです。
壊死した骨は自然治癒しないため、範囲が今以上に拡大する前に適切な治療を受ける必要があります。
当院リペアセルクリニックでは、手術をせずに大腿骨頭壊死の改善を目指せる再生医療による治療をご提供しています。
壊死した骨の切除や人工関節手術を避けられる治療法として注目されている治療法なので、手術を避けたい方は、ぜひ当院までご相談ください。
▼再生医療に関するお問い合わせはこちら
>>(こちらをクリックして)今すぐ電話してみる
目次
大腿骨頭壊死とは
大腿骨頭壊死とは大腿骨頭の一部が、なんらかの原因で血流が途絶えてしまい、骨組織が壊死してしまう病気です。
大腿骨頭壊死の中でも、脱臼や骨折などで理由が明らかになっていれば「特発性大腿骨頭壊死症」と認められています。
特発性大腿骨頭壊死症に認められると、治療が長期化するだけでなく、働く能力も落ちてしまう症状も出るため、早期発見が推奨されています。
日本でも毎年2,000〜3,000人ほど特発性大腿骨頭壊死症に発症し、中でも30〜50歳の方が起こりやすい病気です。
大腿骨頭壊死の初期症状
大腿骨頭壊死の初期症状は、足の付け根が痛み、股関節の関節可動域が制限される症状が出ます。
それぞれの初期症状について、詳しく解説していきます。
足の付け根が痛む
大腿骨頭壊死の初期症状は、足の付け根が痛みはじめます。
注意点として血流が途絶えて壊死が起きるごく最初の段階では痛みは起こりません。
壊死に陥った部分に負荷が加わり、骨が潰れてくれて、徐々に痛みが出現します。
たとえば、関節に体重を乗せたり動かしたりすると、鋭い痛みを感じるケースがあります。
また、骨頭壊死が起こると痛みが出現するタイミングには時間的に差がある点に注意が必要です。
骨頭壊死はあっても、壊死の範囲が小さい場合などでは痛みを起こさない症例もありえます。
股関節の関節可動域が制限される
大腿骨頭壊死の症状が進行していくと、壊死した部分が潰れて大腿骨頭が変形します。
変形した結果、陥没した部分に関節の不適合や不安定性から軟骨のすり減りが進行してしまいます。
結果として「変形性関節症」を生じ、放置したままだと軟骨がなくなってしまうので注意が必要です。
骨同士がぶつかり、変形性関節症が悪化してしまいます。
変形性関節症が進行すると、痛みだけでなく、股関節の関節可動域が悪くなります。
股関節は曲げ伸ばしだけでなく、内旋、外旋などの動きがあるので、病気が進行すると日常生活で、以下のような困難さを感じるので注意しましょう。
|
大腿骨頭壊死で困難になる症状
|
大腿骨頭壊死は、初期症状である「足の付け根の痛み」がある段階で早めに病院で診察を受けましょう。
「どんな痛みがあるの?」「どこが痛むの?」など、より詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
大腿骨頭壊死が発症する原因
大腿骨頭壊死が発症する原因は、股関節の脱臼や骨折に続いて発症するケースがあります。
他にも以下のような症例から発症するケースもあるので、該当する病名がある方は注意してください。
- 糖尿病
- 鎌状赤血球貧血
- 腎臓病
- アルコール依存症
- 痛風
ステロイド投与による副作用や喫煙が関連する可能性もあるため、強い衝撃による損傷のような痛みから発症するわけではありません。
なお、ステロイド投与やアルコールに関しては、国際的な基準が設けられています。
詳しくは以下の記事でまとめているので、あわせてご覧ください。
大腿骨頭壊死になったらやってはいけないこと
大腿骨頭壊死が発症した場合、大腿骨頭を圧迫させないのが重要です。
股関節に体重がかからないよう、杖を使ったり長距離の歩行を控えたりするのが大切です。
大腿骨頭壊死になったらやってはいけないことを以下にまとめたので、症状を患っている方はチェックしてみてください。
【大腿骨頭壊死になったらやってはいけないこと】
- 激しい運動
- 階段の昇り降り
- 重量物の運搬
- 長時間の立ち仕事
- 体重の増加
- しゃがみこみ
- 前屈動作
- 飲酒
- 喫煙
とくに飲酒と喫煙は、壊死した骨を弱らせてしまうため、大腿骨頭壊死の進行度を早める原因になってしまいます。
大腿骨頭壊死になったら、股関節への負荷と飲酒・喫煙を控えるのが大切です。
以下の記事では、より詳しく「大腿骨頭壊死になったらやってはいけないこと」をまとめているので、ぜひご一読ください。
大腿骨頭壊死の診断方法
大腿骨頭壊死における画像検査にはレントゲンとMRI検査が有効です。
それぞれの特徴について解説していきます。
レントゲン撮影
大腿骨頭壊死でレントゲン撮影をするのは一般的な診断手法です。
大腿骨頭壊死の評価にも使用される診断方法です。
レントゲンは骨の形状や変化を評価でき、簡便なので最初の検査として行われるケースが多い傾向にあります。
しかし、大腿骨頭壊死の初期の段階ではレントゲンだけでは診断が難しいケースもあるため、医師と相談の上決めていきましょう。
MRI検査
MRI検査は大腿骨頭壊死の診断に役立ちます。
壊死の範囲を評価するだけではなく、骨折や関節炎など別の病気も診断可能になるからです。
大腿骨頭壊死の診断は、早期発見が重要になるものの、レントゲン撮影では変化が見られないケースもあるため、MRI検査が無難でしょう。
手術が必要な場合では、CT検査も必要になります。
なお、レントゲン撮影でも大腿骨頭壊死と判断つくケースもあるため、症状の進行度とともに医師と相談して判断していきましょう。
当院ではメール相談やオンラインカウンセリングも実施しているので、気になる症状がある方は気軽にご連絡ください。
大腿骨頭壊死の治療法
大腿骨頭壊死の治療法は年齢や本人の状態、病気の範囲、部位など総合的に判断して決定されます。
ここからは大腿骨頭壊死の治療法や入院期間について解説していきます。
保存療法
軽度の大腿骨頭壊死では、痛みを緩和するために安静や杖による免荷、身体活動の制限、重量物の運搬禁止などを行います。
初期症状の範囲では、関節症変化へと進まず可動域の制限も比較的保たれるため、生活指導が主な治療法です。
痛みに対しては消炎鎮痛薬の内服や湿布などを行います。
しかし、保存療法で病気の進行は防げません。
進行が考えられる状態や、進行しつつある状態のときには変形が進む前に手術を受ける方が改善する可能性は高くなります。
手術療法
手術は大きく骨を切って関節を温存する骨切り術と、壊死した骨を切除して金属に置き換える人工関節置換術に分けられます。
骨を切る手術では壊死した部分に体重がかからないように大体骨頭を弯曲させたり、回転させる手術が行われます。
骨を切った後は専用の金属で固定をするため、一定期間の安静が必要ですが、病気が進行する可能性はゼロではありません。
人工関節手術では大腿骨頭だけを置き換える人工骨頭置換術、骨盤側にも金属をいれる人工股関節全置換術があります。
基本的には手術翌日から歩行訓練が可能で、リハビリが早いメリットがありますが、人工関節のためスポーツは制限が必要であり、将来的な再手術の可能性もあります。
入院期間
大腿骨頭壊死で手術をした場合、以下の期間入院する必要があります。
|
手術法 |
入院期間 |
|
骨切り術 |
1〜2カ月 |
|
人工関節 |
2週間〜1カ月 |
大腿骨頭壊死は、骨への栄養補給する血流が途絶えて発症する病気ですが、詳しい原因は未だ不明です。
医療が進歩し、原因が判明すれば入院期間も変動する可能性もあるでしょう。
再生医療なら手術をせずに効果が期待できる!
大腿骨頭壊死は、骨切り術や人工関節手術など手術を避けたい方は、先端医療である「再生医療」も選択肢の一つです。
再生医療とは、人間の持つ再生力を活用し、損傷した骨組織の再生・修復を目指す医療技術です。
当院リペアセルクリニックでも、手術をせずに大腿骨頭壊死の改善を目指せる再生医療をご提供しています。
また、当院では患者さまから採取した細胞や血液のみを使用するため、アレルギー反応や拒絶反応のリスクが少ない治療を実施しています。
「手術を避けたい」という方は、ぜひ当院の再生医療をご検討ください。
▼再生医療に関するお問い合わせはこちら
>>(こちらをクリックして)今すぐ電話してみる
まとめ・大腿骨頭壊死は早期の発見と治療が大切!
大腿骨頭壊死症は骨を栄養している血流が途絶えて発症する、現時点でも原因が不明の難病です。
初期症状は足の付け根の痛みであり、病気が進行すると人工関節手術を受けられなくなってしまうかもしれません。
当院の再生治療は幹細胞を股関節内に投与し、軟骨の修復が可能な治療法です。
痛みでお困りの際にはいつでも気軽にご相談ください。