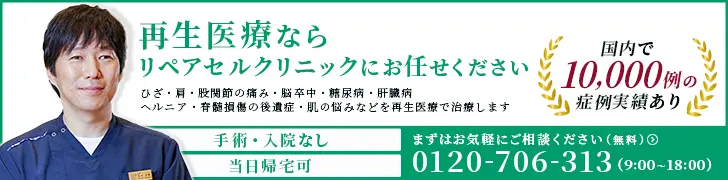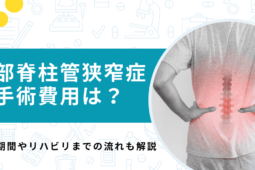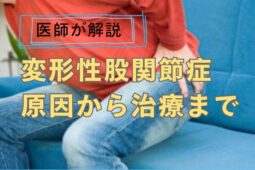- 再生治療
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 脊椎
- 脊柱管狭窄症
- 脊椎、その他疾患
坐骨神経痛とは?整形外科医がわかりやすく徹底解説!
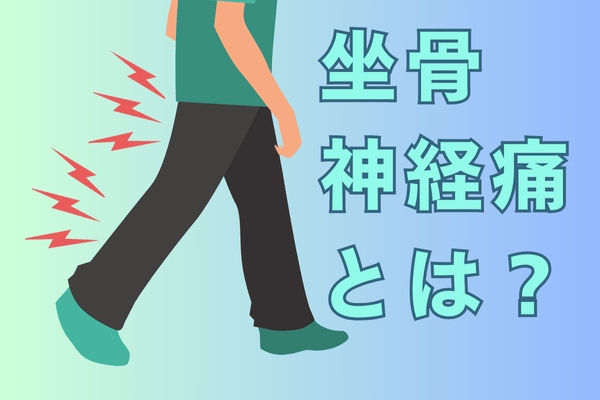
腰や足に響く激痛、痺れ、歩くのもつらい…坐骨神経痛は、人生の質を大きく奪う可能性のある疾患です。
日本人の約3~5%、年間150万人以上が悩むとされるその原因は、腰椎椎間板ヘルニア、梨状筋症候群、脊柱管狭窄症など様々。まるで電気が走るような痛み、鋭い痛み、鈍い痛み…症状も人それぞれです。
この記事では、坐骨神経痛の原因となる3つの主要疾患をわかりやすく解説します。 そして、症状、診断方法、そして薬物療法、理学療法、手術療法といった治療法を比較検討。さらに、普段の生活での注意点、効果的な運動療法、生活習慣の見直しといった予防策や再発防止策についても説明します。
あなたは、坐骨神経痛の症状に心当たりはありませんか? 日常生活に支障をきたす前に、正しい知識を身につけ、適切な対処法を選び取るための第一歩を踏み出しましょう。 この情報が、あなたの痛みからの解放、そして健康な生活を取り戻すための助けとなりますように。
目次
坐骨神経痛の主な原因と症状を理解する
坐骨神経痛とは、腰部から臀部、そして足の方まで伸びています。この神経が何かの影響で圧迫や炎症が起きると、しびれや痛みとして症状にあらわれるのです。まるで電気が走るようなピリピリした痛み、鋭い痛み、鈍い痛みなど、その感じ方は人それぞれです。さらに、温度感覚や触覚が鈍くなり、力が入りにくくなるなど、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。
この章では、坐骨神経痛の主な原因となる腰椎椎間板ヘルニア、梨状筋症候群、脊柱管狭窄症の症状について、具体的な例を交えながらわかりやすく解説します。原因を正しく理解することは、適切な治療や予防につながる第一歩です。
腰椎椎間板ヘルニアによる神経根症状
腰椎椎間板ヘルニアは、背骨の椎体と椎体の間にあるクッションの役割をする椎間板があり、その椎間板が後方に飛び出して、坐骨神経を構成する神経根を圧迫することで、坐骨神経痛を引き起こします。
例えば、転倒して尻もちをついたり、荷物を持った時に腰に激痛が走り、その後お尻や太ももにかけてしびれが広がっていくといったケースが典型的です。この場合、飛び出した椎間板が神経根を直接圧迫している可能性が高いです。
神経根への圧迫の程度によって症状は大きく異なり、我慢できる範囲のしびれだったり、耐え難い激痛で歩くことも困難になる場合もあります。咳やくしゃみをすると腹圧が上がり、症状が悪化することもあります。また、神経根が圧迫されると、足に力が入りにくくなり、つま先立ちやかかと歩きが難しくなることもあります。さらに、神経が押されている状態が続くと、筋肉が痩せてしまうこともありますので注意が必要です。
ヘルニアは、加齢による椎間板の変性によって椎間板がもろくなり、腰に負担がかかることで発症しやすくなります。何時間も椅子に座っているだけでも、椎間板への負担を増大させ、ヘルニアが出てきやすくなります。若い方でも、激しいスポーツなどで腰に過度の負担がかかった際に発症する可能性があります。
| 北米脊椎協会(NASS)のガイドラインでも、これらの要因がヘルニア発症のリスクを高めることが示されています。 |
再生医療の無料相談受付中!
リペアセルクリニックは「再生医療」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。
梨状筋症候群と坐骨神経痛の関連
股関節の後ろ側の奥の方には、梨状筋症候群があり、その中の梨状筋という筋肉が坐骨神経を圧迫することで、坐骨神経痛と同じような症状が出ます。梨状筋は、股関節を外側に回す働きをする筋肉で、そこに挟まれた坐骨神経を圧迫することで症状が現れます。
梨状筋症候群の特徴的な症状は、臀部から足の方へのしびれ感や痛みです。ヘルニアとは違い、腰の痛みはあまり見られません。
梨状筋症候群は、激しい運動や長時間のデスクワーク、足を組む癖など、梨状筋に負担がかかることで発症しやすくなります。
脊柱管狭窄症との比較
脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る神経の通り道である脊柱管が狭くなることで、脊髄の神経が押されることで足にしびれや痛みが現れます。脊柱管狭窄症による症状も坐骨神経痛と似ていますが、多少異なる点があります。
脊柱管狭窄症の代表的な症状は間欠性跛行です。何分か歩いていると、下肢がだるくなったり、痛みが出てくる現象です。両下肢同時に現れることが比較的に多いです。休むとまた歩くことができるようになります。また、前かがみになると症状が楽になる傾向があります。背中を前に曲げることで、脊髄神経を包むトンネルである脊柱管が広がり、脊髄への圧迫が弱まるからです。
一方、坐骨神経痛では、前かがみになっても痛みは軽くなりません。よく患者さんで、『歩くと足がしびれるけれど、自転車ならどこまでも行ける』という話を聞きますが、理屈はこういうことなんです。
脊柱管狭窄症は、加齢によって、脊椎という背骨が変形したり、椎間板ヘルニア、靭帯の肥厚などが原因で起こります。腰仙神経根症の主な原因である変性性脊椎関節症と関連が深いことが、医学文献でも指摘されています。 男女ともに加齢とともに発症リスクは上昇しますが、男性は40代、女性は50~60代に最も多く発症する傾向があります。
坐骨神経痛の診断方法とは?
坐骨神経痛の診断は、皆さんが抱える不安や疑問を解消し、最適な治療への道筋をつけるための大切なプロセスです。まるで探偵が事件を解決するように、医師は様々な情報や検査結果を手がかりに、痛みの原因を突き止めていきます。
問診での重要なポイント
問診は、医師と患者さんとの対話から始まる最初の診断ステップです。患者さんが感じている現在の症状について、その詳細を把握することで、医師は原因を推測し、次のステップへと繋げます。
問診では、例えば「電気が走るような痛みですか?」「縫うような痛みですか?」といったように、痛みの種類を具体的に尋ねます。これは、痛みの種類によって原因が異なる場合があるためです。鋭い痛みは神経の炎症、鈍い痛みは筋肉の緊張を示唆している可能性があります。
また、「いつから痛み始めましたか?」「どのような時に痛みが強くなりますか?」といった質問も重要です。発症時期や痛みが悪化する状況を把握することで、原因を特定しやすくなります。例えば、朝起きた時に痛みを感じやすい場合は、椎間板ヘルニアが疑われます。一方、長時間座っていると痛みが悪化する場合は、梨状筋症候群の可能性が高まります。
さらに、過去の怪我や病歴、日常生活の習慣についても質問します。一見関係ないように思える情報でも、診断の手がかりになることがあるからです。例えば、過去に腰痛やしびれがあったのかなどを聞きます。
身体検査で確認する症状
問診である程度原因を絞り込んだ後は、身体の所見を診ます。実際に患者さんの身体を診ることで、問診だけでは分からない情報を得ることができます。
例えば、足をまっすぐ上げていく検査(下肢伸展挙上テスト)では、坐骨神経が伸展されることで痛みやしびれが増強するかどうかを確認します。これは、坐骨神経痛の診断に役立つ代表的な検査の一つです。他にも、膝の反射や足の感覚、筋力などをチェックすることで、神経の損傷の程度を評価します。
これらの検査を通して、医師は神経の圧迫部位や損傷の程度を把握します。所見を取る際には、患者さんの身体に直接触れるため、医師は常に患者さんの状態に気を配りながら、痛みや不快感を与えないように配慮して行います。
画像検査の役割と種類
身体検査である程度診断がついた後、さらに詳しい情報を得るために画像検査を行います。画像検査は、身体の内部を可視化することで、問診や身体検査では分からなかった原因を特定するのに役立ちます。
検査にはX線検査、MRI検査、CT検査などがあります。
X線検査は脊椎の形やズレがないかを見ます。MRI検査では椎間板がどのくらい突出しているのか、CT検査では骨の詳細な構造をそれぞれ確認することができます。
腰仙神経根症は、神経内科医が扱う最も一般的な疾患の一つであり、筋電図検査の主要な紹介診断となっています。MRI検査では、飛び出した椎間板が神経を圧迫している様子を鮮明に映し出すことができます。また、脊柱管狭窄症に対しては、CT検査で脊柱管の狭窄の程度を正確に測定します。
画像検査の結果と問診、身体検査の結果を総合的に判断することで、坐骨神経痛の原因を特定し、最適な治療法を選択することができるのです。また、腰仙神経根症の有病率は約3~5%と推定され、男女間でほぼ同等に分布しているという疫学データも存在します。男性は40代に症状が現れる可能性が最も高く、女性は50~60代に最も多く発症します。
これらの臨床症候群の主な原因は変性性脊椎関節症であり、加齢とともに増加傾向にあります。
▼坐骨神経痛の辛い痛みを和らげる7つの治療法について、併せてお読みください。
坐骨神経痛の治療方法の比較
痛みやしびれは、日常生活に大きな支障をきたし、気分的にも不安定になります。症状も人それぞれで、電気が走るような激痛、あるいはジワジワと響くような鈍痛、感覚が鈍くなる、力が入らないなどがあります。しかし、諦めないでください。坐骨神経痛は適切な治療によって改善できる可能性が高いのです。
この章では、代表的な治療法について、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、具体的な例を交えてわかりやすく解説します。
薬物療法の効果と副作用
薬物療法は、痛みやしびれの緩和を目的とした治療法で、即効性があることが大きなメリットです。症状に合わせて、鎮痛薬、神経障害性疼痛治療薬、筋弛緩薬など、様々な種類の薬が使用されます。
また、神経の損傷による痛みやしびれには、プレガバリンやガバペンチンなどの神経障害性疼痛治療薬が使用されます。さらに、筋弛緩薬を併用することで、筋緊張を和らげ、より効果的に痛みを緩和することができます。
しかし、薬には副作用のリスクも伴います。NSAIDsは胃腸障害や腎機能障害、神経障害性疼痛治療薬は眠気やめまい、筋弛緩薬は倦怠感などを引き起こす可能性があります。副作用が心配な方は、医師に相談して、自分に合った薬を選択することが重要です。
また、薬物療法だけでは根本的な原因の解決にはならない場合もあるため、他の治療法と組み合わせて行われることが多いです。
理学療法とその効果
理学療法とは、運動や物理療法を用いて、身体の機能回復を目指す治療法です。薬物療法とは異なり、身体への負担が少なく、長期的な改善や再発予防効果が期待できることがメリットです。
種類は様々ありますが、坐骨神経痛に対しては、ストレッチ、筋力トレーニング、マニュアルセラピーなどが有効です。
例えば、梨状筋症候群では、梨状筋のストレッチを行うことで、症状を改善することができます。また、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症では、体幹の筋力トレーニングを行うことで、腰部を安定させて椎間板の突出を防ぎ、神経症状を抑える効果があります。
| 2020年の研究では、坐骨神経痛に対する理学療法の効果が示されており、特に運動療法は痛みの軽減や身体機能の改善に効果的であることが報告されています。 |
理学療法は、継続して行うことで効果を発揮するため、根気強く取り組むことが大切です。
手術療法が必要な場合の基準
坐骨神経痛のほとんどは、保存療法でかなり症状が改善されます。しかし、保存療法で効果がない場合や、馬尾症候群のように、膀胱直腸障害や下肢の麻痺といった重篤な神経症状が現れた場合は、緊急手術が必要になります。これは、神経の圧迫が長時間続くと、不可逆的な神経損傷を引き起こす可能性があるためです。
しかし、手術療法は、根本的な原因を取り除くことができるというメリットがありますが、身体への負担が大きく、入院が必要となる場合もあります。
また、手術したからといって、痺れや筋力低下が確実に治るわけではありません。逆に、手術前にはなかった症状が術後に現れる場合もあります。それだけ神経の治療は難しいということです。
『脊椎の手術をしたけれど、しびれや痛みがさらに悪くなった』『手術をしたので、これ以上の治療はできないとかかりつけ医に言われた』という患者さんがよく来院されます。当院では、このような患者さんに対して、国内ではほとんど行われていない『幹細胞による脊髄腔内へのダイレクト注射』を行なっています。これは、厚生労働省の届出及び認可が必要で、今注目されている再生医療という治療です。
どの治療法を選択するかは、患者さんの症状や状態、生活スタイルなどを考慮しながら、医師とよく相談して決定します。それぞれの治療法にはメリット・デメリットがあるため、医師から十分な説明を受け、納得した上で治療を受けることが重要です。
再生医療の無料相談受付中!
リペアセルクリニックは「再生医療」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。
坐骨神経痛の予防と再発防止策
坐骨神経痛の再発は、本当につらいものです。あの電撃のような痛みやしびれ、一度経験した方なら、もう二度と味わいたくないと強く願うでしょう。私も医師として、多くの患者さんの苦痛を目の当たりにしてきました。しかし、諦めないでください。適切な予防策と再発防止策を実践することで、坐骨神経痛を克服し、快適な生活を取り戻すことは十分に可能です。
この章では、日常生活での注意点、運動療法、普段の生活の見直しについて、具体的な例を交えながらわかりやすく解説します。一緒に、坐骨神経痛に負けない身体づくりを目指しましょう。
日常生活での注意点
日常生活における些細な習慣が、坐骨神経痛の予防と再発防止に大きく関わっています。まるで堤防の小さなひび割れが、いずれ決壊を引き起こすように、毎日の何気ない動作や姿勢の積み重ねが、のちに神経症状の発症につながってくるのです。
まず、正しい姿勢を意識しましょう。立っている時は、背筋を伸ばし、お腹に軽く力を入れて体幹を安定させることが重要です。
猫背は脊椎に負担をかけ、坐骨神経を圧迫する原因となります。逆に、反り腰も腰椎に過度な負担をかけるため注意が必要です。
座る時は、深く腰掛け、背もたれに寄りかかるようにしましょう。浅く座ったり、足を組む癖は、骨盤の歪みや梨状筋の緊張を招き、坐骨神経痛の損傷にながります。
荷物を持ち上げる時も気をつけましょう。腰を曲げて持ち上げるのは、椎間板に負担をかけてしまいます。なるべく腰は真っ直ぐにして、膝を曲げて持つようにしましょう。デスクワークが多い方は、1時間に1回は立ち上がって軽いストレッチや散歩をとりいれるなど、体を動かす習慣を身につけましょう。長時間の座位は、血行不良や筋肉の緊張を招き、坐骨神経への負担を増大させます。
▼坐骨神経痛でやってはいけないこと9選!併せてお読みください。
効果的な運動療法とは
坐骨神経痛の予防と再発防止には、適度な運動が不可欠です。運動不足は筋力の低下を招き、腰椎の安定性を損ないます。腰に負担の少ない、ウォーキングや水泳、サイクリングなどの有酸素運動がおすすめです。
ウォーキングは、1回30分程度、週に3回以上を目標に行いましょう。水泳は、水中では浮力によって腰への負担が軽減されるため、痛みがある方でも比較的行いやすい運動です。
また、ストレッチやヨガなども、筋肉の柔軟性を高め、血行を促進する効果があります。入浴後など、体が温まっている時に行うと、さらに効率が良くなります。
ヨガは、呼吸法と合わせて行うことで、心身のリラックス効果も期待できます。初心者の方は、インストラクターの指導のもとで行うようにしましょう。プールの中で行う水中ウォーキングは、水の抵抗によって筋力トレーニングの効果も得られます。
| 理学療法士による指導に基づいた運動療法は、腰の負担がかからず、神経痛に有効であることが報告されています(Physiotherapy management of sciatica. Journal of physiotherapy 66, no. 2 (2020): 83-88.)。 |
理学療法士は、個々の患者さんの状態に合わせた適切な運動プログラムを作成し、指導してくれます。
生活習慣の見直しポイント
坐骨神経痛の予防と再発防止には、生活習慣の見直しも欠かせません。健康的な生活習慣は、身体の機能を正常に保ち、自己治癒力を高める上で非常に重要です。
まず食事の管理を行い、適正体重を維持しましょう。肥満は腰への負担を増大させ、糖尿病や高血圧などの生活習慣病にも繋がります。野菜、果物、魚、肉などをバランス良く摂取し、栄養バランスの取れた食生活を送りましょう。
喫煙は血行を悪化させ、組織の修復を阻害するため、禁煙することも大切です。
質の高い睡眠を確保することも重要です。睡眠不足は、身体の回復力を低下させ、痛みを悪化させる可能性があります。毎日同じ時間に寝起きし、規則正しい睡眠リズムを保つようにしましょう。
これらの生活習慣の改善は、健康全般の増進にも繋がります。日々の生活の中で、少しずつ意識的に改善していくことで、健康で快適な生活を送ることができるでしょう。
再生医療の無料相談受付中!
リペアセルクリニックは「再生医療」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。
参考文献
- Kreiner DS, Hwang SW, Easa JE, Resnick DK, Baisden JL, Bess S, Cho CH, DePalma MJ, Dougherty P 2nd, Fernand R, Ghiselli G, Hanna AS, Lamer T, Lisi AJ, Mazanec DJ, Meagher RJ, Nucci RC, Patel RD, Sembrano JN, Sharma AK, Summers JT, Taleghani CK, Tontz WL Jr, Toton JF and North American Spine Society. “An evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of lumbar disc herniation with radiculopathy.” The spine journal : official journal of the North American Spine Society 14, no. 1 (2014): 180-91.
- Tarulli AW and Raynor EM. “Lumbosacral radiculopathy.” Neurologic clinics 25, no. 2 (2007): 387-405.
- Bastos RM, Moya CR, de Vasconcelos RA and Costa LOP. “Treatment-based classification for low back pain: systematic review with meta-analysis.” The Journal of manual & manipulative therapy 30, no. 4 (2022): 207-227.
- Ostelo RW. “Physiotherapy management of sciatica.” Journal of physiotherapy 66, no. 2 (2020): 83-88.
監修者

坂本 貞範 (医療法人美喜有会 理事長)
Sadanori Sakamoto
再生医療抗加齢学会 理事
再生医療の可能性に確信をもって治療をおこなう。
「できなくなったことを、再びできるように」を信条に
患者の笑顔を守り続ける。