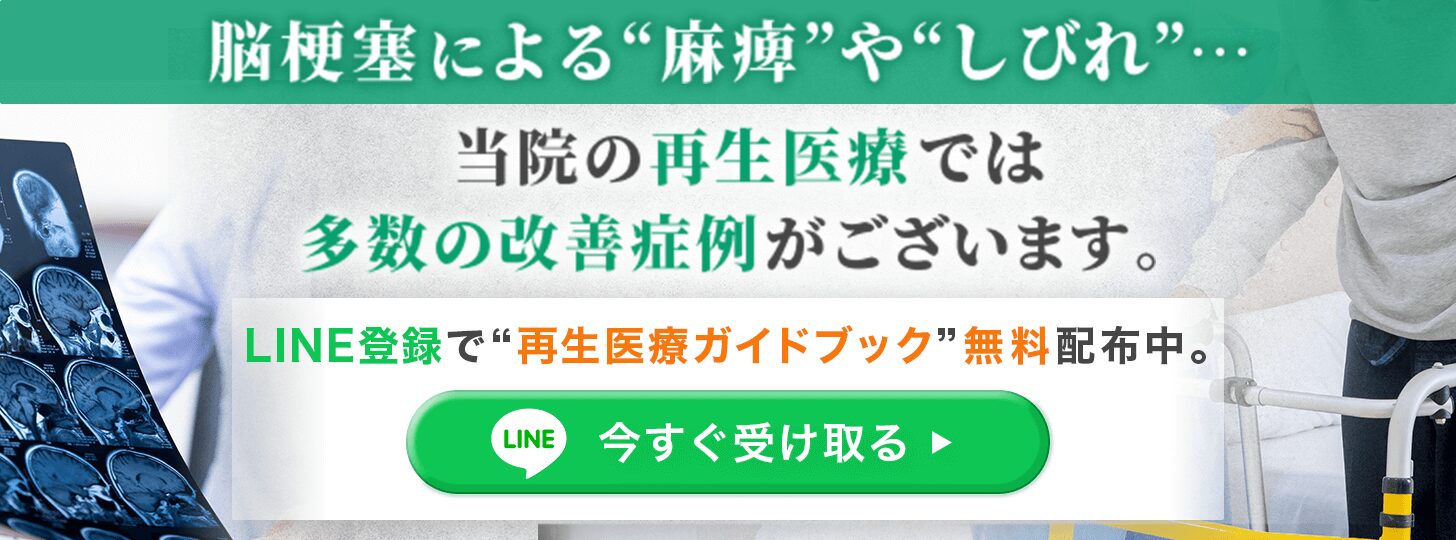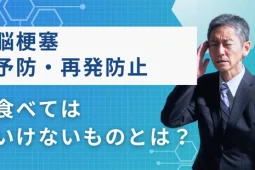- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
心原性脳梗塞の症状を医師が解説|原因や治療法もあわせて紹介

「突然、片側の手足に力が入らなくなった」
「最近呂律が回らず、うまく話せなくなった」
それらの症状は、心原性脳梗塞の可能性があります。心原性脳梗塞は、心臓内で生じた血栓が血流に乗って脳の血管を詰まらせることで発症します。本記事では、心原性脳梗塞について詳しく解説していきます。
- 心原性脳梗塞の症状
- 心原性脳梗塞の原因
- 心原性脳梗塞の治療法
異変を感じた段階で、早期に適切な治療を受けることが大切です。本記事の最後には、心原性脳梗塞に関するよくある質問もまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
心原性脳梗塞の症状
| 症状 | 主な症状 | 特徴・解説 |
|---|---|---|
| 顔面麻痺・手足の痺れ | 顔の片側が動かしにくい、手足の力が入らない、感覚が鈍い | 片側に出やすく、日常生活への影響が大きい |
| 構音障害 | 話しにくさ、言葉が出ない、相手の話が理解できない | 言語機能の障害によるコミュニケーションの困難 |
| 視覚障害 | 視野が狭くなる、物が二重に見える、片目の視力が低下する | 突然の視覚異常による事故や転倒の危険 |
| 高次機能障害 | 記憶力や判断力の低下、注意力の散漫、感情の不安定さ | 脳の機能低下による日常動作や思考の変化 |
心原性脳梗塞は突然発症するケースが多く、本人や周囲が初期症状に気づきにくいこともあります。顔の片側が動かなくなる、手足の痺れ、言葉が出にくい、視界の異常などの症状が現れます。
心原性脳梗塞は、発見が遅れると後遺症のリスクが高まるため、異変を感じた段階で早めに医療機関を受診するのが大切です。
以下の記事では、脳梗塞の症状の対策について詳しく解説しています。
【関連記事】
脳梗塞は症状が軽いうちの治療が大切!原因と対策を解説【医師監修】
脳卒中と脳梗塞の違いは?前兆の症状や後遺症をわかりやすく解説
顔面麻痺・手足の痺れ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原因 | 心臓の血栓が脳の太い血管を詰まらせ、感覚を司る領域への血流が遮断される |
| 障害部位 | 大脳半球の感覚野(頭頂葉) |
| 痺れの仕組み | 神経細胞が酸素不足になり、感覚の信号が伝わらなくなる |
| 出方の特徴 | 顔・手・足の片側に痺れが出る(障害された脳の反対側に症状が現れる) |
| 麻痺との関係 | 感覚野と運動野が近く、痺れと麻痺が同時に出ることが多い |
| 重症化しやすい理由 | 心原性の血栓は大きく、広い範囲で痺れが強く出やすい |
| よく詰まる血管 | 中大脳動脈(MCA) |
脳の一部に血流障害が起こると、身体の左右どちらかに麻痺や痺れが現れるケースがあります。とくに顔の片側がゆがんだり、腕や脚に力が入らないといった症状は、心原性脳梗塞を疑うべきサインです。
顔面麻痺や手足の痺れは前兆なく突然起こることも多く、日常動作に支障をきたすため、早期の診断と対応が必要です。
構音障害
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原因 | 心臓の血栓が脳の太い血管を詰まらせ、言語や発声に関わる部位が障害される |
| 障害される部位 | ブローカ野、運動野(顔面領域)、延髄などの脳幹 |
| 症状の内容 | 発音が不明瞭になる、声が出しづらい、言葉が滑らかに出ない |
| 失語症との違い | 構音障害は発音の仕方に問題があるのに対し、失語症は言葉の意味を理解したり表現したりする能力に障害が出る状態 |
| 構音障害と失語症が併発する可能性 | 構音障害と失語症が同時に起こるケースもある |
| よくある日常のサイン | ろれつが回らない、電話で何を言っているか聞き返される、言葉がつっかえる |
構音障害とは、言葉を発する際にうまく発音できない状態です。舌や唇、口の動きがうまくいかず、音を正確に発音できなくなります。
心原性脳梗塞では、このような話しづらさは発症直後に現れることが多く、本人や周囲も異変に気づきやすいのが特徴です。発音に違和感を覚えたり、ろれつが回っていないと指摘されたりした場合は、ためらわず早めに医療機関を受診しましょう。
視覚障害
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原因 | 心臓から飛んだ血栓が、視覚をつかさどる脳の血管を詰まらせる |
| 障害される部位 | 後頭葉や視神経を支配する動脈(例:後大脳動脈) |
| 代表的な症状 | 両目の片側の視野が見えない(同名半盲) |
| 一時的な視力障害 | 数秒~数分間、片目が真っ暗になる感覚(過性黒内障) |
| 物が二重に見える症状 | 脳幹や小脳が障害されることで起こる複視 |
| 空間感覚の異常 | 距離感がつかみにくくなり、物との位置関係がわかりにくくなる |
心原性脳梗塞で視覚をつかさどる脳の部位が障害されると、視野が欠ける、物が二重に見えるなどの異常が突然現れることがあります。
本人が気づかないケースもありますが、まばたきや目の動きに違和感が出ることがあります。視野が狭まるなどの異常が続く場合は、脳の異常も考え、早めに医療機関を受診しましょう。
脳の高次機能障害
| 主な症状 | 特徴 |
|---|---|
| 記憶障害 | 新しい情報が覚えられない、過去の記憶を思い出しにくい状態 |
| 注意障害 | 集中力の低下、注意の持続が難しい、気が散りやすい状態 |
| 遂行機能障害 | 計画や段取りの困難、手順通りに行動できない状態 |
| 言語障害(失語症) | 言葉が出ない、話す・聞く・読む・書くことの困難 |
| 社会的行動障害 | 感情のコントロールの難しさ、衝動的・不適切な行動 |
心原性脳梗塞では、心臓から流れた血栓が脳の太い血管を塞ぎ、広い範囲の脳組織がダメージを受けることがあります。とくに中大脳動脈が詰まると、記憶や判断、注意、言語、感情などをつかさどる領域が障害され、高次脳機能障害が現れることがあります。
物忘れや段取りの悪さといった症状は、加齢と勘違いされやすいため、見逃されやすいのが特徴です。認知機能の低下に気づいた際には、脳梗塞の可能性も考え、早急に医療機関を受診しましょう。
心原性脳梗塞の原因
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 心房細動 | 心臓が不規則に動き、血栓ができやすくなる不整脈 |
| 心臓弁膜症 | 弁の異常により血液の流れが乱れ、血栓ができやすくなる状態 |
| 心筋梗塞 | 心筋の壊死によって心臓の機能が低下し、血栓が発生しやすくなる状態 |
| 拡張型心筋症 | 心臓の筋肉が弱まり、血液が滞って血栓ができやすくなる病気 |
| 卵円孔開存 | 心房の間に残った穴を通して、血栓が脳に流れ込む状態 |
| 感染性心内膜炎 | 心内膜や弁にできた感染性の塊(疣贅)が血流に乗って脳の血管を詰まらせる状態 |
心原性脳梗塞は、心臓で生じた血栓が血流に乗って脳へ到達し、血管を詰まらせることで発症します。発症の背景には、心房細動や心筋梗塞、心臓弁膜症など、心臓の機能に関わる病気が関係しているケースが多く見られます。
とくに心臓に不整脈や異常を指摘されたことがある方は、脳梗塞のリスクが高まるため注意が必要です。
以下の記事では、脳梗塞になりやすい人の特徴をわかりやすく解説しています。
心房細動・弁膜症
| 項目 | 心房細動が原因となる理由 | 弁膜症が原因となる理由 |
|---|---|---|
| 主な特徴 | 心房が細かく震える不整脈 | 心臓の弁が狭くなる・閉じにくくなる病気 |
| 血液の流れへの影響 | 心房の収縮が弱くなり、血液が滞りやすくなる | 弁の異常で血液の流れが乱れ、特定部位で血液がよどみやすくなる |
| 血栓ができやすい理由 | 滞留した血液が固まり、心房内に血栓ができやすくなる | 血流の乱れと心房の拡大が血栓形成を促進 |
| とくに血栓ができやすい部位 | 左心耳(左心房の袋状の部分) | 拡大した心房内や人工弁の周辺 |
| 脳梗塞が起きる仕組み | 心房内の血栓が全身へ流れ、脳の血管を詰まらせる | 弁膜症により生じた血栓が血流に乗って脳へ運ばれ、血管を詰まらせる |
| 弁膜症との関連 | 弁膜症が原因で心房細動を引き起こすこともある | 心房細動を合併することで、さらに脳梗塞リスクが高まる |
| 治療や注意点 | 抗凝固薬の服用が必要になることが多い | 人工弁使用時は生涯にわたる抗凝固療法が必要 |
心房細動は心臓が不規則に動く不整脈で、心房内に血液がよどみ、血栓ができやすくなります。この血栓が脳に流れると心原性脳梗塞を引き起こします。
高齢者に多い心房細動や弁膜症は自覚しにくく、いずれも脳梗塞のリスクが高いため、心電図や心エコーなどによる定期検査と、循環器内科での継続的な管理が欠かせません。
心筋梗塞・拡張型心筋症
| 項目 | 心筋梗塞が原因となる理由 | 拡張型心筋症が原因となる理由 |
|---|---|---|
| 主な特徴 | 冠動脈の詰まりによる心筋の壊死 | 心室の拡大と収縮力の低下 |
| ポンプ機能への影響 | 心室の動きが悪くなり、血液が滞りやすくなる | 心臓の収縮力が弱まり、血液が心室内に滞留しやすくなる |
| 血栓ができやすい部位 | 壊死した心筋や心室瘤の部分に血液が淀みやすく、血栓が形成されやすい | 拡張した心室内で血液がよどみ、血栓ができやすくなる |
| 合併の多い不整脈 | 心房細動を伴うことがあり、さらに血栓リスクが上昇 | 心不全や不整脈を伴うことが多く、血栓形成の危険性が高い |
| 脳梗塞が起きる仕組み | 心室内の血栓が全身に流れ、脳の血管を詰まらせる | 心臓内でできた血栓が脳に流れ込み、血管を詰まらせる |
心筋梗塞や拡張型心筋症は、心臓の収縮力が低下し、血液が滞ることで血栓ができやすくなります。この血栓が脳に流れると心原性脳梗塞を引き起こす原因になります。
これらの心疾患は見逃されやすいため、心電図や心エコーなどの検査で異常を早期に見つけ、速やかな対処が大切です。心臓病のある方は、心原性脳梗塞など脳の異常にも注意が必要です。
卵円孔開存
卵円孔開存(PFO)は、胎児期に心房をつないでいた通路が出生後も閉じずに残っている状態です。多くは無症状ですが、まれに静脈の血栓がこの穴を通って脳に流れ、脳梗塞を引き起こすことがあります。
「奇異性脳塞栓症」と呼ばれており、とくに若年者で原因不明の脳梗塞が起きた場合、卵円孔開存(PFO)が関係している可能性があるため、心臓の検査が重要です。再発リスクが高い場合は、経過観察やカテーテルによる閉鎖術が検討されます。
感染性心内膜炎
感染性心内膜炎は、心臓の内膜や弁に細菌が感染する病気です。細菌の塊(疣贅)が血流に乗って脳の血管を詰まらせ、心原性脳梗塞を引き起こすケースがあります。
人工弁や先天性心疾患がある方はリスクが高く、歯科治療や手術がきっかけになる場合もあるのが特徴です。発熱、倦怠感、心雑音が続く場合は早めに医療機関を受診する必要があります。
また、診断には血液検査や心エコー(とくに経食道エコー)が有効で、治療は抗菌薬が中心です。重症例では手術が必要になることもあります。
心原性脳梗塞の治療法
| 治療法の種類 | 内容 |
|---|---|
| t-PA静注療法・血管内治療 | 発症早期に行う血栓溶解薬の投与やカテーテルによる血栓除去 |
| 抗凝固薬(ワルファリン、DOACなど) | 血液を固まりにくくし、再発を防ぐための内服治療 |
| 原因疾患の治療(心房細動の管理など) | 心房細動や弁膜症などの心疾患に対する薬物治療や手術 |
| リハビリテーション | 麻痺や言語障害の回復を目指す理学療法・作業療法・言語療法 |
| 再生医療 | 神経機能の回復を目指した新しい治療法の研究・臨床応用 |
心原性脳梗塞の治療は、発症直後の血栓除去と再発予防を目的に行われます。
急性期にはt-PAや血管内治療を行い、以降は抗凝固薬で血栓の再発を防ぎます。脳の障害に応じたリハビリも不可欠です。脳と心臓の両面から総合的に治療を進めていきます。
以下の記事では、脳梗塞は治るのかについて詳しく解説しています。
t-PA静注療法・血管内治療
| 項目 | t-PA静注療法 | 血管内治療 |
|---|---|---|
| 治療内容 | 血栓を溶かす薬(t-PA)を静脈から投与して血管の再開通を図る | カテーテルを使って血栓を直接回収または吸引し、血流を再開させる |
| 主な作用機序 | プラスミノーゲンを活性化し、プラスミンが血栓を分解 | 機械的に血栓を取り除く(ステントリトリーバー・吸引カテーテルなど) |
| 対象となる血栓 | 比較的小さめの血栓に有効 | 太く大きな血栓やt-PAが効きにくい血栓に有効 |
| 適応されるタイミング | 発症から4.5時間以内が目安 | 発症から6時間以内(条件次第で24時間程度まで適応されることも) |
| 心原性脳梗塞との相性 | 心臓由来の血栓が溶解できるケースでは有効 | 心臓由来の大きな血栓を直接除去できるため、心原性脳梗塞に適応しやすい |
| 使用される場面 | 比較的早期で症状が中等度までの患者に多く使用 | 血栓が大きい、症状が重い、t-PA単独で効果が不十分な場合に使用 |
| 他の治療との併用の可能性 | 血管内治療と併用するケースあり | 必要に応じて局所的にt-PAを併用も可能 |
| 治療の目的 | 脳への血流を早期に再開し、後遺症を軽減 | 血栓を確実に取り除き、血流を回復し重症化を防ぐ |
t-PA静注療法は、血栓を溶かす薬剤(アルテプラーゼ)を点滴で投与し、閉塞した脳の血管を再開通させる治療です。発症から4.5時間以内の投与が目安であり、早期の対応が必要となります。(文献1)
血栓が大きい場合は、カテーテルで直接取り除く血管内治療が有効です。これらの治療は脳のダメージを抑えるために行われ、時間と症状の判断が回復を左右します。少しでも異変を感じた場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
抗凝固薬(ワルファリン、DOACなど)
| 種類 | 薬剤 | 特徴 |
|---|---|---|
| ワルファリン | ワルファリン | ビタミンKの働きを抑えて血液を固まりにくくする薬剤。効果の安定には定期的な血液検査(PT-INR)が必要。食事や他の薬との相互作用に注意が必要 |
| 直接経口抗凝固薬(DOAC) | ダビガトラン、リバーロキサバン、アピキサバン、エドキサバン | 凝固因子を直接阻害する新しいタイプの薬剤。定期的な血液検査が原則不要。食事や薬の影響を受けにくく、服用の手軽さが特徴 |
心原性脳梗塞は、心臓内でできた血栓が血流に乗って脳の血管を塞ぐことで発症します。とくに心房細動などの不整脈があると、心房内に血液が滞り、血栓ができやすくなるのが特徴です。
抗凝固薬は血液の固まりにくさを保つことで、こうした血栓の形成を防ぎ、脳梗塞の発症リスクを約3分の1に減らす効果があると報告されています。(文献2)
抗凝固薬には、ワルファリンと、近年使用が増えているDOAC(直接経口抗凝固薬)があります。DOACは定期的な血液検査が不要で、食事や他の薬の影響を受けにくく、一定の用量で効果が安定しているのが特徴です。このため、服薬の負担が少なく、継続しやすい薬とされています。
ただし、抗凝固薬は中断すると効果がなくなり、再発リスクが高まります。症状が落ち着いても自己判断で中止せず、医師の指示に従って服用を続けることが不可欠です。出血のリスクもあるため、異変を感じたら早急に医師へ相談しましょう。
原因疾患の治療(心房細動の管理など)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 血栓形成の予防 | 心房細動を適切に管理すると心房内の血流が改善され、血栓の形成を防ぐ効果がある |
| 抗凝固療法の適用 | リスク評価(例:CHADS₂スコア)に基づき、ワルファリンやDOACを使用して血栓を予防する |
| 心房細動の根治 | カテーテルアブレーションにより、異常な電気信号の発生源を焼灼し、心房細動そのものを治療する |
| 抗不整脈薬の使用 | 心房細動の発作を抑える薬剤により、発作の頻度や持続を減らす |
| 脳梗塞の再発予防 | 血栓の原因となる心房細動を抑えることで、心原性脳梗塞の再発リスクを大きく減らせる |
心原性脳梗塞の予防や再発防止には、血栓をつくらせないための抗凝固療法だけでなく、根本原因となる心疾患の管理が不可欠です。
心房細動がある場合は、心拍を安定させる薬による治療が基本となり、症状が強い場合は、カテーテルアブレーションといった手術も検討されます。
心筋梗塞や弁膜症が原因であるときは、それぞれに合った専門的な治療が必要です。心臓と脳は深く関わっているため、心臓の病気をしっかり管理することが、脳梗塞の再発を防ぐポイントになります。
リハビリテーション
| リハビリの種類 | 対応する症状・目的 | 内容 |
|---|---|---|
| 理学療法(PT) | 手足の麻痺や筋力低下などの運動機能障害 | 筋力や関節の動きを改善し、寝返り・立ち上がり・歩行など基本動作の回復を目指す訓練 |
| 作業療法(OT) | 着替えや入浴などの日常生活動作や、記憶・注意力といった高次脳機能の障害 | 食事や更衣などの日常動作の訓練や、認知リハビリテーションを通じた生活機能の向上 |
| 言語療法(ST) | 話す・理解する・飲み込むなどの言語障害・嚥下障害 | 発音・言語理解・読み書きなどの回復訓練により、コミュニケーション能力の改善を図る |
| 心理・社会的支援 | 病気による不安・うつ・家族の精神的負担 | 心理士・ソーシャルワーカーによる心理サポートや、社会資源の活用支援 |
| 早期リハビリ介入 | 発症直後からのリハビリ開始による後遺症の軽減と回復促進 | 急性期からリハビリを始めることで、機能回復と社会復帰の可能性を高める包括的支援 |
心原性脳梗塞によって生じた後遺症を改善するには、発症後できるだけ早期にリハビリを開始するのが大切です。
手足の麻痺や言語障害、高次機能障害など、それぞれの症状に応じて、理学療法(PT)、作業療法(OT)、言語聴覚療法(ST)などを組み合わせて実施します。
リハビリは、脳の回復力が高い早期に始めることで効果が期待できます。再発を防ぎ、日常生活への復帰を目指すことが主な目的です。
再生医療
心原性脳梗塞による神経のダメージに対して、再生医療は有効な治療法のひとつとされています。
自分の身体から採取した幹細胞を使い、損傷を受けた脳の神経細胞の回復を促すことが目的です。治療を希望する場合は、再生医療を扱う医療機関で医師と十分に相談し、適切な判断のもとで進めていくことが大切です。
以下の記事ではリペアセルクリニックで取り扱っている再生医療についてわかりやすく解説しております。
リペアセルクリニックでは、心原性脳梗塞に対して手術を必要としない再生医療を提案しています。
心原性脳梗塞の症状が改善せずお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にて、当院へお気軽にご相談ください。
心原性脳梗塞の症状を理解し適切な治療で回復を目指そう
心原性脳梗塞は、突然の麻痺や言語障害など、日常生活に大きな支障をもたらす病気です。症状を正しく理解し、早期に治療を受けることで後遺症の軽減や再発予防が期待できます。
手足の突然の麻痺や、ろれつが回らないといった症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
リペアセルクリニックでは、心原性脳梗塞による症状や後遺症に対し、従来のリハビリや治療に加えて、幹細胞を用いた再生医療もひとつの選択肢としてご案内しています。患者様の状態やご希望に応じて、医師と相談の上で治療方法を検討していただけます。
心原性脳梗塞の症状にお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にて、当院へお気軽にご相談ください。
\無料相談受付中/
心原性脳梗塞の症状に関するよくある質問
心原性脳梗塞の予兆としてどのようなものがありますか?
心原性脳梗塞は突然起こることが多いですが、前ぶれとして一過性脳虚血発作(TIA)が現れることがあります。顔や手足の痺れ、言葉のもつれ、一時的な視力障害などが特徴です。
見逃さないためには、FASTチェックが有効です。
- F=顔のゆがみ
- A=両腕が上がるか
- S=言葉の異常
- T=時間が勝負
1つでも当てはまれば、すぐに救急車を呼びましょう。
心原性脳梗塞は再発しますか?
心原性脳梗塞は再発のリスクが高く、心房細動の持続や自己判断による抗凝固薬の中断、生活習慣病の悪化が影響します。
再発を防ぐには、正しい薬の継続服用、定期検査、食事や運動など生活習慣の見直しが大切です。
以下の記事では脳梗塞の予防や再発防止について詳しく解説しています。
心原性脳梗塞の症状に対して家族ができるサポートはありますか?
心原性脳梗塞では、家族のサポートが回復と再発予防において大切です。
異変への早期対応、治療や服薬の支援、リハビリや生活習慣の見直しを共に行うことが求められます。また、不安や抑うつへの心のケアも大切です。
参考資料
(文献1)
Patel T. (2009). Should the Window for Intravenous Administration of Tissue Plasminogen Activator in the Treatment of Acute Ischemic Stroke be Extended to 4.5 Hours? The “PRO” Side. Can J Hosp Pharm, 62(3), pp.248–249.
https://doi.org/10.4212/cjhp.v62i3.798(最終アクセス:2025年6月6日)
(文献2)
平野照之.「日本血栓止血学会サイト お役立ちリンク集」『血戦止血誌』, pp.1-11, 2017年
https://www.jsth.org/publications/pdf/oyakudachi/6-3.pdf?utm_source=chatgpt.com(最終アクセス:2025年5月18日)