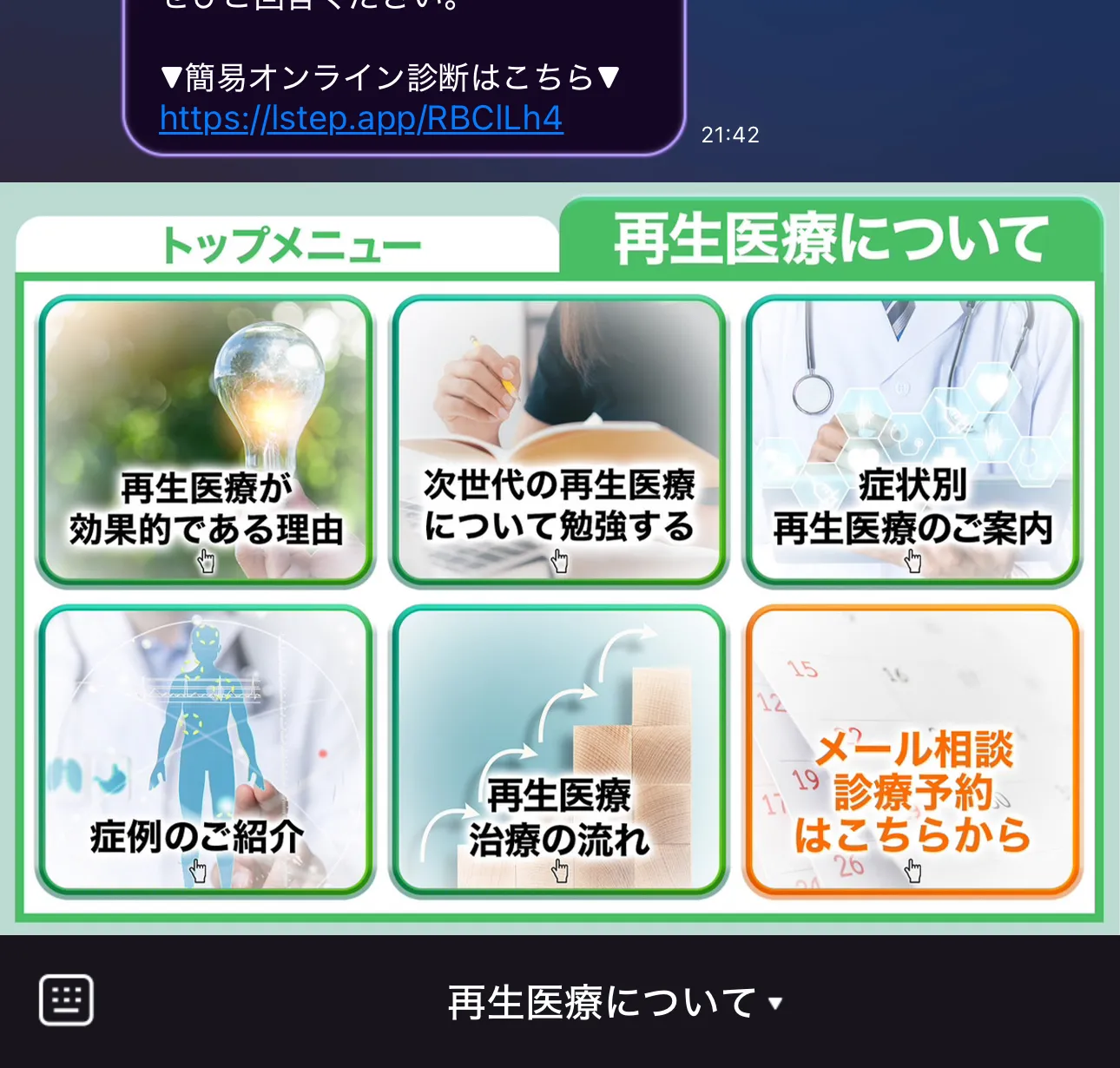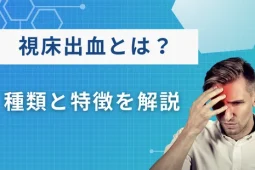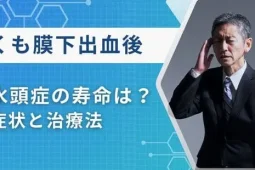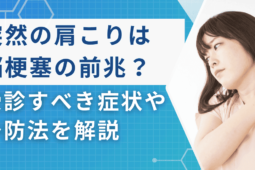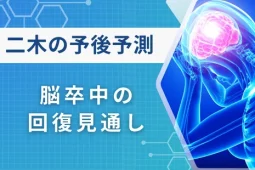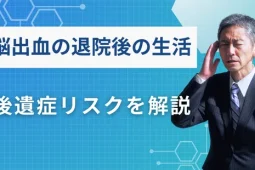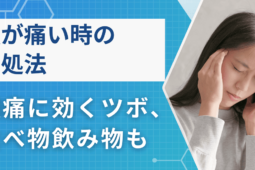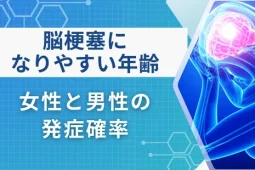- 脳卒中
- 脳出血
- 頭部
【保存版】視床出血の主な症状はなに?原因や治療法・予後について現役医師が解説
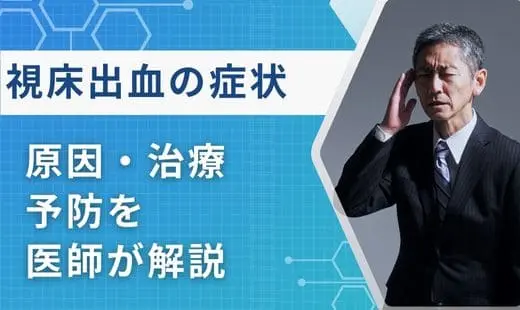
家族が倒れて視床出血と言われたけれど、どんな病気なのだろう。
これからどうなるか心配。
この記事を読んでいるあなたは、「視床出血」という病気を初めて聞き、不安を抱いているのではないでしょうか。「今後、どうなるのだろう」と心配しているかもしれません。
結論、視床出血は脳の奥にある「視床」という部位からの出血で、脳内出血のうち2番目に多い症状です。経過によっては、麻痺やしびれなどの後遺症が出るケースも珍しくありません。
本記事では、視床出血の症状や原因、治療法について、詳しく解説します。記事を最後まで読めば、視床出血に関する基本的な内容がわかり、今後の見通しもたてやすくなるでしょう。
目次
視床出血の主な症状は「感覚障害や麻痺」
視床は、脳の奥に位置する器官です。主に、痛覚、視覚、聴覚、味覚など、嗅覚以外のあらゆる感覚情報や運動機能の調節情報を大脳に伝達する「中継所」の役割を果たします。(文献1)
そのため、出血によって機能が失われると脳内の神経伝達がうまくできなくなり、さまざまな症状が起こります。
視床出血の代表的な症状は、以下のとおりです。
- 意識障害:意識を失ったり刺激に対して反応しなくなったりする
- 眼球障害:両眼が内下方を向き、鼻先を見つめるようになる
- 感覚障害:痺れやピリピリしたような感覚が出る
- 運動障害:手足が思い通りに動かしにくくなる
- 失語:言葉が出てこなくなり会話がしにくくなる
- 視床痛:出血した脳と反対側の手や足に強い痛みが出る
出血の範囲や程度によっては、複数の症状が同時にあらわれるケースも珍しくありません。
また、視床出血には、ほかの脳出血と比べて以下の特徴があります。(文献2)
- 約25%のケースが片側の顔面や手のひらの痺れが起こる「感覚障害」から始まる
- 眼球障害が起こりやすい
感覚障害から始まった視床出血の症状は、その後「焼き付くような」「剣山を押し付けられたような」などと表現される痛みへ移行します。
さらに、脳組織のむくみや髄液という水分の循環が悪くなって起こる「水頭症」なども起こると、症状や予後の悪化につながります。
脳出血や脳梗塞において、麻痺が出るのは「機能が失われた脳の反対側」です。
そのため、右視床出血の場合は左側の麻痺症状、左視床出血の場合は右側に麻痺症状が出るケースが多くみられます。
なお、視床痛は発症後数カ月~数年後にあらわれるケースもあります。
視床出血については、以下の記事でも詳しく説明しています。
また、当院リペアセルクリニックでは、脳梗塞や脳出血といった「脳卒中」の治療法の1つとして再生医療を提供しています。「メール」や「オンラインカウンセリング」によるご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
\無料オンライン診断実施中!/
視床出血の原因やメカニズムは?高血圧による動脈硬化
視床出血の主な原因は、「高血圧による動脈硬化」です。
高血圧が動脈硬化を起こし、視床出血にいたるメカニズムは以下のとおりです。
- 高血圧により血管の内側が傷つき動脈硬化が起こる
- 動脈硬化によって血管がもろくなる
- 高血圧によって血管に高い圧力がかかる
- 血管がやぶれて出血する
多くの場合、出血の原因となるのは「穿通枝(せんつうし)」と呼ばれる非常に細い血管です。
視床出血を含む「脳出血」の前兆は、以下の記事で詳しく説明しています。
視床出血の診断は「頭部CT検査」にておこなう
視床出血の診断は、ほかの脳出血と同様に「頭部CT検査」によっておこなわれます。
CTでは出血部位が白く写るため、視床の部分が白く写れば「視床出血」となるのです。
また、白く写った範囲の広さや場所から「出血の程度」「視床からの出血が脳室まで達しているか」などの重症度を判断し、治療方法や予後を検討します。
なお、MRIでも出血の判定は可能ですが、検査に20〜30分ほど時間がかかるケースもあるため、速やかな診断が必要な脳出血にはあまり適しません。そのため、機械によっては3分程度で検査が終了するCT検査が一般的に用いられます。
視床出血の治療法は2つ
基本的に、視床出血では出血量が多くても血腫(出血による血の塊)を除去する手術はおこないません。
血腫を除去する手術をおこなわない理由は、以下のとおりです。
- 視床は脳の奥深くにあるため、手術が難しいから
- 重要な神経が多く集まるため、手術によって脳がさらなるダメージを受ける可能性が高いから
ただし、以下のような場合は手術をおこなうケースがあります。
- 出血の範囲が非常に大きく、合併症を最小限に食い止めるための手術が必要
- 水頭症による命のリスクがある
本章では、視床出血の基本的な治療である「薬物療法」と、水頭症におこなわれる手術「シャント術」について解説します。
なお、視床出血を含む「脳出血」の入院日数や費用は、以下の記事で解説しています。
薬物療法|血圧コントロール
薬剤による血圧コントロールは、視床出血の重要な治療法です。
視床出血は高血圧が原因となるケースが多く、とくに発症時(急性期)には収縮期血圧が200 mmHg以上となる人も珍しくありません。発症から 6 時間以内は再出血が起こりやすいため、急性期の治療では出血範囲の拡大や再出血の予防を目的に、血圧を安定させる降圧剤の点滴や内服などが使われます。
血圧は収縮期血圧140mmHgを目安に下げるのが一般的ですが、急激に血圧を下げると急性腎障害が増加したという報告もあります。そのため、状況を見ながらの適切な血圧コントロールが大切です。(文献3)
また、慢性期にも生じる可能性がある視床痛は、一般的な鎮痛剤の効かない人が多く、有効な治療法は確立されていません。塩酸マプロチリン、アミトリプチリンなどの抗うつ薬、カルバマゼピンなどの抗けいれん薬を処方して様子を見ますが、効果がない場合はガンマ線を用いた定位放射線手術をするケースもあります。(文献4)
手術療法|シャント術
シャント術とは、脳内に溜まる髄液(硬膜と脳・脊髄の間を満たす液体)を体内の他の場所へ流す通り道を作る手術で、水頭症の治療法です。
髄液は誰にでも存在し、通常は脳内の狭い道を通って血管に吸収されています。しかし、視床出血が起こると通常のように吸収されず、溜まった髄液は脳内を圧迫し始めます。そのため、髄液を流す手術が必要になるのです。
シャント手術の主な経路は、以下のとおりです。
- 脳室から腹部(脳室―腹腔シャント)
- 脳室から心臓(脳室―心房シャント)
- 腰から腹部(腰椎―腹腔シャント)
現在は、脳室―腹腔シャントが最も多くおこなわれています。
当院リペアセルクリニックでは、脳梗塞や脳出血を含む「脳卒中」の治療法として、再生医療を行っています。視床出血の治療法について新たな選択肢を知りたい方は、ぜひお気軽にメールにてお問い合わせいただければ幸いです。
視床出血の予後は出血量と範囲で決まる
一般的に、 出血が多くて広範囲なほど視床出血の予後は不良です。
また、出血範囲が生命を維持するために重要な「中脳」にまでが広がると、生命の危機につながる可能性が高いともいわれています。視床出血の死亡率は一般的に 14〜52 %とされていますが、実際は基礎疾患やもともとの健康状態などに大きく左右されます。
水頭症の発症や再出血、さらなる出血範囲の拡大などがあると、予後がさらに悪化するケースも珍しくありません。そのため、厳格な血圧コントロールや、少しでも後遺症を軽減する早期からのリハビリが重要です。
まとめ|視床出血の症状があらわれたらすぐに受診を
本記事では、視床出血の症状、診断、治療法などを詳しく解説しました。
視床出血は脳の深いところにある「視床」からの出血です。視床は視覚や痛覚など多くの感覚情報の伝達に関わるため、出血によって機能が失われると手足の麻痺や痺れなど、さまざまな症状が起こります。
顔の片側や手のひらの痺れ、身体がうまく動かないなど気になる症状が出た場合は、すみやかに受診しましょう。
当院「リペアセルクリニック」では、再生医療(幹細胞治療)による脳卒中の再生医療をおこなっています。再生医療(幹細胞治療)の効果は、脳神経細胞の修復及び再生と、脳の血管を新しく再生させることです。そのため、視床出血の再発予防や、後遺症の軽減、リハビリ効果の向上などに効果が期待できます。
再生医療へのご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」でも可能です。些細なことでも問題ないため、どうぞ気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
視床出血の症状に関するよくある質問
視床出血ではどのようなリハビリをおこないますか?
視床出血でおこなう主なリハビリは、以下のとおりです。
- 作業療法:麻痺した腕、指先などの使い方や食べ物・飲み物を飲み込む動作を訓練する
- 理学療法:姿勢を保つ、歩くなどの日常動作を訓練する
視床出血をはじめとする脳出血のリハビリは、毎日の継続が大切です。失われた機能の回復に時間がかかるケースもありますが、根気よくリハビリを続けましょう。
視床出血後のリハビリについては、以下の記事で詳しく説明しています。
右視床出血ではどのような症状が出ますか?
右視床出血によって脳の右側の機能が失われると、身体の左側に麻痺や感覚障害が起こります。
麻痺や感覚障害が起こると身体をうまく動かせなかったり、手足のしびれや痛みが出たりします。