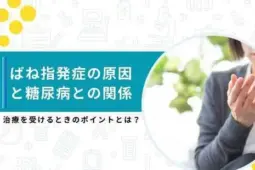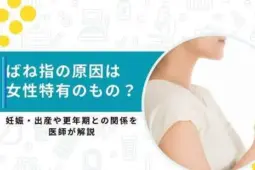- 手部、その他疾患
- 手部
スマホ腱鞘炎とは|症状・原因・治療法を現役医師が解説
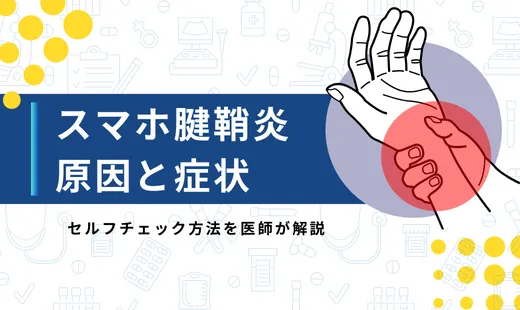
- 「スマートフォンを使うと親指や手首が痛い……」
- 「病院に行った方が良いのかわからない」
スマートフォンを使用する際に、指や手首のだるさや痛みに悩む方もいるでしょう。
スマホ腱鞘炎は、スマートフォンの使いすぎが原因で筋肉と骨をつなぐ腱を包む腱鞘に炎症が起こる疾患です。
親指を使ったスクロールやフリックなど、同じ動作を繰り返すスマートフォン操作では炎症が生じやすく、痛みや腫れなどの症状を引き起こします。
本記事では、スマホ腱鞘炎の症状や原因、治療法などを詳しく解説します。
腱鞘炎治療の選択肢の1つにもなっている「再生医療」について詳しく知りたい方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
スマホ腱鞘炎とは
スマホ腱鞘炎とは、スマートフォンの長時間使用が原因で、指や手首の腱(けん)を包む腱鞘(けんしょう)が炎症を起こす状態です。医学的には「腱鞘炎」の一種であり、主に以下の種類に分類されます。
|
種類 |
主な症状 |
|---|---|
|
ドケルバン病 |
親指を動かすと強く痛む、腫れる |
|
バネ指 |
指を曲げ伸ばしする際に引っかかる |
|
変形性関節症 |
関節が変形し、物を掴むと痛む |
ドケルバン病は、親指の使いすぎによって発症する腱鞘炎です。(文献1)具体的には、スマートフォンを片手で持ち、親指でスクロールする動作が原因といわれています。
バネ指は指の付け根に発症する腱鞘炎で、指を曲げ伸ばしする際に引っかかるように感じるのが特徴です。(文献2)スマートフォン操作で指を酷使する生活習慣だと、バネ指を発症するリスクは高まるとされているため注意しましょう。
変形性関節症は、長期間に及ぶ指関節への負担や加齢によって関節軟骨がすり減り、炎症や変形を起こす疾患です。スマホ腱鞘炎のように手や指を繰り返し使う動作が長期間続くと、関節に慢性的なストレスが蓄積し、軟骨が摩耗しやすくなります。
スマホ腱鞘炎の症状
スマホ腱鞘炎の痛む場所や症状は、スマートフォンの持ち方や操作の癖によって異なり、多岐にわたります。どの部位がどのような原因で痛むのかを把握することが、適切な対策や治療への第一歩です。
代表的な症状を解説するので、ぜひ参考にしてください。
親指の付け根が痛くなる
スマホ腱鞘炎で最も多い症状の1つが親指の付け根の痛みです。物をつかんだり、ビンの蓋をひねったりする際に、ズキッとした鋭い痛みが走るのが特徴です。
初期症状では「押すと少し痛い」程度でも、負荷が続くと痛みが鋭くなり、物をつまむ動作が困難になるケースもあります。
進行すると、ペットボトルのキャップを開ける、物をつかむといった日常動作も困難になる恐れがあるため注意しましょう。
小指の付け根が痛くなる
小指の付け根の痛みは、スマートフォンを片手で持つ際、小指の側面で本体の底を支える癖がある方に現れる症状で「スマホ小指」と呼ばれています。
初期症状は軽い違和感でも、連日の負荷で腫れやだるさが現れ、物を握る動作が重く感じる場合があります。また、悪化すると小指の変形やタコができるだけでなく、小指側の手根部へ痛みが広がり、手首をひねる動作で鋭い痛みが出ることもあります。
小指への過度な圧迫が主な原因となるため、悪化する前に小指の付け根に負担がかからない持ち方に直しましょう。また、大型モデルを長時間使用する場合はスマートフォンの重量が負担を増加させるため、とくに注意してください。
手首が痛くなる
スマートフォンやパソコンを長時間使用すると手首にかかる負担が蓄積し、腱鞘炎や関節炎を発症する場合があります。とくに、親指の付け根の痛みと連動して、手首全体がだるく痛むケースが多いです。
初期症状は「手首を反らすと少し痛む」程度ですが、使い続けるとズキズキとした痛みに変化し、力が入りにくくなる場合もあります。悪化すると、手首の外側や内側まで張りが広がり、スマートフォンを持つ動作ですら負担に感じるケースも珍しくありません。
さらに放置すると握力の低下やしびれが出る可能性があるため、手首を反らしたまま固定する姿勢は直すようにしましょう。
スマホ腱鞘炎の原因3選
スマホ腱鞘炎の最大の引き金は、スマートフォンやパソコンを日常的に使用する現代の習慣です。代表的な原因として、スマートフォン操作時のスクロールやフリックなどが挙げられます。
腱と腱鞘は、手の動きをスムーズにする重要な組織です。
腱は、筋肉と骨をつなぐ丈夫な線維組織であり、筋肉が収縮する際の力を骨に伝える役割を担っています。一方、腱鞘は腱を包む鞘(さや)のような構造で、腱の動きをスムーズにし、摩擦を減らすのが役割です。
スマートフォンを操作する際、親指を曲げたり伸ばしたりする動作を何度も繰り返すと、親指の付け根に通っている2本の腱と腱鞘の間で摩擦が生じ腱鞘炎を引き起こします。
ただし、スマホ腱鞘炎はスマートフォンの操作以外にも、日常生活や体の変化とも深く関係しています。
ここでは、スマホ腱鞘炎を引き起こす代表的な3つの原因を見ていきましょう。
長時間のスマホやパソコンの操作
スマホ腱鞘炎で最も一般的な原因は、長時間にわたるスマートフォンやパソコンの操作です。
以下の動作は腱に対して繰り返し負荷をかけるので注意が必要です。
- スマートフォン画面を支える姿勢
- スクロールやフリップ動作・画面タップ
- パソコンでのタイピング
どの動作も腱と腱鞘の間に摩擦が起こり炎症の引き金となりますが、無意識に行われるため、疲労に気づきにくい点が問題になります。
集中が続くと姿勢が崩れ、腱が硬くなり痛みが強まります。短時間の休憩を挟み、持ち方を変える工夫が回復を促すうえで重要です。
また、寝ながらスマートフォンを扱う姿勢は、手首の角度が急になり痛みを悪化させる原因になります。使用時間を調整し、ストレッチを意識的に取り入れて炎症を予防しましょう。
指や手首に負担をかけるスポーツや生活習慣
スマートフォンやパソコンの使用だけでなく、日常生活や趣味での手の使い方も発症に影響します。
具体的なスポーツや生活習慣は、以下のとおりです。
- テニス
- ゴルフ
- 料理
- ギター
- ピアノ
- 筆記作業
テニスやゴルフなどのグリップを強く「握る」スポーツは、手首や指の腱に大きな負荷を与えます。また、重いフライパンを振る料理動作、ギターやピアノなどの楽器演奏、ペンを強く握る筆記作業なども、特定の動作の繰り返しとなり、腱鞘炎のリスクを高めます。
これらの動作が習慣化している場合、スマートフォン操作による負荷が加わると腱の許容量を超えてしまい、症状として現れやすくなるため注意が必要です。
スマートフォンの使用と同様に、スポーツや生活習慣の過度な負荷と反復動作がスマホ腱鞘炎のリスクである点を理解しておきましょう。
ホルモンの大きな変化
腱鞘炎は、女性ホルモンのバランスが大きく変動する時期にも発症しやすいのが特徴です。
とくにエストロゲンというホルモンには、腱や腱鞘を滑らかに保ち、炎症を抑える働きがあるとされています。なかでも、エストロゲンの分泌量が変動する出産前後や更年期の女性は、腱や腱鞘の柔軟性が低下し腱鞘炎を発症しやすくなります。
また、産後はホルモンの影響に加えて、慣れない育児で赤ちゃんを抱く動作が手首への負担を急増させ、発症リスクを高めます。
スマホ腱鞘炎の治し方
スマホ腱鞘炎の治療は、症状の程度や進行状況によって異なります。初期症状であれば保存療法が中心となりますが、改善が見られない場合は手術療法や再生療法の検討が必要です。
ここでは、3つの治療法について、それぞれの特徴を詳しく解説します。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、オンライン診断も実施しておりますので、お気軽にご登録ください。
保存療法
保存療法は、スマホ腱鞘炎の初期に行われる治療法です。炎症を抑えながら腱の動きを整える方法で、負担を減らす環境を作ります。
具体的な治療法は、以下を参考にしてください。
|
治療方法 |
治療内容 |
|---|---|
|
装具療法 |
サポーターやテーピング、副子(シーネ)で患部を固定し安静にする |
|
薬物療法 |
湿布や軟膏、鎮痛剤、ステロイド注射を用いて痛みや炎症を抑える |
|
理学療法 |
温熱療法で血行を促進させ、筋肉の緊張緩和と痛みの軽減を目的とする |
|
リハビリ |
再発予防のストレッチや筋力強化のためのトレーニングを行う |
腱を休めるために安静時間を確保し、痛みが強い段階ではアイシングで炎症を抑えます。サポーターやテーピングを使うと腱への刺激が弱まるため、痛みの軽減に用いられる方法です。
また、炎症を抑えるための湿布や軟膏・鎮痛剤が処方されますが、症状の改善が見られない場合はステロイド注射が行われます。症状が落ち着いてきた段階では理学療法やリハビリに切り替え、回復を促します。
痛みが続くと回復が遅れやすく、無理に動かし続けると症状悪化の原因になりかねません。適切なタイミングでストレッチを取り入れると動きが滑らかになりますが、自己判断で行うと症状が悪化するケースもあるため、医師や作業療法士の指示に従いましょう。
手術療法
保存療法を数カ月続けても症状が改善しない場合や、ステロイド注射を繰り返しても再発する際には、手術療法が検討されます。
代表的な手術は、狭くなった腱鞘を切開し、腱を解放して動きを滑らかにする方法です。局所麻酔で実施されるため、身体への負担が比較的少なく、短時間で終わるケースも多くみられます。
術後は一時的に腫れや痛みが残りますが、手術により腱の圧迫が根本的に解消されるため、痛みの早期改善と再発率の低下が期待できます。
再生医療
再生療法は、組織の修復力を高めながら痛みの改善を目指す治療です。
代表的なPRP療法は、自身の血液から成長因子を取り出し患部へ注入する方法で、炎症を抑えつつ組織の回復を促します。腱の負担が蓄積した状況では回復が遅れやすく、再生療法を用いると改善が期待できる場合があります。
手術に不安を感じる方は、再生医療の選択肢もあるため医師に相談してみましょう。
当院「リペアセルクリニック」では、腱鞘炎に対する再生医療を提供しておりますので、お気軽にご相談ください。
スマホ腱鞘炎のセルフチェック方法
スマホ腱鞘炎が疑われる場合は、早めに状態を確認するのが大切です。
ここでは、代表的な方法である「フィンケルシュタインテスト」と「アイヒホッフテスト」をご紹介します。
テストで痛みを感じた場合はスマホ腱鞘炎の可能性が高いと考えられます。ただし、強い痛みや症状が続く場合は自己判断せず、必ず専門医を受診しましょう。
フィンケルシュタインテスト
フィンケルシュタインテストは、スマホ腱鞘炎の診断でよく用いられる方法です。手順は以下を参考にしてください。
<フィンケルシュタインテストの手順>
- 親指を内側へ入れ、拳を作る
- 手首が小指側に曲がらないようにまっすぐ固定する
- 反対の手で親指をつかんで小指側に曲げる
小指側に曲げる際は、親指の力を抜いた状態で反対側の手を使って曲げる方向に引っ張りましょう。
手首の親指側や親指の付け根あたりに鋭い痛みが生じた場合は、スマホ腱鞘炎の可能性があります。
アイヒホッフテスト
アイヒホッフテストは「フィンケルシュタインテスト変法」とも呼ばれ、スマホ腱鞘炎(ドケルバン病)を診断するために有効な方法です。
<アイヒホッフテストの手順>
- 親指を手のひらの中に入れるように握る
- 握った手を、小指側に傾ける
テストの際は無理に力を入れず、自然な動きで行いましょう。万が一、強い痛みを感じた場合は速やかに中止し、無理をしないようにしてください。
痛みの強さは個人差がありますが、通常は痛みをほとんど感じないため、親指の付け根から手首にかけ痛みを少しでも感じる場合はスマホ腱鞘炎の可能性があります。
強い痛みがある場合は、すぐに専門医を受診しましょう。なお、フィンケルシュタインテストと併せて行うと、よりテストの精度を高められます。
スマホ腱鞘炎のセルフケア方法
スマホ腱鞘炎は早期に適切なセルフケアを行えば、症状の悪化を防ぎながら回復を目指せます。
ここでは、自宅でも取り入れやすい3つのセルフケア方法を紹介します。ただし、数日続けても改善がみられない場合や腫れが強い場合は、医療機関を受診しましょう。
マッサージする
手首や指の付け根周辺を優しくマッサージすると、血行を促進し、炎症部位の回復を助けます。
親指の付け根から手首にかけての筋肉を軽く押し、30〜60秒ほど円を描くようにほぐすと効果的です。
ただし、強く押しすぎると炎症を悪化させる恐れがあるため、痛みがない範囲で行いましょう。
また、入浴後や手を温めた後に行うと、より血流が良くなります。
テーピングする
テーピングは、炎症部分への負荷を軽くしながら動きを安定させる方法です。
親指や手首を安定させるようにテープを巻いて動きを制限すると、腱や腱鞘へのストレスを軽減できます。
テーピングは市販の伸縮テープを使用し、きつすぎず関節を曲げ伸ばししやすい程度に貼るのがポイントです。万が一、テーピング中にしびれや違和感があった場合は、すぐに外してください。
巻き方を誤ると逆効果になる場合もあるため、わからない場合は専門家の指導を受けましょう。
湿布をする
湿布は、炎症を抑えながら痛みを和らげる方法です。湿布には「冷湿布」と「温湿布」があり、使い分けは以下を参考にしてください。
|
湿布の種類 |
症状 |
|---|---|
|
冷湿布 |
急性の腫れや痛みが強い場合 |
|
温湿布 |
慢性的なこわばりや疲労感が強い場合 |
炎症や腫れなどの急性期の症状がある場合は、冷感タイプの湿布で患部を冷やすと痛みが和らぎます。
また、慢性的なこわばりや疲労感が強いケースでは、温感タイプの湿布で血流を促進するのも効果的です。
ただし、使用時は肌に異常が出ないか確認し、長時間貼り続けないように注意してください。皮膚が弱い方は、かぶれる恐れもあるため、短時間から試しましょう。
スマホ腱鞘炎の症状にお悩みなら早めに受診しよう
スマホ腱鞘炎は、指や手首に痛みを生じる疾患で、現代社会において誰もが発症する可能性があります。
初期段階の治療方法には保存療法が行われますが、症状の改善が難しいと手術療法を検討するケースがあるのも事実です。
マッサージやテーピングなどのセルフケアを行うと、症状悪化のリスクを軽減できる可能性があります。
ただし、セルフケアを行っても痛みや違和感が続くようなら、早めに医療機関を受診しましょう。
当院「リペアセルクリニック」では、再生医療に関する情報提供や簡易オンライン診断を行っております。
再生医療についての疑問や気になる症状があれば、公式LINEに登録してぜひ一度ご利用ください。
\無料オンライン診断実施中!/
スマホ腱鞘炎に関するよくある質問
スマホ腱鞘炎はどれくらいで治る?
スマホ腱鞘炎の治療期間は、軽度であれば数週間〜数カ月ほどですが、重症のケースでは半年ほどかかる場合があります。
スマホ腱鞘炎は早期治療が重要で、適切なケアと休息で回復が早まります。初期段階では軽い違和感や動かしにくさから始まるため軽視しがちですが、放置すると痛みが強くなり、指や手首の動きが制限されるケースがあるのも事実です。
症状が続く場合は、整形外科などの専門医を早めに受診しましょう。
スマホ腱鞘炎の予防法は?
スマホ腱鞘炎の予防法は、以下のとおりです。
- 両手でスマートフォンを使用する
- スマートフォンを使用する際は適度に手を交換する
- 適度な休息と手首や指のマッサージを行う
スマホ腱鞘炎を予防するには、長時間の連続操作を避け、短い休息を挟むのが効果的です。両手で操作する、持つ手を変えるなどの負担を分散させる方法も役立ちます。
画面への入力動作が続くと筋肉が硬くなりやすいため、軽いマッサージやストレッチを行うのも予防につながります。
小さな積み重ねが炎症の抑制に結び付くため、普段から意識すると良いでしょう。
スマホ腱鞘炎を早く治す食べ物はある?
スマホ腱鞘炎の痛みの緩和や炎症抑制に効果が期待される食品は、以下のとおりです。
|
栄養素 |
食品の具体例 |
|---|---|
|
オメガ3脂肪酸 |
サーモン、イワシ、鯖、亜麻仁(あまに)油、キャノーラ油、くるみ、大豆 |
|
ビタミンC |
パプリカ、ブロッコリー、柑橘類、いちご |
|
ビタミンE |
ブロッコリー、ほうれん草、アボカド、ピーナッツ |
|
たんぱく質 |
肉、魚、卵、大豆製品 |
オメガ3脂肪酸や抗酸化作用を持つビタミンC・E、良質なたんぱく質を含む食品は、炎症を抑える効果が期待できます。
特定の食品がスマホ腱鞘炎を直接治すわけではありませんが、炎症が起きた組織を修復する過程において、栄養バランスの取れた食事は非常に重要です。
一方、揚げ物や加工食品などの脂肪分が多い食事やアルコールの過剰摂取は、体内の炎症反応を強める可能性があるため、治療期間中は控えてください。
特定の食品だけに偏るのではなく、体全体の回復力を高めるバランスの良い食事を心がけましょう。
参考文献
文献1
ドケルバン病(狭窄性腱鞘炎)|日本整形外科学会
https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/de_quervain_disease.html
https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/snapping_finger.html