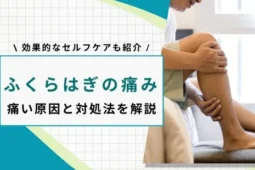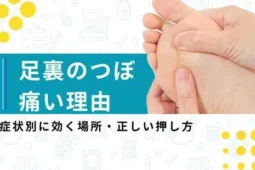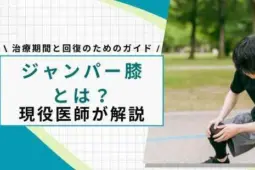- 足部、その他疾患
- 下肢(足の障害)
- 足部
- スポーツ外傷
- その他、整形外科疾患
【医師監修】シンスプリントとは|原因・治し方(治療法)からどこで診てもらうべきかまで解説

「走るたびにすねの内側がズキズキとする」
「足の痛みが日に日に強くなっている」
その症状はシンスプリントかもしれません。シンスプリントは、部活動やランニングに励む人が一度は経験することが多い代表的なスポーツ障害です。運動による負担の蓄積が骨膜の炎症を引き起こす主な原因です。初期対応を誤ると競技への復帰まで時間がかかることもあります。
本記事では、シンスプリントについて現役医師が詳しく解説します。
- シンスプリントの原因
- シンスプリントの初期症状
- シンスプリントの治し方(治療法)
- シンスプリントはどこで診てもらうべきか
- シンスプリントの予防方法
記事の最後にはシンスプリントに関する質問をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
シンスプリントについて気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
シンスプリントとは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な原因 | 筋肉の使い過ぎや足の構造・靴の問題によって骨膜に負担がかかること |
| 症状の特徴 | 運動時や安静時に、すね内側へ広がる鈍い痛みが生じる |
| 治療と予防のポイント | 安静と運動量の調整を行い、ストレッチや靴の見直しで再発を防ぐことが重要 |
(文献1)
シンスプリントは、すねの内側下方に生じる運動関連の骨膜炎で、脛骨過労性骨膜炎とも呼ばれます。ランニングやジャンプ動作を繰り返すスポーツで発症しやすく、陸上競技、バスケットボール、サッカーなどの競技者に多くみられます。
原因は、下腿の筋群が脛骨の骨膜を過度に引っ張ることで、繰り返しストレスが加わり、微小な損傷と炎症が起こるためです。
初期には運動開始時の軽い違和感にとどまりますが、放置すると疲労骨折に移行する可能性があります。早期の発見と適切な対応が、競技復帰を早める鍵となります。
シンスプリントの原因
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| オーバーユース(過度な練習や反復動作) | 長時間の練習や繰り返し動作による骨膜への過剰な負担 |
| 筋力・柔軟性・体幹機能の不均衡 | 下腿や体幹の筋力不足、柔軟性低下による衝撃吸収力の低下 |
| 足部アライメントやフォームの乱れ | 扁平足や回内足、誤ったランニングフォームによる負担の偏り |
| 環境・個体差による影響 | 硬い路面、不適切な靴、成長期や体質による負荷の蓄積 |
シンスプリントは、骨膜に繰り返し負担がかかることで発症するスポーツ障害です。長時間の練習や急激な運動量の増加は骨膜へのストレスを高めます。
筋力や柔軟性の低下、足部のアライメント異常、環境要因などが重なり、骨膜への負担が蓄積してシンスプリントを発症すると考えられます。

以下の記事では、シンスプリントの原因について詳しく解説しています。
オーバーユース(過度な練習や反復動作)
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 骨膜への繰り返しストレス | 走行やジャンプ動作の反復による脛骨骨膜への牽引ストレスと微細損傷の蓄積 |
| 修復と負荷のバランスの乱れ | 急激な運動量の増加や休養不足による修復機能の低下とダメージの慢性化 |
| 特定動作の反復による負担集中 | 長距離走や方向転換動作の繰り返しによる脛骨内側への局所的ストレスの集中 |
シンスプリントの主な原因は、運動負荷の過剰と回復期間の不足による不均衡です。急激なトレーニング量の増加や休息を取らない反復運動によって骨膜に小さな損傷が繰り返し起こり、累積したストレスが炎症を引き起こします。
運動量の急増や硬い路面での長時間の運動などによるオーバーユースが、シンスプリント発症の主な要因とされています。
筋力・柔軟性・体幹機能の不均衡
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 筋力不足 | ふくらはぎや足底の筋力低下による衝撃吸収力の低下と骨膜への負担集中 |
| 柔軟性低下 | 下腿後面やアキレス腱の硬さによる骨膜への牽引ストレスの増大 |
| 体幹機能低下 | 体幹の不安定さによるフォームの乱れと下肢への負担の偏り |
シンスプリントの原因は、筋力・柔軟性・体幹機能のバランスが崩れることです。ふくらはぎや足底の筋力が不足すると衝撃を十分に吸収できず、脛骨への負担が増加します。
さらに、柔軟性の低下により骨膜への牽引力が強まり、微細な損傷が起こりやすくなります。体幹の不安定さによってランニングフォームが乱れると、片側のすねに過剰な負担が集中します。
足部アライメントやフォームの乱れ
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 足部アライメント異常 | 扁平足や過回内による足のアーチ機能低下と脛骨内側の負担増加 |
| フォームの乱れ | 体幹の不安定さや偏った接地による同一部位への繰り返し負荷 |
| 微小外傷の蓄積 | 小さなストレスの反復による骨膜・筋付着部の損傷蓄積と炎症誘発 |
シンスプリントの発症には、足部のアライメント異常やフォームの乱れが大きく関与しています。扁平足や過回内では足のアーチ構造が崩れ、着地時の衝撃を十分に吸収できず、脛骨内側に負担が集中して骨膜炎を起こしやすくなります。
ランニングやジャンプ動作で体幹が不安定になり接地が偏ると、毎回のステップで同じ部位に強いストレスがかかり、とくに片脚への荷重の偏りが炎症を助長します。
こうした不適切な動作が繰り返されることで、骨膜や筋付着部に微細な損傷が蓄積し、炎症が慢性化します。予防には、正しいフォームの習得や、インソール・靴による足部アライメントの補正が不可欠です。
環境・個体差による影響
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 運動環境の影響 | 硬い路面や不整地でのトレーニングにより、着地時の衝撃が増し、足部に負担が集中 |
| 運動量・強度の急激な変化 | トレーニング量や強度の急増による筋肉・骨膜への過剰負荷と疲労蓄積 |
| 個体差(足の形状・筋力など) | 扁平足や回内足、筋力不足や柔軟性低下による骨膜へのストレス増大 |
| 身体的・技術的要因の複合効果 | 体幹の不安定やフォームの乱れと環境・個体差が重なることで発症リスク上昇 |
シンスプリントの発症には環境要因と個人の身体特性が関与しています。硬い路面や不整地での練習、クッション性の低いシューズは着地時の衝撃を増大させます。
運動量の急激な増加、扁平足や回内足などのアライメント異常、筋力不足や柔軟性低下が過剰な負荷と疲労蓄積の原因です。体幹の不安定性やフォームの乱れが加わると、発症リスクはさらに高まります。環境調整と身体機能改善の両面から対策を講じることが重要です。
シンスプリントの初期症状
| 初期症状 | 詳細 |
|---|---|
| 運動時の痛み・違和感 | ランニングやジャンプ動作時に感じるすね内側の鈍い痛みや違和感 |
| 運動後の痛み・不快感 | 運動後に現れる鈍い痛みや重だるさ、不快感の持続 |
| すねの圧痛・筋肉の張り | すね内側を押したときの痛みや、ふくらはぎ全体の張りやこわばり |
シンスプリントの初期には、運動時のすね内側に鈍い痛みや違和感が現れます。症状が進行すると運動後にも重だるさや不快感が残るようになります。
また、すねの内側を押すと痛みを感じ、ふくらはぎの筋肉に張りやこわばりがみられます。初期段階で適切に対応すれば改善が期待できるため、早期発見と休養が重要です。

以下の記事では、シンスプリントの症状チェックのやり方を詳しく解説します。
運動時の痛み・違和感
| 初期症状 | 詳細 |
|---|---|
| 運動時の痛み・違和感 | 運動開始直後の骨膜および筋腱移行部への牽引ストレスによる鈍い痛みや違和感 |
| 運動後の痛み・不快感 | 運動終了後の休息時にも続く違和感や圧痛 |
| 骨膜・軟部組織のストレス | 骨膜や周囲軟部組織への繰り返しの牽引ストレスや衝撃による微細な炎症・ストレス反応 |
シンスプリントは、すねの骨膜に繰り返しストレスがかかることで起こる障害です。ランニングやジャンプなどの運動により骨膜に微小な炎症が生じ、とくに運動開始直後に痛みや違和感が現れます。
初期段階では体が温まると症状が軽減することがありますが、これは異常反応のシグナルと捉えるべきです。症状が進行すると運動後や安静時にも違和感や圧痛が残るようになります。この段階での違和感を軽視せず、運動量の調整や医療機関を早めに受診することが重要です。
運動後の痛み・不快感
| 要因 | 詳細 |
|---|---|
| 骨膜・軟部組織への微小炎症 | 運動による繰り返しストレスで骨膜や筋付着部に炎症が起こり、運動後に痛みや不快感が出現 |
| 筋肉疲労と牽引ストレスの残留 | ヒラメ筋や後脛骨筋の疲労により柔軟性が低下し、骨膜への牽引力が持続・増強 |
| 血流変化による炎症の顕在化 | 運動後の血流変化で炎症が表面化し、安静時に痛みを感じやすくなる状態 |
シンスプリントは、すねの骨膜やその周囲組織に繰り返しストレスがかかることで発症する障害です。運動後に痛みや不快感が強くなることが初期段階の典型的なサインです。
運動を続けることで、骨膜や筋付着部には微小な炎症が生じ、疲労した筋肉が硬くなることで骨膜への牽引ストレスが残りやすくなります。実際、シンスプリントは「繰り返しストレスによって発生する足の痛み・不快感」とされ、運動後に症状が強くなることが知られています。(文献2)
また、運動中は血流が活発になり炎症反応を感じにくい一方で、運動を終えると筋肉の緊張緩和や循環の変化によって炎症が顕在化し、痛みや不快感が現れやすくなります。
運動直後よりも安静時のほうが痛みを感じやすくなるため、この段階で生じる違和感を放置せず、早めに休養を取り医療機関を受診することが重要です。
すねの圧痛・筋肉の張り
シンスプリントでは、繰り返しの運動によって脛骨周囲の骨膜が引っ張られ、脛骨内側の骨膜炎により圧痛が生じます。また、ふくらはぎの主にヒラメ筋や後脛骨筋が疲労して硬くなると、筋肉の柔軟性が低下し、骨膜への牽引ストレスが増加します。これが筋肉の張りや痛みの原因となり、運動中や運動後に症状が強まります。
炎症が進行する前段階では、動作時や直後に押すと痛む、筋肉が硬いといった違和感が先行することが多く、これらは早期発見の重要なサインです。
炎症の拡大が疑われる場合、自己流のマッサージや強いストレッチは避けてください。違和感が続く場合は、整形外科での診察と適切な治療を受けることが重要です。
シンスプリントの症状進行と持続痛について
| 段階 | 状態 | 症状の特徴 |
|---|---|---|
| 初期段階 | 運動中・運動後に痛みが出現 | 休息により症状が軽減することが多い状態 |
| 進行段階 | 炎症・微細損傷の慢性化 | 運動中の痛みが強まり、休息後も症状が残存 |
| 重症段階 | 組織の修復能力を上回る負荷が継続する状態 | 安静時にも痛みが出現し、日常生活への支障 |
シンスプリントは、すねの骨膜や周囲組織に繰り返しストレスが加わることで発症します。初期段階では運動中や運動後に痛みが出現しますが、休息により症状が軽減することが多い状態です。しかし、適切なケアを行わず負荷を続けると、炎症や微細な損傷が慢性化し、症状が進行します。
骨膜や筋腱は休息や修復反応によってダメージを回復させる能力がありますが、修復が追いつかないほど負荷が加わり続けると、損傷と炎症が累積します。進行段階では運動中の痛みが強まり、休息後も症状が残存するようになります。
重症化すると安静時にも痛みが生じて日常生活に支障を来し、持続痛や強い局所痛がある場合は疲労骨折へ進展するおそれもあるため、早期対応が重要です。
シンスプリントの治し方(治療方法)
| 治し方(治療方法) | 詳細 |
|---|---|
| 安静と運動調整 | 痛みの原因となる運動を一時的に中止し、運動量や強度を段階的に調整する休養と負荷管理 |
| 炎症抑制・物理療法 | 炎症や痛みを抑えるためのアイシング、超音波療法、低出力レーザー治療などの実施 |
| ストレッチ・筋力トレーニング・リハビリ | 下腿や体幹の柔軟性・筋力を整え、再発予防を目的とした段階的リハビリの実施 |
| テーピング・装具(インソールなど) | 足部アライメントを整え、衝撃や負担を軽減するためのテーピングやインソールの使用 |
| 薬物療法 | 炎症や痛みを緩和するための消炎鎮痛剤や外用薬の使用 |
| 再生医療 | 慢性化した場合に用いられる、自己修復を促すPRP療法(多血小板血漿注入)などの再生治療 |
シンスプリントの治療は、まず安静と運動量の調整により炎症の悪化を防ぎます。急性期にはアイシングや超音波などの物理療法で痛みと炎症を抑え、回復期にはストレッチや筋力トレーニングで柔軟性と安定性を取り戻します。
足部アライメントを整えるためのインソールやテーピングも有効です。症状が強い場合は薬物療法を併用し、慢性化例では再生医療を検討する場合もあります。ただし、再生医療は適用できる医療機関が限られており、患者の症状によっては適用できないケースもあるため、事前に医師との相談が不可欠です。
以下の記事では、治らないシンスプリントの治療法について詳しく解説しています。
安静と運動調整
シンスプリントの治療において、安静と運動調整が基本です。過度な練習や反復動作で生じた炎症は、運動を続けると悪化するため、安静により炎症を鎮静化させ、組織の修復を促します。運動を完全に止めるのではなく、症状を悪化させない範囲での運動量や内容の調整が大切です。
練習強度を下げる、回数を減らす、水泳や自転車など衝撃の少ない運動へ切り替えることで、体力を維持しながら回復を図ります。発症初期には患部に負担をかけない軽いストレッチや上半身トレーニングが推奨されます。
症状が軽快しても違和感が消えてから数日経過し再発がないことを確認した上で段階的に負荷を増やし、無理な練習継続による慢性化を避ける計画的な復帰が重要です。

炎症抑制・物理療法
シンスプリントは脛骨の骨膜に炎症が生じるため、炎症抑制と物理療法が治療の中心です。急性期には患部を安静にし、アイシングや非ステロイド性抗炎症薬で炎症を鎮めます。超音波療法などの物理療法は血流を改善し、組織修復を促進します。
症状が軽減したらストレッチや筋力強化運動を段階的に行って筋肉や骨膜の回復を促し、痛みが消えた後も急に運動強度を戻すと再発のリスクが高まるため、医師の指導に従い、段階的に運動量を増やすことが重要です。
ストレッチ・筋力トレーニング・リハビリ
| 項目 | 目的・内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ストレッチ | 筋肉や腱の柔軟性向上、関節可動域の拡大、怪我予防、血流促進 | 痛みの手前で止める、反動をつけない、怪我部位は専門指導のもとで実施 |
| 筋力トレーニング | 筋力・持久力の向上、姿勢安定、関節保護、骨密度維持、代謝改善 | 正しいフォームの維持、負荷の段階的増加、呼吸を止めない、持病は医師に相談 |
| リハビリテーション | 機能回復、痛みや拘縮・筋萎縮の改善、日常・スポーツ復帰支援 | 過負荷を避ける、医師の計画に基づく実施、痛み時は中止、継続の徹底 |
ストレッチ、筋力トレーニング、リハビリテーションは、シンスプリントの根本的な改善に不可欠です。ストレッチはヒラメ筋や後脛骨筋を柔らかくし、骨膜への牽引力を軽減して痛みを和らげ、再発を防ぎます。
筋力トレーニングは足部アーチのサポート力や体幹の安定性を向上させ、運動時の負担を分散します。リハビリテーションでは痛みの程度に応じて運動負荷を段階的に調整し、筋肉や骨膜の耐久性を向上させます。これらは医師や理学療法士の指導のもと、個々の症状に応じて実施が重要です。
以下の記事では、シンスプリントに対して有効なリハビリ方法を解説しています。
テーピング・装具(インソールなど)
| 項目 | 目的・効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| テーピング | 関節や筋肉の安定化、損傷部位の保護、痛みの軽減、フォーム補正 | 強く巻きすぎない、長時間の使用を避ける、皮膚トラブルに注意、根本治療ではなく補助的手段 |
| 装具 | 関節の安定・保護、変形や再発の予防、動作補助、痛み軽減、歩行や姿勢の改善 | 長時間使用による筋力低下に注意、医師の指示に従う、装着部の皮膚状態を確認 |
| インソール | 足部アライメントの矯正、荷重分散、歩行・ランニング効率の改善、スポーツ障害の予防 | サイズや靴との相性を確認、定期的な見直し、合わない場合は使用を中止 |
テーピングとインソールは、シンスプリントの症状軽減と再発予防に有効な補助手段です。適切なテーピングは脛骨周囲の筋肉や骨膜を適度に圧迫し、筋肉の振動や骨膜への牽引力を抑制することで、痛みの軽減と炎症の進行予防に役立ちます。
また、足部の安定性を高め、床からの衝撃や不均等な負担を分散させることで、患部へのストレスを軽減します。さらに、テーピングは関節の過度な動きを制限し、筋肉や関節の過負荷を防ぐため、スポーツ活動時の怪我予防や再発予防に効果的です。
インソールは足部アーチをサポートし、歩行や運動時の足全体のバランスを整えることで、骨膜への負担を軽減します。これらの補助手段は、根本的な治療ではありませんが、ストレッチや筋力トレーニングと併用することで、症状の改善と長期的な再発予防が期待されます。
以下の記事では、シンスプリントにおけるテーピング方法について詳しく解説しています。
薬物療法
シンスプリントは脛骨の骨膜や筋腱付着部の炎症により発症するため、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)による炎症抑制が症状軽減に有効です。内服薬や外用薬は炎症と痛みを軽減し、日常生活やリハビリを行いやすくします。
ただし、薬物療法は過度な炎症反応をコントロールして自然治癒を助ける補助的な役割です。安静、物理療法、リハビリテーションと組み合わせることで効果が最大化されます。
薬物療法は短期間の使用が推奨されるため、市販薬を自己判断で長期間使用することは避け、医師の指示に従って服用してください。根本的な改善のためには、薬物療法に加えて運動量の調整や筋力・柔軟性の改善など、包括的なアプローチが欠かせません。
再生医療
シンスプリントは脛骨周囲の骨膜や筋腱付着部に繰り返しストレスが加わり、炎症や微細な損傷が生じる状態です。多くは安静や運動調整で改善しますが、症状が慢性化したり再発を繰り返したりする例も存在します。
難治性の症例では、脂肪由来幹細胞による組織修復促進や血小板に含まれる成長因子による抗炎症作用が期待される再生医療が治療の選択肢となる場合があります。
ただし、再生医療を実施できる医療機関は限られており、患者の症状や状態によっては適用できないケースもあるため、治療を検討する際には医師への相談が不可欠です。
以下の記事では、再生医療について詳しく解説しています。
シンスプリントはどこで診てもらうべき?
| 項目 | 医療機関(整形外科) | 整体・接骨院 |
|---|---|---|
| 診断 | 医師が診察・画像検査で原因を特定 | 画像検査ができず診断不可 |
| 対応内容 | 医学的治療・リハビリの計画 | 筋肉調整やマッサージ中心 |
| 適応範囲 | 炎症・骨膜障害・疲労骨折など幅広く対応 | 軽度の筋緊張緩和のみ |
(文献3)
シンスプリントが疑われる場合、整形外科またはスポーツ整形外科の受診が基本です。自己判断でストレッチや湿布のみで対応すると、炎症が悪化して回復が遅れる可能性があります。
整形外科では問診・触診に加え、レントゲンやMRI検査などで疲労骨折との鑑別診断を行います。これにより症状の進行度を正確に評価し、適切な治療方針を決定します。
とくにスポーツ整形外科では、アスリートや運動習慣のある方を対象に、再発予防まで含めた包括的なリハビリを提供します。理学療法士が筋肉の柔軟性や体幹バランスを評価し、段階的な運動再開をサポートします。
なお、接骨院や整体などでの施術は一時的に症状が軽減したように感じられることがありますが、根本的な改善につながる医学的根拠は十分に確立されていません。まずは医療機関での正確な診断を受けることが重要です。

シンスプリントの予防方法
| 予防方法 | 詳細 |
|---|---|
| 運動量と休養の調整 | 運動量や強度を段階的に増やし、疲労を蓄積させないスケジュール管理。十分な休養日を設け、筋肉や骨膜の回復を促すバランス調整 |
| 身体機能の改善(筋力・柔軟性・フォーム) | 下腿筋群のストレッチや筋力トレーニングによる衝撃吸収力の向上。ランニングフォームや着地動作の改善による負担分散 |
| 外的要因への対応(シューズ・インソール・環境) | クッション性やフィット感に優れたシューズの選択。インソールによる足部アライメントの補正。硬い路面や傾斜地での練習回避 |
シンスプリントの予防には、運動負荷と身体機能、環境要因への多角的なアプローチが必要です。まず、急激な運動量の増加を避け、十分な休養を確保することで組織の修復を促します。
次に、下腿筋群や体幹の筋力強化、ストレッチによる柔軟性向上、正しいランニングフォームの習得を行い、衝撃吸収能を高めて負荷を適切に分散させます。
クッション性に優れたシューズの選択や足部アライメントに合わせたインソールの使用、硬い路面を避けた練習環境の見直しも重要です。これらの要素を総合的に実践することで、シンスプリントの発症リスクを効果的に低減できます。

運動量と休養の調整
シンスプリントの予防には、運動量の段階的調整と適切な休養の確保が基本となります。加えて、筋力強化やストレッチによる柔軟性向上、正しいフォームの習得といった身体機能の改善により、下腿への負担を軽減できます。
さらに、足に合ったシューズやインソールの活用、硬い路面の回避など外的環境を整備することも重要です。これらの対策を総合的に実践することで、シンスプリントの発症・再発リスクを抑制し、継続的な運動が可能になります。
身体機能の改善(筋力・柔軟性・フォーム)
シンスプリントの再発予防には、身体機能の総合的な改善が重要です。筋力強化では、ヒラメ筋や後脛骨筋を鍛えることで骨への負担を軽減します。ゴムチューブを用いたふくらはぎのトレーニングや足指でタオルを引き寄せる運動が効果的です。
柔軟性向上ではヒラメ筋を中心としたストレッチを運動前後に習慣化し、フォーム改善では適切な着地方法や膝の角度、姿勢を段階的に習得することで、炎症リスクと脛骨への衝撃を軽減します。
適切な運動量の調整や休養を取り入れながら実践することで、衝撃を吸収する力が高まり、筋肉への牽引ストレスが減少し、荷重のバランスも整いやすくなります。
外的要因への対応(シューズ・インソール・環境)
シンスプリントの再発予防には、練習環境やシューズなど外的要因への配慮が重要です。クッション性が低下したシューズや足に合わない靴を使用すると、着地時の衝撃が脛骨へ直接伝わり骨膜への負担が増大します。
競技特性や足型に合ったシューズを選び、定期的に交換することが大切です。扁平足や過回内がある場合は、医療用またはスポーツ用インソールで足のアライメントを補正し、荷重バランスを整えることが有効です。
また、アスファルトなどの硬い路面ばかりで練習せず、芝生やゴムトラックなど柔らかい地面を取り入れることで衝撃を軽減できます。これらの外的要因を見直すことは、身体への負担を減らし再発予防を支える重要な要素です。
シンスプリントを理解して適切な対策を講じよう
シンスプリントは、スポーツを続ける人に多く見られる下肢の障害で、脛骨周囲の骨膜や筋肉に炎症やストレスが生じることで発症します。初期の段階で適切に対応すれば回復しやすいため、違和感を放置せず早めにケアしましょう。
運動量の調整やストレッチ、シューズの見直しなど、日常の工夫で負担を軽減できます。症状が続く場合や再発を繰り返す場合は、整形外科での診断とリハビリが必要です。
シンスプリントの治療についてお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。当院では、患者さまご自身の細胞や血液成分を用いる再生医療を行っており、損傷した組織の修復をサポートする治療の選択肢としてご案内しています。症状や状態に応じて、適切な方法を検討しご提案いたします。
ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。
\無料オンライン診断実施中!/
シンスプリントに関するよくある質問
シンスプリントは休養期間を設ければ改善しますか?
シンスプリントは、適切な休養を取ることで改善が期待できる場合があります。初期症状であれば約2週間の安静で痛みが和らぐこともありますが、無理な運動再開は再発の原因になります。
症状が続く場合は医療機関での診察やリハビリが必要です。筋力や柔軟性の改善を並行して行うことが回復への近道です。
以下の記事では、シンスプリントの休むべき期間について詳しく解説しています。
家族がシンスプリントになったときはどうすれば良いですか?
シンスプリントの回復には、休養とセルフケアに加え、心身のサポートが重要です。お子さまが痛みを抱えているときは、無理に運動を続けさせず安静を保つことが大切です。
症状が落ち着いたら、自転車や水泳など負担の少ない運動に切り替え、段階的に練習を再開しましょう。アイシングやテーピング、インソールの使用も有効です。
思うように動けない時期は焦りや不安を感じやすいため、ご家族が寄り添い、前向きな気持ちで回復に取り組めるよう支えることも大切です。痛みが続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
シンスプリントは走りながら治すことはできますか?
シンスプリントは脛骨周囲の骨膜や筋付着部に炎症が生じる障害です。痛みを抱えたまま走り続けると疲労骨折へ進行するおそれがあるため、推奨されません。
初期の違和感程度であれば、医師の診断を受けた上で運動強度や距離を調整し、路面やシューズを見直すことで回復を図れます。
治療は安静や物理療法、筋力・柔軟性の向上を基本とし、症状が落ち着いてから段階的に運動の再開が望まれます。
以下の記事では、シンスプリントを走りながら治せるかについて詳しく解説しています。
参考文献
(文献1)
シンスプリント|MSD マニュアル プロフェッショナル版
(文献2)
Medial tibial stress syndrome: conservative treatment options|PMC PubMed Central®