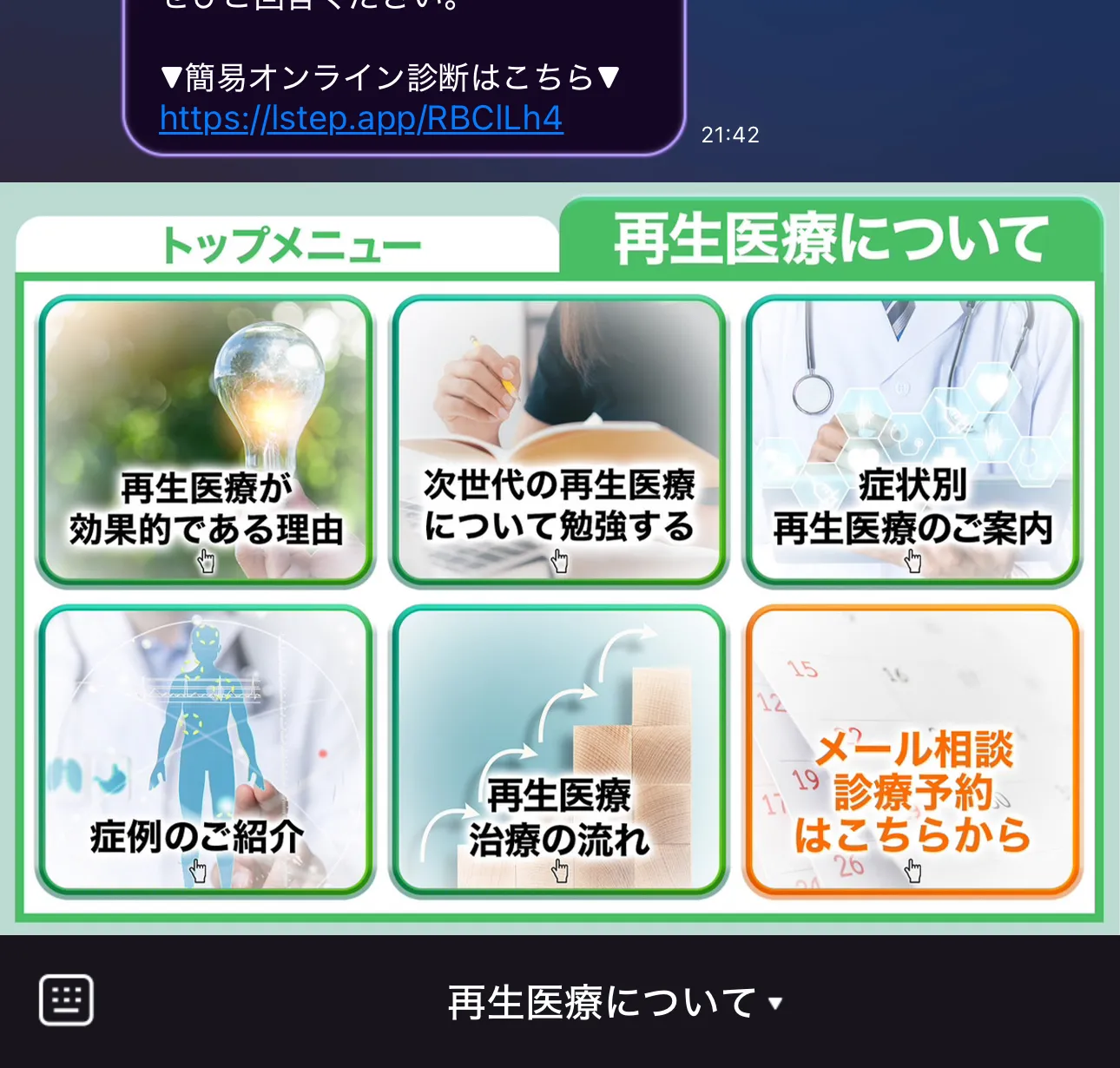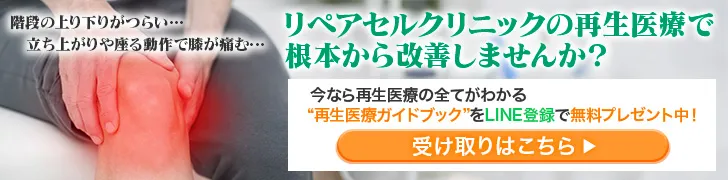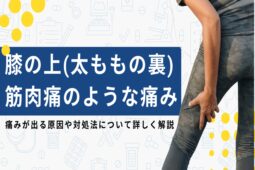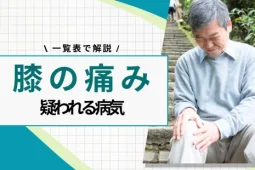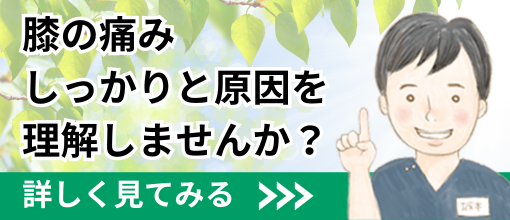- ひざ関節
- 変形性膝関節症
変形性膝関節症の治療ガイドライン(治療方針)に基づいた運動療法

目次
変形性膝関節症の治療ガイドライン(治療方針)に基づいた運動療法とは
「変形性膝関節症のため、膝が痛い」そんなお悩みはありませんか?
変形性膝関節症は、膝にかかる衝撃を吸収・分散する役割を担う関節軟骨がすり減ることで、関節内部に炎症が起きるほか、関節に変形が起こり痛みを感じる疾患です。
男女比は、女性に多く、年齢は50代以降と年を重ねるほど罹患率は高くなります。
膝の痛みで病院を受診し、変形性膝関節症と診断されると、膝に負担がかかる日常生活を見直すよう指導されるほか、運動療法により膝を安定させる筋肉を鍛えるよう指導されます。
このような治療方針は、変形性膝関節症の「診療ガイドライン」に基づき決定されています。この記事では、「変形性膝関節症のガイドライン」と、それに基づいた運動療法をご紹介します。
変形性膝関節症との診断で指導されるガイドライン(治療方針)
- 日常生活を見直すよう指導(膝に負担がかからぬよう)
- 運動療法(リハビリ)で筋肉を鍛えて膝を安定させる
変形性膝関節症のガイドライン(治療方針)とは
変形性膝関節症には、糖尿病診断に用いる血糖値・HbA1cというような基準が確立されていません。
そのため変形性膝関節症の進行度合いや、治療効果を評価するために各国独自で診療ガイドラインが作成されています。日本では日本整形外科学会の定めた「変形性膝関節症の管理に関するOARSI勧告 OARSIによるエビデンスに基づく「エキスパートコンセンサスガイドライン変形性膝関節症ガイドライン」があります。
これは変形性膝関節症唯一の国際学会であるOARSIが定めたガイドラインを翻訳し、日本人向けに適合させたガイドラインです。
そんな日本整形外科学会の変形性膝関節症ガイドラインには「定期的な有酸素運動、筋力強化訓練および関節可動域訓練を実施し、かつこれらの継続を奨励する」と記載されていることからも、変形性膝関節症の治療に、運動療法が有効だと推奨されています。
運動療法を行うことで、筋力低下、加齢により不安定になった膝の安定性を高め、痛みをかばうことで拘縮が起きている膝の可動域を向上させます。
また運動療法は、膝への負担になる肥満の解消にもつながることからも、変形性膝関節症に対して基本の治療として評価されています。
”引用:変形性膝関節症の管理に関する OARSI 勧告―OARSI によるエビデンスに基づくエキスパートコンセンサスガイドライン(日本整形外科学会変形性膝関節症診療ガイドライン策定委員会による適合化終了版)”
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/106/1/106_75/_pdf/-char/ja
ガイドライン(治療方針)に基づいた痛みを緩和する運動療法とは
次にガイドラインに記載されている「有酸素運動」「筋力強化訓練」「可動域訓練」を紹介していきます。
有酸素運動
有酸素運動とは酸素を取り込みながら行う運動で、ウォーキングのほか長距離走・ヨガなどがあります。有酸素運動は酸素を取り込まずに行う無酸素運動と比べて、緩やかな運動が多いため、変形性膝関節症のように膝に痛みを抱えている方にはおすすめです。
その中でもウォーキングや、プールなどでの水中運動が変形性膝関節症の方に一般的な有酸素運動です。
変形性膝関節症の方のウォーキングは、無理のない距離とペースで取り組むことが大切です。1日1万歩と推奨されていることがありますが、無理に行う必要はありません。
無理をすると、かえって膝を傷めるばかりか、痛みが落ち着くまで運動に取り組めないなど、治療に支障をきたします。
またウォーキングをすると、痛みが強く満足に取り組めない場合は、プールでの水中運動がオススメです。水中では浮力がかかる分、膝をはじめ全身への負荷が下げることができます。
筋力強化訓練
大腿四頭筋などを筋力強化することで、膝の安定性が増します。代表的なものに、足あげトレーニングがあります。椅子に座った姿勢、または仰向けに寝転んだ状態で行います。
片側の膝を伸ばし、90度(寝た状態では30〜45度)挙上した状態で10秒ほどキープ、降ろして数秒間休憩します。これを20回繰り返します。全身を動かすウォーキングと違い、低負荷で大腿四頭筋をピンポイントに鍛えることができます。
可動域訓練
膝に痛みがある状態では、立ち座り、歩くといった動作がおっくうになってしまい、次第に関節の可動域が低下します。可動域が低下すると関節の柔軟性がなくなり余計に痛みを感じやすくなることから、普段から膝を曲げ伸ばしして、可動域を広げていく必要があります。
可動域訓練は、足あげトレーニングと同じ座った姿勢で、膝を曲げたり伸ばしたりすることにより可動域を広げていきます。筋力強化訓練・可動域訓練ともに椅子に座りながら行える点から、どちらの運動をしているのか混同しないように、意識して使い分けることがポイントです。
まとめ・変形性膝関節症の治療ガイドライン(治療方針)に基づいた運動療法
今回紹介した有酸素運動・筋力強化訓練・可動域訓練に取り組むにあたり、いきなり長い距離を歩いたり、強度な運動をすると、かえって膝の負担になります。
くれぐれも無理はせず、これまでの運動習慣や痛みの程度と相談しながら運動に励みましょう。
また歩行で痛みを感じる際には「杖の使用」をおすすめします。一般的な杖に、持ち手がT字のものがありますが、最近ではノルディック杖のようなスポーティーなタイプも普及しており、選択肢は増えています。
変形性膝関節症になると、膝の痛みをかばい、活動量が減ってしまいがちですが、ガイドラインで推奨されているように、体を動かしながら悪化を防ぐことが基本的な治療方法だと覚えておきましょう。
もし、膝関節の痛み、変形性膝関節症でお悩みなら私どもにご相談ください。先端分野である再生医療でお役に立てるかもしれません。症状は、遅れれば遅れるほど進行する恐れがあります。
痛みは早期治療が大原則です。
もう一つの再生医療(幹細胞治療)
当院にいただくお問い合わせでよくお聞きするのは、
「治療に行ってもヒアルロン酸の注射や、痛み止めしかなく、改善しない」ということ。
実のところ、従来の治療では、現在の症状を回復させることはできず、痛みを緩和することしかできません。それもそのはず、痛みを伴う軟骨のすり減りを改善させることは難しく、痛みを少なくする方法しかなかったからです。
その結果、症状が進行し、人工関節の手術ということになりがちでした。そんな中、医学の進歩で「再生医療」という医療分野が発達してまいりました。
自分自身の「幹細胞」を用いた自己治癒力で軟骨を再生できるようになったのです。
当院は厚生労働省から認められた再生医療専門です。
「幹細胞?」「自己治癒力?」「再生医療?」・・・ご不明点は、ご遠慮なくお問い合わせください。
▲リペアセルクリニック医師が解説。こちらの動画も参考になりましたら幸いです。
変形性膝関節症は、「再生医療」により手術せずに症状を改善することが可能です
▼以下もご参考していただけます
変形性膝関節症の進行を予防するために!膝の負担を減らす方法を医師が解説