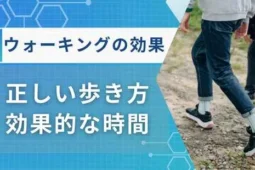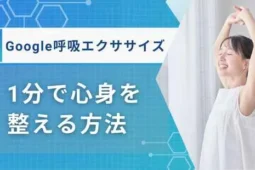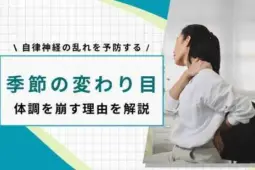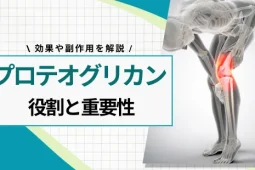- 健康・美容
骨を強くする食べ物とは?社会人や高齢者向けに医師が詳しく解説

「骨粗しょう症が心配」「関節痛が気になる」と悩んでいませんか。骨が弱くなる大きな原因はカルシウムの不足ですが、他の栄養素によるサポートも丈夫な骨を作るためには欠かせません。また、生活習慣の見直しも大切です。
本記事では、社会人や高齢者が骨を強くするための食事・生活習慣を医師が紹介します。骨のために避けたい食事・生活習慣もお伝えするので、普段の生活を見直し丈夫な骨を作っていきましょう。
目次
骨を強くする食べ物はどんなもの?4つの栄養素がカギ

日本人の多くはカルシウム不足だといわれます。また、丈夫な骨を作るためにはカルシウム以外の栄養素もバランスよく摂ることが大切です。
以下では骨を強くするためにとくに大切な4つの栄養素について説明します。
| 栄養素 | 効果 |
| カルシウム | 骨の材料となる |
| ビタミンD | カルシウムの吸収を助ける |
| ビタミンK | 骨が作られるのを助ける |
| マグネシウム | 骨が作られるのを助ける |
カルシウム|骨を丈夫にする
カルシウムは骨に最も多く含まれるミネラルです。
カルシウムが不足して骨が弱くなれば、骨折のリスクが増加します。また、立つ・歩くなど生活動作を行う身体能力が徐々に低下し、日常生活に支障が出たり要介護状態となったりするのです。
この身体能力の低下を「ロコモティブシンドローム(ロコモ)」といい、近年問題視されています。
骨のカルシウムを維持して元気に暮らし続けるために、以下のようなカルシウムを豊富に含む食品を積極的に摂りましょう。
|
とくに乳製品および大豆食品中のカルシウムが吸収されやすいとの報告があります。野菜や海藻はこれらの食品と一緒に摂ると、吸収されやすくなるためおすすめです。
参考:もっと知ろう!「ロコモティブシンドローム」|日本整形外科学会
骨を強くするメリット
骨を強くするということは、骨密度が高い丈夫な骨をつくるということを意味します。骨を強くすると、加齢に伴う骨粗鬆症や骨折などのリスクを少なくし、要介護や寝たきり状態の予防に繋がるのです。
また、骨を強くする方法は、関節軟骨のすり減りを抑える方法とも深い関わりがあるため、関節痛や腰痛の予防にも高い効果を発揮します。
骨折や関節痛に悩まされる事の無い生活を送るためにも、骨を強くするための生活習慣について知っておきましょう。
ビタミンD|カルシウムの吸収を助ける
ビタミンDは、腸からのカルシウムの吸収を助ける栄養素です。尿中に出ていくカルシウムを減らすはたらきもあり、カルシウムを効率よく利用するために欠かせません。
ビタミンDは魚類やきのこに多く含まれます。具体的には以下の食品です。
|
しいたけに含まれるビタミンDは、紫外線に当たると増える性質があります。生でも干ししいたけでも、食べる前に天日に当てるとより多くのビタミンDを摂取できます。
ビタミンK|骨の形成を促進する
ビタミンKは、体内に吸収されたカルシウムが骨に取り込まれるのを助ける栄養素です。以下のように、色の濃い葉野菜や納豆に多く含まれます。
|
ビタミンKは油とともに食べると吸収されやすくなります。野菜は炒め物にしたり肉類と一緒に食べたりするほか、油の入ったドレッシングをかけるのもおすすめです。
納豆はとくにビタミンKが豊富ですが、血栓症予防のための抗凝固薬の効果を妨げる場合があります。このような薬を服用中の方は、主治医の指示に従ってください。
マグネシウム|骨の形成を促進する
マグネシウムは、カルシウムが骨に取り込まれるのを助けるほか、骨の材料としても大切な栄養素です。体内にあるマグネシウムのうち、50〜60%は骨に存在します。
マグネシウムを多く含む食品には次のものがあります。
|
大豆製品や魚介類にはカルシウムも豊富です。ぜひ積極的にとりましょう。
参考:1-7 ミネラル(1)多量ミネラル①ナトリウム(Na)|厚生労働省
骨を強くする栄養素の吸収を促す食品を摂ることも大切
食事で摂るカルシウムは、そのままでは腸から吸収されにくい性質があります。効率よく吸収されて骨に取り込まれるためには、サポートする栄養素と組み合わせることが重要です。
また、骨にはコラーゲンなどのたんぱく質も含まれます。コラーゲンはカルシウムが固まるための「骨組み」となり、骨のしなやかさを保つ役目があるため、カルシウムと同様に骨の健康を保つ上で大切です。
カルシウムのはたらきをサポートする栄養素と、それらが多く含まれる食品を以下にまとめました。
| 栄養素 | 効果 | 主な食品 |
| たんぱく質 | コラーゲン(骨の骨組み)の材料となる | 豆腐、肉、魚 |
| ビタミンC | コラーゲンが作られるのを助ける | 野菜、果物 |
| ビタミンD | カルシウムの吸収を助ける | きのこ類 |
| ビタミンK | 骨が作られるのを助ける | 納豆 |
| マグネシウム | 骨が作られるのを助ける | 大豆、アーモンド |
これらの食品を、カルシウムを多く含む食品と合わせて摂ると食事全体のバランスも良くなるためおすすめです。
骨を強くすると骨折・関節痛・腰痛などを予防できる
骨を強くするには、骨密度が高い丈夫な骨を作ることが必要です。骨を強くすると、加齢に伴う骨粗しょう症や骨折などのリスクを減らし、要介護や寝たきり状態の予防につながります。
また骨を強くする方法は、関節軟骨のすり減りを抑え、関節痛や腰痛の予防にも高い効果を発揮します。
骨折や関節痛に悩まされることの無い生活を送るためにも、骨を強くするための生活習慣を知っておきましょう。
骨にいい食べ物以外で骨を強くするための方法
骨に良い食べ物に、以下の対策を組み合わせることで、より効果的に骨の強化が可能です。
|
ここでは社会人・高齢者の方にも取り入れやすい方法を紹介します。
積極的に日に当たる
カルシウムの吸収を助けるビタミンDは、紫外線に当たることで皮膚でも作られます。屋内で過ごす時間が長い方や、綿密な紫外線対策を行っている方は、毎日意識して日光浴を取り入れましょう。日焼けが気になる場合は、手のひらを日光浴させるだけでも効果があります。
日光浴の時間の目安は、冬場なら日なたで30分〜1時間程度、夏場なら木陰で15分〜30分程度です。直射日光を浴びなくても窓際で過ごしたり、洗濯物干しのついでに陽に当たったりすれば十分です。紫外線を浴びすぎると皮膚がダメージを受けるため、日光浴は適度な時間に留めましょう。
適度に運動する習慣をつける
骨に適度な刺激が加わると、骨を作る細胞が活発化します。日常生活の中で運動量を増やすことで、骨が強くなるのです。
以下では社会人や高齢者が取り組みやすい運動を紹介します。
社会人で運動不足になりがちな方向け
社会人の方は、通勤や移動時間を活用して、意識して運動量を増やしましょう。歩幅を広くしたり、早歩きしたりするだけでも負荷は上がります。
できれば普段の道のりより少し遠回りするなど工夫して10分長く歩いてみましょう。階段も積極的に利用してください。上りよりも下りの方が、骨に負荷がかかりやすいためおすすめです。
その他ストレッチやラジオ体操も、運動不足に効果的です。余力があれば、自宅で軽い筋力トレーニングも行ってみましょう。
高齢で身体に無理なく運動したい方向け
高齢の方は、けがや体の負担に気をつけながら、少しずつ活動量を増やしてみましょう。洗濯や掃除、買い物に出かけるなどの家事も立派な運動です。日常の活動量を増やすことから始めるとハードルが下がります。
室内で壁に手をついての片足立ちや、椅子の背などにつかまってかかとを上げて落とす運動を行うと、手軽に骨を鍛えられます。体の負担になりにくいウォーキングや水泳もおすすめです。
以下の記事も参考に、健康的な生活を目指しましょう。
骨の強化を妨げる食事・生活習慣に注意
骨を弱くするリスクのある食事・生活習慣について、以下にまとめました。思い当たるものがないかチェックしてみましょう。
|
上記で当てはまる項目が多いほど、知らないうちに骨が弱くなっている可能性があります。
O脚の方は、筋力の低下や変形性膝関節症が原因かもしれません。これらは運動不足をはじめ、骨を弱くする生活習慣とも関わります。加齢によって骨は弱くなりやすく、とくに閉経後の女性は骨粗しょう症のリスクが高いといわれるため注意が必要です。
骨のために改善したい食事・生活習慣について、以下で詳しく説明します。
|
外食・コンビニ食のしすぎ
加工食品などに使われる食品添加物には、ミネラルの一種であるリンが多く含まれます。リンはさまざまな食品に含まれており、骨の材料としても重要ですが、とりすぎるとカルシウムの吸収を妨げます。
外食やコンビニ弁当などを頻繁に利用する方は、とくにリンの摂りすぎに注意しましょう。魚のフライよりも焼き魚を選ぶなど、シンプルな調理方法のメニューを選ぶと添加物を避けやすいです。
参考:1-7 ミネラル(1)多量ミネラル①ナトリウム(Na)|厚生労働省
塩分の多い食べ物の摂りすぎ
塩分のとりすぎも、カルシウムの吸収を妨げます。濃い味付けが好きだったり、スナック菓子を頻繁に食べたりすると塩分過多になりやすいです。
また、カルシウムを摂るためにチーズや小魚を食べ過ぎると、塩分も摂り過ぎる可能性があります。
減塩の食品を選んだり、塩分が添加されていない牛乳やヨーグルトに置き換えたりして塩分の摂取量に気をつけましょう。
過度なダイエット・偏食
極端なダイエットや食事制限をしていると、若い人でも骨密度が低下しやすいです。
栄養不足になれば、骨の材料となる栄養素や、骨が作られるのを助ける栄養素も不足しがちになります。また、やせると体重による骨への負荷が減るため、骨を作る細胞への刺激も減ります。
骨密度が低下すると、将来骨粗しょう症になるリスクが高まります。無理な食事制限は行わず、1日3食バランスよく食べてしっかり運動しましょう。
過度な飲酒(アルコール摂取)
お酒を飲み過ぎるとカルシウムの吸収が悪くなります。また、アルコールの利尿作用によって尿量が増え、尿中にカルシウムが排出されやすいです。
ただ、適量のアルコールであれば骨を強くし、骨粗しょう症の予防につながるともいわれています。
飲酒は適量に抑えるか、休肝日を作るように心がけましょう。お酒の飲み方は以下の記事も参考にしてください。
喫煙(タバコ)の習慣
喫煙は骨粗しょう症の危険因子のひとつです。タバコに含まれるニコチンはカルシウムの吸収を妨げます。女性の場合は、骨を丈夫に保つ女性ホルモン(エストロゲン)が減るのも懸念点です。喫煙習慣のある方は、禁煙するか本数を減らすだけでも骨を強くする効果が期待できます。
タバコは軟骨への悪影響も指摘されており、関節症が悪化しやすいです。以下の記事も併せてご覧ください。
まとめ|骨を強くする食べ物を積極的に摂り健康的に過ごしましょう
骨の強さを表す骨密度は加齢に伴い減少していきます。とくに女性は閉経を期に骨密度が大きく低下し、骨粗しょう症のリスクが増大するといわれています。また、中高年に限らず若い方も、極端なダイエットや食事制限は骨密度の低下を引き起こすためおすすめできません。
骨を健康な状態に保つには、食事によるカルシウムの十分な摂取と適度な運動の2点が重要です。カルシウムの吸収を妨げる食事や生活習慣はなるべく避けましょう。
以上を気をつけていても膝や股関節の痛みでお悩みの場合は、当院へご相談ください。初回カウンセリングでは専門医が丁寧にご説明いたします。電話・メールでの無料相談も行っていますので、お気軽にご連絡ください。
\無料オンライン診断実施中!/