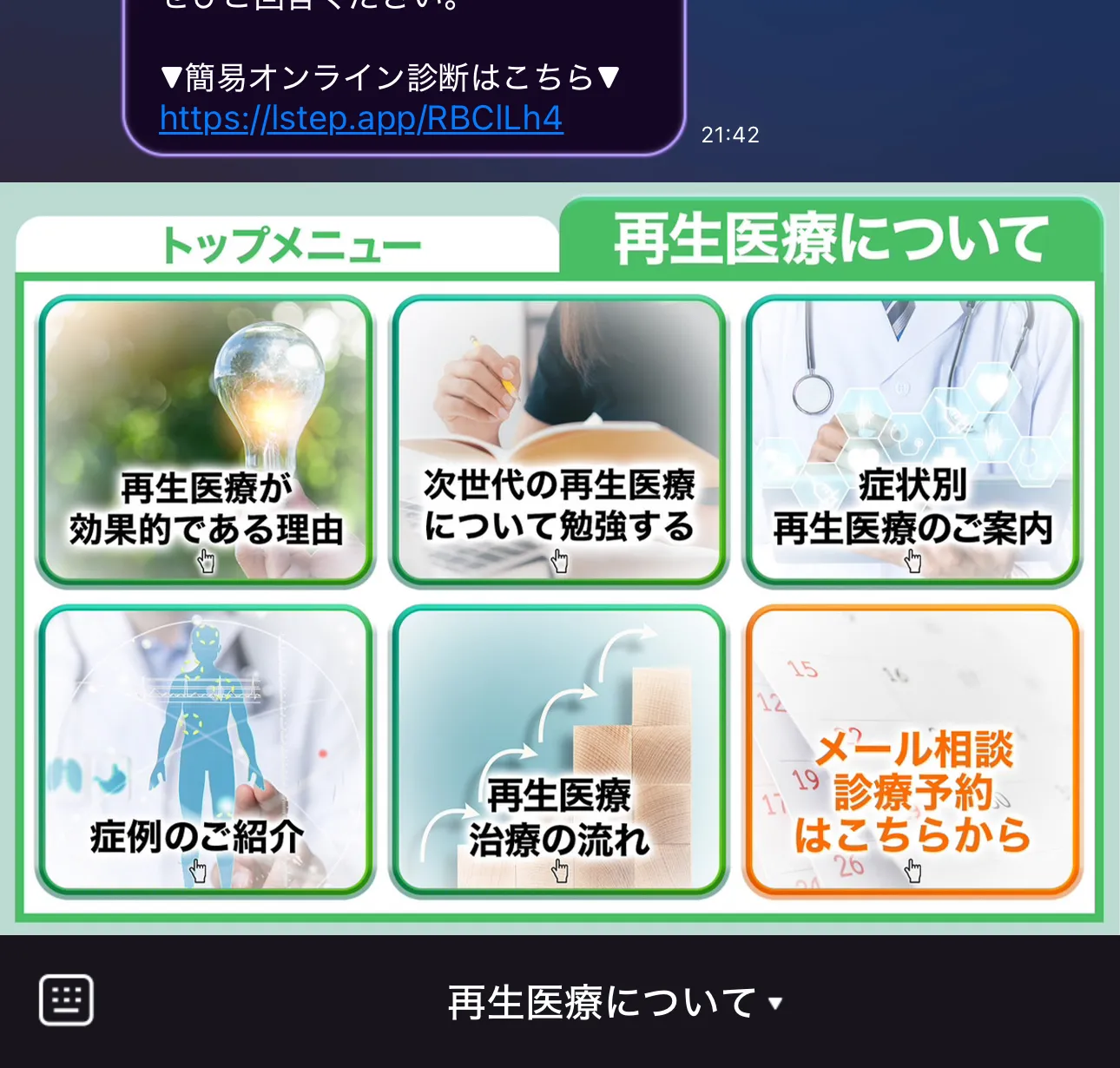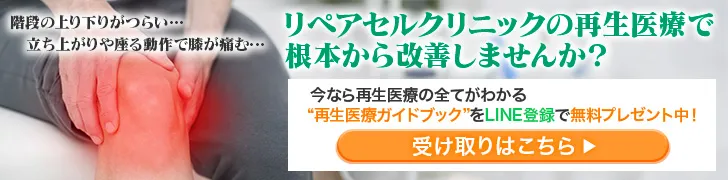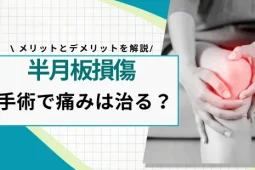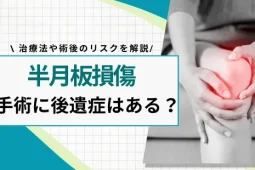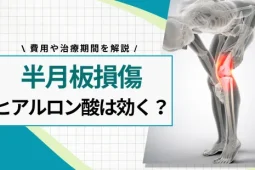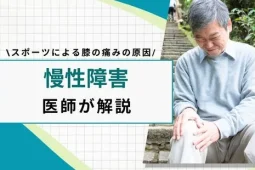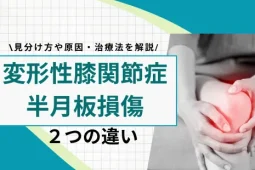- 膝の外側の痛み
- ひざ関節
腸脛靭帯炎(ランナー膝)を早く治す方法!ストレッチ・やってはいけないことを医師が解説

「腸脛靭帯炎が長引いていて辛い。」「早く治すにはどうしたらいい?」
腸脛靭帯炎は、ランナー膝とも呼ばれるスポーツ障害で、膝の外側が痛むのが特徴です。放置すると回復まで数か月かかることもあり、早く治したいと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、腸脛靭帯炎を早く治すためには、まず安静にして痛み・炎症を落ち着かせることが大切です。その後、軽いストレッチやトレーニングを行いつつ、段階的に運動を再開しましょう。
本記事では、腸脛靭帯炎を早く治す方法について、医師監修のもとストレッチから日常生活での注意点を解説します。
また、当院「リペアセルクリニック」では腸脛靭帯炎に効果が期待できる再生医療を提供しています。
腸脛靭帯炎の症状にお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にご相談ください。
目次
腸脛靭帯炎を早く治すためのケア方法4選
腸脛靭帯炎を早く治すためには、痛みを和らげる対処から始め、段階的にストレッチや筋トレを取り入れていきましょう。
ここでは以下の4つのポイントを紹介します。
- 安静
- おしりや太ももの外側・ふくらはぎのストレッチ
- おしりの横の筋力トレーニング
- 痛みが少ない適度な運動
それぞれ詳しく解説していきます。
安静
腸脛靭帯炎の初期症状で最も大切なのは、安静にして休養を取ることです。
痛みを我慢してランニングやスポーツを続けると、炎症が悪化して長期化するリスクが高まります。
そのため、痛みが強い場合は最低でも2〜3日は安静にすることをおすすめします。
痛みが強い場合は整形外科を受診して、炎症や痛みを抑える薬の使用も検討してください。
おしりや太ももの外側・ふくらはぎのストレッチ
腸脛靱帯にかかる負担を減少させるため「おしりや太ももの外側の硬さを改善するストレッチ」もおすすめです。
以下の手順で1日2〜3回、各部位15〜30秒ずつ行うのが理想的です。
- 立った状態で両足を交差させる(足同士はこぶし1つ分ほど離します)
- 両手を組んで頭の上にあげて後ろになっている足に向かって体を横に倒す
- できるだけ体を倒した状態で15秒〜30秒キープする
ただし、痛みを感じるような強いストレッチは逆効果となるため、気持ちよく伸びる程度の強さで実施しましょう。
おしりの横の筋力トレーニング
腸脛靭帯炎の早期回復には、おしりの横の筋肉(中殿筋)を鍛えておくのも効果的です。
なぜなら、中殿筋は膝の安定性を高め腸脛靭帯への負担を軽減する働きがあるためです。
おしりの横の筋肉を鍛えるには以下の手順で行ってみましょう。
- 横向きに寝て両膝を曲げる
- 上になっている足の膝をまっすぐ伸ばした状態で持ち上げる
- 足の付け根が曲がらないように意識しながら10秒キープする
徐々に回数や強度を上げていくと効果的な筋力アップに期待できます。
痛みが少ない適度な運動
症状が落ち着いてきたら段階的に運動を再開していきましょう。
まずは、ウォーキングや水中歩行など膝への負担が少ない運動から始め、痛みがない状態が続いたら、ゆっくりとしたジョギングに移行していきます。
万が一運動後に痛みが出た場合は、すぐに運動を中止して安静にしてください。焦らず段階的に運動強度を上げていくと、早期の回復も見込めます。
さらに詳しく腸脛靭帯炎(ランナー膝)治療法について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
腸脛靭帯炎(ランナー膝)は何日で治る?
腸脛靭帯炎(ランナー膝)の回復期間は、症状の程度や日常生活での対処法によって大きく異なります。
軽症の場合は数週間から1カ月ほどで治ることがほとんどですが、中度以上の腸脛靭帯炎は完治まで1~3カ月かかることもあります。
本章では、軽度から中度以上の症状まで、それぞれの回復にかかる期間と適切な対処法についてみていきましょう。
軽症の腸脛靭帯炎は数週間〜1カ月で治ることが多い
軽症の腸脛靭帯炎は適切な対処によって「数週間〜1カ月」での回復が見込めます。
初期症状の特徴はランニング中や運動後に膝の外側に軽い痛みを感じる程度です。
この段階で休息を取り、適切なケアを始めれば早期に改善するケースが多く見られます。
ただし、痛みが軽いからといって運動を継続してしまうと、症状が悪化する可能性が高まりますので注意してください。
中度以上の腸脛靭帯炎は1〜3カ月かかる場合がある
中度以上の腸脛靭帯炎では、日常生活にも支障をきたすほどの痛みを伴います。
階段の上り下りや長時間の歩行で強い痛みを感じ、夜間に痛みで目が覚めることもあるはずです。
このような状態からの回復には「通常1〜3カ月程度」の時間が必要です。
ただし、適切な治療とケアの継続によって症状は改善していきます。
焦って早期復帰を目指すのではなく、段階的なリハビリを行いながら、じっくりと回復を目指していきましょう。
ランナー膝の詳しい症状については、以下の記事を参考にチェックしてみてください。
腸脛靭帯炎を早く治すためにやってはいけないこと
腸脛靭帯炎を早く治すためには、症状を悪化させる行動を知り避けることが重要です。
腸脛靭帯炎の治療中に控えるべき動作には、以下の4つが挙げられます。
- 過度な運動や負荷のかかる動作
- 長時間の立ち仕事や同じ姿勢の維持
- 急激な方向転換やジャンプ
- 間違ったストレッチ
それぞれ詳しく解説していきますのでチェックしておきましょう。
過度な運動や負荷のかかる動作
ランニングやジョギングなど、膝に直接負荷がかかる運動は要注意です。
痛みを感じているにもかかわらず運動を続けると、炎症が悪化して治療期間が長引いてしまいます。
そのため、まずは痛みが落ち着くまで、膝に負担のかかる運動は控えめにしましょう。
代わりに水中ウォーキングなど、負荷の少ない運動であればおすすめです。
長時間の立ち仕事や同じ姿勢の維持
立ち仕事や座りっぱなしの姿勢は、膝への負担が蓄積していく原因となります。
そのため、同じ姿勢を長時間続けていると腸脛靭帯炎の症状が悪化するリスクが高まりますので避けてください。
もし、立ち仕事が避けられない方は30分おきに軽い屈伸運動を行うなど、こまめに姿勢を変えてみましょう。
また、座る時は膝を90度に保ち足を組まないよう心がけるのも大切です。
急激な方向転換やジャンプ
スポーツ時の急な方向転換やジャンプによる着地の衝撃は、腸脛靭帯に大きな負担をかけます。
とくにバスケットボールやテニスなど、急な動きの多いスポーツは要注意です。
回復の期間中はこれらの動作を極力避け、膝への負担が少ない動きを心がけましょう。
どうしてもスポーツを行う必要がある場合は、事前のウォーミングアップを丁寧に行い、動きをコントロールするのが重要です。
間違ったストレッチ
ストレッチは腸脛靭帯炎に効果的なケア方法でもありますが、誤った方法で行うと逆効果となります。
とくに痛みを我慢して無理に伸ばす動作は症状を悪化させる原因となります。
痛みを感じない範囲でゆっくりと行うのがベストであり、炎症が強い時期は避けるべきです。
腸脛靭帯炎の回復初期の段階では、医師や理学療法士に相談しながら、適切な方法でストレッチを実施しましょう。
腸脛靭帯炎の具体的な治療方法
腸脛靭帯炎の治療方法は、症状の程度に応じて段階的なアプローチを取ります。
多くの場合、以下の治療法を組み合わせることで改善が期待できます。
- 保存療法として安静・ストレッチ・リハビリを行う
- 運動環境やフォームを改善して負担を軽減する
- 保存療法で効果がない場合に外科的治療を検討する
- 再生医療で腸脛靭帯の修復を促進する
まずは炎症を抑えるのが重要です。適度な安静を保ちながら、専門家の指導でストレッチやリハビリに取り組みましょう。
次に大切なのが環境改善です。シューズの選び方や走り方のフォームを見直すと膝への負担を大幅に軽減できます。
ただし、これらの保存療法で改善が見られない場合は、外科的治療も選択肢として検討していきます。
また、新しい治療法としてPRP療法などの再生医療も注目を集めています。
体内の治癒力を高め、より効果的な回復が期待できるでしょう。
腸脛靭帯炎の具体的な治療法について、さらに詳しく知りたい方はぜひ以下の記事もご覧ください。
まとめ|腸脛靭帯炎を早く治すためには正しいケア方法を理解しよう
この記事では腸脛靭帯炎を早く治す方法から予防法まで詳しく解説してきました。
症状は人それぞれ異なりますが、基本的なケア方法を理解し実践していくと改善は十分に見込めます。
今回ご紹介した治療中にやってはいけない動作を避けつつ、あなたに合った回復プランを見つけてください。
腸脛靭帯炎の治療を検討している方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
腸脛靭帯炎を早く治す方法についてよくある質問
痛みを和らげるためのサポーターは効果がありますか?
サポーターには一時的な痛み軽減効果があり、膝を安定させて過度な負担を防ぐ役割を果たします。
しかし、長期的な使用は筋力低下を招く可能性もあります。
そのため、初期の痛み軽減時のみ使用し、症状が改善したら徐々に使用を控えるのが良いでしょう。
また、テーピングや靴選びについては以下の記事も参考にしてください。
腸脛靭帯炎とランナー膝は同じものですか?
腸脛靭帯炎は医学的な正式名称で、ランナー膝は一般的な呼び名であるため、同じ症状を指します。
長距離走者に多い症状のため「ランナー膝」と呼ばれていますが、運動習慣のない方でも発症する可能性があります。
また、立ち仕事や急な運動開始でも起こりうるため、運動経験に関係なく注意が必要な症状です。
ランナー膝の治し方について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。