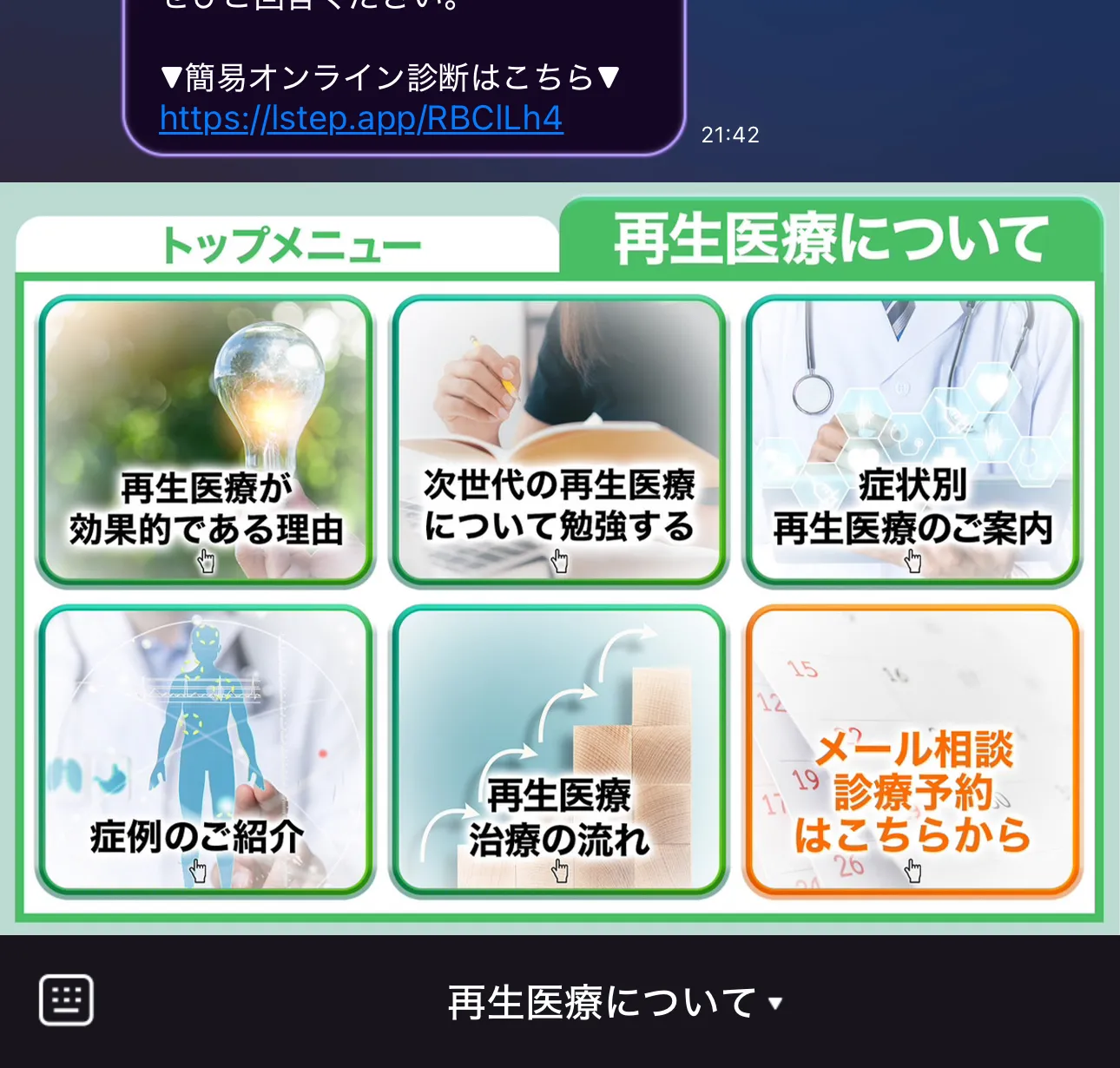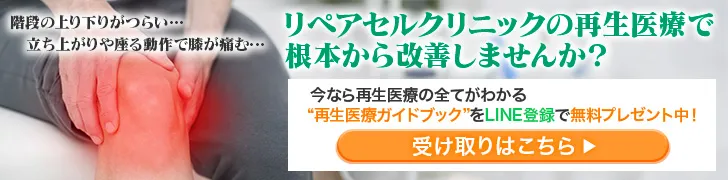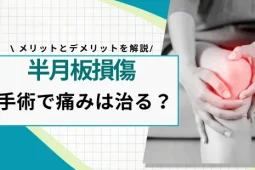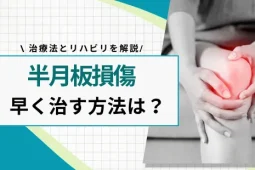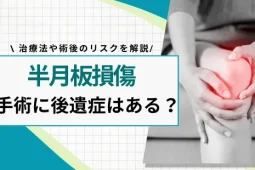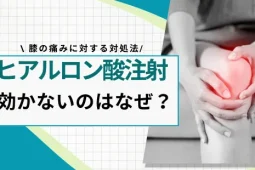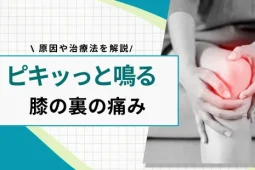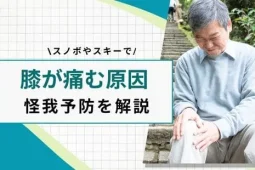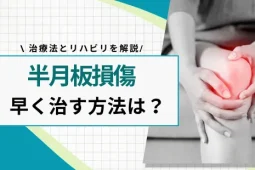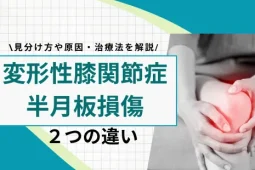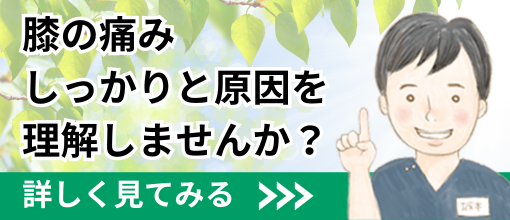- ひざ関節
- 膝の外側の痛み
- 半月板損傷
半月板損傷の手術に後遺症はある?現役医師が治療法や術後のリスクを解説!
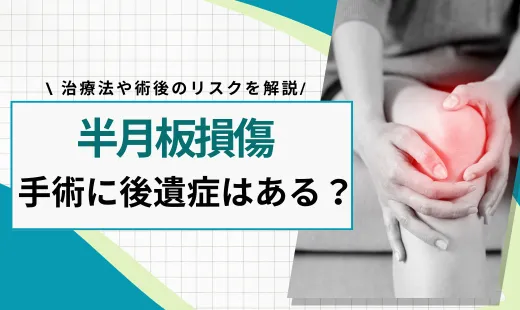
「膝の痛みが気になっているけれど手術するか悩む……」
「手術をしたあと後遺症が心配……」など、気になっていませんか?
半月板損傷の手術で起こる後遺症が心配になり、放置すると症状を悪化させる可能性があります。
そこで本記事では、半月板損傷で施す手術療法の種類とともに、治療の注意点を解説しています。
手術をして起こりうる後遺症、手術しないリスクについてもまとめました。半月板損傷でおすすめしたい治療法も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
半月板損傷とは
膝の半月板とは、膝関節の太ももの骨(大腿骨:だいたいこつ)とスネの骨(脛骨:けいこつ)の間にある軟骨で、衝撃を吸収する役割があります。
「C型」や「O型」をした線維の軟骨からなり、内側と外側の両方に存在します。上半身の負荷や関節をスムーズに動かす大切な存在ですが、実は半月板には約10〜20%しか血が通っていません。
一度損傷してしまうと自然に治癒するのは極めて困難です。
再発防止やスポーツ活動への復帰を考慮して保存療法ではなく、手術を選択される方もいます。
40歳を超えたら半月板損傷がよくみられるので、以下の症状がある方は手術を検討しましょう。
【半月板損傷の主な症状】
- 膝の痛みや腫れがある
- 膝の動きが制限される
- 普段より膝に水が溜まりやすくなる など
膝の半月板手術を受ける上で、先に細かい注意点が知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。
半月板損傷の手術療法の違いとそれぞれの注意点
半月板損傷の手術療法は大きく分けて以下の手術を行います。
- 内視鏡術
- 縫合術
- 切除術
手術療法の違いについて、それぞれの違いや注意点を解説していきます。
内視鏡術
半月板損傷の症状が長引くか、良くなっても再発する場合は、関節鏡を使用した内視鏡手術を行います。
内視鏡術は腰椎麻酔で行うケースが多く、手術中は意識があるので希望する方に向け、説明をしながら手術を受けられるのが特徴です。
しかし画像上で半月板に損傷がみられても、痛みの程度や動作による支障があまり出ていない症状も考えられるでしょう。
症状によっては、投薬し安静にしていれば症状が軽くなる場合もあります。
縫合術
半月板損傷の手術は、安定した生活動作や若年層の方、スポーツによるパフォーマンス維持のためにも、可能な限り縫合術で行います。
半月板が中心で裂けるように損傷しているケースでは、縫合術の適応となります。
損傷の度合いや形態を観察し、損傷しているカ所の激しい患部を優先的に処置する施術です。
血液の流れを考慮しながら、組織の状態が良好な部分は最大限に活かす方向で縫合していきます。
膝の外側に3cmほど切開をつくり、縫合専用の器具を使用して半月板に糸を数本通し、膝の関節の外側で結びつけて縫合していく流れです。
糸を膝関節の外側に通して縫合していますが、損傷しているカ所によっては関節の中だけで処置を終え、手術跡を作らず済む方法もあります。
ただし縫合術を終えたあとは、以下の点には注意しましょう。
- 入院期間である術後2週間は足を床につけてはいけない
- 固定具を装着し膝を伸ばした状態をキープする
- 2週間後は経過観察の上で適切なリハビリを実施する
詳しいリハビリ法については、以下の記事でまとめていますので、ぜひあわせてご覧ください。
また、手術をすれば必ず痛みが取れるわけではありません。
手術をしても「痛みが取れない」「手術前よりも痛くなった」とよく言われます。
リスクを回避する方法については、以下のページで詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
切除術
半月板損傷で行う切除術は、断裂している部分に血行がなく、断裂しているカ所が縫合しても改善されないほど損傷が大きい場合に適応されます。
損傷範囲が広い症状では、断裂している部分を専用器具で切り取り除去します。
半月板の辺縁部分には血行があるため、縫合術で対応するのが大半です。
しかし、断裂部分の繊維が不揃いになっているときには、切除しながら辺縁部を整える必要があるので、切除術が選択肢になります。
傷んだ半月板が膝関節部の軟骨と摩擦せず、軟骨の損傷をも防げます。
注意点として、切除術は半月板の機能を低下させるリスクやデメリットがあるので注意が必要です。
可能な限り温存させる方向で、必要最低限の切除にとどめた手術を行います。
他にも以下のケースで切除術が行われるので、症状によって適切に判断しましょう。
- 縫合が可能な辺縁部と切除する部分の両方が損傷している(縫合術との組み合わせ)
- 円板状半月板の方
半月板の治療で切除術を選択した場合、関節軟骨が変形する「膝関節症」になる可能性もあります。
術後1〜2カ月は水が溜まりやすく、むくみが生じるリスクもあるので注意しましょう。
縫合術との違いは、術後翌日には歩行になり、退院も4日程度なので比較的すぐ歩けるようになる点です。
切除術もまた縫合術と同じく、手術をすれば必ず痛みが取れず、むしろ余計に痛みを感じた方もいます。
半月板損傷の手術後の後遺症
手術後は、以下のようなリスクが存在するため、術後には注意して観察が必要となります。
- 感染
- 静脈血栓塞栓症(肺血栓塞栓症)
- しびれ
それぞれの後遺症について、詳しく解説していきます。
感染
半月板の手術で起こる可能性がある後遺症でまず挙げられるのが細菌感染です。
手術時の傷跡から細菌に感染し、化膿すると発症します。
内視鏡術の場合で細菌感染する可能性は、1%と言われていますが、一度感染すると半月板損傷としての治療以外を行うリスクが伴います。
あらかじめ細菌感染の後遺症が発症しないよう、抗生物質を使うケースもあるので、専門医のカウンセリングで相談しておくのが無難です。
静脈血栓塞栓症(肺血栓塞栓症)
静脈血栓塞栓症(肺血栓塞栓症)は、半月板の手術で発症する後遺症ではないものの、下肢の手術や脊椎の手術、骨折などにより発症しやすくなります。
名の通り、足の静脈にできた血栓が、肺の動脈で詰まってしまう症状です。
長時間座ったままでいたときにも起こる可能性がある症状なので、胸の痛みや呼吸困難を感じた方は要注意です。
半月板の手術自体で発症する後遺症ではなくても、気になる症状がある方は、ぜひ以下の記事も参考にしてください。
膝の痛みを感じた方がよく処置を受ける「膝の水を抜く」治療を行ったあとの注意点をまとめています。
しびれ
半月板損傷の手術をすると、患部にしびれを感じます。
手術の過程で下肢への血流を遮断しているので、しびれが起きます。
しかし多くの場合で術後数日ほどで、しびれが改善するので、改善されない場合は必ず担当医師に相談しましょう。
半月板損傷の手術をしたあとの後遺症を含め、不安に感じている点があれば、当院ではオンラインカウンセリングも実施しています。
「1週間経ってもしびれが改善されない」「痛みが軽減されない……」など、お気軽にご連絡ください。
半月板損傷を放置するリスク
半月板損傷が発症していて、手術を検討していても、後遺症が心配な方のなかには「後遺症があるならそのままにしよう」と考える方もいるでしょう。
半月板損傷の手術で起こる可能性がある後遺症が気になり、放置してしまうと、以下のリスクが起きてしまいます。
- ロッキング現象が起こる
- 水が溜まり運動機能が低下する
半月板損傷を放置するリスクも、把握できるよう順番に解説していきます。
ロッキング現象が起こる
半月板損傷を放置すると、ロッキング現象が起こります。
ロッキング現象とは、膝の痛みだけでなくロックされたように動かなくなる症状です。
ロッキング現象は何かの予兆があるわけではなく、急に起こる可能性があります。半月板損傷で発症した破片が膝に引っ掛かり起こる症状なので、目で見て判断するのは困難です。
ロッキング現象が起こると、膝の曲げ伸ばしなどの動きが制限されるので、手術をしなければいけなくなります。
水が溜まり運動機能が低下する
半月板損傷が発症すると水が溜まりやすくなり、何度も溜まった結果、運動機能が低下する可能性もあります。
膝に水が溜まったら抜けば良いと思われがちですが、根本的な治療を施さない限り、また溜まってしまいます。
半月板損傷の慢性化により発症する傾向にあるので、放置するより手術で根本的な治療をするのが良いでしょう。
以下の記事では、半月板損傷が発症したときにやってはいけない項目をまとめています。
放置するリスクとともに、リスク回避の参考にしてもらえると幸いです。
手術後の後遺症を抑えたいなら再生医療がおすすめ!
半月板損傷の手術には縫合術・切除術ともにリスクを伴います。
実は幹細胞を用いた再生医療では、手術による後遺症のリスクを負わず治療を受けられるのです。
縫合術との比較
縫合術の場合、縫い合わせた半月板が再断裂する可能性があり、縫合術をして4年後に再断裂をする確率は30%と言われています。
縫合をしても半月板がしっかりとくっついていないため発生するのです。
一方で幹細胞治療の再生医療では、断裂した半月板を接着剤で留めるように修復するので、日常生活だけでなくスポーツ復帰も可能です。
縫合術を受けると2週間は足に体重をかけられなかったり、4週間ほどの松葉杖生活を強いられます。
再生医療では、治療を受けた当日に歩いて帰れるのが特徴です。
切除術との比較
切除術の場合、半月板の一部を取り除くので、関節のクッション性がなくなります。
数年後には関節軟骨がすり減り、変形性膝関節症になる方が大半です。
実際に切除術を行なった10年後には、一般の方であれば30%、スポーツをしている方は70%もの方が変形性膝関節症へと移行しています。
切除術をすると切った部分から再び断裂が生じる可能性もあり、術後数週間が経過した頃より再び膝の痛みを感じるでしょう。
一方で幹細胞治療は、半月板をそのまま温存できるので、クッション性がなくなる心配がありません。
変形性膝関節症や再断裂のリスクも減らしてくれるのが再生医療の魅力です。
幹細胞治療は手術を受けた後でも有効!
切除術で半月板を切り取ってしまうと、切り取った半月板が元に戻りません。
後戻りができない治療を受ける前だけでなく、術後の再断裂の予防にも再生医療を検討する価値は十分にあると言えます。
縫合術を受けた後に幹細胞治療を行えば、より強固に半月板が修復されるでしょう。切除術を受けた後も同様に、断面に新たな亀裂が生じ痛みが再発する場合もよくあります。
しかし、多くのケースで「手術は成功しています。しばらく様子を見ましょう。」と言われるでしょう。
幹細胞治療は、再発した術後の痛みの原因となっている新たな半月板損傷の治療としても有効です。
▼ 半月板損傷を再生医療で治療する方法があります
再生医療なら半月板損傷は、手術せず、入院せず改善を目指せます
まとめ・後遺症が不安なら受診とともに再生医療を検討しよう!
本記事では半月板損傷の手術をしたあとに起こる可能性がある後遺症について解説しました。
膝の痛みや腫れ、動きが制限されるなどの症状が伴う半月板損傷の手術をしても、感染、静脈血栓塞栓症などの後遺症が挙げられます。
後遺症になるのは避けたく、手術せずに放置するとロッキング現象や水が溜まりやすくなり運動機能の低下が起きてしまいます。
膝の曲げ伸ばしができず歩きにくくなるので、半月板損傷を放置するのは避けるべきでしょう。
適切な処置をするためにも、自分で判断せず病院やクリニックで受診するのをおすすめします。
▼以下もご参考にしてください