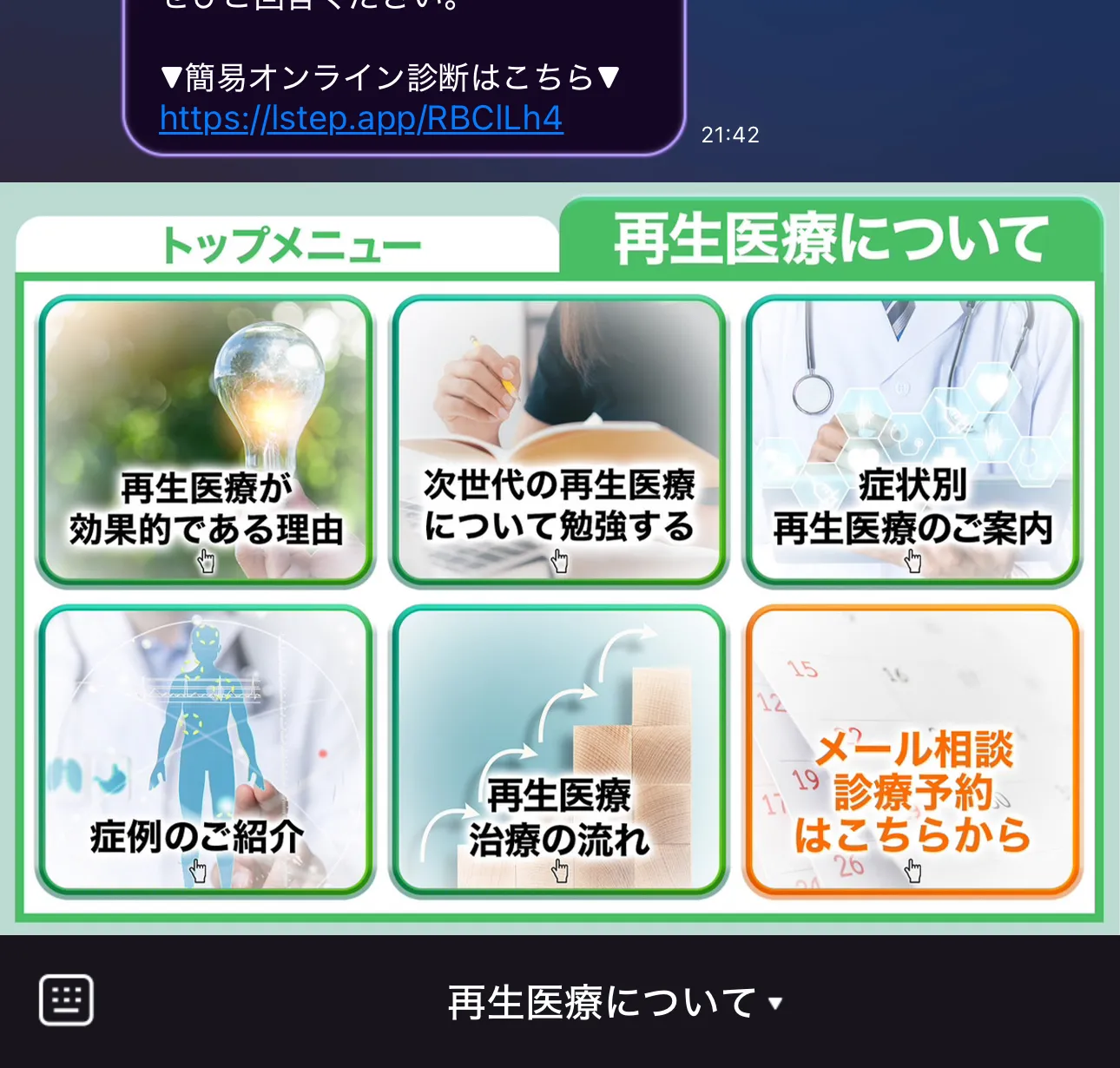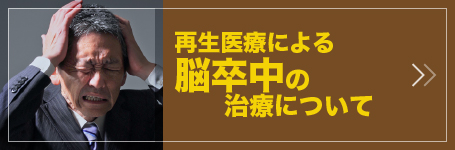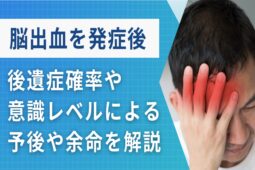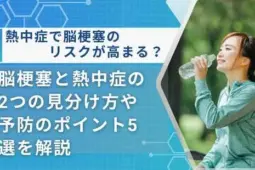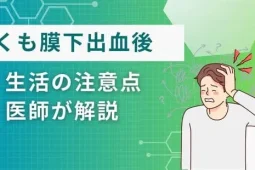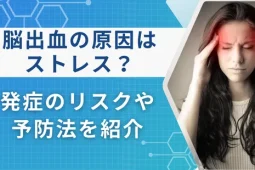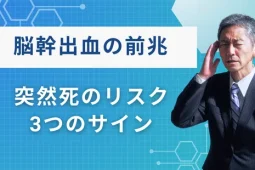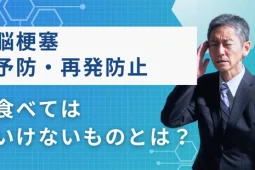- 脳卒中
- 頭部
- 脳出血
脳溢血による後遺症とは?運動麻痺や感覚障害の治療法を医師が解説
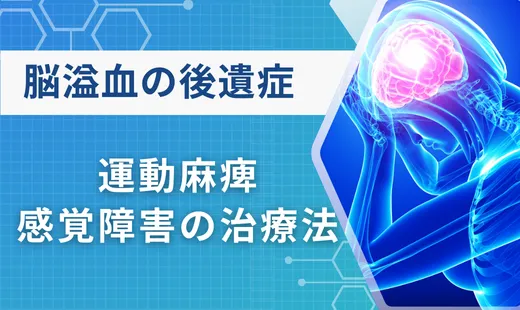
脳溢血を発症すると、運動麻痺や感覚障害などの後遺症が出る可能性があります。しかし、リハビリや適切な治療を継続的におこなえば、機能の回復や症状の改善が期待できます。
リハビリをおこなう際は、焦りは禁物です。負担のかかる無理な運動をすると、症状の悪化や再出血のリスクが高まります。医師や専門スタッフの指導のもとで自分の症状や回復段階に合ったリハビリを進めていきましょう。
本記事では、脳溢血による後遺症の種類や回復過程について解説します。リハビリ以外の療法や治療法も紹介しているので、後遺症の改善を目指している方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
脳溢血(のういっけつ)で後遺症が出るリスク
脳溢血は発症後に治療しても後遺症が出るケースが少なくありません。脳の細胞がダメージを受けて、体の麻痺や感覚の障害などが残る可能性もあります。
そもそも脳溢血とは、脳の血管が破れて血液が流出してしまう病気です。現在は脳出血と呼ばれることが多くなりました。
脳溢血の後遺症によっては、治療後も日常生活に影響が出る場合があるので、症状だけでなく後遺症の理解も深めておきましょう。
脳溢血の有効な治療法の1つに「再生医療」があります。
これまで一度死んだ脳細胞は戻らないとされてきました。しかし、再生医療は脳細胞を復活させ、脳溢血を含む脳卒中の後遺症を改善できることがわかってきたのです。
詳しい治療法や効果が知りたい方は、再生医療専門の『リペアセルクリニック』にお気軽にお問い合わせください。
脳溢血で残りうる後遺症の種類7選
脳溢血で残りうる7種類の後遺症を解説します。
|
後遺症 |
症状 |
|
運動麻痺 |
・運動麻痺は脳溢血の代表的な後遺症 |
|
感覚障害 |
・感覚障害も脳溢血の代表的な後遺症 |
|
言語障害 |
言語障害は主に以下の2種類 |
|
視野障害 |
・目の見える範囲が狭くなったり、物が二重に見えたりする |
|
嚥下障害 |
・のどの筋肉の動きが悪くなり、食事や水分を飲み込みにくくなる |
|
高次脳機能障害 |
高次脳機能障害とは、脳の細胞がダメージを受けて脳機能が低下した状態。下記のように複数の症状が現れる。 |
|
感情障害 |
・常にイライラしたり、感情の起伏が激しくなったりする |
脳溢血による後遺症は運動機能から精神面まで多岐にわたります。症状に応じた適切な治療法を選択し、確実な回復を目指していく姿勢が大切です。
脳溢血による後遺症の軽減が期待できるリハビリの進め方
早期からのリハビリ開始で、脳溢血による後遺症は大きく改善する可能性があります。発症からの時期に応じて、3段階のリハビリプログラムを進めていきます。
・急性期
・回復期
・維持期
リハビリの内容を順番に見ていきましょう。
急性期
脳溢血の発症から約2週間は「急性期」と呼ばれ、命を守る治療が最優先となります。体の状態が不安定なため、急な運動は血圧上昇や再出血を招く危険があるため焦ってのリハビリは禁物です。
しかし、ずっとベッドで安静にしていると「廃用症候群」(寝たきりによって筋肉の衰えや関節の硬化が起こる症状)を引き起こす恐れがあります。廃用症候群になると、床ずれや感染症のリスクも高まります。
そのため、急性期のメインとなるリハビリは、手足のストレッチや体位の交換といったベットの上でできる軽い運動です。
回復期
急性期を乗り越えて、体の状態が安定し、本格的にリハビリが始まる時期を「回復期」と呼びます。この時期には、日常生活に戻ることを意識しながらリハビリを進めていきます。
|
【主なリハビリ内容】 |
医師や専門スタッフの指導のもと、段階的に運動量を増やしながら機能回復を目指します。
維持期
回復期のリハビリで日常動作ができるようになり、自宅での生活が始まる時期を「維持期」と呼びます。
病院で回復した体の機能を保つため、定期的に外来リハビリに通ったり、日常生活で体を動かしたりする習慣が大切です。
脳溢血の後遺症に有効な4つの治療方法
麻痺の治療については近年研究が進んでおり、リハビリ以外にもさまざまな方法があります。ここでは、リハビリ以外の有効な治療法を4つ紹介します。
・CI療法(Constraint-induced movement therapy)
・促通反復療法
・電気刺激療法・磁気刺激療法
・再生医療
治療方法を選択する際の参考にしてみてください。
CI療法(Constraint-induced movement therapy)
CI療法は、麻痺した手が少しでも動かせる人を対象におこなう機能回復トレーニングです。
麻痺していない手を動かせないように固定し、麻痺した手を日常生活で多く使うよう促すことで麻痺した手の機能回復を目指します。
1回あたり6時間以上の訓練が必要になるため負担は大きいですが、実際に手の動きが良くなったという報告もあります。
促通反復療法
促通反復療法は、同じ運動を繰り返しおこない、脳の損傷した神経回路を修復・強化するリハビリ方法です。手足の麻痺が改善したという報告が多く寄せられています。
電気刺激療法・磁気刺激療法
麻痺した手足の筋肉に弱い電流を流したり、頭部に磁気を与えたりすることで、衰えた筋肉の働きを活性化します。主に歩行機能の回復が期待できる療法です。
促通反復療法と一緒におこなうと、より高い効果が期待できます。
再生医療
再生医療とは、修復力のある幹細胞の働きを利用して、弱ったり、傷ついたりした神経細胞を修復する新しい治療法です。
再生医療では、麻痺や痺れといった脳溢血の後遺症の回復を早めたり、脳卒中の再発を予防したりする効果が期待されています。
再生医療で脳溢血の治療を進めたい方は、弊社『リペアセルクリニック』にご相談ください。再生医療の症例数10,000例以上の経験を活かし、患者さま一人ひとりに合った治療プランをご提案いたします。
\無料オンライン診断実施中!/
まとめ|脳溢血の後遺症に有効はリハビリと治療法を知って症状の軽減を目指そう
脳溢血は運動麻痺や感覚障害といった後遺症が出る可能性のある病気です。
安静による筋力低下を防ぎ、後遺症からの機能回復を図るためにはリハビリが欠かせません。回復過程に合わせた無理のないリハビリを進めて、着実な改善を目指しましょう。
近年では、脳溢血における後遺症の治療法として「再生医療」が注目されています。
再生医療は人間の自然治癒力を活用した最先端の医療技術です。幹細胞の修復力を利用して、脳細胞の機能回復を促進します。
「再生医療に興味があるけど具体的なイメージがつかめなくて不安…」という方は、再生医療専門の『リペアセルクリニック』にお気軽にお問い合わせください。
脳溢血の後遺症に関するよくある質問
最後に脳溢血の後遺症に関するよくある質問と回答をまとめます。
脳梗塞と脳溢血(脳出血)における後遺症の違いはなんですか?
脳梗塞は、脳の血管が詰まることで脳細胞が死滅し、正常な機能が失われる病気です。一方、脳出血は血管が破裂して出血する病気です。
両者とも脳で起こる病気のため、後遺症の種類は似ています。
|
【脳梗塞と脳溢血の両方に見られる後遺症の例】 |
発症する部分や重症度によって、後遺症の種類や症状の程度が異なります。
以下の記事では、脳梗塞の後遺症や治療方法について解説しています。脳梗塞の理解を深めたい方はぜひ合わせてご覧ください。
脳溢血(脳出血)で後遺症なしの確率はどれくらいですか?
脳溢血で後遺症なしの確率を証明する公的なデータは見つかりませんでした。
しかし、厚生労働省が実施した脳卒中患者(18-65歳)の予後調査によると、1,584例中、後遺症がまったく残らなかったのは344例でした。
つまり、脳出血を発症した患者の約2割が完全回復し、約8割の患者には脳卒中による何らかの影響が残る結果となりました。
以下の記事では、脳出血で後遺症なしになる確率について解説しているので詳細が気になる方はぜひあわせてご覧ください。