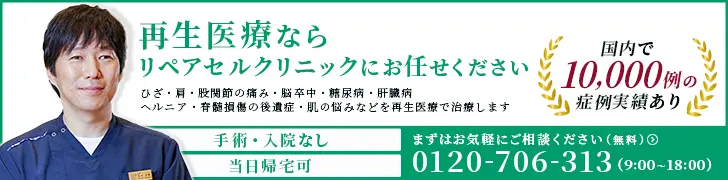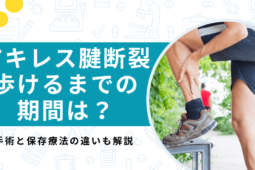- 足部、その他疾患
足がつる原因とは?医師が解説

夜中に突然襲われる激痛、運動中に感じるつっぱり…。足がつる経験、あなたにもありませんか? 実はこの「こむら返り」、決して珍しい症状ではなく、多くの人が悩まされています。2023年の国民生活基礎調査によると、国民の約3割が足がつる経験があると回答しています。
その原因は、ミネラル不足、脱水、運動不足など様々。意外なことに、コーヒーとの関係性も指摘されています。 この記事では、足がつる原因を4つの主要な要因に分け、分かりやすく解説します。
さらに、足がつった時の即効性対処法から、予防のための生活習慣、そして日常で気をつけるべきポイントまで、具体的な方法を詳しくご紹介します。この記事で原因を知り、適切な対策を講じることで、快適な生活を取り戻しましょう。
目次
足がつる原因とは?主な要因4つ
運動中に激痛が走った、寝ている時に足がつった。みなさん、一度は体験したことがあると思います。一般的に「こむら返り」とも言われます。何が原因で起こるのか分からず、不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
足のつりは、単一の要因ではなく、様々な要素が複雑に絡み合って起こる症状です。ここでは、大きな原因を4つをできるだけ分かりやすく解説します。
ミネラル不足と足がつる関係
ミネラルは、私たちの体にとって、骨や歯を作るだけでなく、筋肉や神経の働きにも必要不可欠な栄養素です。特に、カルシウム、マグネシウム、カリウムは、筋肉の収縮と弛緩をスムーズに行う上で重要な役割を果たしています。
これらの栄養素が不足すると、筋肉が思うように動かなくなり、痙攣、つまり足がつりやすくなります。例えば、激しい運動の後や、妊娠中、高齢期にはミネラルの必要量が増えるため、こむら返りの原因となります。
バランスの良い食事を心がけることが重要です。高齢者の場合、加齢に伴いミネラルの吸収率が低下することもよくあります。マグネシウムに関しては、高齢者の特発性骨格筋痙攣、つまり原因が特定できない足のつりに対して、マグネシウムを補給しても、けいれんを予防する効果はあまり期待できないという研究結果も出ています。
| ミネラル | 働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| カルシウム | 骨や歯の形成、筋肉の収縮を助ける | 牛乳、チーズ、ヨーグルト、小松菜、ひじき |
| マグネシウム | 筋肉や神経の働きを正常に保つ | 納豆、豆腐、アーモンド、ほうれん草 |
| カリウム | 体内の水分バランスを調整する、筋肉の働きを助ける | バナナ、オレンジ、ほうれん草、じゃがいも |
ただ、いくら特定の食品にミネラルが多く含まれているからといって、そればかりを食べるのではなく、様々な食品をバランスよく摂取することが大切です。
脱水症状が引き起こす足の筋肉の痙攣
私たちの身体は、約60%が水分となります。この水分は、体温調節や栄養の運搬、老廃物の排出など、生命維持に欠かせない役割を担っています。脱水状態になると、血液がドロドロになり、筋肉への酸素供給が滞ってしまいます。
同時に、汗とともにミネラルも排出されるため、脱水となりこむら返りになります。普段からこまめな給水を意識しましょう。
脱水症状は、軽度であれば、喉の渇きや皮膚の乾燥といった症状が現れます。中等度になると、めまいや立ちくらみ、倦怠感などが起こり、ひどくなると、意識障害やショック状態に陥ることもあります。
- 水分不足で起こる症状の例
- 軽度:喉の渇き、皮膚の乾燥、尿量の減少、集中力の低下
- 中等度:めまい、立ちくらみ、倦怠感、頭痛、吐き気
- 重度:意識障害、ショック、痙攣、腎不全
運動不足が及ぼす影響
適度な運動は、筋肉を鍛え、血行を促進するだけでなく、ミネラルバランスの維持にも役立ちます。適度な運動を心がけ、筋肉を健康な状態に保つことが大切です。
運動中に起こる足のつり(運動関連の筋けいれん:EAMC)の原因は、以前は、運動による疲労や脱水、電解質異常と考えられていましたが、近年の研究では、単一の原因ではなく、様々な内的要因と外的要因が複雑に関係していると考えられています。
例えば、運動前の準備運動不足や、急に激しい運動を始めた場合、筋肉が急激な負荷に耐えられず、けいれんの原因となります。また、気温や湿度が高い環境で運動すると、体温が上昇しやすく、脱水症状を引き起こし、こむら返りにつながります。
コーヒーと足のつりの関係性
「夜中に足がつって目が覚めた」「運動中に激痛が走った」など、とても辛いですよね。足のつりは、ふくらはぎの筋肉がつる場合が多いですが、足の裏や太もも、足の指などがつることもあります。
様々な要因が考えられますが、今回は「コーヒー」との関係性について詳しく見ていきましょう。「コーヒーを飲むと足がつりやすくなる」という噂を耳にしたことがある方もいるかもしれません。その真偽や、コーヒーを飲む上での注意点などを、できるだけわかりやすく解説していきます。
カフェインの筋肉への影響
コーヒーに含まれるカフェインには、筋肉を興奮させる作用があります。カフェインは、私たちの脳や体に様々な影響を与える物質です。
適度なカフェイン摂取は、運動能力の向上や疲労軽減、集中力アップにつながると言われています。しかし、摂りすぎると、筋肉が過剰に興奮し、足のつりやけいれん、ひどい場合は震えなどを引き起こす可能性があります。
カフェインは、筋小胞体と呼ばれる筋肉細胞内にある小さな袋のような器官からカルシウムイオンを放出させます。このカルシウムイオンは、筋肉の収縮に必要不可欠な物質です。しかし、過剰に放出されると、筋肉が異常に収縮し、こむら帰りとなるのです。
また、カフェインには利尿作用もあるため、脱水となり足がつりやすくなります。
専門家が語るコーヒー摂取の注意点
専門家の間では、コーヒーの摂取自体が直接的に足のつりを起こすとは断定されていません。コーヒーと足のつりの関係性については、更なる研究が必要とされています。
Voskoboinikらは、紅茶やコーヒーの摂取は、適度であれば様々な心臓血管疾患において有害ではなく、むしろ有益である可能性があると報告しています。例えば、心臓の筋肉に血液を送る血管が狭くなる狭心症や、心臓のポンプ機能が低下する心不全などです。
適度なコーヒーの摂取は、これらの病気のリスクを減らす可能性があるという研究結果が出ているのです。しかし、カフェインの過剰摂取は、足のつり以外にも、不眠、動悸、不安感などの症状を引き起こす可能性があります。
過剰摂取のリスクとそのメカニズム
カフェインの過剰摂取は、様々な病気のリスクを高める可能性があります。カフェインは中枢神経系を刺激するため、過剰に摂取すると、神経過敏、めまい、頭痛、吐き気などの症状が現れることがあります。
カフェインには、常用するとだんだん効きにくくなり、同じ効果を得るためには量を増やす必要があるという特徴があります。いわゆる「依存性」です。長期間にわたって過剰摂取を続けると、カフェインを急に断った時に離脱症状(頭痛、疲労感、集中力の低下、イライラなど)が現れる可能性があります。
さらに、カフェインは胃酸の分泌を促進するため、胃腸の弱い方は、胸やけや胃痛などの症状を引き起こす可能性も懸念されます。コーヒーを飲む際には、自分の体質や体調に合わせて、飲み過ぎには注意しましょう。
カフェインの致死量は、体重1kgあたり150〜200mgとされています。健康な成人の場合、カフェインの1日摂取量は400mgまでが安全とされています。コーヒー1杯には約60〜100mgのカフェインが含まれているため、1日に4〜5杯程度までであれば、問題ないと考えられます。
しかし、子供やカフェインに敏感な人、妊娠中や授乳中の人は、カフェインの摂取量を控えるべきです。また、寝る前にコーヒーを飲むと、睡眠の質が低下する可能性があります。
足がつった時の対処法と予防策
寝ていたら足がつってしまった。あまりの痛みに「どうすればいいの!?」とパニックになってしまう方もいるかもしれません。足のつりのメカニズムを理解し、適切な対処と予防を身につけることで、痛みや不安から解放され、快適な毎日を送れるように一緒に考えていきましょう。
足がつった時に試すべき即効性対処法
足がつってしまった時は、まずは落ち着いて深呼吸をし、パニックにならないようにすることが大切です。そして、以下の方法を試してみてください。
-
つった筋肉をゆっくりと伸ばす:ふくらはぎがつった場合は、つま先を体の方へゆっくりと引き寄せ、アキレス腱を伸ばします。この時、アキレス腱が固まっていると感じる方もいるかもしれません。アキレス腱は、ふくらはぎの筋肉と踵の骨をつないでいる腱で、ジャンプや歩行などの動作をスムーズに行うために重要な役割を担っています。このアキレス腱を伸ばすことで、収縮したふくらはぎの筋肉をリラックスさせる効果が期待できます。太ももの前側がつった場合は、膝を曲げてかかとをお尻に近づけるようにします。このとき、無理に伸ばそうとすると、筋肉を傷めてしまうことがあるので、痛みを感じない程度に、ゆっくりと行うことが重要です。
-
マッサージをする:つっている筋肉を優しくマッサージすることで、血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎ、痛みが軽減されます。マッサージは、指先や手のひらを使って、円を描くように優しく行うのがポイントです。強く押しすぎると、かえって痛みが増すことがあるので注意が必要です。
-
温める:温かいタオルや湯たんぽなどで、つっている部分を温めるのも効果的です。温めることで、血行が促進され、筋肉がリラックスしやすくなります。寒い季節、足が冷えやすい時期には、効果を実感できるでしょう。ただし、炎症や腫れがある場合は、冷やす方が良い場合もあります。自己判断せずに、医師に相談するようにしましょう。
-
水分とミネラルを補給する:筋肉の収縮を調整する上で重要な役割を果たしているため、少ないと筋肉がけいれんを起こしやすくなります。すると足がつりやすくなります。スポーツドリンクや経口補水液は、おすすめです。高齢者の原因がよくわからない足のつりに対しては、マグネシウムを補給しても効果は薄いという研究結果も出ています。原因がわからない場合は、医療機関を受診するようにしてください。
足のけいれんを予防するための生活習慣
足のつりを予防するためには、日頃の生活習慣を見直すことが重要です。以下のポイントに注意してみましょう。
-
十分な水分補給:こまめな水分補給を心がけましょう。特に、運動の後には、意識的に水分を摂るようにしましょう。具体的には、1日に1.5~2リットル程度の水分摂取が推奨されています。
-
バランスの取れた食事:ミネラル、特にマグネシウム、カルシウム、カリウムは、筋肉の正常な機能に不可欠です。これらの栄養素は、緑黄色野菜、果物、乳製品、海藻類などに多く含まれています。バランスの良い食事を心がけ、これらの食品を積極的に摂るようにしましょう。必要に応じて、サプリメントで補うことも有効です。
-
適度な運動:ウォーキングやストレッチなど、適度な運動を習慣づけることで、筋肉をやわらげて足のつりを予防することができます。激しい運動は、かえって足がつる原因になることもあるので、無理のない範囲で行うようにしましょう。
-
十分な睡眠:睡眠不足は、筋肉の疲労を回復させにくくし、足がつりやすくなります。毎日同じ時間に寝起きし、睡眠時間を確保することで、睡眠の質を高めることができます。質の高い睡眠を十分に取るように心がけてください。
日常生活で気をつけるべきポイント
日常生活の中で、少し意識を変えるだけで、足のつりを予防することができます。
-
同じ姿勢を長時間続けない:同じ姿勢を長時間続ける場合は、こまめに休憩を取り、軽いストレッチや散歩をするなどして体を動かすようにしましょう。同じ姿勢を長時間続けると、血行が悪くなり、筋肉が硬直しやすくなります。
-
冷えに注意:体が冷えると血行が悪くなり、筋肉が硬直しやすくなります。特に冬場は、温かい服装を心がけましょう。寝る時は靴下を履くのも効果的です。
-
アルコール摂取を控える:アルコールには利尿作用があり、脱水を招きやすく、足のつりの原因となります。アルコールの摂取は控えめにしましょう。
-
適切な靴を選ぶ:きつい靴やヒールが高い靴は、ふくらはぎに負担をかけてしまします。足のサイズに合った、歩きやすい靴を選ぶようにしましょう。
漢方薬
整形外科医なら誰もが知っている、芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)という漢方薬です。私はよく外来で、こむら返りで困った方に処方していました。管理の確立でこむら返りが無くなります。
ただ、根本的に治すには、やはり上記のようにストレッチや生活習慣が大切です。よくマラソン大会に行くと、この漢方薬をポケットに入れているランナーを見かけます。それだ効果は高いものと認識されているのでしょう。
これらのポイントを参考に、足のつり(こむら返り)の痛みや不安から解放されて、快適な毎日を送りましょう。
参考文献
- Young G. “Leg cramps.” BMJ clinical evidence 2015, no. (2015): .
- Miller KC, McDermott BP, Yeargin SW, Fiol A, Schwellnus MP. “An Evidence-Based Review of the Pathophysiology, Treatment, and Prevention of Exercise-Associated Muscle Cramps.” Journal of athletic training 57, no. 1 (2022): 5-15.
- Garrison SR, Korownyk CS, Kolber MR, Allan GM, Musini VM, Sekhon RK, Dugré N. “Magnesium for skeletal muscle cramps.” The Cochrane database of systematic reviews 9, no. 9 (2020): CD009402.
- Kaufman N, White D, Bull J, Radi R, DeSanto K. “Does Magnesium Supplementation Treat Nocturnal Leg Cramps?” American family physician 108, no. 6 (2023): 619-620.
- Voskoboinik A, Koh Y, Kistler PM. “Cardiovascular effects of caffeinated beverages.” Trends in cardiovascular medicine 29, no. 6 (2019): 345-350.