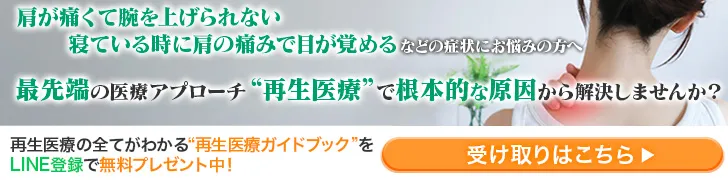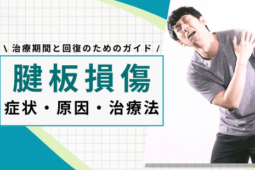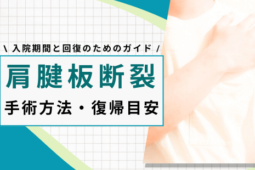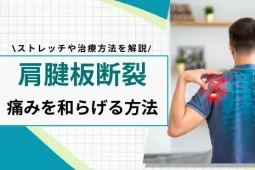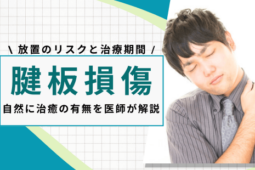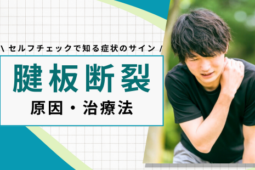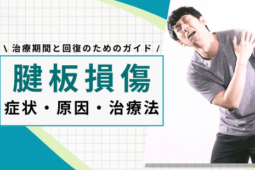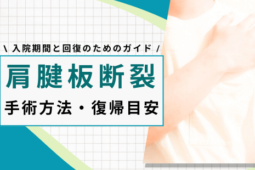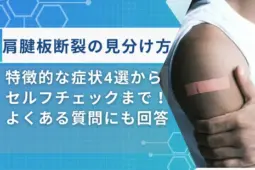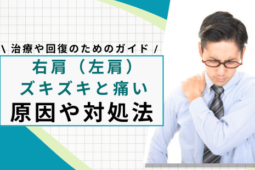- 腱板損傷・断裂
- 肩関節
腱板損傷の治療法|どのくらいで治るのか・放置によるリスクを現役医師が解説
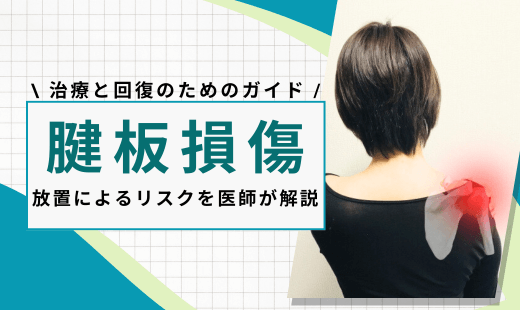
「腱板損傷の症状が一向に良くなる兆しが見えない」
「腱板損傷はどれくらいで治るのか知りたい」
違和感や力の入りにくさを感じると、仕事や私生活に大きな支障が生じます。腱板損傷と診断されても、どのような治療法があり、どれくらいで回復できるのかがわからず、不安を抱く方は少なくありません。
とくに日常的に肩を酷使する人やスポーツ愛好者にとって、放置による悪化は避けたいものです。本記事では、腱板損傷の治療法について現役医師が詳しく解説します。記事の最後には、腱板損傷の治療についてよくある質問をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
腱板損傷の治療法について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
腱板損傷はどれくらいで治る?
| 進行度 | 詳細 |
|---|---|
| 軽度 | 保存療法による日常生活の改善期、症状の安定期(慢性化抑制)、3〜6カ月で日常生活動作の支障軽減、最大6カ月でスポーツ・肉体労働復帰の目安 |
| 中等度 | 保存療法とリハビリ継続、6カ月〜12カ月程度の治癒期間、症状の程度や個人差による回復期間の変動、日常生活や軽いスポーツ復帰の可能性 |
| 重度 | 手術が必要な場合が多い術後2〜3カ月で日常生活の支障が軽減し、3カ月頃から軽作業が可能、6カ月程度で重作業やスポーツ復帰目安、場合により1年以上の回復期間 |
腱板損傷の回復期間は、損傷の程度や治療方法、肩の使い方によって異なります。
軽度は保存療法で数週間〜3カ月で症状が安定し、3〜6カ月で日常生活に支障がほぼなくなります。中等度は6〜12カ月、重度は6カ月〜1年以上かかることもあります。(文献1)
広範囲の断裂では手術が必要となり、術後2~3週間の固定と2~3カ月のリハビリが必要です。(文献2)
年齢や基礎疾患、肩を酷使する習慣も影響するため、早期からの適切な治療とセルフケアが重要です。
腱板損傷の原因や治療法など、包括的な内容に関しては「【医師監修】腱板損傷とは|症状・原因・治療法を詳しく解説」をご覧ください。
腱板損傷|軽度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 状態 | 腱板の一部に炎症や小さな損傷がある状態 |
| 主な治療法 | 安静、日常動作の見直し、物理療法(温熱・冷却)、消炎鎮痛薬、軽いリハビリ |
| 回復までの目安 | 日常生活の改善は3〜6カ月、スポーツ・重作業復帰は最大6カ月ほど |
| 注意点 | 肩に負担をかける動作の回避、症状が軽くても無理をしない |
| 予後・見通し | 早期治療により損傷拡大を防ぎ、数週間〜3カ月で症状を安定させる |
軽度の腱板損傷は、腱の一部に炎症や小さな損傷がある状態です。原因は繰り返しの肩の使用や急な動作による負荷で、放置すると悪化し中等度・重度になる可能性が高い状態です。治療は安静、生活動作の見直し、物理療法、消炎鎮痛薬、リハビリを組み合わせて実施されます。
早期治療で損傷の拡大を防ぎ、症状は数週間〜3カ月で安定します。日常生活には早期復帰できますが、スポーツや重作業は3〜6カ月かかる場合があり、痛みが軽くても肩の酷使を避け、休養と段階的リハビリが必要です。
腱板損傷|中等度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 状態 | 腱板の一部に部分断裂や炎症の拡大 |
| 主な治療法 | 安静、日常動作の見直し、物理療法(温熱・冷却)、消炎鎮痛薬、計画的なリハビリテーション |
| 回復までの目安 | 日常生活復帰は約2〜3カ月。スポーツ・重作業復帰は一般的に6〜12カ月 |
| 注意点 | 痛みが軽減しても無理な復帰は再発リスク。リハビリ・保存療法で十分な改善が得られない場合は手術を検討 |
| 予後・見通し | 計画的な治療・リハビリ継続で比較的円滑な社会・スポーツ復帰が可能(ただし症状や治療法により期間は前後) |
中等度の腱板損傷は、腱の部分断裂や炎症が広がり、肩の可動域制限や筋力低下がみられる状態です。治療は安静、生活動作の見直し、物理療法、薬物療法、リハビリを組み合わせた保存療法が中心で、改善が乏しい場合や断裂範囲が広い場合は関節鏡手術を検討します。
保存療法では、日常生活復帰まで約2〜3カ月、スポーツ・重作業復帰まで約6カ月、治癒まで6〜12カ月かかる場合が多いです。手術を行った場合は術後リハビリを含め半年以上かかります。自然治癒は難しいため、無理な動作を避け、医師や理学療法士の指導に沿って段階的に回復を進めることが重要です。
腱板損傷|重度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 状態 | 腱の完全断裂により日常動作や腕の挙上が著しく制限される状態 |
| 主な治療法 | 手術による腱の修復、術後3〜6週間の固定・安静後にリハビリ開始 |
| 回復までの目安 | 術後2〜3カ月で日常生活の支障が軽減し、3カ月頃から軽作業が可能、6カ月でスポーツ・重作業復帰が一般的だが個人差大 |
| 影響要因 | 放置による関節変形や機能回復の限界、再断裂リスク、リハビリの継続と医師指導の厳守が重要 |
| 注意点 | 年齢、損傷範囲、治療法、リハビリ状況などによる回復期間の差異 |
重度の腱板損傷は、腱が完全に断裂し、日常生活の動作や腕の挙上が著しく困難となる状態です。保存療法のみでの回復は難しく、多くの場合は手術による修復が必要です。手術後は約3〜6週間の安静期間を経てリハビリを開始し、縫合部の修復にはおよそ3カ月を要します。
日常生活への復帰は術後2〜3カ月、軽作業は術後3カ月頃から可能となる場合が多く、スポーツや重作業への復帰は術後6カ月以降が目安です。全体の回復期間は半年〜1年程度ですが、損傷範囲や年齢、肩の使用状況によっては1年以上を要することもあります。
保存療法を選択した場合でも、重度損傷では回復に半年以上かかることが多いため、放置による関節変形や機能低下を防ぐために、早期の医療介入と計画的なリハビリの実施が重要です。
以下の記事では、重度の腱板損傷について詳しく解説しています。
腱板損傷の治療法
| 治療法 | 詳細 |
|---|---|
| セルフケアと生活上の工夫を実践する | 肩への負担の軽減、姿勢・動作の見直し、日常生活での適切な休養と工夫 |
| 温冷療法 | 急性期の冷却による炎症抑制、慢性期の温熱による血流促進と筋肉のこわばり緩和 |
| 薬物療法 | 消炎鎮痛薬の内服、局所ステロイド注射による炎症抑制と症状の緩和 |
| リハビリテーション | 可動域改善、筋力強化、専門家指導のもと段階的に負荷を増やす運動療法 |
| 手術療法 | 重度断裂に対する腱の修復手術、術後の安静期間と段階的リハビリ |
| 再生医療 | 幹細胞・PRP療法による腱修復促進、保存療法や手術の補完的治療 |
腱板損傷の治療は、症状や損傷の程度に応じて適切な方法を選択します。セルフケアでは、肩への負担を減らし、姿勢や動作を見直し、十分な休養を取ることが重要です。温冷療法は、急性期に冷却で炎症を抑え、慢性期に温熱で血流を促進します。
薬物療法では、消炎鎮痛薬の内服や局所ステロイド注射により炎症と痛みを軽減します。リハビリテーションは、可動域改善や筋力強化を目的に、専門家の指導のもと段階的に運動を行います。重度断裂では、腱修復手術が必要となり、術後には安静期間と継続的なリハビリが欠かせません。
再生医療は、幹細胞やPRP療法で腱修復を促す方法ですが、実施医療機関が限られており、事前に対応可否と適応の有無について医師の診察を受ける必要があります。
以下の記事では、肩腱板断裂(腱板損傷)の痛みについて詳しく解説しています。
セルフケアと生活上の工夫を実践する
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 肩への負担を減らす生活習慣の見直し | 重い物を持つ・腕を急に上げる動作の回避、姿勢改善による肩への負担の軽減 |
| 温冷療法の活用 | 怪我初期は冷却で炎症抑制、その後は温熱で血流促進と筋緊張緩和 |
| 適切なリハビリやストレッチの実践 | 医師の指導で痛みのない範囲の運動・可動域拡大、筋力強化 |
| 適切な安静と休息 | 無理な動作を避け、日常生活で安静時間を確保 |
| 医療機関でのフォローに併せた自宅ケア | 注射・物理療法の補完として計画的なセルフケア継続 |
腱板損傷は自然治癒が難しく、肩への負担軽減と肩周囲筋の強化が症状の軽減と機能維持に重要です。セルフケアでは、無理な腕の挙上や高所への手の動きを避け、就寝時は肩を圧迫しない姿勢を保ち、必要に応じてタオルやクッションで支えます。
荷物は片手に偏らず両手や身体全体で分散し、デスクワークではモニター位置を調整して長時間同姿勢を避けることで、炎症悪化防止や可動域維持、再発予防につながります。医療機関での治療と併用することで、より効果的な症状管理が可能です。
以下の記事では、肩の腱板損傷のセルフケアに役立つテーピングについて詳しく解説しています。
温冷療法
| 方法 | 適用時期・目的 | 実施方法 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 冷却療法(アイシング) | 急性期(受傷〜48時間以内)、炎症・腫れの抑制、二次損傷予防 | 氷嚢やアイスパックをタオルで包み、患部に15分程度あてる。15〜20分ごとに繰り返す | 直接長時間あてない、皮膚の凍傷防止、間隔を空ける |
| 温熱療法 | 慢性期・回復期、血行促進、筋肉や腱の柔軟性改善、可動域拡大 | ホットパック、温タオル、入浴などで温める | 急性期は避ける、皮膚低温やけど防止、持病がある場合は医師へ相談 |
温冷療法は、腱板損傷による痛みや炎症の管理に有効な方法です。冷却療法は、受傷直後や急性期に氷嚢やアイスパックをタオルで包み、15分程度患部にあてることで血管を収縮させ、炎症や腫れを抑えます。これにより二次的な組織損傷の予防にもつながります。
温熱療法は、炎症が落ち着いた慢性期や回復期に行います。ホットパックや入浴で肩を温めることで血流を促進し、筋肉や腱の柔軟性を高め、可動域の改善や痛みの緩和を図ります。症状や時期に応じた適切な使い分けが重要です。
冷やすべき時期に温めると悪化する恐れがあります。また、長時間の直接冷却や高温での長時間温熱は避け、持病がある場合は必ず医師に相談の上で実施する必要があります。
薬物療法
| 薬物療法の種類 | 詳細 |
|---|---|
| 消炎鎮痛剤(NSAIDs) | 飲み薬や貼り薬による炎症物質生成の抑制と症状軽減、軽度〜中等度症状への初期対応、日常動作負担の軽減 |
| 局所ステロイド注射 | 関節内や周囲への直接注入による強力な炎症抑制、即効性のある一時的効果、4回以上の連続使用非推奨、医療機関での実施とリハビリ併用 |
| その他の補助的薬物療法 | 筋弛緩薬や鎮痛補助薬による補助的対応、消炎鎮痛剤の補完的使用 |
薬物療法は、炎症を軽減し機能回復を支援する目的で行われます。一般的に使用される非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は炎症や疼痛の軽減に使用される薬剤です。
急性期や症状が強い場合は関節内ステロイド注射で炎症を抑え、リハビリや生活を行いやすくします。長期使用は副作用の恐れがあるため医師の指示に従い、生活改善やリハビリと併用して効果を高めます。
リハビリテーション
| 段階 | 詳細 |
|---|---|
| 急性期 | 安静、アイシング、無理のない範囲での肩関節可動域運動 |
| 回復期 | ストレッチ開始、肩の柔軟性回復、肩甲骨・肩関節周囲筋の軽い筋力強化 |
| 強化期 | 抵抗トレーニング導入、肩周囲筋力と持久力向上 |
| 維持期 | 適切な負荷管理下での定期的運動継続、肩機能維持と再発防止 |
| 患者指導 | 痛みを悪化させる動作回避法、日常生活での肩負担軽減法 |
| 医療機関との連携 | 段階的運動負荷調整、安定したリハビリ進行のための医師・理学療法士の指導 |
腱板損傷の回復と疼痛軽減には、段階的かつ計画的なリハビリテーションが重要です。リハビリは可動域改善と筋力強化によって肩関節の安定性を高め、肩甲帯の適切な働きで関節への負担を減らします。
急性期は安静とアイシング、軽い可動域運動で炎症を抑え、回復期にはストレッチや軽い筋力トレーニングで柔軟性と支持力を回復します。
強化期には抵抗運動で筋力・持久力を高め、維持期では定期的な運動と負荷管理で再発を防ぎます。全過程を通じて、医師や理学療法士の指導のもと日常生活での負担軽減と安定した運動進行を実施することが大切です。
以下の記事では、腱板損傷に効果的なリハビリ方法について解説しています。
手術療法
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 手術の目的 | 保存療法で改善しなかった場合、重度機能障害を伴う場合に有効 |
| 主な適応 | 大きな断裂、進行例、保存療法で改善が乏しい症例 |
| 手術方法 | 関節鏡視下手術による断裂腱の縫合固定、腱と骨の再連結 |
| 手術の流れ | 肩に小切開を数か所、関節鏡と専用器具で断裂部確認・修復 |
| 手術後経過 | 数週間の固定後、専門的リハビリ開始、軽作業は数カ月、運動復帰は半年程度 |
| 期待される効果 | 肩機能改善、可動域制限や再断裂リスク低減、長期的予後の向上 |
保存療法(リハビリや薬物療法)では修復が困難な大きな断裂や進行例に有効です。対して手術療法は、重度の機能障害や保存療法で改善しない場合に推奨されています。
主流は関節鏡視下手術で、小切開からカメラと器具を挿入し断裂部を修復、腱を骨に縫合固定します。腱と骨の癒合により肩の安定性と可動域が改善します。術後は数週間固定し、その後リハビリを行い、軽作業は数カ月後、スポーツや重作業は半年程度で復帰可能です。
再生医療
腱板損傷に対する再生医療は、患者自身の幹細胞や血小板を培養し、損傷部へ注射して組織の修復・再生を促す治療法です。
自然治癒が難しい損傷に対し、痛みの緩和と正常に近い組織回復を目指します。手術や入院の負担がなく侵襲も少ないため、保存療法と併用して回復を促すこともあります。ただし、適応条件や症例は限られ、実施施設も限られているため、医師の慎重な判断が必要です。従来治療で効果が不十分な場合や手術を避けたい場合に選択されます。
当院「リペアセルクリニック」では、腱板損傷に対する再生医療の症例を紹介しています。ぜひご確認いただき、再生医療も治療法の一つとしてご検討ください。
腱板損傷を放置するリスクと注意点
| 放置するリスク | 詳細 |
|---|---|
| 症状の進行と機能低下 | 断裂部位の拡大、肩関節の筋力低下、可動域制限、日常生活動作の困難 |
| 炎症の慢性化と関節変形 | 慢性的な炎症の持続、滑膜炎、関節内の癒着、関節の変形や骨の摩耗 |
| 生活・仕事への影響 | 肩の動かしにくさ、作業や趣味の制限、睡眠障害や日常動作への支障 |
| 手術が必要になることもある | 保存療法での改善困難、断裂の悪化、機能回復不全、最終的に手術や人工関節置換術の必要性 |
腱板損傷を放置すると損傷拡大や炎症慢性化により、筋力低下や関節変形、日常生活への支障が進行します。断裂が進めば手術が必要となり、回復期間が長期化する恐れがあります。
症状の進行防止と機能低下の抑制のため、早期に医療機関で診断を受け、適切な治療を開始することが重要です。
以下の記事では、腱板損傷を放置するリスクについて詳しく解説しています。
症状の進行と機能低下
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 断裂部位の拡大 | 損傷部が自然修復されず裂け目が広がることで、肩の安定性低下 |
| 筋肉の萎縮 | 使わなくなった腱板筋のやせ細りによる筋力低下 |
| 可動域の制限 | 筋力低下や断裂の進行による関節の動きの狭まり |
| 慢性炎症と拘縮 | 持続する炎症による組織の硬化と肩のこわばり |
| 関節変形の進行 | 軟骨摩耗による骨同士の接触と変形性関節症の発症 |
腱板は肩関節の安定を保つ重要な組織ですが、血流が乏しく自然修復が難しいため、損傷を放置すると悪化しやすくなります。
時間の経過とともに断裂が拡大し筋力が低下、可動域制限や拘縮が進行して肩の動きが困難になります。長期間放置すると軟骨摩耗や骨の接触による変形が進み、痛みや機能低下で日常生活に影響を及ぼすため早期治療が必要です。
炎症の慢性化と関節変形
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 炎症の慢性化 | 損傷部位の持続的刺激による炎症継続、組織の硬化と拘縮発生、肩可動域の制限、痛みや使いにくさの長期化 |
| 関節変形 | 腱板機能低下による軟骨摩耗、骨同士の直接接触、骨形態の変化(変形性肩関節症)、肩動作の制限と痛みの悪化 |
腱板損傷を放置すると肩関節内の炎症が慢性化し、周囲組織が硬くなる拘縮が生じることで、可動域が制限され、腕の動かせる範囲が狭くなります。
腱板機能の低下が長期化すると肩関節への負担が増え、軟骨摩耗や骨の変形を伴う変形性肩関節症へ進行する危険が高まります。変形が進行すると不可逆的な変化となり、手術を含む大規模な治療が必要になる場合があるため、早期診断と適切な治療で重度の関節障害を防ぐことが重要です。
生活・仕事への影響
| リスク・注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 炎症の慢性化 | 長期間の損傷による炎症持続、肩周囲組織の硬化(拘縮)、痛みや不快感の長期化 |
| 関節変形 | 腱板機能低下による軟骨摩耗、骨同士の接触、変形性肩関節症への進行と症状悪化 |
| 生活・仕事への影響 | 腱板筋力低下による動作不全、日常生活動作の困難化、睡眠や仕事への悪影響 |
腱板損傷を放置すると炎症が慢性化して拘縮が起こり、可動域が制限されます。さらに機能低下が進み、軟骨摩耗や骨の接触から変形性肩関節症へ進行し、痛みや動作制限が悪化します。
筋力低下による動作不全は日常生活や仕事、趣味に支障をきたし、生活の質低下や精神的負担を招くため、早期診断と適切な治療が重要です。
手術が必要になることもある
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 断裂の拡大による修復困難 | 切れた腱板が自然修復されず裂け目が広がり、手術での修復難易度が上昇 |
| 症状悪化による生活支障 | 強い痛みや可動域制限による日常生活・仕事・趣味の制限 |
| 筋力低下・腱の退縮 | 長期放置による筋萎縮や腱の硬化による回復不良と再断裂リスク増加 |
| 重症化による手術の必要性 | 進行例で腱板修復が困難となり、筋膜移植や人工関節置換術が必要となる可能性 |
腱板損傷は肩関節の安定と動きを担う腱が切れる病態で、軽症なら保存療法で改善することもありますが、放置すると損傷が進行し、断裂拡大により手術が難しくなり、痛みや可動域制限で生活に支障をきたします。
長期放置は筋萎縮や腱退縮を招き、再断裂や機能回復不良のリスクを高め、重症化すれば大規模手術が必要になります。症状が悪化したり生活への影響が大きい場合は、早期に専門医を受診し、手術時期を含めた治療方針を検討することが重要です。
腱板損傷の再発を防止する方法
| 再発を防止する方法 | 詳細 |
|---|---|
| 適切なリハビリで肩周囲筋と肩甲帯を強化する | 棘上筋・棘下筋・肩甲骨安定化筋の筋力向上、肩関節と肩甲帯の安定性確保 |
| 定期的なストレッチと可動域訓練で柔軟性を維持する | 肩関節と肩甲骨周囲の筋群の柔軟性保持、関節可動域の正常化 |
| 姿勢や腕の動きを見直し肩への過負荷を抑える | 猫背や巻き肩の矯正、腕の急激な挙上や過度な外旋の回避 |
| 回復期には運動強度を段階的に調整して進行させる | 急激な負荷増加の回避、運動内容と強度の計画的漸増 |
腱板損傷の再発を防ぐには、回復後も肩周囲筋と肩甲帯の安定性を維持することが重要です。棘上筋・棘下筋・肩甲骨安定化筋を中心とした筋力強化と、定期的なストレッチや可動域訓練による柔軟性保持が欠かせません。
日常生活では猫背や巻き肩を避け、急激な腕の挙上や過度な外旋など肩に負担をかける動作を控えます。さらに、作業環境やスポーツ動作を見直し、運動強度は段階的に調整することが大切です。こうした継続的な取り組みにより、再発リスクを低減し、肩機能の長期的な維持が可能となります。
適切なリハビリで肩周囲筋と肩甲帯を強化する
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 肩関節周囲のストレッチと可動域訓練 | 肩甲骨周囲の柔軟性向上、関節可動域の拡大 |
| チューブや軽い抵抗を使った筋力トレーニング | 回旋筋群(外旋・内旋)と肩甲帯の段階的強化、肩状態に応じた負荷調整 |
| 姿勢改善や動作指導 | 肩への過度な負担軽減、日常生活や仕事での適切な肩の使い方指導 |
| 医師の指導のもとでの段階的リハビリ | 理学療法士などによる継続的な運動指導、再発予防 |
腱板損傷は、保存療法で改善が見込める段階を過ぎると腱の再接合が難しくなり、手術が必要になる場合があります。手術は有効な治療法ですが、身体的・精神的負担が大きく、術後には長期間のリハビリが必要です。
軽度〜中等度の損傷は、保存療法で回復することが一般的ですが、放置すると断裂の進行や慢性痛により手術が必要になるリスクが高まります。早期治療は手術回避や将来の機能低下防止に有効です。
定期的なストレッチと可動域訓練で柔軟性を維持する
| 運動名 | 詳細 |
|---|---|
| 振り子運動 | 前かがみ姿勢で反対腕を支え、痛む腕を下に垂らして左右・前後に小さく揺らす可動域拡大運動 |
| クロスボディストレッチ | 腕を肩の高さまで上げ、反対の手で肘を体側へ引き寄せ肩後方を伸ばす柔軟性向上運動 |
| 手のひら回し | 両腕を肩の高さに上げ、手のひらを回して肩甲骨周囲を動かす可動性向上運動 |
| 腕の上げ下げ運動 | 椅子に座って背筋を伸ばし、痛みのない範囲で腕をゆっくり上げ下げする可動域維持運動 |
腱板損傷のリハビリでは、肩関節の柔軟性を保ち可動域を広げることが重要です。振り子運動やクロスボディストレッチ、手のひら回し、腕の上げ下げ運動などを痛みのない範囲で行いましょう。
筋肉が硬くなると可動域が狭まり、肩に過度な負担がかかりやすくなります。これを防ぐためには、定期的なストレッチや可動域訓練を習慣化することが大切です。肩回しや肩甲骨を意識したストレッチを日常に取り入れ、とくに起床時や運動前後に実施することで筋肉の柔軟性を維持し、再発リスクを減らせます。
姿勢や腕の動きを見直し肩への過負荷を抑える
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 姿勢改善 | 猫背矯正と背筋伸展による肩甲骨位置の正常化、デスクワーク時のモニター高さ・椅子高さ調整 |
| 腕の動きの工夫 | 過度な挙上や急なねじり動作の回避、肩負担軽減を意識した動線確保 |
| 肩甲骨の動きを意識 | 肩甲骨安定化筋の活用による滑らかな肩・腕の動作、肩甲骨周囲ストレッチやエクササイズの実践 |
| 仕事・日常動作の見直し | 両手での物の持ち運び、左右の腕の使用バランス確保による肩負担分散 |
腱板は肩関節の動きと安定性を支える重要な組織です。不適切な姿勢や腕の使い方は過剰な負担となり損傷や再発の原因になります。猫背や巻き肩は肩甲骨の動きを制限し、肩関節に不要なストレスを与えます。
腕の無理な高挙や急なひねり、誤ったスポーツフォームはリスクを高める原因です。日常生活や仕事では背筋を伸ばし、モニターや椅子の高さを調整して姿勢を整え、物は両手で持ち左右均等に使います。肩甲骨安定化筋を鍛える運動やストレッチも有効です。必要に応じて専門家の動作指導を受けることが望まれます。
回復期には運動強度を段階的に調整して進行させる
腱板損傷のリハビリでは、回復期に運動強度を段階的に調整することが重要です。損傷部が完治する前に強い負荷をかけると、腱や筋肉に過剰なストレスがかかり、再断裂や炎症悪化の恐れがあります。
初期は軽い可動域訓練から始め、回復状況に応じてチューブや軽負荷を使った筋力強化へ移行し、最終的には日常生活やスポーツ動作に進めます。
段階的な負荷増加は腱や筋肉の適応を促し、肩関節の安定性を高める上で効果的な方法です。医師や理学療法士の指導のもと、状態に合わせた調整を行うことで無理なく長期的な機能回復に寄与します。
腱板損傷の治療にお悩みの方は当院へご相談ください
腱板損傷は放置すると断裂の進行や慢性化を招き、痛みや可動域制限が悪化して日常生活に大きな支障をきたす恐れがあります。早期に正しい治療を開始し、継続的に取り組むことが回復への近道です。
腱板損傷が改善せずお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。当院では、損傷部位の修復を目的とした再生医療を選択肢のひとつとしてご案内し、症状や状態に応じた治療方針を検討いただけます。
ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。
腱板損傷の治療に関するよくある質問
腱板断裂でやってはいけないことはありますか?
腱板断裂では、肩に大きな負担をかける動作は避けましょう。重い物を持ち上げる、遠くへ手を伸ばす、腕を強くひねる、急な動作や過度な力をかける、肩を後ろに回すなどは悪化や再断裂の原因になります。
とくに手術後3カ月ほどは無理な運動を控え、医師の指示に従って段階的に動かすことが大切です。
腱板損傷の筋力や痛みを確認する方法はありますか?
腱板損傷の状態を確認するには、自宅でできるセルフチェックと医療機関での検査があります。腕の挙上時に肩の中央付近で痛む(ペインフルアークサイン)、腕の内外旋で痛みや力の入りにくさがある、肩の外転時に筋力低下や痛みが出る場合は注意が必要です。
医療機関では徒手筋力テスト、視診・触診、超音波やMRIで損傷の程度を評価します。痛みや筋力低下が続く場合は早期受診が重要です。
腱板損傷で社会保険(労災・障害年金など)は受けられますか?
腱板損傷で社会保険を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
| 種類 | 条件 |
| 労災保険 | 仕事中や業務関連の事故・負傷で「業務遂行性」と「業務起因性」が認められること |
| 勤務中の作業や出張中の事故、業務に密接した活動中の負傷が対象 | |
| 重作業の蓄積で発症した場合も対象となることがある | |
| MRIや診断書など医学的証拠が必要、原因の業務起因性の明確化が必須 | |
| 障害年金 | 腱板損傷により肩の機能障害や可動域制限が残り、日常生活や労働に著しい支障がある場合 |
| MRI画像や可動域制限の度合いにより12級や14級などの障害等級が認定されることがある | |
| 医師の診断書提出が申請に必須で、障害状況が詳細に評価される |
この表は、労災保険は業務に関連した明確な原因が認められ、医学的証拠が必要である点、障害年金は日常生活や労働に著しい支障をきたす機能障害が条件となることを示しています。
それぞれの制度で求められる証明や認定基準に基づいて申請されます。これにより患者様は、労災保険と障害年金の適用条件を理解し、適切な手続きを行うためのポイントが把握できます。
参考文献
(文献1)
肩腱板損傷はどのくらいで治る?日常生活への影響と回復のタイムライン|むとう整形外科・MRIクリニック
(文献2)
「肩腱板断裂」|公益社団法人 日本整形外科学会