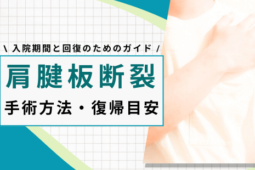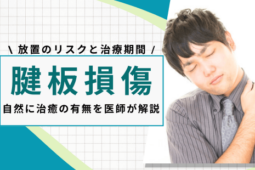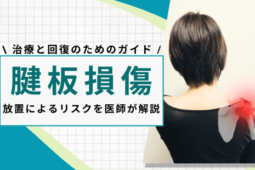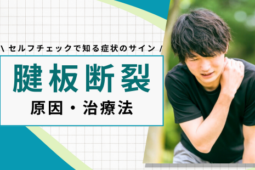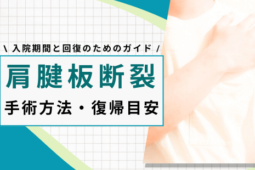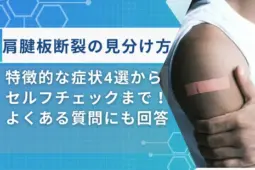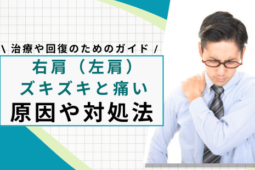- 腱板損傷・断裂
- 肩関節
【医師監修】腱板損傷とは|症状・原因・治療法を詳しく解説
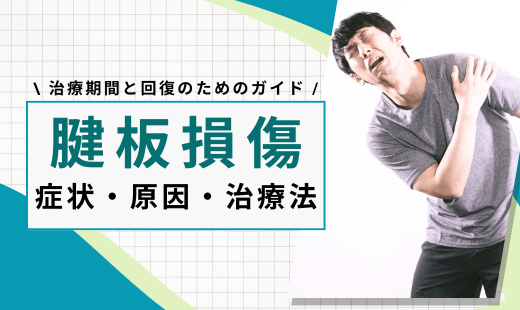
「肩や腕に違和感がある」
「肩に力が入りにくい」
腱板損傷が疑われたとき、対処に迷う方は少なくありません。五十肩との違いがわからず、不安が強まるケースもあります。肩や腕の不調を放置すると症状が悪化する可能性があるため、早期の判断が重要です。腱板損傷の症状や原因を理解すれば、適切な対処方法が見えてきます。
- 腱板損傷の症状
- 腱板損傷の原因
- 腱板損傷の治療法
- 腱板損傷の予防と再発防止策
記事の最後には、よくある質問をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
腱板損傷について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
腱板損傷とは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 腱板損傷の症状 | 肩や腕の動かしにくさや特定角度での違和感、夜間の不快感、力が入りにくいことや筋力低下などが挙げられる |
| 似た症状の病気との違い | 五十肩(肩関節周囲炎):関節包の炎症が主な原因で、動かし始めの違和感が強く、時間の経過とともに可動域が制限されます。一方、腱板損傷は腱の損傷により筋力低下が生じる点が特徴です。 |
| 変形性肩関節症:軟骨のすり減りによる関節の変形と違和感が原因。画像診断で確認 | |
| 神経由来の痛み:首の神経圧迫による肩・腕のしびれや痛み。腱板損傷は局所の腱損傷が原因 | |
| 原因 | 加齢、肩の使いすぎ、外傷など |
| 診断 | 肩の動かしにくさや特定の角度での違和感が続く場合は、整形外科への受診が必要 |
腱板損傷は、肩の筋肉と腱で構成される腱板が傷ついた状態です。腱板は肩関節を安定させ、腕を動かす役割があります。負担や加齢によって腱に傷ができると、肩の動きが制限され、違和感が生じます。
日常生活に支障をきたすこともあるため、適切な診断と治療が必要です。軽度の場合は保存療法が中心で、症状や生活環境によっては手術が検討されます。
以下の記事では、腱板損傷と断裂の違いについて詳しく解説しています。
腱板損傷の症状
| 症状 | 詳細 |
|---|---|
| 肩や腕を動かしにくい | 肩や腕の動作制限、腕を上げる動作が困難になる |
| 特定の動作で違和感が出る | 腕を一定の角度に動かした際の引っかかり感や不快感 |
| 夜間や安静時に症状が強まる | 夜間や休息時の肩の不快感、睡眠障害の可能性 |
| 肩の力が入りにくい | 筋力低下による物を持つ・支える動作が困難になる |
腱板損傷では、肩や腕の動かしにくさ、特定の動作での痛み、夜間痛、筋力低下などの症状がみられます。
これらの症状は、物を持つ、腕の挙上、寝返りを打つといった日常の動作を妨げ、生活の質を低下させます。症状が強く時間が経っても改善しない場合は損傷が進行する恐れがあるため、早期に整形外科を受診することが重要です。
以下の記事では、腱板損傷の筋力や痛み確認方法について詳しく解説しています。
肩や腕を動かしにくい
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 力が入らない | 腕を横や上に持ち上げようとしても途中で力が抜ける状態 |
| 特定の角度で止まる | 肩を一定の角度までは上げられるが、それ以上は力が入らず動かない |
| 日常生活での不便 | 洗濯物を干す、棚の上の物を取る、髪をとかす・結ぶなどの動作が難しい |
| 他人が動かそうとしても動かない | 違和感が強く出る場合、自分以外が肩を動かしても固まって動かせないことがある |
| 似た症状との違い | 五十肩と違い、急に力が入らなくなることや特定方向だけ動きにくい特徴がある |
腱板損傷では、腕を上げる・横に広げる・後ろに回すなどの動作で肩の痛みが生じ、動きが制限されます。
高い所の物を取る、服を着替えるといった日常動作にも支障が出ます。これは損傷した腱が正常に機能せず、肩関節の動きが妨げられるためです。
特定の動作で違和感が出る
腱板は肩関節を安定させ、腕を動かす役割を持つ組織で、動きの方向によって特定の部分が強く働きます。損傷があると、腕を横から90度まで上げる、後ろポケットに手を回す、頭上に物を持ち上げるなどの動作で負担が集中し、引っかかり感、脱力感、疼痛が生じやすくなります。
原因は腱が骨にこすれ、正常に収縮できず関節が不安定になるためです。腱板損傷では、できる動作とできない動作の差が特徴で、五十肩は方向に関係なく全体的に固くなります。また、動作中に「コキッ」という音や引っかかり感、腕を下ろす途中で力が抜けるドロップアームサインがある場合は、腱板の完全断裂が疑われます。
夜間や安静時に症状が強まる
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 寝る姿勢と肩の負担 | 横向きで痛む側を下にすると体重で肩が圧迫され、仰向けでも腕の重みで肩に負担がかかる |
| 筋肉の緊張と血流の悪化 | 筋肉が緊張して血流が悪くなり、酸素や栄養が届きにくくなるため、違和感が出やすくなる |
| 関節の安定性低下による刺激 | 腱板損傷で筋肉と腱の連結が弱くなり、安静時でも肩関節内で組織が擦れ刺激を受けやすい |
| 炎症の影響 | 損傷部位の炎症が夜間に強まり、血流悪化と体の休息中に違和感が増し、目が覚めることがある |
肩の痛みは、腱板損傷により夜間や安静時に強まることがあります。寝る姿勢や腕の重みで肩に負担がかかり、筋肉の緊張や血流悪化で炎症が悪化するためです。
安静時でも肩内部で組織が擦れて刺激を受けやすく、痛みで目が覚めることもあります。姿勢の工夫と適切な治療が不可欠です。
肩の力が入りにくい
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 腱板の役割と損傷の影響 | 肩関節の安定と腕を動かす筋腱複合体の損傷による力の伝わりにくさ |
| 筋力低下のメカニズム | 腱断裂による筋肉の付着不全と炎症による筋力低下 |
| 筋肉の萎縮や硬直 | 肩の使用減少による筋肉の細化と硬直 |
| 安定性低下に伴う不安定感 | 肩関節の緩みやずれ感による力の入りにくさと違和感・不安感 |
腱板は、肩関節を安定させながら腕を動かす重要な筋肉群の腱の集合体です。腕を上げる動きにも欠かせず、損傷すると肩に力が入りにくくなります。
とくに重い物を持つ時や腕を伸ばして物を取る時に力が出ず、腕が上がらないことがあります。これは、腱断裂により筋肉が骨にしっかり付着できなくなり、炎症や痛みによって筋力が低下するためです。
また、肩を使わない状態が続くと筋肉が痩せたり硬くなったりし、力が入りにくくなります。関節の安定性も損なわれ、動かす際にぶれやずれを感じることがあります。
腱板損傷の原因
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 加齢による腱の変化 | 加齢に伴う腱の弾力性低下や摩耗による損傷の起こりやすさ |
| 肩の使いすぎや外傷による負担 | 繰り返しの動作や急な衝撃による腱への過度な負担 |
| 生活習慣や体質の影響 | 姿勢不良や血流不足、体質的な腱の弱さによる損傷の起こりやすさ |
腱板損傷は、加齢、肩の使いすぎ、外傷、姿勢不良、血流障害などによって腱が損傷し、肩関節の動きや腕の挙上が制限される状態を指します。
予防には肩への負担を減らしつつ、適度な運動で柔軟性を保つことが大切です。異常を感じたら早めに医療機関を受診してください。
加齢による腱の変化
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 腱の柔軟性や強さの低下 | 腱の弾力や強度の低下、腱の硬化による負担耐性の減少 |
| 血流の悪化と修復力低下 | 血管の細さや閉塞による栄養不足、腱の修復能力の低下 |
| 繰り返しの負荷による摩耗 | 長期間の肩使用による腱の摩耗と変性、断裂リスクの増加 |
| 気づかない損傷の進行 | 進行がゆっくりで自覚症状が遅れることによる突然の症状出現 |
腱板は肩の動きを支える重要な腱ですが、加齢や長年の使用で弾力や強さが低下し、変性しやすくなります。細胞やコラーゲンの劣化、血流悪化で修復力も落ち、小さな負荷で損傷が進みやすくなります。
この変化は自覚しにくく、突然の痛みや動かしにくさとして現れることが多いため、違和感が出た場合は、早めの受診が大切です。
肩の使いすぎや外傷による負担
肩を繰り返し使いすぎると腱板に小さな損傷が蓄積し、炎症や違和感が生じやすくなります。野球やテニス、バレーボールなどのスポーツや重量物を扱う重労働は、肩の骨と腱が擦れたり衝突したりして損傷する原因のひとつです。
転倒や打撲、重い物を持ち上げた際の急な力でも損傷が起こり、突然の痛みや動かしにくさが現れます。とくに棘上筋は骨の突起の下を通るため摩擦や衝突を受けやすく、損傷しやすい部位です。そのため、肩を日常的に酷使する人は損傷が進行しやすくなります。
生活習慣や体質の影響
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 年齢による変性(体質的影響) | 加齢に伴う腱の老化と血流低下による修復力の低下、高齢者や大きな断裂のリスク増加 |
| 喫煙 | ニコチンなどによる腱の細血管損傷と代謝・回復能力の低下 |
| 肥満・高BMI | 体重増加による肩関節と腱への負担増加、慢性的炎症による腱の劣化促進 |
| 姿勢の悪さ | 猫背や前かがみによる肩の動きの不均衡と腱への異常圧力・摩擦 |
| 運動不足 | 筋肉や腱の弱化による支持力低下と損傷のリスク増加 |
| 家族歴(遺伝的体質) | 家族に腱板損傷の経験があることで、同様の体質的弱点の存在 |
| 生活習慣性疾患 | 高血圧や糖尿病による微小血流障害と腱の修復力低下、とくに糖尿病患者の組織老化促進 |
腱板損傷や腱板不全症候群は、加齢や生活習慣、体質が関与し、とくに65歳以上や広範囲の断裂がある方、喫煙者、糖尿病患者、筋萎縮や脂肪浸潤がある方、術後ケアを守らない方で発症リスクが高くなります。
2008年の研究では断裂の発生率が50~59歳で13%、60~69歳で20%、70~79歳で31%、80歳以上では51%に増加しています。(文献1)
喫煙は腱への血流を悪化させ修復力を低下させ、糖尿病などの生活習慣病も組織の修復を妨げます。遺伝的な体質が腱板の脆弱性に関与する可能性もあります。予防には、禁煙や適正体重の維持、良い姿勢と肩周りの軽い運動、慢性疾患の適切な管理が重要です。
腱板損傷の治療法
| 治療法 | 詳細 |
|---|---|
| 保存療法(薬物療法・注射・理学療法) | 痛み軽減のための薬物使用、炎症抑制のステロイド注射、関節可動域維持の理学療法 |
| リハビリテーション | 肩周辺筋肉のストレッチと強化訓練、肩関節の動きの改善、関連部位の調整 |
| 手術療法 | 関節鏡視下手術による腱板断裂の修復、必要に応じた上方関節包再建術や人工肩関節置換 |
| 再生医療 | 神経や筋肉の機能改善を目指す細胞治療や組織修復技術 |
腱板損傷の治療は、症状や損傷の程度に応じて保存療法、リハビリテーション、手術療法、再生医療が選択されます。保存療法では薬剤や注射で炎症や痛みを抑え、理学療法で肩の可動域を維持します。
リハビリテーションでは筋力や柔軟性を向上させて日常生活での負担を軽減し、損傷が大きい場合や改善が得られない場合には手術を行います。
腱板損傷の治療法として、幹細胞を活用した再生医療も選択肢のひとつです。しかし、取り扱う医療機関が限られているため、事前に問い合わせや診察を受ける必要があります。
以下の記事では、腱板損傷の治療および自然治癒する可能性について詳しく解説しています。
【関連記事】
腱板損傷の治療法|どのくらいで治るのか・放置によるリスクを現役医師が解説
腱板損傷は自然に治癒する?放置のリスクと治療期間を現役医師が解説
保存療法(薬物療法・注射・理学療法)
| 治療法 | 詳細 |
|---|---|
| 薬物療法 | 違和感や炎症を和らげる消炎鎮痛剤の使用(飲み薬、湿布)による一時的な違和感の軽減と日常生活の改善 |
| 注射療法 | 超音波エコーで炎症部位を確認しながら行うステロイド注射やハイドロリリースによる炎症抑制と腱の拘縮を軽減 |
| 理学療法 | 理学療法士の指導による筋力強化運動、可動域拡大のストレッチ、温熱療法や電気治療を用いた負担を抑えた治療 |
| 注意点 | 腱の完全再生は困難で小康状態の維持を目指すこと、症状悪化時の医師受診の重要性、日常生活での肩負担軽減の工夫を含む |
腱板損傷の保存療法は、手術を行わずに炎症や痛みを抑え、肩の機能維持を目指す治療法です。違和感や炎症を和らげる薬物療法(内服薬や外用薬)、直接炎症部位に注射をする注射療法(ステロイド注射やヒアルロン酸注射など)、そして温熱療法や電気療法を含む理学療法による血行促進や関節可動域の改善が行われます。
腱板が完全に治癒することは難しい場合もありますが、これらの方法で痛みの軽減や肩の動きの改善を目指します。
とくに加齢や軽度・部分断裂、高齢で活動量の少ない方では、保存療法で約75%の方に症状改善が見込まれます。(文献2)
以下の記事では、腱板損傷に対する保存療法について詳しく解説しています。
【関連記事】
肩の腱板損傷にはテーピングが有効!巻き方やリハビリについて専門医が解説
【痛み止め】関節症に使うステロイド注射の効果は?気になる副作用も解説
膝のヒアルロン酸注射が効かないのは失敗が原因?効果を感じないのはなぜ?
リハビリテーション
| リハビリ内容 | 詳細 |
|---|---|
| 段階的な運動療法 | 初期の軽い可動域訓練・ストレッチによる関節可動域回復、腱板筋群強化、肩甲骨運動によるバランス改善 |
| 物理療法の併用 | アイシング・温熱療法・超音波治療・電気刺激による痛みと炎症の軽減、血流改善 |
| 姿勢や動作の指導 | 日常生活での正しい肩の使い方や姿勢指導、負担軽減動作の習得 |
| 医師による継続的サポート | 理学療法士や医師による個別プログラム作成と症状・状態に応じた進行管理 |
| 注意点 | 段階的な負荷設定の重要性、自己判断での継続回避、強い違和感が出た場合の中止と医師への相談 |
リハビリテーションは、腱板損傷の症状を改善し、肩の動きをスムーズにしながら筋力を強化して関節の安定性を高め、日常生活への支障を減らす重要な治療です。
痛みを軽減し、硬くなった関節の可動域を広げ、肩を支える筋肉を鍛えることで再発や悪化を防ぎます。理学療法士の指導によるストレッチや筋力強化運動で正常な肩の機能を取り戻し、生活の質向上と予防につながります。
以下の記事では、腱板損傷のリハビリや痛みを和らげる方法について詳しく解説しています。
【関連記事】
腱板損傷に効果的なリハビリとは?NG行為や治るまでの期間も解説
肩腱板断裂の痛みを和らげる方法5選!ストレッチや治療方法を現役医師が解説
手術療法
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 手術が有効な理由 | 自然治癒困難な腱を物理的に修復して機能回復を図る効果、科学的根拠に基づく症状改善、早期修復による悪化防止 |
| 手術方法 | 関節鏡視下腱板修復術(ARCR)による小切開での腱板縫合と身体の負担軽減 |
| 手術の流れと適応 | 急性完全断裂や大きな損傷、保存療法無効例、生活や仕事への支障例での早期手術検討 |
| 効果 | 術後2〜10年間での肩の動きと機能回復の持続、従来法より優れた長期成績 |
| 注意点 | 感染症・神経障害・再断裂リスク、術前術後管理の重要性 |
(文献3)
損傷した腱は自然治癒が難しいため、手術で物理的に修復することで肩の違和感や動きの改善が期待できます。また、放置すれば損傷が拡大し、関節機能の低下や将来的な関節炎につながります。したがって、早期修復は進行防止に有効です。
現在主流の関節鏡視下腱板修復術は、小切開で腱を骨に縫合する低侵襲手術であり、術後の回復や合併症リスクの軽減が見込まれます。ただし、手術には感染、神経損傷、再断裂などのリスクがあります。とくに高齢者や大きな断裂、脂肪浸潤がある場合は再断裂のリスクが高く、術後リハビリの質が治療結果を左右するため適切な管理が必要です。
以下の記事では、肩腱板断裂の手術と入院期間について詳しく解説しています。
再生医療
再生医療は、患者様自身の脂肪組織や血液から採取した幹細胞や血液成分を用い、損傷した腱板の修復や再生を目指す治療法です。手術を伴わないため身体への負担が少ないのが特徴です。
幹細胞の働きによって、従来の薬物療法やリハビリでは改善が難しい損傷にも根本的な回復が期待できます。細胞は培養後に損傷部位へ注射で投与され、治療後も通常の生活を送りやすいのが利点です。
当院「リペアセルクリニック」では、腱板損傷に対する再生医療の症例を紹介しています。ぜひご確認いただき、再生医療も治療法の一つとしてご検討ください。
腱板損傷の予防と再発防止策
| 予防と再発防止策 | 詳細 |
|---|---|
| 生活習慣の見直しで肩への負担を減らす | 重い物の持ち上げを控える、無理な動作の回避、禁煙による血流改善、健康的な体重維持 |
| 運動とストレッチで肩の柔軟性を維持する | 肩周りの筋力強化運動、肩甲骨の動きを良くするストレッチ、適切なウォームアップとクールダウン |
| 定期的な検診で早期発見につなげる | 医師による状態評価、リハビリ進行の確認、違和感や痛みの早期相談による再発予防 |
腱板損傷を防ぐには、日常生活や運動習慣の見直しが重要です。重い物を避け、無理な動作を控え、禁煙と適正体重の維持によって肩の負担を軽減し、血流を改善します。
肩周囲の筋力強化や肩甲骨のストレッチ、適切なウォームアップとクールダウンで柔軟性を保つことも大切です。また、定期的な診察で状態を確認し、違和感があれば早めに医師に相談することで再発を防げます。
生活習慣の見直しで肩への負担を減らす
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 肩への過度な負担の軽減 | 繰り返しの動作や重い荷物、長時間同じ姿勢による腱への負担減少、腱の疲労や損傷予防 |
| 筋肉や腱の老化・劣化の遅延 | 適度な運動やストレッチによる筋肉の柔軟性維持、血流改善による腱の健康促進と損傷リスクの軽減 |
| 肩の安定性と動きのサポート | 無理な動作の回避や正しい荷物の持ち方による関節負担の軽減とケガ予防 |
| 炎症や疲労の蓄積防止 | 休息・睡眠の確保、ストレス管理による炎症悪化防止と肩の健康維持 |
| 具体的な生活習慣の見直し例 | 休憩の確保、体全体を使った荷物の持ち方、姿勢改善、適度な運動とストレッチによる肩周辺筋力と柔軟性の維持 |
生活習慣の見直しは腱板損傷の予防と再発防止に効果的です。繰り返し動作や重い荷物の持ち運び、長時間同じ姿勢など肩に負担をかける行動を減らすことで、腱の疲労や損傷を防げます。
適度な運動やストレッチ、正しい姿勢は筋肉の柔軟性と血流を保ち、腱の老化や劣化を遅らせます。肩の使い方を工夫し、重い物は両手で持つ、長時間同じ姿勢を避ける、作業中は休憩を取る、睡眠時の枕や姿勢に配慮することが大切です。
運動とストレッチで肩の柔軟性を維持する
| 予防ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 肩の柔軟性維持 | 肩の筋肉や腱の硬さや動きの悪さを防ぎ、不自然な負担を軽減し腱の損傷リスクを抑制 |
| 筋力強化による関節安定性向上 | 肩周囲の筋肉を適度に鍛え、肩関節を安定させ腱板への負担を分散、損傷予防に寄与 |
| 血流改善による組織回復促進 | 運動やストレッチで肩周辺の血行促進、栄養と酸素供給を増やし腱や筋肉の修復と疲労回復を支援 |
| こわばり予防と動作負担軽減 | 肩のこわばりや硬さを防ぎ、動かしやすくすることで動作時の負担を減らし腱板の保護を図る |
| 運動時の注意点 | 無理のない範囲での定期的なストレッチ、痛みがある場合は中止し専門家相談、軽い筋力トレーニング推奨 |
肩の柔軟性維持は腱板損傷の予防に有効で、筋力強化は関節を安定させ負担を分散します。運動やストレッチは血流を促し修復を助け、こわばり予防で腱板を守ります。
違和感がある場合は無理をせず医師の指導を受けることが大切です。
定期的な検診で早期発見につなげる
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 軽い損傷や初期変化の発見 | 問診・動作チェック・エコー・MRIによる自覚症状が軽い段階での異常発見 |
| 早期発見による治療効果 | 保存療法や生活習慣の見直しで状態安定、悪化防止と手術回避の可能性向上 |
| 再発・悪化リスクの管理 | 継続的な肩の状態確認と再発防止のための指導 |
| 状態把握によるセルフケア | 日常生活での肩の使い方指導により無理な動作を避けやすく、良好な状態維持支援 |
肩に違和感が出た場合、放置せず早めに整形外科を受診しましょう。早期診断と適切な治療・ケアで症状の悪化や重症化を防げます。
とくにスポーツや肉体労働で肩を酷使する方は、症状がなくても定期検診で小さな異変を早期発見し、予防対策を講じることが大切です。
以下の記事では、MRI検査について詳しく解説しています。
腱板損傷でお悩みなら当院へご相談ください
腱板損傷は、日常生活に支障をきたします。腱板損傷を改善するには原因の特定と正しい治療の継続が不可欠です。
腱板損傷の症状が改善しない、強い違和感にお悩みの方は当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。当院では、腱板損傷の症状に直接アプローチする再生医療を、治療の選択肢のひとつとして提案しています。
再生医療は、薬物や手術を用いず、幹細胞を投与することで損傷した腱板を再生させる可能性がある治療法として、近年注目されています。
ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。
\無料オンライン診断実施中!/
腱板損傷に関するよくある質問
腱板損傷でやってはいけないことはありますか?
腱板断裂の悪化や再断裂を防ぐためには、肩への負担を避けて安静を保つことが重要です。
具体的には、重い物を持ち上げる動作(とくに頭上や水平位置)、無理に遠くや高所へ手を伸ばす動作、腕を強くひねる動作、急な動きや肩を大きく後ろに回す動作を控えましょう。症状や治療経過に応じて、医師の指示に従いましょう。
以下の記事では、腱板断裂の際にやってはいけないことを詳しく解説しています。
腱板損傷(断裂)は自然治癒で治りますか?
腱板断裂は程度によりますが、自然治癒は一般的に期待できません。完全断裂や広範囲断裂では自然には治らず、放置すると症状が悪化することがあります。
そのため、多くの場合は手術などによる治療が必要です。症状が改善しない場合は、医療機関を受診しましょう。
以下の記事では、腱板断裂の自然治癒について詳しく解説しています。
片桐作成KW(腱板損傷 自然治癒)
腱板損傷(断裂)を放置するとどうなりますか?
腱板断裂は自然に治癒せず、放置すると断裂が広がります。筋肉は萎縮して脂肪に置き換わり、修復が困難になります。
腱板の機能が失われると肩関節が変形し、違和感や動作制限、筋力低下で腕が挙がらなくなり、進行すると睡眠や服の着脱など日常生活にも支障が出るため、早期診断と適切な治療が重要です。
以下の記事では、腱板損傷を放置するリスクを詳しく解説しています。
腱板損傷を発症したスポーツ選手や有名人はいますか?
腱板損傷や断裂を経験したのは以下の日本人スポーツ選手です。
- 山本由伸(プロ野球・ドジャース)
- 由規(元ヤクルト)
- 浅尾拓也(元中日)
- 斉藤和巳(元ソフトバンク)
- 福田秀平(元ソフトバンク/ロッテ)
腱板損傷はプロスポーツ選手にも発症し、競技パフォーマンスや選手生命に大きな影響を与えることがあります。
以下の記事では、山本由伸選手が発症した腱板損傷について詳しく解説しています。
参考文献
修正中