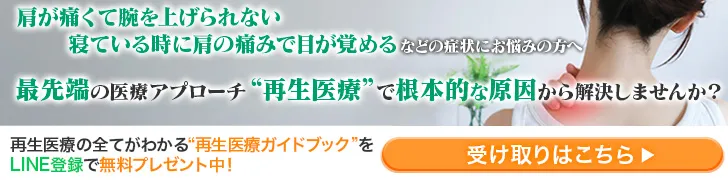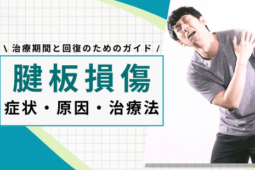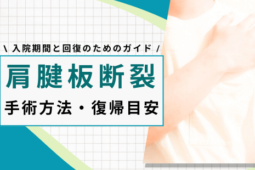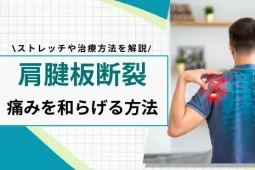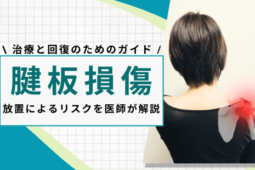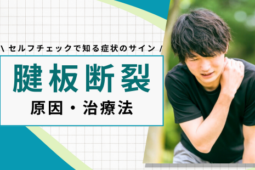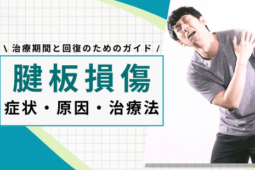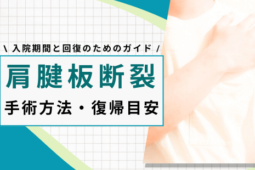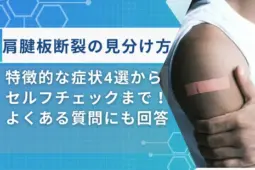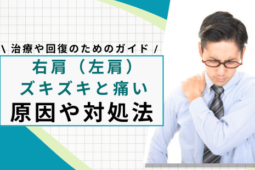- 腱板損傷・断裂
- 肩関節
腱板損傷は自然に治癒する?放置のリスクと治療期間を現役医師が解説

「腱板損傷は安静にすれば自然に治るのでは?」
「手術や注射を避けたい」
本記事では、腱板損傷が自然に治癒する可能性や治療期間、放置による悪化のリスクについて、医学的根拠に基づき現役医師が解説します。
記事の最後にはよくある質問をまとめています。まずは自分の症状と損傷の程度を正しく把握し、適切な治療と生活管理を始めましょう。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
腱板損傷の治療について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
目次
腱板損傷は自然治癒する?
| リスク項目 | 内容 |
|---|---|
| 断裂拡大 | 放置により断裂が広がる可能性 |
| 機能低下 | 肩の筋力や動きの制限による日常生活への支障 |
| 手術困難 | 長期放置で脂肪浸潤・変性が進み再縫合が困難になる可能性 |
| 関節症進行 | 腱板断裂性肩関節症への移行リスク |
| 手術成績への影響 | 断裂が進行した状態での手術は術後の回復遅延や満足度低下のリスクが高い |
腱板は肩の重要な働きを担う組織で、血流が乏しく自然治癒が極めて困難な部位です。1996年と2002年に行われたMRIによる経過観察では、完全断裂の約66%が拡大し、縮小例はゼロでした。中等度の部分断裂でも縮小は27%にとどまり、自然治癒はまれと報告されています。(文献1)
放置すると断裂拡大や筋力低下が進行し、洗濯干しや着替えなどの日常動作に支障をきたす恐れがあります。さらに、長期放置は手術の難易度を上げ、術後の回復や満足度に影響します。保存療法で痛みを抑えることは可能ですが、断裂そのものの修復はできません。早期に医療機関で画像検査を受け、適切な治療方針を立てることが重要です。
腱板損傷の原因や治療法など、包括的な内容に関しては「【医師監修】腱板損傷とは|症状・原因・治療法を詳しく解説」をご覧ください。
腱板損傷を放置するリスク
| 放置するリスク | 詳細 |
|---|---|
| 断裂が進行し機能が低下する | 断裂部の拡大による肩の可動域と筋力の低下。日常生活の基本動作が困難になる状態 |
| 手術が必要になる可能性 | 断裂の悪化で手術適応となるリスク増大。放置による筋肉の脂肪浸潤や変性による縫合困難 |
| 腱板断裂性肩関節症に進行するリスク | 肩関節のバランス崩壊による軟骨・滑液包障害。人工肩関節置換を検討せざるを得ない段階 |
| 肩以外にも負担が広がる | 周囲の筋肉や関節への過負荷。肩こり、腰痛、姿勢不良など他部位の不調の原因となる状態 |
腱板損傷を放置すると損傷が拡大し、肩の可動域が狭まり日常生活や仕事に支障が出ます。初期は保存療法で改善するケースもありますが、進行すれば手術が必要になる場合が多く、肩を酷使する人ほど悪化は早まります。
長期放置で肩関節が変形し腱板断裂性肩関節症に進行すると治療は複雑化します。また、肩をかばうことで首や背中、反対側の肩などにも負担がかかり、二次的な不調や全身バランスの崩れを招きます。早期診断と適切な治療が不可欠です。
以下の記事では、腱板断裂を放置するリスクを詳しく解説しています。
【関連記事】
腱板断裂を放置するとどうなる?日常生活や仕事への影響を現役医師が解説!
腱板損傷と断裂の違いは?症状の進行や治療法について現役医師が解説
断裂が進行し機能が低下する
| 放置による影響 | 詳細 |
|---|---|
| 腱の裂け目拡大と張力の喪失 | 断裂部分の拡大による腱板の安定性低下。本来の張力喪失による腕の挙上・支え動作の困難 |
| 筋肉の萎縮・脂肪化 | 使われない腱板筋の萎縮と脂肪浸潤。不可逆的変化による筋力回復困難 |
| 肩の連携動作の乱れ | 腱・筋連動の喪失による肩甲骨運動障害。負荷の偏りによる他の腱板や筋肉への損傷拡大 |
| 生活動作の制限 | 腕の動き制限による洗濯・着替え・整髪動作の困難。生活の質低下と介助依存のリスク増大 |
腱板損傷は、日常的な肩の使用により徐々に進行する可能性があります。とくに、断裂部に持続的な負荷が加わると、裂傷が拡大し、部分断裂から完全断裂へ移行することがあります。
断裂範囲が拡大すると、腕の挙上や物の把持といった基本的な動作が困難となり、肩の機能は顕著に低下します。
手術が必要になる可能性
断裂が進行すると修復は難しくなり、手術が複雑化して回復も遅れます。活動的な方や症状が長く続く場合は、断裂部を骨に縫合する手術で機能改善が期待できますが、リスクもあるため必ず医師と相談してください。
放置は将来的に手術が必要になるリスクを高めるため、早期の診断と適切な治療・リハビリの検討が重要です。
以下の記事では、肩腱板断裂の手術と入院期間について詳しく解説しています。
腱板断裂性肩関節症に進行するリスク
| 進行する理由 | 詳細 |
|---|---|
| 腱板断裂による肩の安定感喪失 | 腱板の支え消失による上腕骨の位置異常と関節動作の不安定 |
| 骨同士の衝突と軟骨摩耗 | 上腕骨の上方移動による肩峰との接触と関節軟骨の持続的摩耗 |
| 関節変形と機能低下 | 軟骨消失による関節裂隙の狭小化、骨棘形成、骨変形による摩擦増加 |
| 筋肉バランスの崩れと関節不安定化 | 腱板機能の喪失による筋肉の不均衡と骨・軟骨への負荷増大 |
腱板損傷を長期間放置すると、肩関節の安定性が失われ、腱板断裂性肩関節症へ進行する可能性があります。これは肩関節内の軟骨が摩耗し、関節自体が変形する病態です。
一度変形した関節は元に戻らず、強い痛みが慢性化して日常生活に大きな障害をもたらします。
肩以外にも負担が広がる
腱板損傷で肩の機能が低下すると、首や肩甲骨周囲の筋肉、腰、肘、手首、反対側の肩などに過度な負担がかかり、こりや痛みが広がります。
これは肩の回復ではなく代償動作によるもので、全身のバランスを崩す原因となります。早期診察と適切な治療で負担拡大と症状悪化を防ぐことが重要です。
腱板損傷の治療期間
| 進行度 | 詳細 | 注意点 |
|---|---|---|
| 軽度の腱板損傷(保存療法で3〜6カ月) | 安静、薬、リハビリにより約3カ月で日常動作が可能に。スポーツや重作業復帰は最大6カ月。断裂は修復されず症状コントロールが目的 | 年齢・筋力・仕事内容で回復に差。無理な運動は再断裂リスク。必ず医師・理学療法士の指導下で実施 |
| 中等度の腱板損傷(6〜12カ月) | 2〜3カ月で日常生活復帰。可動域・筋力回復には6〜12カ月。軽作業は約3カ月で可能だが、高負荷作業・スポーツは6カ月が目安 | 3カ月以上改善が乏しい、断裂範囲が広い場合は手術検討。年齢・生活スタイルを踏まえ治療方針を決定 |
| 重度・広範囲断裂(手術必要例|6カ月〜1年以上) | 手術後の回復は6カ月〜1年以上。年齢・断裂の大きさ・筋肉状態で差あり。MRIや超音波で定期評価しながらリハビリ継続 | 回復は長期計画が必要。自己判断で負荷増加しない。医師・リハビリ専門職と連携 |
腱板損傷の回復期間は損傷の程度によって異なります。軽度では、安静や薬、リハビリなどの保存療法で3〜6カ月が目安です。受傷から約3カ月で日常動作がほぼ可能になりますが、断裂が完治するわけではありません。
中等度では、日常生活復帰に2〜3カ月、肩の動きや筋力の回復に6〜12カ月かかります。軽作業は約3カ月で可能な場合もありますが、重い作業や高負荷スポーツは6カ月程度が目安です。3カ月以上治療しても改善がない場合や断裂が大きい場合は手術を検討します。
重度・広範囲では手術が必要で、回復には半年〜1年以上かかります。年齢や筋力、生活環境により差があるため、無理をせず医師や理学療法士の指導のもとで治療とリハビリを行うことが重要です。
腱板損傷の治療法
| 治療法 | 詳細 |
|---|---|
| 薬物療法 | 症状緩和目的の消炎鎮痛剤や湿布、関節内注射による炎症抑制 |
| 温冷療法 | 血流促進と筋肉の緊張緩和を狙う温熱・冷却処置。リハビリ補助療法 |
| リハビリテーション | 肩周囲筋の筋力維持・可動域拡大。残存機能の強化と動作指導 |
| 手術療法 | 断裂部の縫合修復。関節鏡による小切開手術が主流。重症例で適応 |
| 再生医療 | 幹細胞等を用いて損傷組織の再生促進。新規治療法として注目 |
腱板損傷の治療は、患者の年齢や活動レベル、損傷の範囲・重症度を総合的に考慮して決定されます。保存療法では、消炎鎮痛剤や湿布、関節内注射による炎症抑制、温熱や冷却による血流改善と筋緊張緩和、肩周囲筋の筋力維持や可動域拡大を目的としたリハビリテーションを行います。
重度の断裂や保存療法で改善が得られない場合は、関節鏡による小切開での縫合修復術などの手術が適応です。幹細胞を用いた組織再生を促す再生医療も、新たな選択肢として注目されています。
薬物療法
| 有効な理由 | 詳細 |
|---|---|
| 炎症や腫れの抑制 | NSAIDsやステロイド注射による炎症抑制と腫れ軽減。夜間の不快感や動作時の負担軽減 |
| リハビリ継続のための環境づくり | 痛み軽減による可動域訓練や筋力トレーニング開始の容易化 |
| 日常動作のストレス軽減 | 家事や運転などの日常動作時の違和感や不安の軽減 |
| 保存療法の柱としての役割 | 保存療法構成要素の一つとして症状軽快の確率向上。手術回避の補助 |
腱板損傷に対する薬物療法は、炎症や腫れを抑えて痛みを軽減し、治療を円滑に進めるための重要な方法です。NSAIDs(消炎鎮痛薬)やステロイド注射は、痛みや可動制限を緩和し、夜間の不快感や日常生活での負担を減少させます。
ステロイド注射は腱の損傷を悪化させずに症状を改善し、その効果が半年以上続くため、リハビリ継続と肩機能の改善に寄与します。
薬物療法は腱を修復する治療ではありません。しかし、残存する腱や筋肉の機能を活かし、肩の使い方を改善するための支援となります。リハビリや他の治療と組み合わせることで、機能回復を効果的に支えます。
温冷療法
| 状況・時期 | 詳細 |
|---|---|
| 急性期(受傷〜48時間以内) | アイスパックや冷湿布による炎症・腫れの抑制。痛みの緩和と患部保護 |
| 慢性期(炎症が落ち着いた後) | 温湿布や温浴による血行促進。筋肉のこり緩和と関節可動性の向上 |
| 温→冷の交替使用 | 血流改善とこわばり軽減。疲労回復の補助 |
| 日常生活での取り入れやすさ | 自宅でも実施可能な負担軽減法。リハビリ前後の補助にも有用 |
| 注意点 | 1回15分以内・1時間に1回目安。冷やす際は肌を保護。温め過ぎはやけどリスク。循環障害・皮膚脆弱部位は医師指示必須 |
温冷療法は、腱板損傷の症状や回復段階に応じて冷却と温熱を使い分ける方法です。受傷直後や炎症が強い急性期は、冷却により炎症と腫れを抑え、痛みを軽減します。炎症が落ち着いた慢性期には温めることで血流を促し、筋肉のこりを和らげ、肩関節の動きを改善しやすくします。
また、温めた後に冷やす交替浴により循環が促進され、こわばりの軽減にもつながります。自宅でも実践可能で、リハビリ前後の痛みコントロールや準備運動の補助として有効です。ただし、冷やしすぎや温めすぎは逆効果となる場合があり、皮膚の保護や時間管理が重要です。
また、循環障害や皮膚が弱い方は使用前に医師へ相談しましょう。温冷療法は腱断裂を直接治すものではなく、あくまで保存療法の一部として症状緩和と機能改善を支える補助的役割を果たします。
リハビリテーション
| 有効な理由 | 詳細 |
|---|---|
| 周囲の筋肉で肩を支える | 残存する筋肉や肩甲骨周辺の動きを整え、三角筋などで断裂部を補う安定性の向上 |
| 可動域維持と拘縮予防 | 動かせる範囲を保ち、肩のこわばりや凍結肩の発症を防ぐ可動域練習 |
| 筋力回復による日常動作改善 | 手を挙げる・物を持つ動作を支える筋力強化による機能回復 |
| 正しい姿勢と使い方の習得 | 肩甲骨の動かし方や姿勢の修正による再断裂予防と負担軽減 |
| 手術回避や術後回復の促進 | 中等度以下では保存療法で症状改善、術後の機能回復促進 |
腱板損傷は断裂した腱の自然修復は極めて困難ですが、リハビリテーションにより残存する筋群や肩甲骨周囲の機能を整え、肩関節の安定性と可動性を向上させることが可能です。とくに三角筋などの働きが断裂部を補完し、日常生活動作の円滑化に寄与します。
長期間の不動は拘縮や凍結肩を招きやすいため、疼痛のない範囲で関節可動域を維持することが重要です。さらに、段階的な筋力強化により物の把持や挙上動作が改善し、生活復帰が促進されます。理学療法士による姿勢や肩の使用方法の適正化は、再発予防にも効果的です。
軽度〜中等度の損傷では手術回避が可能な場合があり、手術を行う場合でも術後の機能回復を支援します。定期的な評価と継続的介入が良好な治療成績と将来的な肩障害予防につながります。
以下の記事では、痛みを和らげる方法やストレッチの方法をわかりやすく解説しています。
手術療法
| 有効な理由 | 詳細 |
|---|---|
| 腱板断裂を元の位置につなげる唯一の方法 | 関節鏡や直視下手術による断裂部の再固定と修復 |
| 進行防止と肩機能維持 | 偽性麻痺や変形関節症への進行予防 |
| 関節鏡手術による低侵襲治療 | 約1.5cmの小切開から器具を挿入し、出血・感染・身体負担を軽減 |
| 手術は早期ほど有利 | 早期対応で医療費増加や再治療リスクを抑制 |
| 術後リハビリの重要性 | 可動性と筋力を段階的に回復させ結果を向上 |
腱板損傷の手術は、切れた腱を骨へ再固定できる唯一の方法です。自然治癒ではほとんど再接着しないため、進行すれば肩を上げられなくなる偽性麻痺(肩を上げられなくなる状態)や、関節の変形を伴う変形性関節症に至る危険があります。
現在は関節鏡を使った低侵襲手術が主流です。1.5cm程度の小切開から器具を挿入するため出血や感染のリスクが少なく、身体への負担も軽減されます。
腱板損傷は手術開始の遅れが再治療リスクを高める可能性があり、術後は理学療法士の指導による早期リハビリで可動域と筋力を回復させることが、長期的な肩機能の維持と生活の質向上に直結します。
再生医療
再生医療は、自身の身体から採取した幹細胞を培養・増殖させ、損傷部へ注射することで腱板の修復・再生を促す先進的治療法です。従来の薬物療法やリハビリでは改善が難しい場合でも、損傷した腱板の治癒力を高め、根本的な回復を目指せます。
手術のような大きな切開や入院を伴わず、注射で行うため身体への負担が少なく、感染症リスクも極めて低いことが特徴です。さらに、日常生活への制限がほぼなく、リハビリと併用することで機能回復をより効果的に進められる可能性があります。
ただし、実施している医療機関は限られているため、受診前に対応可否を確認することが必要です。痛みの軽減と腱板の再生を同時に実現し、手術を回避できる選択肢として有効性が期待されています。
当院「リペアセルクリニック」では、腱板損傷に対する再生医療の症例を紹介しています。
また、以下の記事では、再生医療について詳しく解説しているのでご覧ください。
【関連記事】
肩の腱板損傷にはテーピングが有効!巻き方やリハビリについて専門医が解説
腱板損傷は自然治癒に頼らず医療機関を受診しよう
腱板損傷は放置すると進行し、手術が必要となる可能性があります。軽度の場合でも、画像診断で損傷範囲を正確に把握し、適切な治療計画を立てることが重要です。早期に受診すれば保存療法による改善が期待でき、生活や仕事への影響を最小限に抑えることが可能です。
腱板損傷でお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。当院は、腱板損傷の治癒に有効である再生医療を選択肢のひとつとしてご提案しています。再生医療は、手術に伴う感染症や薬物による副作用のリスクが低いメリットがあります。
ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。
\無料オンライン診断実施中!/
腱板損傷の自然治癒に関するよくある質問
サプリメントや市販品で腱板損傷は良くなりますか?
腱板損傷は、サプリメントだけで断裂が治る科学的根拠はありません。成分によって痛みの軽減など短期的な効果が期待できる場合はありますが、腱を物理的に修復する証拠はなく、機能改善の裏づけも不十分です。
サプリに頼りすぎることで治療のタイミングを逃し、症状が悪化する恐れがあります。まずは医師による診察と画像検査で損傷の程度を確認し、適切な治療計画を立てることが大切です。
腱板損傷を再発させない方法はありますか?
腱板手術後は、専門家の指導のもとで可動域回復から筋力強化まで、段階的にリハビリを行うことが推奨されます。
日常生活では、重い荷物の運搬や腕を大きく振る動作を避け、肩甲骨周囲の筋力と柔軟性を維持します。姿勢の改善、過負荷の回避、適切な栄養管理も再断裂予防に重要です。
参考文献
(文献1)
腱板断裂の自然経過|J-STAGE