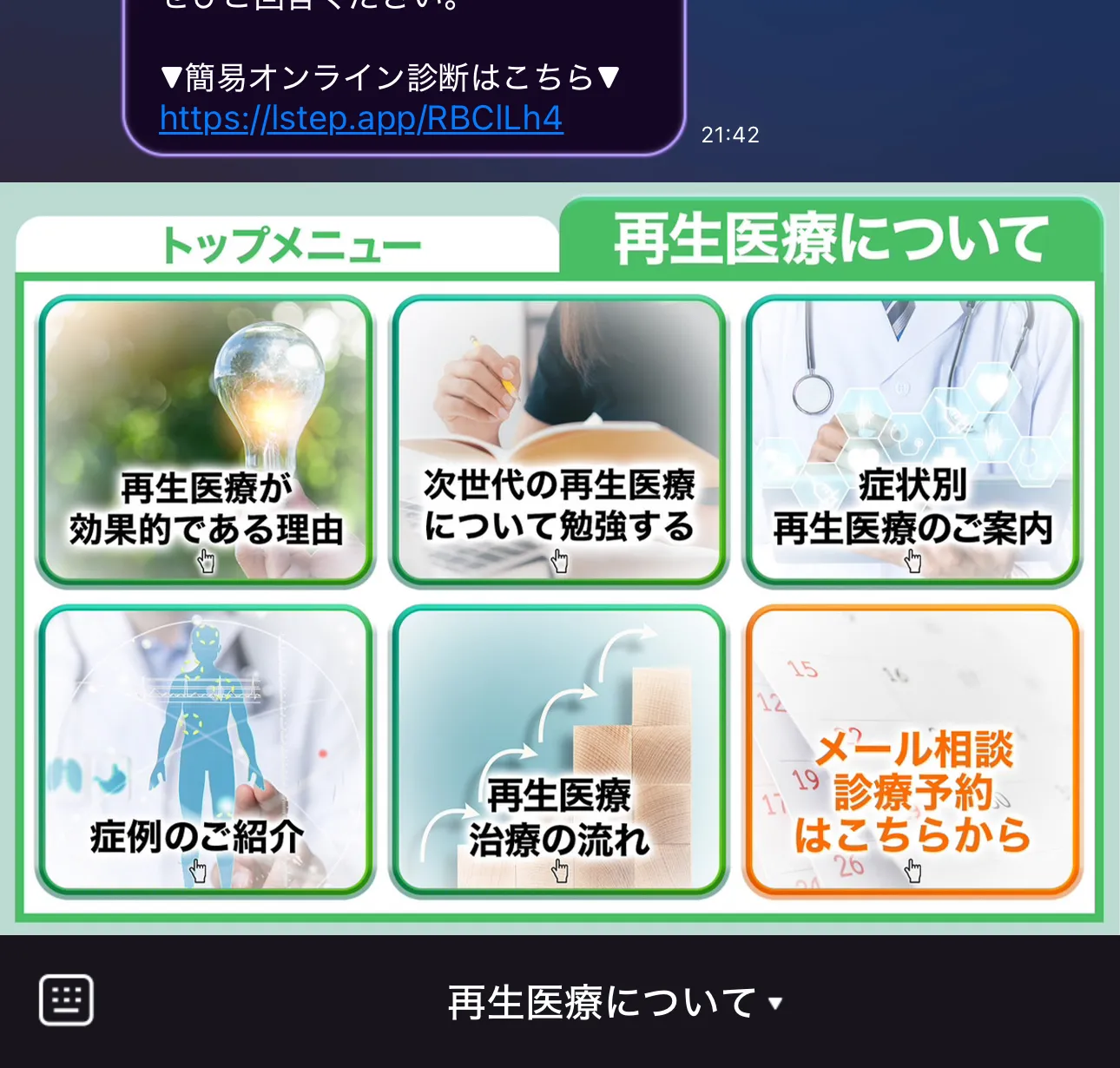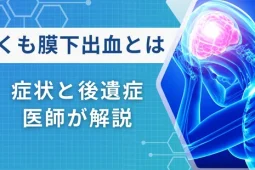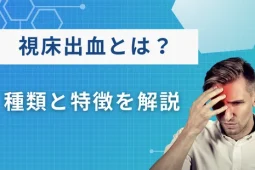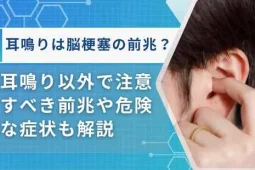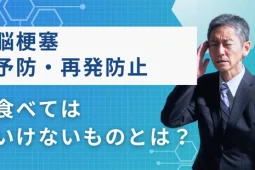- 脳卒中
- 頭部
二木の予後予測とは?脳卒中の回復期リハビリや注意点を医師が解説
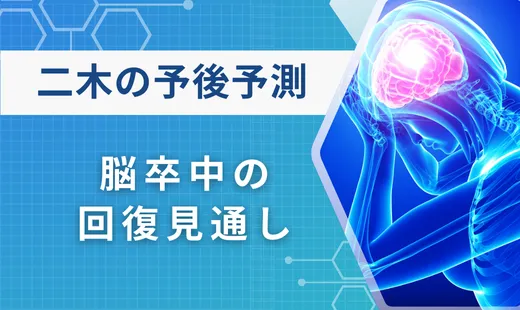
二木の予後予測って何?
脳卒中のリハビリの見通しはどうやって立てる?
脳卒中を発症した家族を支えるのは、大きな不安と向き合う日々の連続です。「どのくらい回復するのか」「いつ自立できるのか」など、先が見えない状況に戸惑う方も多いでしょう。
そのようなときに役立つのが「二木の早期自立度予測基準」です。
本記事では、入院時・発症2週・1カ月時点での予後予測の具体的な活用方法を解説します。
予後を知ることで、リハビリ計画が立てやすくなりますので、ぜひ最後までご覧ください。
また、当院「リペアセルクリニック」では手術や入院を必要としない「再生医療」を提供しています。
脳卒中の後遺症治療にも効果が期待できますので、「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にご相談ください。
目次
二木の予後予測(早期自立度予測基準)とは?
脳卒中後の回復を予測する「二木の早期自立度予測基準」は、医療経済学者の二木立医師が研究・提唱したリハビリ計画を立てる際に重要な指標です。
入院時・発症2週・1カ月時点で回復の見込みを段階的に予測し、患者の自立度を評価します。
|
予測時期 |
評価項目 |
目的 |
|---|---|---|
|
入院時 |
運動機能、意識レベル、嚥下機能 |
初期の回復見込みを判断する |
|
発症2週時 |
運動機能、日常動作、コミュニケーション |
リハビリの強度や内容を調整する |
|
発症1カ月時 |
歩行能力、手足の動き、日常生活動作 |
退院後の生活計画を立てる |
本章では、それぞれの時期における予測のポイントを解説します。内容を参考に、リハビリを進めるうえでの指針を明確にしましょう。
入院時の予測
入院時の予測では、発症から入院後できるだけ早い段階で、患者さんの状態を評価して行う予測です。
具体的には年齢、麻痺の程度、そして日常生活動作(ADL)の3つの要素から総合的に判断します。
|
入院時のADL能力 |
歩行能力予測 |
|---|---|
|
ベッド上の生活自立(※1) |
歩行自立(大部分が屋外歩行可能で、かつ1カ月以内に屋内歩行自立) |
|
基礎的ADL(※2)のうち2項目目以上実行 |
歩行自立(大部分が屋外歩行かつ、2カ月以内に歩行自立) |
|
運動障害軽度(※3) |
|
|
発症前の自立度が屋内歩行以下かつ運動障害重度(※4)かつ60歳以上 |
自立歩行不能(大部分が全介助) |
|
Ⅱ桁以上の意識障害かつ運動障害重度(※4)かつ70歳以上 |
※1:介助なしでベッド上での起坐・座位保持が可能
※2:基礎的ADL=食事、尿意の訴え、寝返り
※3:Brunnstorm stage4以上(麻痺側下肢伸展挙上可能)
※4:Brunnstorm stage3以下(麻痺側下肢伸展挙上不能)
発症2週時での予測
脳卒中の発症から2週間が経過すると、ある程度の回復が見られるようになり、この時点で再度、患者さんの状態を評価し予後予測を行います。
具体的には麻痺の程度、日常生活動作などを総合的に判断します。
|
発症2週時でのADL |
歩行能力予測 |
|---|---|
|
ベッド上生活自立(※1) |
歩行自立(かつその大部分が屋外歩行、かつ大部分が2カ月以内に歩行自立) |
|
基礎的ADL(※2)3項とも介助かつ、60歳以上 |
自立歩行不能(かつ、大部分が全介助) |
|
Ⅱ桁以上の遷延性意識障害、重度の認知症、夜間せん妄を伴った中程度の認知症があり、かつ60歳以上 |
※1:介助なしでベッド上での起坐・座位保持が可能
※2:基礎的ADL=食事、尿意の訴え、寝返り
発症1カ月時の予測
発症から1カ月が経過すると、多くの患者さんで症状が安定してきますので、この時点で、より詳細な評価を行い最終的な予後予測を行います。
具体的には麻痺の程度、日常生活動作、認知機能などを総合的に判断材料とします。
|
発症1カ月でのADL |
歩行能力予測 |
|---|---|
|
ベッド上生活自立(※1) |
歩行自立(かつ、その大部分が屋外歩行、3カ月以内に歩行自立) |
|
基礎的ADL(※2)の実行が1項目以下かつ、60歳以上 |
自立歩行不能(かつ、大部分が全介助) |
|
Ⅱ桁以上の遷延性意識障害、重度の認知症、両側障害、高度心疾患などがあり、かつ60歳以上 |
※1:介助なしでベッド上での起坐・座位保持が可能
※2:基礎的ADL=食事、尿意の訴え、寝返り
以下の記事では、脳卒中後のリハビリ方法について詳しく解説していますので、興味がある方はぜひご覧ください。
【脳卒中】予後予測に基づくリハビリが重要な理由
脳卒中の発症後、予後予測に基づくリハビリが重要な理由は以下の2つです。
- リハビリ計画を立てる上で目標設定に役立つ
- 患者や家族が将来の見通しを知り安心できる
本章を参考に、二木の予後予測への理解を深めましょう。
リハビリ計画を立てる上で目標設定に役立つ
リハビリには、明確な目標設定が欠かせません。
予後予測の活用によって回復見込みを把握し、段階的なリハビリ計画を立てられます。
無理のない範囲で適切な目標設定をしておくと、リハビリへのモチベーションも維持しやすくなります。
たとえば、発症2週時点での評価をもとに、どの程度歩行訓練を進めるべきかの判断も可能です。
また、発症1カ月時の予測によって、退院後の生活を見据えた計画も立てやすくなります。
患者や家族が将来の見通しを知り安心できる
予後の見通しがわかることで、患者や家族の不安が軽減されるメリットもあります。
脳卒中の回復には個人差がありますが、二木の予後予測を活用すれば、ある程度の見通しを立てられるためです。
たとえば、1カ月時点の予測をもとに、退院後に自宅でどの程度自立した生活が送れるかを判断できます。
そのため、必要な介護サービスの手配や、住環境の調整もスムーズに進めやすくなります。
予後を知ることで、家族も適切なサポートができるようになり、患者の自立を支える大きな力となるでしょう。
脳卒中の種類と原因については以下の記事で解説しています。予防するための注意点もチェックできますので、ぜひ参考にしてください。
脳卒中の予後は損傷部位や大きさによって変わる
脳卒中の回復度合いは、損傷した部位や病変の大きさによって大きく異なります。
同じ規模の脳卒中でも、損傷部位によって運動機能の回復が難しい場合や、逆に予後が良好なケースもあります。
本章では以下3つの損傷部位・損傷の大きさに分けて、予後への影響を解説します。
- 損傷が小さくても予後が不良な部位
- 損傷の大きさに比例して運動予後が決まる部位
- 損傷が大きくても運動予後が比較的良好な部位
本章の内容を、自分やご家族の予後をイメージするのにお役立てください。
損傷が小さくても予後が不良な部位
損傷が小さくても予後が不良な部位には以下が挙げられます。
- 放線冠(中大脳動脈穿通枝領域)の梗塞
- 内包後脚
- 脳幹(中脳・橋・延髄前方病巣)
- 視床(後外側の病巣で深部関節位置覚脱失のもの)
上記のような部位で脳梗塞が起こると、わずかな損傷でも機能低下を引き起こしやすいのが特徴です。
とくに内包や脳幹といった重要な神経経路を含む部位では、小さな病変でも運動機能に深刻な影響を与えます。(文献1)(文献2)
手足の動きや歩行能力が低下する可能性があるため、わずかな損傷でも機能回復が難しくなりやすいのです。
リハビリでは損傷部位に応じた適切なアプローチが求められます。
麻痺が強く残る可能性がある場合でも、適切なリハビリの継続によって、日常生活での自立度を向上させる可能性もあります。
損傷の大きさに比例して運動予後が決まる部位
病巣の大きさと比例して、運動予後がおおよそ決まるものは以下のとおりです。
- 被殻出血
- 視床出血
- 前頭葉皮質下出血
- 中大脳動脈前方枝を含む梗塞
- 前大脳動脈領域の梗塞
脳の大部分では、損傷の大きさが予後に直結します。損傷が大きいほど回復には長期間のリハビリが必要になる傾向があります。
適切な訓練を継続すれば、少しずつでも機能の回復を促すことが可能です。
無理をせず、損傷状態に合わせたプログラムを取り入れていけば、少しずつ日常動作の改善が期待できるでしょう。
損傷が大きくても運動予後が比較的良好な部位
大きい病巣でも運動予後が良好なものは、次のとおりです。
- 前頭葉前方の梗塞・皮質下出血
- 中大脳動脈後方の梗塞
- 後大脳動脈領域の梗塞
- 頭頂葉後方~後頭葉、側頭葉の皮質下出血
- 小脳半球に発生した片側性の梗塞・出血
たとえば、大脳皮質の非優位半球に損傷がある場合、もう一方の半球が機能を代償しやすいため、運動機能の回復が比較的良好な傾向にあります。
このような代償機能を「脳の可塑性(かそせい)」といいます。可塑性によって損傷が大きくても回復が進むケースがあるのです。
ただし、脳の可塑性を活用して回復を促すには、早期からの適切なリハビリが重要です。適切なトレーニングの継続で、日常生活に必要な動作を取り戻せる可能性があります。(文献3)
脳卒中の症状や治療法については、以下の記事でわかりやすくまとめていますので、ぜひご確認ください。
二木の予後予測の注意点は?
二木の予後予測は、脳卒中リハビリにおける有益な指標ですが、以下の点には注意が必要です。
- あくまで予測であることを理解する
- 過信しすぎない
本章では、予後予測に関するそれぞれのポイントをわかりやすく解説します。
あくまで予測であることを理解する
二木の予後予測は、過去のデータに基づいて統計的に算出されたものです。
しかし実際の予後は個人差があり、予測よりも回復が早かったり、遅かったりするケースもあります。状態や置かれている環境によって、回復の度合いは大きく異なる可能性があるでしょう。
そのため、予後予測はあくまでも参考程度にとどめ、過度な期待や不安を抱かないように注意してください。
過信しすぎない
二木の予後予測の内容を過信しすぎないことも大切です。
予後が良いと予測されていても、積極的なリハビリテーションを行わなければ十分な回復を得られない可能性があります。
一方、予後が悪いと予測された場合でも、諦めずにリハビリを続けていれば状態が改善するケースもあります。
予後予測の結果を過信しすぎず、医師や専門家の指示のもと、適切なリハビリテーションを行いましょう。
まとめ|脳卒中のリハビリには二木の予後予測を取り入れよう
脳卒中の回復には、適切なリハビリ計画が欠かせません。
二木の予後予測の活用により、回復の見通しを立てやすくなり、より効果的なリハビリが可能になります。
入院時・発症2週・1カ月の評価を基に、適切なプランを立てることが重要です。
二木の予後予測を取り入れ、無理のないリハビリを続けて脳卒中後の自立を目指しましょう。
また、当院「リペアセルクリニック」では脳卒中の後遺症にお悩みの方へ、手術や入院の必要がない「再生医療」を提供しています。
まずはお気軽に「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてご相談ください。

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
\無料オンライン診断実施中!/
二木の予後予測に関するよくある質問
脳卒中の回復期はどれくらいの期間ですか?
脳卒中の回復期は、一般的に発症後1カ月〜6カ月程度と言われています。(文献4)
この時期は、集中的なリハビリテーションによって、機能回復が期待できる大切な時期です。
しかし、回復の度合いは個人差が大きく、損傷部位や程度、年齢、合併症の有無などによって大きく異なります。
リハビリにおける予後予測とは何ですか?
リハビリにおける予後予測とは、患者さんの状態や検査結果などを基に、リハビリテーションによってどれくらい回復が見込まれるのかを予測する指標です。
予後予測は、リハビリテーションの目標設定や計画立案、患者本人や家族への説明にも役立ちます。
ただし、予後予測はあくまでも予測であり、実際の回復状況とは異なる場合がある点も理解しておく必要があります。
参考文献
(文献1)
生理学研究所「脳卒中後のリハビリによる運動機能の回復には、脳幹を介した複数の回路が協力して関わる」
https://www.nips.ac.jp/release/2019/09/post_399.html
(文献2)
Chen CL, et al. (2000). Brain lesion size and location: effects on motor recovery and functional outcome in stroke patients. Arch Phys Med Rehabil, 81(4), pp.447-452.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10768534/(最終アクセス:2025年2月28日)
(文献3)
角田 亘「脳卒中リハビリテーションの今後|臨床神経学(60巻,3号)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/60/3/60_cn-001399/_article/-char/ja/#article-overiew-abstract-wrap