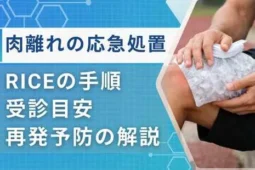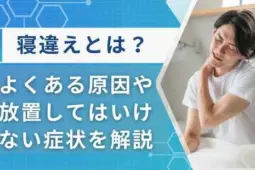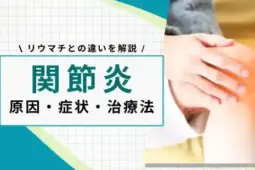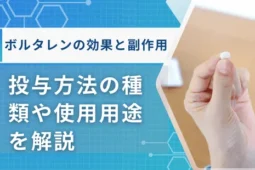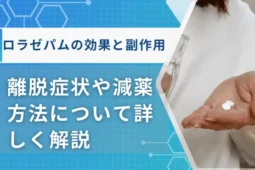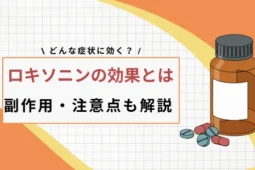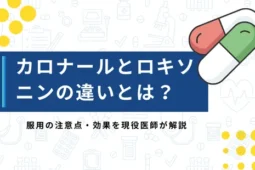- その他、整形外科疾患
太ももの肉離れを早く治すには?症状の特徴や原因などを解説【医師監修】

「太ももに激痛が走り、歩くのもつらい」「太ももに違和感がある」というお悩みを抱えていませんか。
これらの症状は、太ももの筋肉に負荷がかかり、肉離れを引き起こしている可能性があり、適切な応急処置と治療が必要です。
本記事では、太ももの肉離れを早く治すための治療法や対処法について詳しく解説します。
- 太ももの肉離れで見られる症状
- 太ももが肉離れを起こす原因
- 肉離れの重症度と病院に行くべき目安
- 太ももの肉離れを早く治す方法
肉離れは症状を正しく理解し、適切な治療を受ければ、改善を目指せる外傷です。ぜひ、本記事を肉離れの症状軽減にお役立てください。
また、「肉離れを少しでも早く治したい」という方は、ぜひ再生医療による治療をご検討ください。
\肉離れの早期改善を目指す「再生医療」とは/
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を向上させることで、損傷した組織の再生・修復を促す治療法です。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 肉離れによる痛みを早く治したい
- 再発リスクをできるだけ抑えたい
- 痛み止めや湿布が効かない、あるいはすぐに痛みがぶり返す
>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する
当院リペアセルクリニックでは、肉離れに対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。
目次
太ももの肉離れの症状
太ももにいつもと違う違和感があれば、肉離れの可能性があります。肉離れは、早期発見で症状悪化を防げるため、肉離れかどうかの迅速な判断が求められます。
肉離れの代表的な症状は、以下のとおりです。
それぞれ、詳しく解説しますので、早期発見に役立ててください。
激しい違和感に襲われる
肉離れは、筋肉が切れたり裂けたりして、炎症や内出血が起こる外傷です。
また、断裂の多くは部分的に起こりますが、まれに筋肉が完全に断裂してしまうケースもあります。
とくに、太ももからブチッと音が聞こえ、違和感で立ち上がれない場合は、肉離れの可能性が高いです。
激しい違和感に襲われ、立てない状態の場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
患部の腫れ・内出血
肉離れは、患部の腫れや内出血を引き起こします。
筋肉が急激な力で引き伸ばされたり、断裂したりすると、その部分の毛細血管が損傷するため、内出血が起こります。
腫れの程度は、損傷の大きさや出血量によりますが、重度の場合だと広範囲にわたって腫れ上がり、内出血の症状も顕著です。
ブチッという異音を耳にし、上記の症状が現れた際は、安静・冷却をして炎症の進行を防ぎましょう。
なお、炎症や腫れに対し応急処置を行ったら、すぐに医療機関を受診しましょう。
筋肉が痙攣する
太ももの肉離れが発症すると、筋肉の痙攣が起こることがあります。筋肉が痙攣する主な理由やメカニズムは、以下のとおりです。
| 原因 | メカニズム |
|---|---|
| 損傷部位の保護反応 | 損傷した筋肉を保護するため、周囲の筋肉が反射的に収縮する |
| 神経系の影響 | 筋肉の損傷が周囲の神経を刺激し、異常な信号が送られる |
| 電解質バランスの乱れ | 激しい運動や発汗により、筋肉の興奮性が高まる |
(文献1)
筋肉の痙攣が頻繁に起こる場合は、運動を中止し、医療機関を受診しましょう。
患部が熱をもつ
肉離れによって炎症が起こると、患部の血流が増加し、局所的に熱感を伴うことがあります。
また、損傷した筋繊維や血管から出血が生じ、血液が組織内に滞留することで、腫れや熱感がみられる場合もあります。
症状が強い場合には、自力での歩行が難しくなることがあるため、医療機関の受診が必要です。
太ももの肉離れの原因
太ももの肉離れの主な原因は、運動によって引き起こされるものです。しかし、肉離れを受傷する際のシチュエーションは多岐にわたります。
ここでは、太ももの肉離れが起こりやすくなる主な原因として、以下の5つを解説します。
肉離れの主な原因を把握し、予防に役立ててください。
急激な動作による筋肉への過度な負荷
急な走り込みや、急ブレーキは太ももの肉離れを誘発します。
筋肉疲労や十分な準備運動ができていない状態で、急激な動作を繰り返すと、筋肉が急な衝撃に適応できません。結果的に、太ももの筋肉が衝撃に耐えられず、肉離れを受傷します。
太ももの肉離れに直接つながる動作は、以下を参考にしてください。
| 原因となる動作 | 筋肉への負荷 | 具体例 |
|---|---|---|
| 急なダッシュやストップ | 筋肉が急激に伸び縮みし、耐えきれずに損傷する | ・スポーツでの全力疾走 ・急ブレーキ |
| ジャンプや踏み込み動作 | 筋肉が強く縮んだり、急激に引き伸ばされたりする | ・バスケットボールのジャンプ ・サッカーの着地 |
| 方向転換(急な切り返し) | 片足に強い力がかかり、筋肉が急激に引き伸ばされる | ・テニスの方向転換 ・サッカーのドリブル |
スポーツを行う以上、ある程度の負荷は避けられません。十分な準備運動やウォーミングアップを行い、筋肉への負担を軽減しましょう。
筋肉の疲労
筋肉に疲労が蓄積した状態では、柔軟性が低下し、筋肉組織の損傷を起こしやすくなります。
エネルギー不足や疲労物質の蓄積、血流の低下が筋肉の活動を低下させ、肉離れを引き起こします。
具体的なメカニズムは、以下のとおりです。
| 疲労の種類 | 筋肉の状態 | 肉離れのリスク |
|---|---|---|
| エネルギー不足 | 筋肉を動かすエネルギーが足りない | 力が入らず、無理に動かすと筋肉が損傷しやすい |
| 疲労物質の蓄積 | 筋肉に疲労物質がたまり、動きが鈍くなる | 筋肉が硬くなり、急な動作に対応できない |
| 血流の低下 | 筋肉への酸素や栄養が不足する | 筋肉の修復力が低下し、柔軟性も失われる |
(文献2)
筋肉疲労を起こさないためには、適度な休息や運動前後のストレッチ・マッサージ、水分補給・栄養摂取を怠らないことが大切です。(文献2)
ウォーミングアップ不足
ウォーミングアップが不十分な状態での運動は、「筋肉の収縮」や「脳と筋肉の連携」が乱れてしまい、肉離れを引き起こすリスクが高まります。
| ウォーミングアップが不足した状態 | 体に起こる変化 | 肉離れのリスク |
|---|---|---|
| 筋肉が硬く、伸びにくい | 急な動きに対応できない | 筋肉が損傷しやすい |
| 筋肉への酸素や栄養が不足する | 血流が不十分になる | 筋肉が硬くなり、傷つきやすい |
| 脳と筋肉の連携が乱れる | 動作がスムーズに行えない | 必要以上に筋肉へ負荷がかかり、損傷しやすい |
(文献2)
ウォーミングアップは筋肉を温め、血流を促進する効果があります。運動前に軽いジョギングや屈伸運動を行い、身体を温めて筋肉の柔軟性を高めると、肉離れを起こすリスクを減らせます。
筋肉の柔軟性不足
筋肉の柔軟性が不足すると、急な動きや衝撃に太ももが耐えきれず、肉離れを引き起こします。(文献3)
また、筋肉の柔軟性不足は主に、準備運動不足や加齢、筋肉疲労の蓄積によって引き起こされます。
柔軟性不足を解消するために、日頃からストレッチや適度な運動を行い、運動後はマッサージや温浴で筋肉をケアする習慣を取り入れましょう。
筋力低下
筋力低下は、太もも周囲を支える力が失われている状態であり、柔軟性も低い状態です。
筋力が低下すると、運動時の負荷や、不意に足がもつれてしまった際に、肉離れを引き起こす可能性があります。
日頃から適度な筋力トレーニングを実施し、筋力低下を防ぎながら肉離れの予防をしましょう。
肉離れの重症度|病院に行くべき目安
肉離れは、MRI検査などの画像診断に基づいて、損傷の程度により3段階に分類されます。(文献1)
重症度によって治療期間や復帰までの期間が大きく異なるため、正確な診断を受けることが重要です。
| 重症度 | 損傷の状態 | 具体例 |
|---|---|---|
| Ⅰ型(軽症) | ・筋繊維の微細な損傷 ・腱や筋膜には損傷なし ・筋肉内に出血あり |
階段の昇り降りで違和感がある程度 |
| Ⅱ型(中等症) | ・筋繊維の損傷 ・筋膜や腱(筋腱移行部)の一部損傷 ・完全断裂や付着部裂離はなし ・皮下出血を伴うことが多い |
・普段の歩行が困難になり、足を引きずった状態になる |
| Ⅲ型(重症) | ・筋腱の完全断裂 ・または付着部からの裂離 ・広範囲の内出血 |
・安静時でも強い痛みがある ・歩行などの日常動作が困難 |
(文献1)
なお、病院へ行くかどうかの目安は、以下の項目を目安にしてください。
- 患部に強い痛みがあり、歩行や日常動作に支障がある
- 患部が腫れている、または内出血で青黒く変色している
- 受傷時に「ブチッ」という断裂音を感じた
- 数日経っても痛みや違和感が改善しない
- 過去に肉離れを経験しており、同じ部位に痛みがある
また、軽症といわれるⅠ型でも、自己判断で放置すると回復が遅れる可能性があります。念のため、医療機関と受診してください。
太ももの肉離れを早く治すには?正しい応急処置と治療法
太ももの肉離れを早く治すためには、受傷直後の適切な応急処置と、その後の段階的な治療・リハビリテーションが重要です。
具体的には、以下の対処法が有効とされています。
それぞれ、詳しく解説します。
RICE処置|発症直後の対処法
肉離れの受傷直後は、「RICE処置」と呼ばれる応急処置を行います。(文献4)
RICE処置は、骨折や捻挫、打撲、肉離れなどの外傷を受けたときの基本的な応急処置方法です。早期に適切な処置を行うことで、内出血や腫れ、痛みを抑え、回復を助ける働きがあります。
RICE処置の具体的な方法は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 | 理由 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| Rest(安静) | 太ももを動かさないようにし、安静に保つ | 損傷した筋肉の回復を促し、悪化を防ぐ | 横になって足を高く上げる、松葉杖を使う |
| Icing(冷却) | 患部を氷や冷却パックで15~20分冷やし、数時間おきに繰り返す | 炎症と腫れを抑え、症状を軽減する | 冷凍した保冷剤や氷嚢をタオルで包み、患部に当てる |
| Compression(圧迫) | 弾性包帯などで患部を圧迫し、腫れを防ぐ | 内出血と腫れを抑制する | 太もも全体を覆うように弾性包帯を巻く(締めすぎに注意) |
| Elevation(挙上) | 患部を心臓より高い位置に保ち、腫れを軽減する | 重力により腫れや内出血を抑制する | クッションや椅子を使って太ももを高く上げる |
なお、RICE処置はあくまで応急処置のため、対応後は早急に医療機関を受診しましょう。
以下の記事では、肉離れの応急処置について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
リハビリテーション
応急処置の後は、医師の指導のもと、重症度に応じたリハビリテーションプログラムを段階的に進めていきます。
リハビリテーションの主な目的や内容は以下のとおりです。
| 目的 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 筋肉の修復促進 | ストレッチ、軽い運動 | 回復期(受傷後1週間~数週間) |
| 筋力低下の防止・回復 | 段階的な筋力トレーニング | 回復期、スポーツ復帰期 |
| 再発予防 | 正しい体の使い方、運動方法の習得 | スポーツ復帰期 |
なお、リハビリは無理せず、違和感があれば医師に相談しましょう。
再生医療(PRP療法)
PRP療法は、自身の血液から抽出したPRP(多血小板血漿)を用いる治療法です。
PRPに含まれる成長因子などの成分には、組織の修復を促す働きがあり、肉離れの治療選択肢の一つとなります。
PRP療法はご自身の血液を使用するため、アレルギー反応や感染症のリスクが比較的低く、血液採取から治療まで当日中に行えるのもメリットです。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 肉離れによる痛みを早く治したい
- 再発リスクをできるだけ抑えたい
- 痛み止めや湿布が効かない、あるいはすぐに痛みがぶり返す
>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する
当院リペアセルクリニックでは、肉離れに対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。

スポーツ外傷は⼿術しなくても治療できる時代です。
太ももの肉離れに効果的な日常のケア
肉離れの回復を促し、再発を予防するためには、日常的なケアが重要です。医師の判断を仰ぎながら、以下のケアを試してみてください。
それぞれ詳しく解説します。
太もも前側・裏側のストレッチ
太もも前側(大腿四頭筋)の筋肉は、ジャンプ動作や急激なキック動作で肉離れしやすい部位です。
太もも前側には、以下のストレッチが有効です。
- 横向きに寝そべり、下側の膝を曲げて前方に置く
- 上側の足首を持ち、かかとをお尻に近づける
- そのまま足を後方へ引き、太ももの前側の筋肉を約10秒間伸ばす
- 反対側の足も同様に行う
太もも裏側(ハムストリング)の筋肉は、急なダッシュやストップ動作が多い競技で肉離れが発生しやすい部位です。
太もも裏側には、以下のストレッチが有効です。
- 仰向けに寝る
- 片側の膝関節と股関節を曲げる
- 太ももの裏を両手で支え、胸に引き寄せる
- 股関節の角度を保ったまま、膝関節をゆっくり伸ばす
- 太ももの裏が伸びていると感じる位置で、約6〜8秒間保つ
- 反対側の足も同様に行う
肉離れに効果的なストレッチ方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
太ももへのテーピング
テーピングやサポーターは、回復期の日常生活やスポーツ復帰期において、患部の保護と再発予防に役立ちます。
具体的なテーピング方法は、以下の順序を参考にしてください。
- 椅子に座り、太ももが安定する姿勢を取る
- 膝の少し上から付け根に向かって、太ももを一周するようにテープを巻いていく(このとき、テープは半分重ねながら巻いていく)
- 太ももの付け根付近まで巻いたらテープを切り、端を押さえて固定する
なお、テーピングは症状の改善を保証するものではありません。痛みが続くようであれば、医療機関を受診しましょう。
太ももの肉離れを疑う際は医療機関を受診しよう
太ももの肉離れは、急な運動や筋肉への過度な負荷によって起こりやすく、痛みや腫れ、内出血など、さまざまな症状を伴う外傷です。
軽度の場合でも、自己判断で放置すると回復が遅れたり、再発につながったりする可能性があります。
受傷直後には安静や冷却などの応急処置を実施し、早急に医療機関を受診しましょう。
なお、近年は肉離れの治療において、早期改善を目指せる「再生医療」のPRP治療が注目されています。
肉離れでお悩みの方は、治療の選択肢としてご検討ください。
\肉離れの早期改善を目指す「再生医療」とは/
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を向上させることで、損傷した組織の再生・修復を促す治療法です。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 肉離れによる痛みを早く治したい
- 再発リスクをできるだけ抑えたい
- 痛み止めや湿布が効かない、あるいはすぐに痛みがぶり返す
>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する
当院リペアセルクリニックでは、肉離れに対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。
太ももの肉離れに関するよくある質問(FAQ)
太ももの肉離れは温めるのと冷やすのどちらが正解?
受傷直後の急性期(受傷後48〜72時間程度)は、アイシング(冷却)が正解です。患部を冷やすと炎症や内出血を抑えられ、腫れの拡大を防ぎます。
一方、数日経って炎症が引いた慢性期には、温熱療法が有効です。温めることで血流が促進され、損傷した組織の修復が促されます。
急性期に温めると炎症が悪化するため、時期を間違えないよう注意してください。
歩けるけど痛い場合は病院に行くべき?
少しでも違和感があれば、医療機関への受診をおすすめします。
「歩ける=軽傷」とは限りません。歩行が可能でも、実際には筋腱移行部に損傷が及んでいる場合があります。
太ももの痛みが続く場合は、肉離れかどうかを正しく判断するためにも、早めに医療機関への受診を検討しましょう。
湿布だけで肉離れは治る?
湿布だけで肉離れを根本的に治すことは難しいです。湿布は消炎鎮痛を目的としており、痛みや炎症を一時的に和らげる働きはありますが、断裂した筋繊維をつなげる働きはありません。
肉離れの治療には、適切な安静や圧迫固定、段階的なリハビリテーションなどが必要です。
湿布はあくまで補助的な手段として捉え、専門医の診断と指導のもとで治療を進めましょう。
参考文献
(文献1)
肉離れの診断と治療|第26回 日本臨床スポーツ医学会 学術集会
(文献2)
運動後の筋疲労回復処置がストレスマーカーに及ぼす影響|理学療法―臨床・研究・教育
(文献3)
5.肉離れ|スポーツ損傷シリーズ