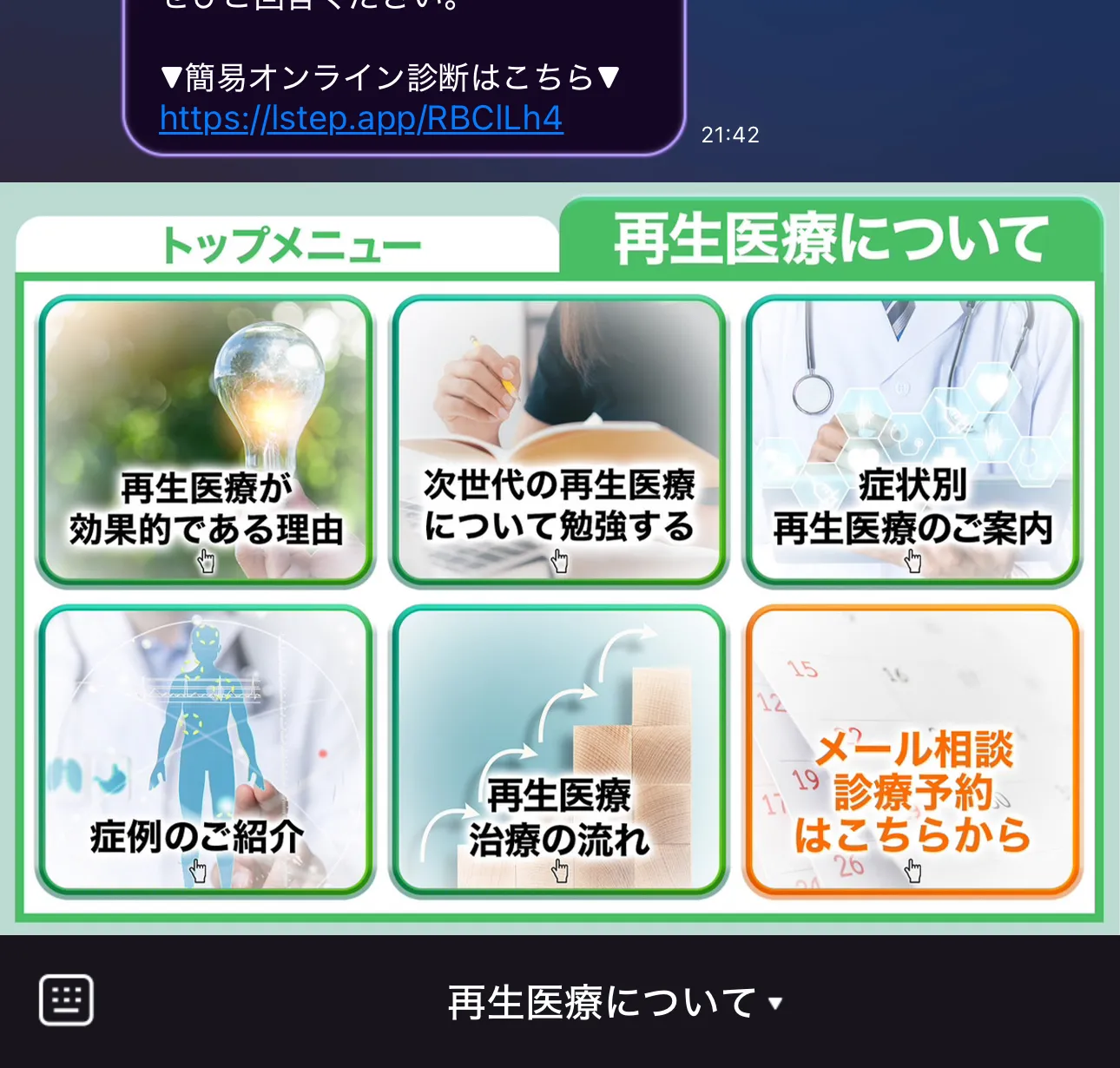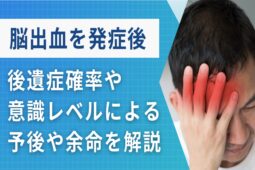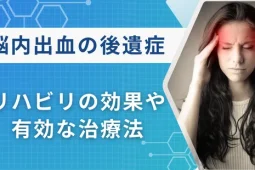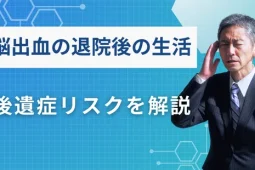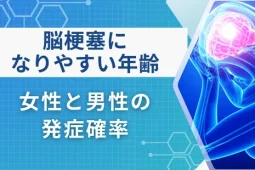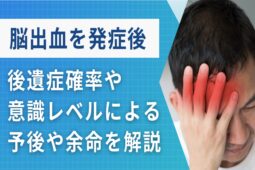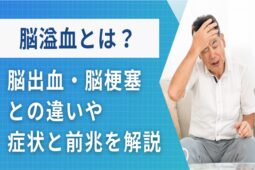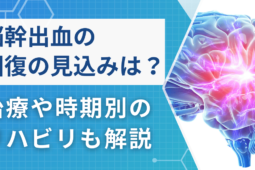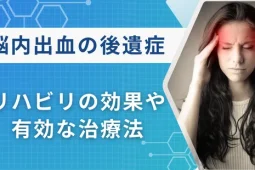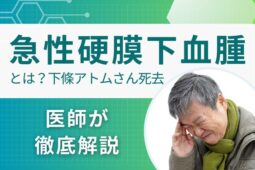- 脳卒中
- 脳出血
- 頭部
脳出血後の看護ケアとは?家族ができること・退院後気をつけることを医師が解説!
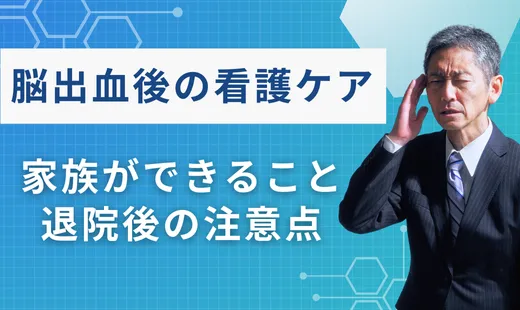
「脳出血後のケアは何をすれば良いの?」「脳出血後の看護や介護はどうすればいい?」と疑問に感じていませんか。
退院後の生活やリハビリに向けたサポートは、何を優先すべきか悩む場面も多いでしょう。
脳出血の患者本人は、長期間の治療やリハビリによって精神的・社会的負担が大きくなりがちです。そのためご家族による適切なサポートが重要といえます。
この記事では、脳出血後の患者を支えるための基本的な看護・介護方法と、退院後に家族が実践できる具体的な対策を解説します。
脳出血の看護ケアで不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
また、当院「リペアセルクリニック」では脳出血の後遺症に効果が期待できる再生医療も行っております。
気になる症状がある方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にご相談ください。
目次
脳出血後における7つの看護ケア
脳出血後のケアは、患者の回復に直結するため、日常の観察や丁寧なサポートが欠かせません。
本章では、具体的な看護ケア方法を7つの観察項目と合わせて紹介します。
1.意識レベルの確認
2. 呼吸管理
3. 血圧と心拍数のチェック
4. 電解質バランスの変化(輸液管理)
5. 口腔ケア・体勢の管理
6. 嘔吐時の対処・吐物管理
7. 発作や薬の管理
入院中は、どの観察ポイントを重視するかを確認しておきましょう。
1. 意識レベルの確認
意識レベルの確認は、観察項目の中でも状態を把握する上で非常に重要です。
具体的には、呼びかけへの反応、目の開き具合、手足の動きなどを観察します。
Glasgow Coma Scale (GCS) やJCSといった評価方法もあり、異常があれば速やかに医師への報告が必要です。
意識レベルの低下は、病状の悪化を示すサインの可能性があるため、看護する上でも注意が必要です。
また、こちらの記事では脳出血を発症後の意識レベルによる予後や余命を詳しく解説しています。
後遺症について気になる方は、ぜひご覧ください。
2. 呼吸管理
脳出血後、脳の損傷により呼吸をコントロールする機能が低下する場合があります。
そのため、適切な呼吸管理は命を守るために不可欠です。
呼吸の回数や深さ、呼吸音などを注意深く観察し、呼吸状態の変化や異変があれば酸素投与や人工呼吸器の使用が行われます。
3. 血圧と心拍数のチェック
血圧と心拍数の変動は、脳出血後の状態に大きな影響を与えるため、こまめなチェックが重要です。
血圧の急激な上昇や低下は、再出血や他の合併症を引き起こす可能性があるためです。
具体的には、定期的な測定を行い、変動があれば医師に報告します。
また、薬による血圧コントロールも行われます。
4. 電解質バランスの変化(輸液管理)
体内の電解質バランスは、生命維持に欠かせない重要な役割を担っています。
脳出血後は、電解質バランスが崩れやすいため、輸液管理による適切な調整が必要です。
たとえば、点滴で水分や電解質を補給し、血液検査でその値をモニタリングします。
これにより、体内の状態を安定させていきます。
5. 口腔ケア・体勢の管理
口腔ケアと体勢管理は、感染症や床ずれの予防に欠かせません。
免疫力が低下すると、口腔内の細菌が感染を引き起こす可能性があります。
また、同じ体勢が続くと床ずれのリスクが高まるため注意が必要です。
歯磨きやうがい、体位変換を定期的に行い、必要に応じて専用のケア用品の活用によって、患者の健康と快適さを管理できます。
6. 嘔吐時の対処・吐物管理
脳出血後には嘔吐が起こるケースがあり、適切な対処と吐物の管理も重要です。
とくに、嘔吐物が気道に詰まる(誤嚥)リスクを防ぐのは重要だといえるでしょう。
嘔吐時には顔を横に向け、吸引器で吐物を除去するなどの対応を行います。
また、吐物の量や性状を観察し、記録するのも大切です。
これらの対応により、誤嚥性肺炎などの合併症を予防できます。
7. 発作や薬の管理
脳出血後は発作が発生する可能性もあるため、薬の時間や量を守るように管理するのも重要です。
また、発作の兆候が見られた場合はすぐに医師へ報告します。
指示に従い、薬の正しい管理が症状の安定を促します。
また、脳出血の原因については以下の記事でも解説しているので、参考にしてください。
【退院後】脳出血の看護で家族ができることは?
脳出血による退院後の生活は、ご家族によるサポートが重要です。ご家族のサポートが患者の回復を支え、日常生活の質も維持できるようになります。
脳出血の看護において家族が行えることは、以下の6つが挙げられます。
- 日常生活の介助や見守り
- 要介護認定を早めに申請する
- 地域の介護サービスを活用する
- 住宅改修で自宅の環境整備を行う
- 施設介護サービスも検討する
- 介護疲れをしないように休息を取る
本章では、家族が取り組むべき具体的なケアやサポート方法を紹介するので参考にしてください。
日常生活の介助や見守り
退院後、患者の日常生活には継続的な介助と見守りが必要です。
食事や入浴、排泄などのサポートを行い、無理なく生活できる環境を整えます。
また、転倒などのリスクを防ぐため、常に患者の動きに注意を払いましょう。
適切な介助は、患者の安心感と回復の大きな助けとなります。
また、脳出血の後遺症やリハビリについては以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
要介護認定を早めに申請する
要介護認定を受けることで、家族の金銭的な負担が軽減できます。
しかし、認定が遅れると必要なサービスが受けられなくなる可能性があります。
そのため、入院中の段階から市区町村の窓口に相談し手続きを進めておきましょう。
地域の介護サービスを活用する
地域にはさまざまな介護サービスがあるので、積極的に活用するのがおすすめです。
訪問看護やデイサービスの利用によって、専門的なケアを受けながら患者本人の日常を支えられます。
退院後には地元の介護支援センターなどに相談し、利用可能なサービスを確認しましょう。
住宅改修で自宅の環境整備を行う
退院後の生活を安心して送るためには、住宅改修が必要になる場合があります。
手すりの設置や段差解消など、患者が安全に動ける環境作りを検討すると良いでしょう。
公的補助金を利用できる場合もあるため、必要に応じて専門家に相談するのがおすすめです。
施設介護サービスも検討する
在宅介護が難しい場合、施設介護サービスの検討も選択肢の1つです。
ショートステイや特別養護老人ホームなど、患者の状態や家族の状況に応じた施設を選びましょう。
専門スタッフのケアが受けられるため、安心感があります。
介護疲れをしないように休息を取る
家族の介護負担が大きくなると、心身に疲れがたまりやすくなります。
そのため、適度に休息を取り、家族内での役割分担を決めたり、地域の支援を活用したりするのがおすすめです。
家族の健康が患者本人の回復にもつながりますので、無理をせずサポート体制を整えてください。
脳出血の看護・介護時における4つの注意点
脳出血後の看護・介護は、患者の回復を支える上で非常に重要です。
ここでは、介護時に注意すべき4つのポイントを解説します。
- 転倒を予防するための工夫
- 食事はゆっくりと食べやすい形状で提供
- 排泄をサポートする際はプライバシーを配慮
- 精神的なケアを継続的に行う
介護する家族の負担軽減にもつながりますので、チェックしておきましょう。
転倒を予防するための工夫
脳出血後には、筋力低下やバランス感覚の喪失で転倒リスクが高まります。
そのため、家具の配置を工夫し、滑り止めマットや手すりを設置するのも良いでしょう。
また、歩行補助具の使用も効果的です。
転倒防止は患者の安全を守るだけでなく、さらなる合併症の予防にもつながります。
食事はゆっくりと食べやすい形状で提供
食事は、ゆっくりと食べやすい形状で提供するのが重要です。
これは、嚥下機能(飲み込む力)が低下している場合、誤嚥のリスクが高まるためです。
具体的には、とろみをつける、刻み食やペースト食などに調理し、一口ずつゆっくりと食べさせてあげましょう。
さらに、食事中の姿勢や飲み込みの様子を注意深く観察し、誤嚥を防ぐ工夫も必要です。
排泄をサポートする際はプライバシーを配慮
排泄はデリケートな問題ですので、サポートする際はプライバシーへの配慮が重要です。
たとえば、専用のカーテンや扉を使用し、必要以上に介助者が近づきすぎないよう心がけましょう。
また、定期的な排泄スケジュールを組んでおくと、患者の負担を軽減しつつ快適なケアを提供できます。
精神的なケアを継続的に行う
脳出血後、患者は不安や孤独感を抱きやすくなります。
そのため、定期的な会話や声かけを行い、安心感を与えてあげると良いでしょう。
また、リハビリや介護の進捗を共有し、前向きな気持ちを引き出すことも重要です。
精神的なケアは患者の回復を支える大きな力になります。
まとめ|脳出血の看護に家族ができることは理解しておこう!
この記事では、入院中の看護ケアや退院後に家族が行えるサポート、注意点について詳しく解説しました。
脳出血後の看護ケアは、患者の回復に大きな影響を与えます。
また、入院中の医療従事者によるケアに加え、退院後の家族のサポートも欠かせません。
本記事で紹介した情報を活用し、医療や介護サービスと連携しながら療養生活を支えましょう。
また、当院「リペアセルクリニック」では脳出血や脳梗塞の後遺症治療も行っております。「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
脳出血の看護に関するよくある質問
脳出血の看護で留意すべき点は何ですか?
脳出血の看護では、日々の体調管理とリスク回避が欠かせません。
意識レベルの確認や呼吸・血圧のチェックを行い、異常があれば速やかに医師へ相談します。
また、転倒や誤嚥などのリスクを防ぐため、環境整備や適切な食事提供も重要です。
患者の安全を第一に考える看護が求められます。
脳出血の急変時の対応はどうすれば良いですか?
急変時には、まず落ち着いて状況を確認し、必要に応じて医師や救急車を呼びます。
意識が低下した場合は、気道確保を優先し患者を安静に保つのが大切です。
症状や変化を正確に医療スタッフに伝えることで、迅速な対応が可能になります。
当院「リペアセルクリニック」では脳出血の治療も行っております。気になる症状がある方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にてお気軽にご相談ください。