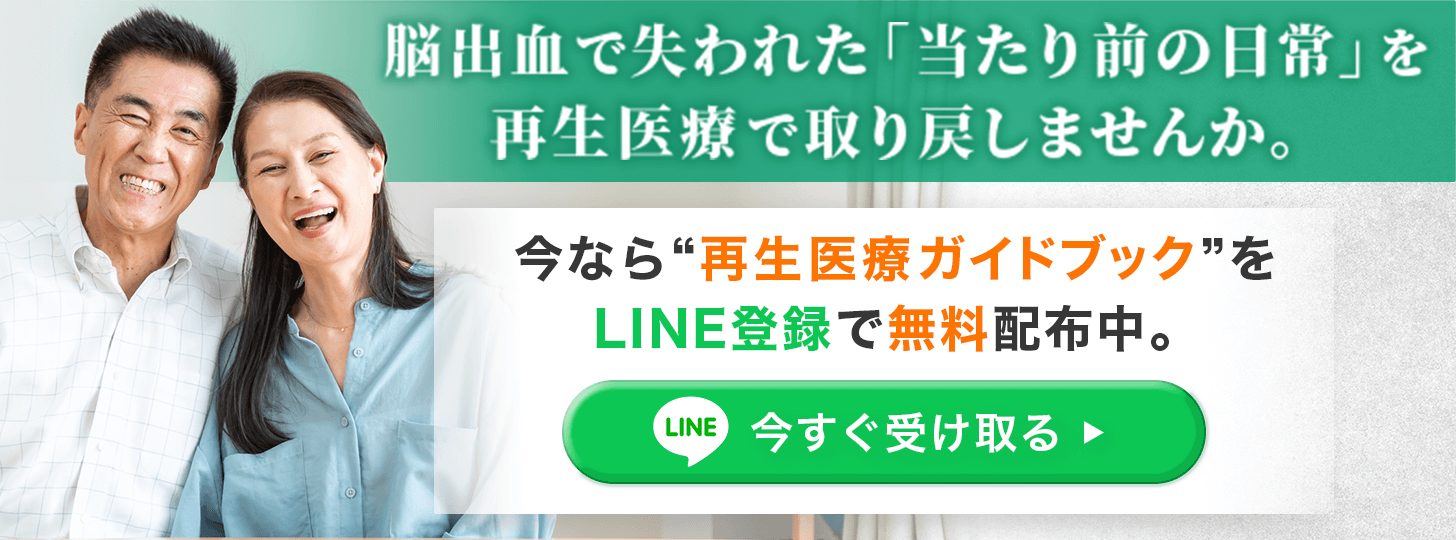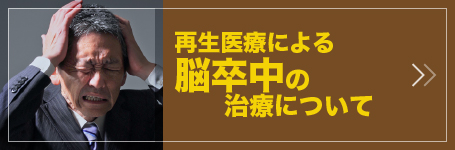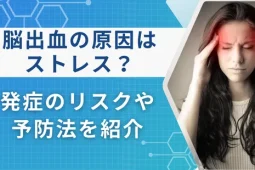- 脳卒中
- 頭部
- 脳出血
脳出血の退院後の生活は?後遺症リスクや寝てばかりにならない方法を医師が解説
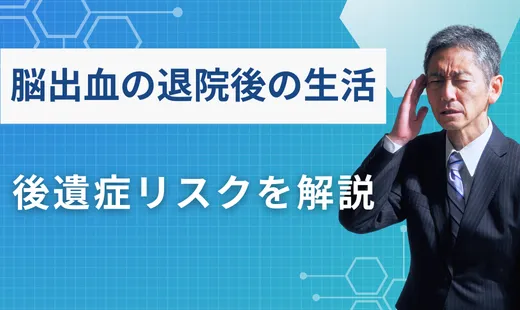
脳卒中の退院後の生活への影響は、症状の程度によって大きく異なります。重度の後遺症が出ると、退院後も寝たきりになってしまう可能性もあります。
寝たきりになるリスクを避け、元の生活に戻るためには、適切なリハビリと生活習慣の改善が欠かせません。
本記事では、脳出血の退院後の生活について詳しく解説します。効果的なリハビリや退院後の生活で気をつけるべきことも紹介しているので、自宅に戻った後の過ごし方を考えたい方はぜひ参考にしてみてください。
目次
脳出血の退院後の生活【後遺症が出て寝たきりになる可能性も!?】
脳出血の後遺症が重症であると、そのまま回復せず寝たきりになってしまう可能性もあります。
後遺症の影響を最小限に抑え、日常生活の質を向上させるためには、入院中だけでなく退院後も継続的なリハビリを続けていく必要があります。
以下の記事では、脳出血で後遺症なしになる確率について解説しているので、後遺症の有無が気になる方はあわせてご覧ください。
そもそも脳出血とは、脳の中の血管が破れて頭の中で出血が起こる病気です。たまった血液が神経細胞を圧迫することで、さまざまな症状を引き起こします。
たとえば、手足が動かない麻痺症状や言葉の出にくさなどの後遺症です。
脳出血の有効な治療法の1つに「再生医療」があります。
これまで一度死んだ脳細胞は戻らないとされてきました。しかし、再生医療は脳細胞を復活させ、脳出血を含む脳卒中の後遺症を改善できることがわかってきたのです。
詳しい治療法や効果が知りたい方は、再生医療専門の『リペアセルクリニック』にお気軽にお問い合わせください。
\無料オンライン診断実施中!/
脳出血の退院後の生活に欠かせないリハビリとは
脳出血による筋肉低下や後遺症の訓練に欠かせないのがリハビリです。
脳出血後の回復する過程は以下3段階にわかれており、各段階に応じたリハビリをおこなっていきます。
- 急性期
- 回復期
- 維持期
リハビリの内容を順番に見ていきましょう。
急性期|入院中のリハビリ
急性期は、脳出血の発症直後から2週間程度までの期間を指します。急性期は全身の状態がまだ不安定な時期のため、容体が悪化しないよう慎重な経過観察が必要です。
同時にこの時期は、長時間の安静により筋肉や関節の機能が低下する「廃用症候群」を防ぐ必要があります。廃用症候群は床ずれ(褥瘡)や感染症のリスクを高めます。
廃用症候群を予防するためのリハビリには、手足の軽い運動や体位の交換が有効です。
障害を受けた神経細胞は発症後3カ月がもっとも回復が期待できる時期といわれています。早期からリハビリをはじめれば、脳機能の回復や運動機能の改善につながるでしょう。
回復期|退院後の生活を意識したリハビリ
回復期とは、急性期の期間が過ぎたあとの約6カ月間を指します。回復期では、患者の症状に合わせたリハビリがはじまります。
主な目的は、可能な限り発症前の生活に戻れるよう、必要な動作や体の機能を強化することです。
リハビリの内容は患者一人ひとりの生活環境や目標に応じて設定されます。退院後の生活をイメージしながら、個別の訓練プログラムを組んでいきます。
以降では回復期におこなわれる「運動機能のリハビリ」「言語機能・嚥下機能のリハビリ」「高次脳機能障害に対するリハビリ」について詳しく解説します。
運動機能のリハビリ
回復期におこなわれる運動機能の強化を図るリハビリを6つ紹介します。
|
リハビリ |
内容 |
|
筋力強化 |
安静にしていた期間に低下した筋力を回復する目的のリハビリです。自分の体重や軽い重りを利用したトレーニングをおこないます。 |
|
持久力強化 |
体力の向上を目的としたリハビリです。ウォーキングや自転車型の運動器具を使ってトレーニングをおこないます。 |
|
協調運動訓練 |
体の各部位の力加減を調整し、安定した動きができるように訓練するリハビリです。 |
|
基本動作訓練 |
日常生活に戻るために必要な動作の訓練をおこないます。具体的にはベッドからの起き上がりや車椅子の乗り移りなどの動作です。 |
|
歩行訓練 |
歩行機能の向上を図ります。杖や歩行器を活用しながら安定した歩行をおこなうための練習をします。 |
|
巧緻(こうち)動作訓練 |
手指のこまかい動きの回復を目指すリハビリです。具体的には箸を使ったり、ペンで文字を書いたりするなどの動きです。 |
移動に関する練習は理学療法士が、食事や身の回りの動作は作業療法士が担当します。
なお、脳出血の治療には「再生医療」が効果的です。
再生医療は人間の自然治癒力を活用した最先端の医療技術です。幹細胞の修復力を利用して、損傷した脳細胞の機能回復を促進します。
脳出血の後遺症も治療対象なので、具体的な治療法や効果が知りたい方は再生医療専門の『リペアセルクリニック』にお気軽にお問い合わせください。
言語機能・嚥下機能のリハビリ
言葉がうまく出てこない失語の症状が見られる場合には、話す練習や読み書きを通じてスムーズに言葉を扱えるように訓練をします。
食べ物を安全に胃まで運ぶ働きの「嚥下(えんげ)機能」が低下している場合は、口・喉・舌の筋肉を鍛える運動をおこないます。嚥下の機能低下は、食事が気管に入り込み、肺炎を引き起こす危険があるため、早い段階でのリハビリが必要です。
高次脳機能障害に対するリハビリ
「高次脳機能」は記憶力、注意力、感情のコントロールを担う働きを指します。脳の損傷でこれらの機能が低下した状態を「高次脳機能障害」と呼びます。
高次脳機能障害に対するリハビリでは、以下のように目的に応じた訓練をおこないます。
| ・記憶力向上:言葉や絵を使った記憶訓練、メモの活用練習 ・注意力回復:計算問題など集中力を高める訓練 |
リハビリを続けないと、体や心の機能がさらに低下する恐れがあります。根気よく取り組むことが回復の鍵です。
また、高次脳機能障害のリハビリには、周囲の協力も大切です。たとえば、わかりやすい言葉で話しかけたり、生活環境を整えたりするなどのサポートが求められます。
維持期|退院後のリハビリ
維持期とは急性期と回復期を終えて、症状がある程度安定した時期を指します。維持期のリハビリは、主に自宅や施設でおこなわれます。
維持期のリハビリの目的は、急性期や回復期で回復した機能の維持です。リハビリを中断すると機能が再び低下する可能性があるため、継続が大切です。
また、後遺症が出ると、以前は簡単にできた動作が難しくなり、生活の満足度が下がる場合があります。維持期のリハビリは、生活を少しでも楽にするための訓練も進めていきます。
なお、脳出血を含む脳卒中の治療には「再生医療」が有効です。身体のしびれや麻痺、言語障害といった後遺症も治療対象に含まれます。
期待できる治療効果が知りたい方は、再生医療専門の『リペアセルクリニック』にお気軽にご相談ください。
脳出血の退院後の生活で気をつけるべき4つの注意点
脳出血の退院後は、再発を防ぐために日常生活で気をつけるべき点があります。とくに以下4つの生活習慣が、再発リスクを高める要因となります。
- ストレスをためる
- 塩分の高い食生活を送る
- タバコを吸う
- 過度な飲酒をおこなう
注意点をおさえて、健康的な生活を心がけましょう。
ストレスをためる
脳出血の要因となるのは高血圧です。ストレスがたまると血圧が上がりやすくなるため、同じ状況下で生活を続けていると、脳出血の再発リスクを高めます。
以下はストレス発散に効果的な方法です。
| ・趣味の時間を作る ・規則正しい生活リズムを保つ ・無理のない範囲で軽い運動をする ・深呼吸やストレッチで気分転換をおこなう |
血圧を安定させ脳出血の再発リスクを軽減させるためにも、自分に合ったストレス解消法を見つけ、ストレスケアをおこなっていきましょう。
以下の記事では脳出血とストレスの関係性を解説しています。ストレスによって生じる脳出血のリスクについて詳しく知りたい方は、ぜひあわせてご覧ください。
塩分の高い食生活を送る
塩分の高い食生活は血圧が上がりやすくなり、脳出血の再発につながる可能性があります。以下のような塩分を減らした食事を心がけましょう。
| ・料理の味付けを薄くする ・塩分控えめの商品を購入する ・外食では低塩メニューを選ぶ |
塩分の高い食生活で血圧が上がると血管に負担がかかります。脳卒中のリスクを軽減するためにも、日々の食生活の見直しをしていきましょう。
タバコを吸う
喫煙は血管を収縮させ、血圧上昇を招きます。禁煙は脳出血の再発予防にもつながるため、以下のような手段でタバコを吸う機会を減らしてみてください。
- 禁煙外来の利用
- ニコチンガムの活用
- ニコチンパッチの使用
- 禁煙イベントの参加
タバコを吸うと再発リスクが高まるだけでなく、肺がんや心疾患といった別の病気を引き起こす原因になります。健康的な生活を送るためにも、タバコを断つ努力を続けましょう。
過度な飲酒をおこなう
過度な飲酒も血圧を上げ、脳出血を再発させるリスクがあります。
適量を超える飲酒は体にも大きな負担がかかるため、飲酒量を制限し適量を守りましょう。日常的にアルコールを飲む習慣がある場合、週に数日は休肝日を設けるのがおすすめです。
以下の記事では、脳出血の予防や再発防止に効果的な血圧管理方法を解説しています。高血圧の心配がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ|脳出血の退院後の生活は寝てばかりにならないようにリハビリを続けよう
脳出血後のリハビリは、早めに開始して根気強く続ける意識が大切です。動かない時間が増えると、筋力が落ちたり、体の機能が戻りにくくなったりするからです。
家族や周囲の人々のサポートも回復の大きな力となります。生活環境を整え、患者の状態に合わせた適切な援助が必要です。
毎日少しずつ努力を重ねれば、発症前の生活に近づける可能性が高まります。自分のペースで無理なくリハビリを続けていきましょう。
なお、脳出血の治療には「再生医療」が有効です。
再生医療は人間の自然治癒力を活用した最新の医療技術で、身体機能(後遺症)の回復や脳卒中における再発予防の効果が期待できます。
具体的な治療方法が気になる方は、再生医療専門の『リペアセルクリニック』にお気軽にお問い合わせください。
\無料オンライン診断実施中!/