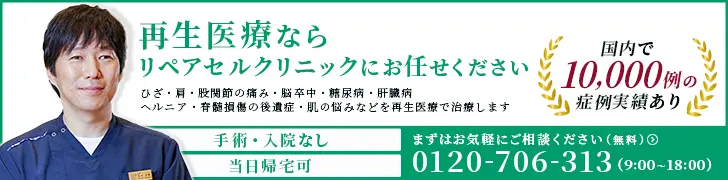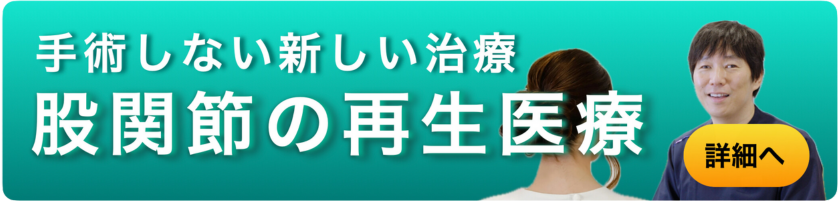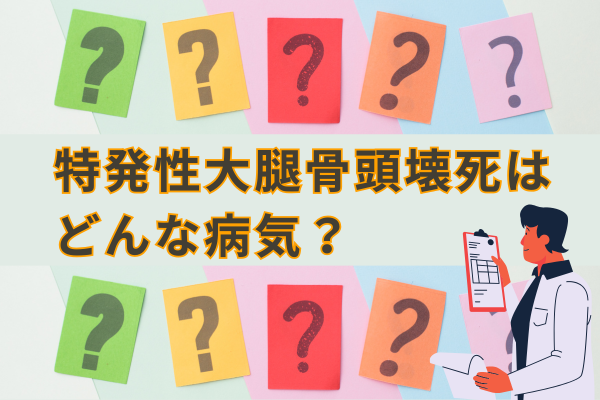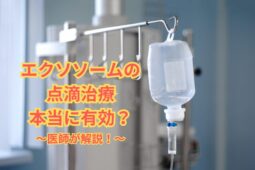- 変形性股関節症
- 再生治療
- 股関節
変形性股関節症の原因から治療まで医師が解説
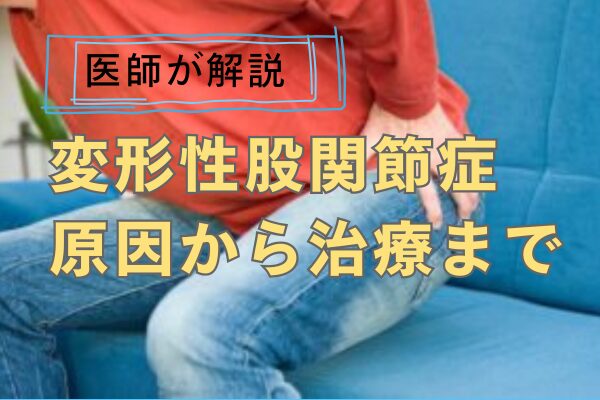
あなたは、散歩して歩いている時や寝ている時に、股関節に違和感や痛みが出たことがありますか?そんな時は、股関節の代表的な疾患である変形性股関節症を少し疑ってみましょう。この記事を読んでいただければ、変形性股関節症のポイントがよくわかるように説明しております。是非、最後までご覧ください。
70代以上の高齢者の多くが、程度の差こそあれ発症すると言われている変形性股関節症。主に加齢によって軟骨が傷つき少なくなっていくのが原因ですが、肥満や運動不足のほかに遺伝もリスクを高める要因となります。1kgの体重増加で股関節には3~6kgもの負担がかかるというデータもあります。
初期症状は動作開始時の痛みや可動域の制限ですが、放置すると安静時にも痛みが生じてしまいます。診断にはレントゲンやMRIなどの画像診断が必要で、状態に応じて運動療法、内服薬、そしていよいよ痛みが強くなれば手術療法となります。
この記事では、変形性股関節症を知るところから、治療法に至るまでをわかりやすく、私の体験も含め解説いたします。股関節が痛い方、また今後、変形性膝関節症になるかもしれないと不安な方、ぜひ読み進めてこの症状への理解を深めていただけたら幸いです。あなたが少しでも健康な生活を送れるように、今すぐ知識を深めましょう。
目次
変形性股関節症の原因とリスク要因
股関節の痛み、気になりますよね。もしかしたら変形性股関節症かも…と不安になっていませんか?
ここでは、変形性股関節症の原因およびqリスク要因について、整形外科医の立場からわかりやすく解説していきます。原因を知ることで、予防や治療への意識も高まりますので、ぜひ最後までお付き合いください。
加齢と変形性股関節症の関係
年齢を重ねると、どうしても体のあちこちにガタがきてしまいます。これは、長年使い続けた機械が徐々に劣化していくのと似ています。加齢も大きな原因で、徐々に関節の軟骨もすり減っていきます。
若い頃は、股関節の骨の表面を覆う軟骨がクッションの役割を果たし、骨同士がスムーズに動くようサポートしてくれています。。この軟骨は、潤いと弾力性が保たれており、衝撃を吸収してくれるため、私たちは痛みを感じることなく、歩行やジョギングができるのです。。しかし、年齢とともにこの軟骨がすり減ってしまい、骨と骨が直接ぶつかり合うことで、炎症や痛みが生じます。
高齢化社会の現代において、変形性股関節症はとても身近な病気と言えるでしょう。40歳代ぐらいから発症し、70代以上になると股関節の軟骨は傷ついて少なくなる可能性が高くなります。軟骨のすり減りの原因は、加齢以外にも肥満や遺伝、怪我の経歴などが関係しており、これらの要因が重なることでより早く軟骨がすり減ってしまう可能性があります。
体重コントロールが必要

体を支える上で、股関節はとても大切です。体重が増えるほど負担が増し、軟骨がすり減りやすくなってしまいます。結果として、変形性股関節症へと進行してしまいます。適正体重を維持することは、股関節の健康を保つ上でとても大切です。具体的には、BMI(Body Mass Index)を25以下に保つことが推奨されています。BMIは、体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)で計算できます。
股関節の無料相談受付中!
リペアセルクリニックは「股関節」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。
運動不足がもたらすリスク

逆に、運動不足だと筋肉が衰え、関節に負担がかかることで軟骨が傷つきやすくなります。さらに運動不足は体重増加となりさらに負担がかかるという悪循環に陥ります。
ウォーキングや水泳など、股関節に負担の少ない運動を継続的に行うのが理想です。プール内でのウォーキングは、浮力により関節への負担が軽くなり、変形性股関節症の方にもおすすめです。1回30分程度、週に3回以上を目安に行うと良いでしょう。
遺伝的要因と家族歴の影響
変形性股関節症は、遺伝的な要因も関係していることが知られています。両親や兄弟姉妹など、家族に変形性股関節症の方がいる場合、自身も発症するリスクが高まる可能性があります。これは、軟骨の質や骨盤の形などが遺伝的に受け継がれるためと考えられています。
遺伝的な要素は変えられませんが、生活習慣を改善することで、発症リスクを下げたり、病状が進むのを予防することができます。変形性股関節症は、加齢や肥満などにも強いつながりがあり、日々の生活の中で予防に取り組むことが重要です。
▼変形性膝関節症の原因や予防のヒントについて、併せてお読みください。
変形性股関節症の症状と診断方法
股関節の痛みは、日常生活に大きな支障をきたす悩ましい症状です。中高年の方には変形性膝関節症に続いてよくみられます。できるだけ早期に発見し治療にかかれば、ある程度の病状の進行は抑えられます。
ここでは、変形性股関節症の症状および診断方法について、整形外科医の立場からわかりやすく解説します。ご自身に少しでもあてはまることがあれば、ぜひ参考にしてみてください。
よくみられる症状:痛みと関節の動きの制限
変形性股関節症の主な症状は、関節の痛みと動きの制限です。初期には、立ち上がったり、歩き始めたりしたときなど、関節に負荷がかかり始める時に痛みを感じることが多いですが、安静にしていると痛みは治まります。この時点では、まだ軟骨の損傷は軽微であるため、少し休むことで痛みは治ることが多いです。
しかし、病状が進み関節軟骨がすり減ると、骨同士が接触する面積が増えてきます。すると、炎症が慢性化し、安静時にも痛みを感じるようになります。さらに進行すると歩くことも困難となります。また、関節の動く範囲が狭くなり、足を自由に動かせなくなることもあります。正座やあぐらが難しくなったり、靴下を履く動作で痛みを感じたりする方もいます。
変形性股関節症の症状は、痛みと可動域制限以外にも、下記のような症状もよく言われます。
- こわばり: 朝起きた時や長時間同じ姿勢でいた後に、股関節の動きにぎこちない感じや、痛みが生じることがあります。これは、関節液の循環が悪くなっていることが原因と考えられます。
- 引っかかり感: 関節がスムーズに動かない感じや、カクンと引っかかるような感覚が生じることがあります。
- 音: 関節を動かしたときに、クリック音やゴリゴリ音など認めることがあります。これは、骨同士が擦れ合っている音です。
これらの症状は、すべての人に現れるわけではなく、症状の強さも人それぞれです。高齢化と肥満人口の増加に伴い、変形性関節症の有病率は増加しているという報告があります。もし心当たりのある症状があれば、早めに医療機関を受診することが大切です。
痛みの特徴とその場所

初めの頃は、立ち上がる時や、歩き始めに痛みが出て、しばらくすると軽くなることが多いです。これは、動き始めに関節に負荷がかかるためです。また、運動後や長時間の歩行後に痛みが増すこともあります。痛みの出方は人それぞれで、鈍い痛み、刺すような鋭い痛み、うずくような痛みなど、個人によって様々な症状が出ます。私の今までの経験では、股関節の痛みと同時に、太ももの前から膝にかけて痛みを訴える方が多くおられました。
また、痛みの特徴は、関節の変形の程度によって変わることが多いですが、末期になってもあまり痛みが感じなかったり、初期でもかなり痛みが強い方も多く見られました。初期の頃は動く時だけ痛みが出ますが、中期や末期になると安静や夜間で痛みが現れます。
画像検査
一般的によく使用されるレントゲン検査、さらに詳しく調べるためのMRI検査、CT検査などがあります。
レントゲン検査では、軟骨がどのくらい減ったのかを見る目安となる関節の隙間などを知ることができます。変形性股関節症では、関節の間が狭くなったり、骨の棘と書いて骨曲(こつきょく)が出てきます。ただ、この骨曲があることで痛みが強くなるということはありません。
MRI検査では、軟骨や靭帯、筋肉の状態や位置関係などを詳しく調べることができます。レントゲンではわからない、軟骨や靭帯の状態もわかります。レントゲンだけではなく、MRIを撮影してみると、大腿骨頭壊死が見つかったということはよく臨床の場では経験しました。
CT検査は、骨の状態をより詳細に調べるのに役立ちます。特に、手術を検討する場合に、骨の形、位置関係、そして周りの神経の確認もできるので必要となります。近年では、3D-CTを用いることで、立体的な病変の把握が可能となりました。
変形性股関節症の診断は、症状や身体の所見、レントゲンやMRIなどの画像診断を含め総合して総合的に判断して行います。
▼MRIの費用相場や撮り方について、併せてお読みください。
治療方法
変形性股関節症の症状を改善するためには、日常生活での工夫が大切です。
- 運動療法: ウォーキングや水中でのウォーキングなど、股関節に負担をかけすぎない運動が有効です。水中ウォーキングは浮力によって股関節への負担が軽減されるため、比較的に筋力の弱い高齢者の方におすすめです。理学療法士による自宅でできる筋力トレーニングやストレッチの指導を受けることで、さらに症状の軽減を目指しましょう。
- 体重管理: 肥満は股関節に大きな負担がかかります。適切な体重を維持することが重要です。栄養バランスの良い食事を心がけ、適度な運動を継続しましょう。BMIを25以下に保つことが推奨されています。
- 装具の使用: 杖、歩行器、装具などを使用して股関節の負担を減らします。
- 薬物療法: 痛み止めやヒアルロン酸注射などを行います。痛み止めは、痛みを止める作用はありますが、根本的な治療にはなりません。ヒアルロン酸注射は、関節液の粘性を高め、関節の動きをスムーズにする効果があります。
- 手術療法: 保存療法でも痛みがおさまらなければ、人工股関節置換術などの手術が検討されます。金属製人工関節で関節ごと入れ替えます。
できるだけ早期に見つかれば、軟骨のすり減りを少しでも食い止めることができるのです。股関節のいつもと違う違和感や痛みなどが現れたら、早い目にレントゲンなどの検査をしましょう。
新しい選択肢としての再生医療
従来の医療では、保存療法で痛みがおさまらなければ、手術という流れになっていたのですが、最近では、変形性股関節症に対する再生医療が注目されています。『いったい再生医療ってなんだろう』『どの再生医療がいいの?』という疑問に対して、こちらでわかりやすく解説しています↓
股関節の無料相談受付中!
リペアセルクリニックは「股関節」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。
- Cibulka MT, Bloom NJ, Enseki KR, Macdonald CW, Woehrle J, McDonough CM. “Hip Pain and Mobility Deficits-Hip Osteoarthritis: Revision 2017.” The Journal of orthopaedic and sports physical therapy 47, no. 6 (2017): A1-A37.
- Hunter DJ, Bierma-Zeinstra S. “Osteoarthritis.” Lancet (London, England) 393, no. 10182 (2019): 1745-1759.
監修者

坂本 貞範 (医療法人美喜有会 理事長)
Sadanori Sakamoto
再生医療抗加齢学会 理事
再生医療の可能性に確信をもって治療をおこなう。
「できなくなったことを、再びできるように」を信条に
患者の笑顔を守り続ける。