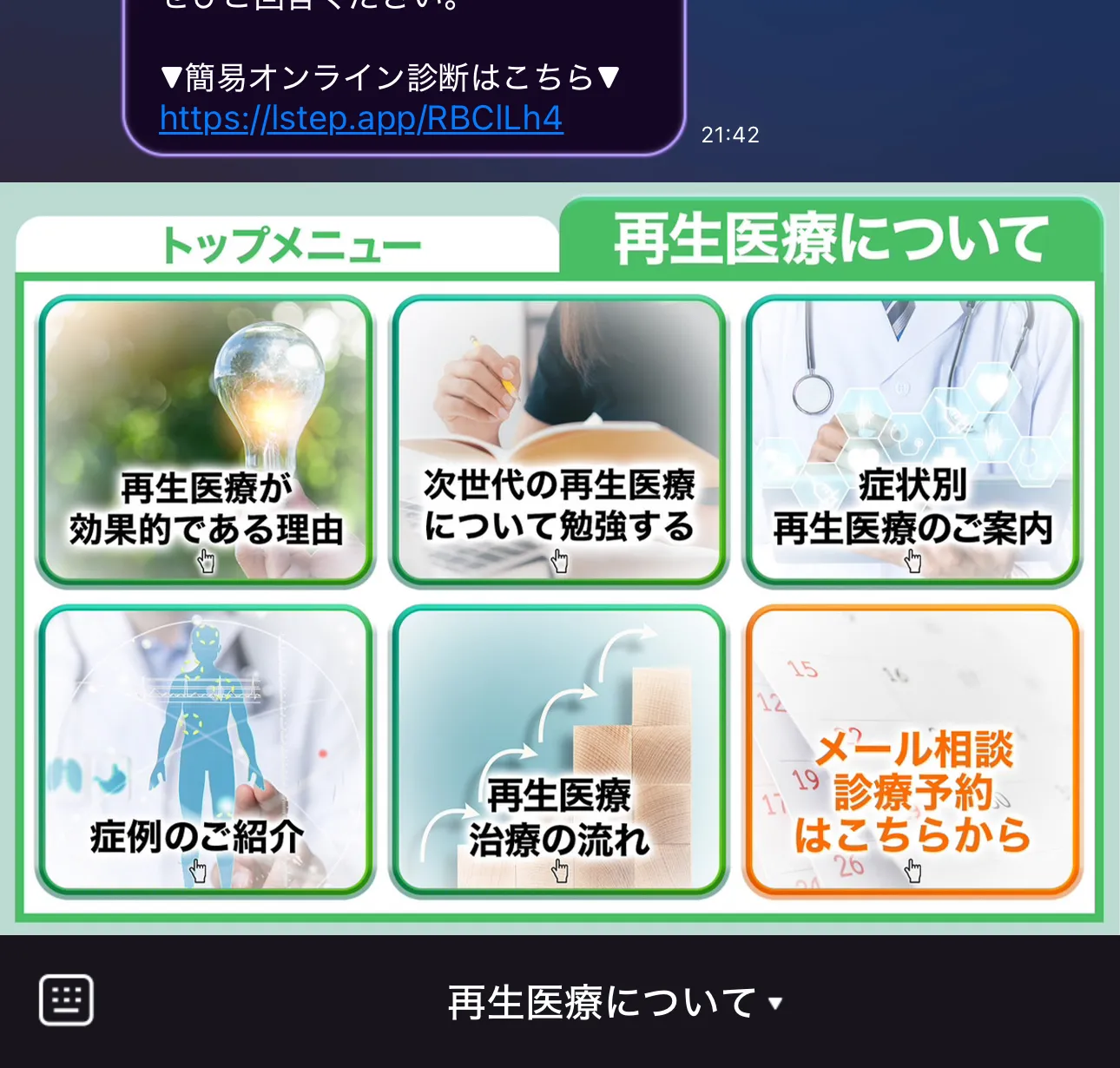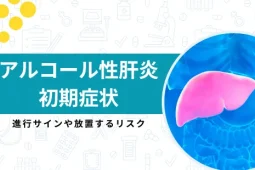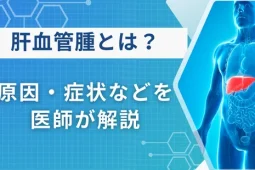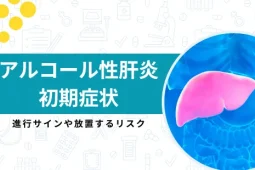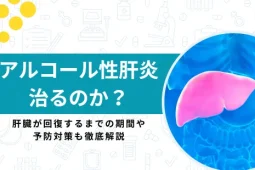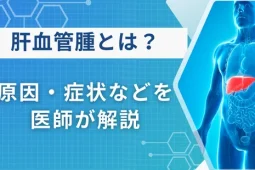- 肝疾患
- 内科疾患
女性に多い肝臓の病気や自己免疫性肝炎の症状とは【現役医師が解説】
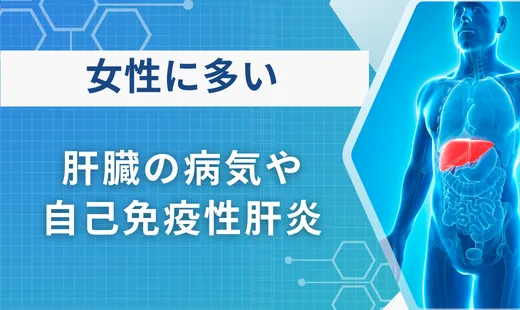
「肝臓の病気である自己免疫性肝炎の症状は?」
「自己免疫性肝炎は女性に多いの?」
自己免疫性肝炎は、体のなかで最大の臓器である肝臓に起こる病気で、とくに女性に多く認められます。
初期症状では、異常に気づきにくい場合も多いです。しかし、放置すると肝硬変や肝不全、肝がんなどの重大な病態にいたる可能性もあります。
自己免疫性肝炎の原因や症状、診断に必要な検査、治療方法を解説します。
肝臓の症状悪化を防ぐには早期治療が重要です。肝臓の病気などに不安を感じておられる方は、ぜひ医療機関に訪れて医師からの診断をあおいでみてください。
目次
女性に多い自己免疫性肝炎とは【肝臓の病気】
自己免疫性肝炎(じこめんえきせいかんえん)は、一般的に慢性に進行する肝障害をきたす病気です。
発症は60歳ごろがピークとされ、中年に多いとされています。
男女比は1:4.3と、男性よりも女性に多い傾向があり、日本では約3万人強の患者さまがいると推定されています。
自己免疫性肝炎は、国が定める指定難病です。一定の重症度を満たす場合は、医療費が公費補助の対象となります。
肝臓の病気である自己免疫性肝炎の原因
自己免疫性肝炎の原因は、まだ完全に明らかになっていません。しかし、さまざまな要素から、免疫が自身の体を攻撃する場合に起こる「自己免疫疾患」と考えられています。
実際に自己免疫性肝炎では、肝臓に免疫細胞が多く集まり、炎症をきたしている所見が確認できます。
ただ、アルコールをまったく摂取しない人や、ウイルス性肝炎を起こすB型肝炎、C型肝炎の感染がなくても病気が発症する場合もあるのです。
たとえば、特定の遺伝因子を持つ人が発症しやすいといわれています。しかし、一般的に行われている検診などでは、発症のしやすさを判定できません。
肝臓の病気である自己免疫性肝炎の合併症
自己免疫性肝炎は、ほかの自己免疫疾患との合併が多く認められます。
たとえば、以下のような疾患を患っている方は、自己免疫性肝炎を発症するリスクが高まります。
【自己免疫性肝炎に多い合併症の例】
|
肝臓の病気である自己免疫性肝炎の症状
残念ながら「〇〇の症状があれば、自己免疫性肝炎が疑われる」など、特徴的なものはありません。
早期に発見されるきっかけは、無症状のまま健康診断などで肝障害を指摘される場合が多いです。
肝臓は別名「沈黙の臓器」と呼ばれています。そのため、肝障害は早期の段階で病気に気づきにくいのです。
一方で、急激な経過をたどる場合は、以下のような自覚症状を認める場合があります。
以下の症状は、自己免疫性肝炎に特異的ではありませんが、複数のものが該当するときは、急激に進む重度の肝障害が起こっている可能性があるため、早期に受診しましょう。
【急性肝炎として発症する場合の症状の例】
|
一部の方は、気づかないうちに病状がかなり進行して、肝硬変をきたしている場合があります。
肝臓の病気や自己免疫性肝炎の診断に必要な検査

肝臓の病気や自己免疫性肝炎を調べるときは、さまざまな検査を行って総合的に診断します。
まずは血液検査で肝臓の障害があるか、障害の程度を含めて判断する流れが一般的です。
AST(GOT)・ALT(GPT)の数値検査
健康診断でよく見る AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇が参考になる所見です。
数値が高いときは、肝臓の機能になんらかの異常がある可能性を示しています。
ちなみに、AST(GOT)とは「アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ」と呼ばれる酵素です。ASTは細胞がダメージを受けると、血液中に酵素が放出されます。
また、ALT(GPT)は「アラニンアミノトランスフェラーゼ」と呼ばれる酵素です。主に肝臓に存在しており、肝細胞が破壊されると血液中に放出されます。
IgG・自己抗体検査
免疫関連の検査として、IgG(免疫の成分である抗体の量を見る検査)を行います。
いくつかの自己抗体(自分の体を攻撃する抗体についての検査)も重要です。
B型・C型肝炎ウイルス検査
肝臓にダメージを与えるB型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスなど、感染の有無を調べます。
画像検査
エコー、CTなど、肝臓の画像検査も必須です。
肝障害をきたす脂肪肝など、他疾患の有無、肝臓の硬さ、悪性腫瘍(とくに肝がん)における合併の有無を評価します。
肝生検
診断においてとくに重要なのは、肝臓の組織の検査、肝生検です。
肝生検には「経皮的肝生検」と「腹腔鏡下肝生検」の2つがあります。
基本的には、体に負担の少ない「経皮的肝生検」が行われる場合が多いです。経皮的肝生検では、実際にエコー下で肝臓を確認しながら、細い針を刺して組織を採取します。
出血などのリスクがある検査で、終了後の安静が求められるので短期間の入院が必要です。
肝生検で採取した組織は特殊な染色を行い、顕微鏡で観察します。検査により、以下の内容を確かめられます。
|
自己免疫性肝炎で特徴的なのは、インターフェイス肝炎(Interface hepatitis)と呼ばれるものです。
肝臓へ血液を運ぶ肝動脈、門脈や胆汁を運ぶ胆管が集まった「門脈域」に、リンパ球や形質細胞(一部のリンパ球が成熟した細胞)などの炎症細胞が集まります。
周囲の肝細胞を破壊しながら、炎症がさらに広がっていく様子が認められるのです。このような所見は全例で見られるわけではありませんが、認められれば診断への重要な手がかりとなります。
肝生検はほかの原因を除外し、自己免疫性肝炎の診断を確実にするために重要な検査です。ただ、患者さまの体の状態が悪く、肝生検をしないほうが良いケースには行いません。
自己免疫性肝炎の病気における治療法【副作用も解説】
自己免疫性肝炎の治療は、基本的にステロイドを使います。ステロイドは副腎皮質から分泌されるホルモンをもとにつくられた薬剤です。
強力な抗炎症作用や免疫抑制作用をもっており、自己免疫性肝炎を始め、さまざまな自己免疫疾患の治療に使われています。
治療における流れは以下のとおりです。
【自己免疫性肝炎の治療における流れ】
|
開始後は、最低でも2週間程度は初期量の継続が必要です。
以降は肝機能の数値(主にALT)を見ながら少しずつ減量します。急いで減量や中止をすると、再燃のリスクがあるからです。
ほかには、肝機能の改善を助けるウルソデオキシコール酸が処方される場合があります。
また、治療困難例やステロイドを多く使えない場合には、免疫抑制薬をステロイドと併用で使うときもあります。
ただ、長期で大量に使用すると、以下のようにさまざまな副作用をきたすので注意が必要です。
【ステロイドの副作用の例】
|
副作用がないか適宜検査を行い、予防可能なものには対策をしていきます。気になる症状があれば主治医と相談しましょう。
また、肝臓に関わる病気では、治療方法のひとつに再生医療がございます。
症状に悩まれておられる方は、ぜひ当院のメールや電話からご相談ください。
自己免疫性肝炎の病気で日常生活を送るときの注意点
日常生活では栄養バランスの取れた食事をとり、間食を控えるのが大切です。また、外出時は人混みを避けて手洗いやマスク着用、うがいなどの感染予防行動を徹底しましょう。
注意しておきたいのが、続発性副腎機能不全です。ステロイド薬の内服により、引き起こされた副腎皮質ホルモンの不足を指します。
生理的な量を超えるホルモンを長期で内服すると、副腎は本来のホルモン分泌を怠るようになります。
そのため、長期内服者が薬を自己判断で中断してしまうと、ホルモン不足が起こるかもしれません。副腎皮質機能不全となると、以下のような症状が出てきます。
【副腎皮質機能不全の症状例】
|
また、重症になると意識を失ったり、ショック状態になったりする場合もあります。
ステロイドを自己判断で減量や中止してしまうと、病状悪化だけでなく、命に関わる副腎機能不全をきたすリスクもあるので、必ず医師の指示通りに内服しましょう。
自己免疫性肝炎の病気は進行するの?【肝臓の症状悪化を防ぐには早期治療】
自己免疫性肝炎の多くは治療が有効である一方、最初は軽症でも放置をすれば命に関わる事態になります。
自己免疫性肝炎を放置すると炎症が沈静化せず、肝臓の線維化が進みます。肝臓の線維化が進行して固くなった状態が「肝硬変」です。
肝臓では栄養素の代謝やエネルギー貯蔵、有害物質の分解や解毒などが行われていますが、肝硬変が進むと機能障害が起こります。
肝臓の働きが大きく損なわれてしまった状態を「肝不全」と呼びます。さらに、肝硬変は肝がんの発生が起こりやすく、肝がんは治療しても再発しやすい厄介ながんです。
肝硬変・肝不全・肝がんへの進行を防ぐには、早期から適切な治療を受けるのが重要です。自己免疫性肝炎では、治療によりASTやALTの数値を基準値内に保てれば、生命予後は良好とされています。
肝硬変の症状や原因については、以下の記事もあわせてご確認ください。
肝臓の症状や自己免疫性肝炎の病気が心配な女性は内科を受診しよう
自己免疫性肝炎に特徴的な症状はありませんが、ときにだるさや黄疸などをきたす場合があります。また、無症状で発見される場合も多いです。
診断は血液検査や画像検査などを行い、総合的に判断して行います。とくに組織の検査は非常に重要とされています。
治療の第一選択薬はステロイドです。副作用も多いですが、対策をしながら長期的に使用します。
自己免疫性肝炎を放置すると命に関わる「肝硬変」に進展するため、診断を受けたら定期的に通院をして服薬を続けましょう。
健康診断で肝臓の数値が高いと言われた方や、肝臓が悪いときの症状に思い当たる節がある方は、まずは医療機関で検査を受けてみてください。
また、肝臓に関わる病気については、治療方法のひとつとして再生医療があります。肝臓の病気に関わる症状に悩まれておられる方は、ぜひ当院のメールや電話からご相談ください。
女性に多い肝臓の病気や自己免疫性肝炎の症状についてよくある質問
実際に患者さまからよくお聞きする質問や、肝臓の病気に関わるQ&Aをまとめています。
Q.自己免疫性肝炎の病気では、最終的にステロイドを止められますか?
A.経過によっては中止が可能ですが、全員ではありません。中止できるときも、多くの場合は年単位の時間がかかります。
また、中止した場合には再燃するリスクもあります。減量や中止については個々のケースで大きく異なるので、主治医とよく相談するのが良いでしょう。
Q.原発性胆汁性胆管炎の病気も肝臓の自己免疫疾患と聞きましたが、違いはなんですか?
A.どちらも中年以降の女性に多い自己免疫性疾患ですが、障害が起こる部位が異なります。
自己免疫性肝炎では、肝細胞の障害が中心です。原発性胆汁性胆管炎で起こるのは、肝臓内の胆汁が通る管(胆管)の破壊です。
そのため、胆汁の流れが滞り、ALPやγ-GTPなど、胆道系酵素や黄疸をきたすビリルビン値の上昇が目立ちます。進行すると黄疸や皮膚のかゆみを生じます。
また、病気を放置すると肝硬変へ進展するので、必ず医療機関での治療が必要です。
各種検査で自己免疫性肝炎との鑑別を行いますが、2つの病態が合併している場合もあります。
Q.アルコールを飲む機会が多いと肝臓の病気になりますか?
A.アルコールを飲む量や本人の体調によっては、肝臓の病気になる可能性があります。
とくに長期間にわたり、アルコールの大量摂取を行うと、肝臓に大きなダメージを与えてしまうからです。
実際に、厚生労働省の情報でも、アルコールの飲みすぎは脂肪肝やアルコール性肝炎など、肝臓病につながりやすいと指摘しています。
日頃からお酒を飲まれる方で、肝臓への負担が気になる方は、アルコール性肝炎の初期症状などを解説している以下の記事もあわせて参考にしてみてください。
Q.肝臓の病気があるときに食べてはいけないものはありますか?
A.糖質や脂質が多く含まれているような食べ物は避けましょう。
たとえば、以下の食べ物が例にあげられます。
| ・糖質が多いもの:ジュース類、駄菓子、果物 など ・脂質が多いもの:揚げ物、肉の脂身、ドレッシング など |
肝臓をいたわる食事の例を知りたい方は、以下の記事も参考になります。
Q.肝臓に血管腫があるときはどうすれば良いですか?
A.肝血管腫とは、肝臓で異常増殖した細い血管が絡み合い、塊になった際にできる良性腫瘍です。
小さな病変かつ無症状であれば、基本的に経過観察のみと考えて良いでしょう。
大きくても増大傾向がなく、かつ無症状であれば経過観察可能と判断される可能性が高いと思われます。
また、肝臓に血管腫があるときは、医療機関での定期検査を行いましょう。気になるような症状や異変を感じた場合には、すぐ診療してもらうのが大切です。
以下の関連記事で詳細を解説しているので、あわせて参考にしてみてください。
Q.脂肪肝を改善するにはどうすれば良いですか?
A.生活習慣や食事などの改善が必要です。
脂肪肝になった原因によって、以下のように改善方法は変わります。
|
また、脂肪肝を指摘されたときは、放置せずに早めに医療機関を受診して治療を行うのが重要です。
脂肪肝の改善に関わる詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。
Q.肝疾患の相談などができる支援機関はありますか?
A.以下の支援機関で、肝疾患に関わる情報提供や相談を行っています。
・肝炎情報センター:情報の提供
・肝疾患相談支援センター:相談など
|
参考文献
厚生労働省難治性疾患政策研究事業「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班 |