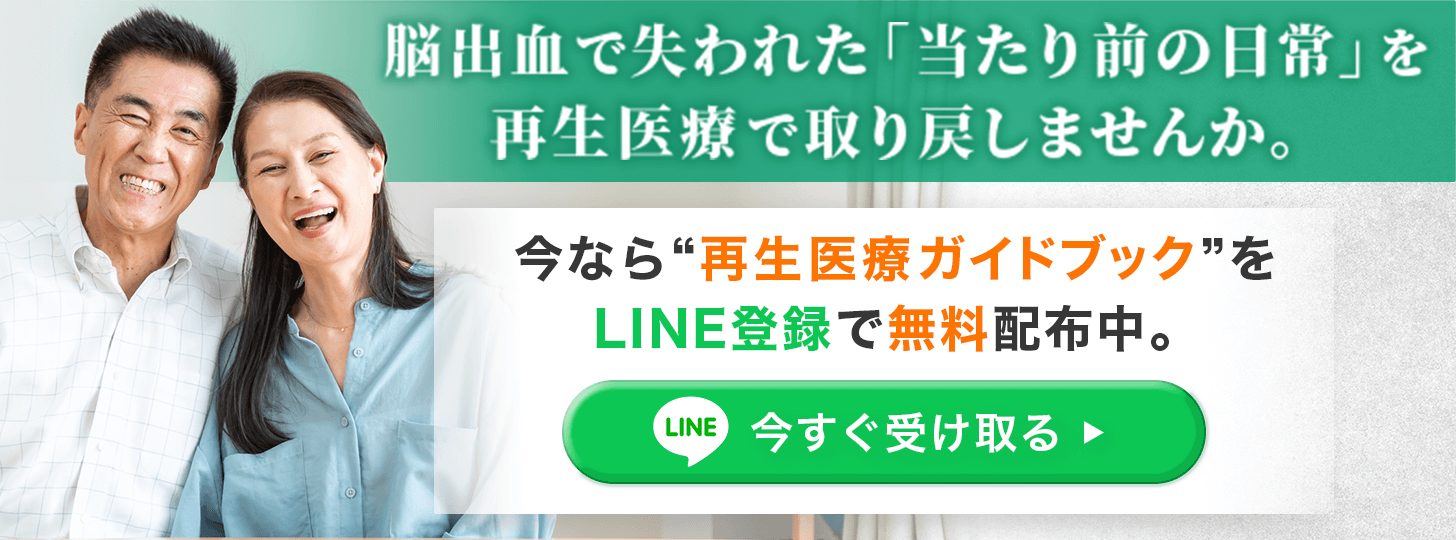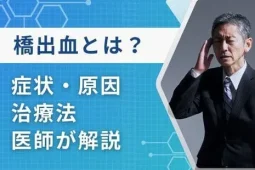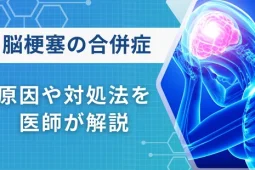- 脳卒中
- 頭部
- 脳出血
橋梗塞(橋出血)のリハビリプログラムを紹介!症状を知って改善を目指そう

橋梗塞(橋出血)ではどんな症状が出るのだろう。
橋梗塞(橋出血)になったらどんなリハビリが必要なのかな。
この記事を読んでいるあなたは、橋梗塞の症状やリハビリについて不安を抱いているのではないでしょうか。「橋梗塞」という病気自体に馴染みがなく、今後の治療・リハビリの流れを知りたいと思っているかもしれません。
結論、橋梗塞になると麻痺やしびれなどが多く見られます。しかし、梗塞の程度や治療開始までにかかった時間などにより、その後の経過や必要なリハビリに個人差があるのも事実です。
本記事では、橋梗塞(橋出血)の症状やリハビリについて、詳しく解説します。記事を最後まで読めば、症状や経過がわかり、今後の見通しを立てやすくなるでしょう。
目次
橋梗塞(橋出血)における4つの症状
橋梗塞(きょうこうそく)とは、脳の奥にある「脳幹」の一部、「橋(きょう)」という部分の血管が詰まり、脳細胞の機能が失われる病気です。橋梗塞は脳梗塞全体の約7%を占めるといわれています。(文献1)
橋は大部分の脳神経の出入口であり、運動や感覚をつかさどる神経が通る部分です。り、睡眠や覚醒、呼吸運動や循環機能などの「自律運動」をつかさどり、人間の生存や活動に重要な役割を果たします。っている重要な部分です。
そのため、橋梗塞(橋出血)が起こると、以下のような症状が出ることがあります。
- 運動失調
- 感覚障害
- 嚥下障害
- 四肢の麻痺(閉じ込め症候群)
ほかにも、意識障害や高熱、瞳孔縮小、高血圧、呼吸異常、眼球運動障害などが出るケースもあります。
なお、橋梗塞(橋出血)による麻痺は、梗塞によって機能が失われた脳の反対側に見られるのが一般的です。
本章の内容をもとに、橋梗塞(橋出血)のおもな症状を理解しておきましょう。
橋出血の症状については、以下の記事で詳しく説明しています。
運動失調
運動失調とは、運動麻痺が認められにくい、または軽度であるにもかかわらず動作や姿勢保持などの協調運動ができなくなる状態です。
運動失調の代表的な症状は、以下のとおりです。(文献2)
- 言葉がうまく出ない
- 呂律がまわらなくなる
- 起立・歩行時にふらつく
- 字を書くのが下手になる
- ボタンかけがうまくできない
- 手が震えて、コップに入れた水をこぼす
- 箸がうまく使えず、スムーズな食事ができない
運動失調は、障害された部位によって以下の表にある3つの種類に大きく分けられます。(文献3)
| 運動失調の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 小脳性運動失調 |
|
| 感覚性運動失調 |
|
| 前庭性運動失調 |
|
橋と小脳は神経でつながっているため、橋梗塞(橋出血)が起こると小脳への伝達がさまたげられます。そのため、橋梗塞(橋出血)により小脳性運動失調をきたすケースがあるのです。
感覚障害
感覚障害とは、神経伝達がうまくできなくなり、手や身体などからの感覚に麻痺や違和感が出る症状です。
感覚障害の代表的な症状は、以下のとおりです。(文献4)
- しびれ感がある
- 少しの刺激でも強い痛みや刺激を感じる
- なにかを触っても感覚がしない(温かさ・硬さ・重さなど)
健康な人では、身体からの感覚は脳へスムーズに伝達されます。
しかし、橋梗塞(橋出血)により神経の伝達がさまたげられると、身体の感じた刺激がうまく脳へ伝わらなくなります。
その結果、「しびれる」「感覚がおかしい」など、生活の質に大きな影響が生じる感覚障害が出るのです。
運動失調や感覚障害については、以下の記事も参考にしてください。
嚥下障害
橋を含む「脳幹」で梗塞が起こると、飲み込みに関する神経が傷ついたり神経伝達が阻害されたりして、「嚥下障害」になるケースがよく見られます。(文献5)
嚥下障害のおもな症状は、以下のとおりです。
- 食べ物・飲み物でむせやすくなる
- 食べるのに疲れ、食事を嫌がるようになる
- 食べたものが気管に入る「誤嚥」のリスクが上がる
- 口から食べ物がこぼれるため、食事を楽しめなくなる
嚥下障害は、食べ物が気管に入って炎症が起こる「誤嚥性肺炎」のリスクが上がるのも大きな問題です。
ただし、一度食べられなくなっても、リハビリをすれば少しずつ機能が回復するケースもあります。
四肢の麻痺(閉じ込め症候群)
橋の機能が大きく失われ四肢がまったく動かせなくなると、眼球やまぶたしか自分の意思で動かせなくなる「閉じ込め症候群」になるケースがあります。
閉じ込め症候群は、本人の意識は保たれているにもかかわらず身体を動かせないのが大きな特徴です。
また、閉じ込め症候群の人は、嚥下機能も大きく低下する傾向があります。
その結果、誤嚥性肺炎をはじめとする感染症により命を落とすケースは珍しくありません。(文献6)
当院「リペアセルクリニック」では、橋梗塞(橋出血)の症状や後遺症に対して、再生医療(幹細胞治療)をおこなっています。治療により傷ついた脳細胞が再生されれば、橋梗塞によるつらい症状の改善が期待できます。
ご質問やご相談は「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」から、気軽にお問い合わせください。
\無料オンライン診断実施中!/
橋梗塞(橋出血)による運動失調のリハビリプログラム4選
橋梗塞(橋出血)によって起きた運動失調に対するリハビリプログラムは、以下の4つです。
- フレンケル体操
- 重り負荷での運動
- 弾性緊縛帯での運動
- 固有受容性神経筋促通手技(proprioceptive neuromuscular facilitation:PNF)
本章の内容をもとに、リハビリについて理解しておきましょう。
橋梗塞を含む脳梗塞のリハビリについては、以下の記事でも詳しく解説しています。リハビリ内容について詳しく知りたい方はあわせてチェックしてみてください。
フレンケル体操
フレンケル体操は、運動失調のリハビリとして古くから行われている治療法です。
自分の動きを目で見ながら身体の動きをコントロールし、同じ動作を繰り返します。
何度も繰り返し練習することで、協調運動を再びできるようにするのが狙いです。
重り負荷での運動
重り負荷での運動では、足や手の関節や腰に重りをつけ、負荷をかけた状態で運動をおこないます。
身体に重りが付くと、運動量が増えて身体が受ける感覚が強まります。その結果、過剰な運動を抑える力が働き、運動失調が軽減するのです。
弾性緊縛帯での運動
弾性緊縛帯での運動も、重り負荷での運動と同じ発想に基づくリハビリ方法です。
弾性緊縛帯とは、弾性包帯やサポーターなどの身体を圧迫して圧力をかけるものです。上肢・下肢近位部の関節を圧迫して身体への感覚を強化します。(文献7)
感覚入力が強化されると上下肢の過剰な運動が抑えられ、運動失調の軽減が期待できるでしょう。
固有受容性神経筋促通手技(proprioceptive neuromuscular facilitation:PNF)
固有受容性神経筋促通手技(proprioceptive neuromuscular facilitation:PNF)とは、筋肉や皮膚、関節などにある感覚の受容体を刺激しながら身体を動かすリハビリ方法です。
この手法は、治療者(セラピストなど)と患者本人のペアでおこないます。
- 1.治療者は患者の関節を交互に動かす
- 2.患者は関節を動かす治療者の動きに負けないように、関節を特定の位置に保つ
効果の持続は短時間にとどまりますが、毎日反復しておこなえば機能の回復が期待できるという報告もあります。
当院「リペアセルクリニック」では、橋梗塞(橋出血)後の治療として再生医療(幹細胞治療)をおこなっています。治療と並行して理学療法士、柔道整復師、鍼灸師などを含むチーム体制によるリハビリテーションも可能です。
ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」から気軽にお問い合わせください。
橋梗塞で行われる3つの治療
橋梗塞でおこなわれる治療は、以下の3つです。
- 血栓溶解療法(t-PA治療)
- 血管内治療(血栓回収療法)
- 抗血栓療法(内服治療)
なかでも血栓溶解療法は、梗塞が生じてから4.5時間以内に始める必要があるため、早く気付いて治療を始めることが非常に大切です。
機能が失われた脳の部位によっては、急激に体調が悪化するリスクもあります。橋梗塞では呼吸や心機能などの全身管理を慎重におこないながら、スピーディな治療がおこなわれます。
橋梗塞を含む脳梗塞の治療については、以下の記事も参考にしてください。
まとめ|運動失調は橋梗塞(橋出血)の症状!リハビリで後遺症を改善しよう
本記事では、橋梗塞(橋出血)の症状や運動失調のリハビリについて詳しく解説しました。
橋梗塞は脳の奥にある「脳幹」の一部「橋」の血管が詰まり、脳細胞がダメージを受ける病気です。運動失調や感覚障害、嚥下障害などが起こり、必要に応じて治療やリハビリがおこなわれます。
適切なリハビリをおこなえば、後遺症の改善が少しずつ見込めるでしょう。
当院「リペアセルクリニック」では、橋梗塞をはじめとする脳梗塞に対して再生医療(幹細胞治療)を提供しています。
再生医療(幹細胞治療)は、ダメージを受けた脳細胞の再生による後遺症の回復や、リハビリ効果の向上などが期待できる治療です。
再生医療へのご質問・ご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けております。気になる点がありましたら、どうぞ気軽にご相談ください。
\無料オンライン診断実施中!/
橋梗塞の症状やリハビリが気になる人によくある質問
橋梗塞と脳梗塞の違いは?
橋梗塞は脳梗塞の一部で、両者の違いは「梗塞の起きた部分の範囲」です。
- 橋梗塞:脳のなかにある「脳幹」のさらに一部「橋」で起こった梗塞のみを指す
- 脳梗塞:脳内で起きた梗塞すべてを指す
つまり、橋梗塞の方が脳梗塞よりも起きた場所が限定された梗塞といえるでしょう。
脳梗塞については、以下の記事で詳しく解説しています。
運動失調と麻痺の違いは?
なにかの運動をしようとする際に障害がある状態を、運動障害といいます。
運動障害には「運動麻痺」と「運動失調」があり、症状や原因に以下の違いがあります。
| 症状 | 原因 | |
|---|---|---|
| 運動麻痺 | 筋肉を自分の意思で動かせない | 筋肉そのものや、筋肉に命令を送る大脳皮質や脊髄・末梢神経がダメージを受けた |
| 運動失調 | スムーズな運動が難しい |
運動に関わる筋肉の動きを調整する機能が失われた
|
リハビリの効果を高めるための方法はあるの?
リハビリの効果を高める方法には、「自己脂肪由来幹細胞の投与」があります。
自己脂肪由来幹細胞の投与には、リハビリの効果を高めることに加え、脳神経細胞の修復再生による運動失調からの回復効果も期待できます。
リハビリには失われた機能を改善する効果が期待できますが、橋梗塞(橋出血)により失われた脳細胞の再生は困難です。
また、発症から時間が経つにつれて、リハビリの効果はあらわれにくくなることもあります。
リハビリの効果が上がらない、早く効果を上げたいなどの方は再生医療の利用も検討してみてはいかがでしょうか。ご質問・ご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けております。どうぞ気軽にご相談ください。
リハビリ効果を上げる方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。