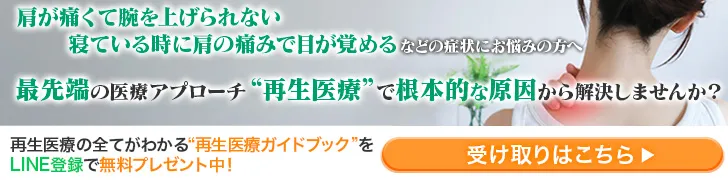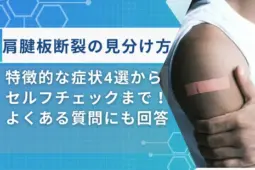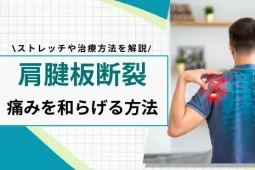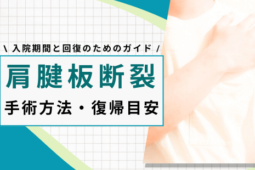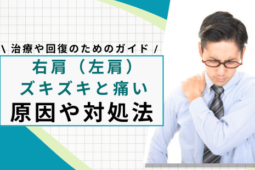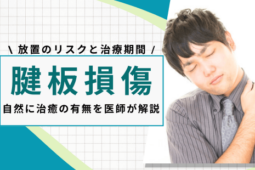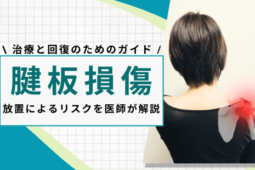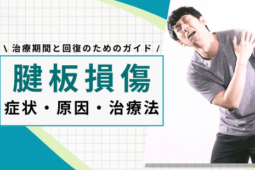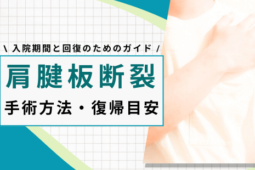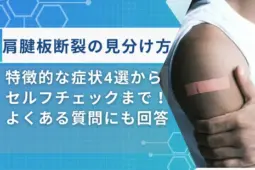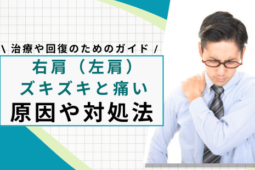- 腱板損傷・断裂
- 肩関節
【医師監修】腱板断裂とは|原因・治療法・セルフチェックで知る症状のサインについて解説
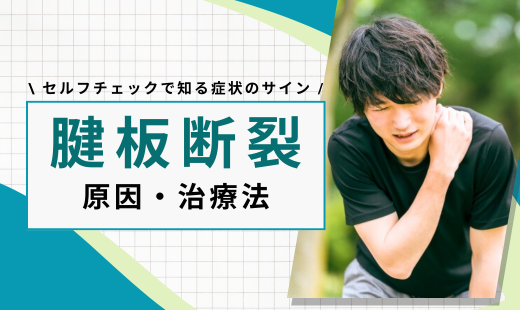
「肩に違和感がある」
「夜中に目が覚めるほどつらい」
それは腱板断裂のサインかもしれません。腱板断裂とは、肩の腱板が損傷または断裂し、腕が上がらない、筋力低下、夜間の痛みなどを引き起こす疾患です。とくに肩を長年酷使してきた人や中高年では発症リスクが高まります。
本記事では、腱板断裂について現役医師が詳しく解説します。
- 腱板断裂の原因
- 自分でできる腱板断裂のセルフチェック
- 腱板断裂の治療法
- 腱板断裂の予防法
- 腱板断裂と似ている症状
腱板断裂は、適切な診断と治療により症状の改善が期待できます。本記事を通じて症状を正しく理解し、治療法の選択に役立てください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
腱板断裂について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
腱板断裂とは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 肩の深部にある腱板の腱が、上腕骨の付着部から部分または完全に剥がれた状態 |
| 役割 | 肩関節の安定維持と腕の上下・回転動作の補助 |
| 構成筋 | 棘上筋・棘下筋・肩甲下筋・小円筋 |
| 主な原因 | 加齢による腱の弱化、肩の酷使(スポーツ・肉体労働)、外傷(転倒や事故) |
| 症状 | 腕の挙上や物を持つ力の低下、挙上制限、肩の不安定感、動作時や夜間の違和感 |
| 診断方法 | MRI検査、超音波検査、医師による徒手テスト |
| 要点 | 発症は中高年に多く、原因や症状は多様。早期診断と適切な治療が肩機能維持の鍵 |
腱板断裂は、肩の運動と安定性に重要な腱板が損傷または断裂した状態です。腱板は棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋の4つの筋肉の腱で構成され、上腕骨頭と肩甲骨をつなぎ、腕の挙上や回旋を担います。
損傷が生じると、肩の違和感や筋力低下、可動域の制限などが現れ、日常生活に支障を及ぼします。断裂にはすべての腱が切れる完全断裂と、一部のみが損傷する部分断裂があります。放置すると悪化し、回復が難しくなる場合があるため、症状が見られた場合は早期に医療機関で診断と適切な治療を受けることが重要です。
以下の記事では、肩腱板断裂(損傷)について詳しく解説しています。
腱板断裂の原因
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 加齢による腱の変性と断裂のリスク | 腱の老化・血流低下による組織の弱化および弾力低下 |
| スポーツや肉体労働による肩の酷使 | 繰り返しの肩使用や過度の負荷による腱の摩耗・損傷 |
| 転倒や事故など外傷による断裂 | 強い衝撃や捻挫による急激な腱の断裂・損傷 |
腱板断裂は、加齢に伴う腱の老化や血流低下による組織の弱化・弾力低下、スポーツや肉体労働などでの繰り返しの肩使用による摩耗、さらに転倒や事故による強い衝撃や捻挫など、さまざまな要因で発症します。原因を理解することは、予防や早期発見のためにも重要です。
加齢による腱の変性と断裂のリスク
加齢により肩の腱は弾力や柔軟性を失い、損傷しやすくなります。原因はコラーゲン繊維の劣化、水分量の減少、血流低下による修復力の低下です。
日常生活や仕事、スポーツでの長年の使用による摩耗も影響し、わずかな負荷や軽い外傷でも断裂が起こります。40歳以降でリスクが高まり、60歳を超えると発症が増えます。(文献1)肩の違和感や動きの変化があれば、早期の医療機関への受診が重要です。
スポーツや肉体労働による肩の酷使
肩を繰り返し使うスポーツや肉体労働は腱板に負担をかけ、損傷や断裂の原因となります。野球やテニス、水泳、重量物の持ち運びなどの頭上動作は肩関節への負荷が大きく、腱板が骨にこすれて摩耗しやすくなります。
この摩耗が蓄積すると強度が低下し断裂に至ります。利き腕に多く、慢性的な酷使が主因ですが、転倒など一度の衝撃でも発症します。肩の痛みや違和感があれば早期の受診が必要です。
以下の記事では、腱板が再断裂する原因を詳しく解説しています。
転倒や事故など外傷による断裂
腱板は腕の動きと肩関節の安定に重要で、強い外力で急に損傷することがあります。高所からの転倒や交通事故、スポーツ中の衝突などで肩や腕に瞬間的な過負荷がかかると、とくに腕を伸ばして手をついた場合や肩から転倒した場合に断裂しやすくなります。
加齢や酷使で変性した腱板はわずかな外力でも断裂することがあるため、受傷後に肩の動きや筋力に異常を感じたときは早期に診察と画像検査を受けることが重要です。
自分でできる腱板断裂のセルフチェック
| セルフチェック | 詳細 |
|---|---|
| ドロップアームテスト | 腱板の主に棘上筋の断裂や筋力低下の有無 |
| リフトオフテスト | 腱板の主に肩甲下筋の損傷や機能低下の有無 |
| ホーンブローワーテスト | 腱板の主に棘下筋や小円筋の損傷や外旋筋力低下の有無 |
腱板断裂が疑われる場合、自宅で行える簡易的な確認方法として、ドロップアームテスト・リフトオフテスト・ホーンブローワーテストがあります。ドロップアームテストは、腕を横に上げたまま保持できず途中で落ちる場合に棘上筋の損傷や筋力低下を調べる検査です。
リフトオフテストは、腰の後ろに回した手を背中から離せない場合、肩甲下筋の機能低下が疑われます。ホーンブローワーテストは、腕を外に開く動作で力が入らないず場合に棘下筋や小円筋など外旋筋の状態を確認する検査です。これらはいずれも目安であり、異常があれば医療機関での診断が必要です。
ドロップアームテスト
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 目的 | 腱板のうち主に棘上筋の断裂や筋力低下の有無の確認 |
| 方法 | 腕を真横に90度(肩の高さ)まで上げ、そのまま支えずにゆっくり下ろす動作の観察 |
| 陽性所見 | 腕が途中で急に落ちる、または動作をコントロールできない状態 |
| 判定の意味 | 陽性の場合は棘上筋を中心とした腱板損傷の可能性 |
| 留意点 | 自分一人でも行える簡易的な確認方法だが、陽性時は医療機関での診察・画像検査が必須 |
ドロップアームテストは、棘上筋損傷を確認するための簡易検査です。腕を横に伸ばして肩の高さまで上げ、そのまま支えずにゆっくり下ろします。健康な腱板であれば滑らかに下ろせますが、損傷があると保持できず途中で落ち、動きが不安定になります。
棘上筋は腕を横に上げる筋肉で、損傷すると筋力低下や動作制限が起こるため、異常があれば早期の受診とMRIや超音波検査による診断が必要です。
リフトオフテスト
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 目的 | 肩甲下筋の損傷や機能低下の確認 |
| 方法 | 片手を背中の腰あたりに回し、手の甲を背中につけた状態から背中から離す動作の実施 |
| 陽性所見 | 手を背中から離せない、動かしづらい状態 |
| 特徴 | 肩甲下筋の機能確認に有効な簡易的セルフチェック方法 |
| 注意点 | 異常を感じた場合は放置せず、医療機関での検査を推奨 |
リフトオフテストは、肩のインナーマッスルである肩甲下筋の損傷や機能低下を調べる簡易検査です。肩甲下筋は肩関節の内旋(腕を内側にひねる動き)を担い、腱板を構成する4つの筋肉のひとつです。
テスト方法は、背中の腰あたりに手を回し手の甲を背中につけ、その状態から手を背中から離そうとします。正常であれば手を浮かせられますが、損傷があると自力で離せなかったり、痛みで動かせなかったりします。この検査で異常がある場合は肩甲下筋の腱板断裂が疑われ、早期に整形外科で診察と画像検査を受けることが重要です。
ホーンブローワーテスト
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 目的 | 棘下筋や小円筋の損傷や機能不全の確認 |
| 方法 | 腕を肩の高さ(外転90度)に上げ、肘を90度に曲げた状態で腕を外に押し出す動作の実施 |
| 陽性所見 | 腕がスムーズに動かない、力が入らない、または動作時の違和感 |
| 特徴 | 外旋筋群の機能を評価できる簡易的セルフチェック方法 |
| 注意点 | 陽性の場合は医師による診察と画像検査の受診推奨 |
ホーンブローワーテストは、肩の腱板の中でも主に棘下筋と小円筋の機能を評価するための検査です。方法は、腕を肩の高さ(外転90度)に上げ、肘を90度に曲げた状態で、腕を外に回す動作(外旋)を行い、その際に抵抗を加えます。
筋肉や腱の損傷があると動きが不自然になり、力が入らず違和感が生じ、これは腱板断裂の可能性を示します。自宅でも鏡を見ながら実施できますが、結果が陽性の場合や症状が続く場合は、早期に整形外科を受診し、MRIなどで状態を確認することが重要です。
腱板断裂の治療法
| 治療法 | 詳細 |
|---|---|
| 保存療法(薬物療法・注射・リハビリテーション) | 薬剤や注射で痛みを抑え、リハビリで肩の動きを改善する方法 |
| 手術療法(関節鏡手術・縫合術など) | 関節鏡などを使って断裂した腱板を修復する方法 |
| 再生医療 | 幹細胞やPRPで腱の修復を促す先進的な治療方法 |
腱板断裂の治療は、損傷の程度や症状、日常生活への影響に応じて方法を選びます。軽度の場合は、鎮痛薬や注射で痛みを抑え、リハビリで肩の動きや筋力を取り戻す、保存療法が行われます。これは手術をせずに回復を目指す方法です。
一方、大きな断裂や保存療法で改善が見られない場合は、関節鏡を用いて断裂した腱を縫い合わせる「手術療法」が選ばれます。適切な治療選択のためには、早めの診察と正確な診断が重要です。
近年では、幹細胞療法やPRP療法などの再生医療も腱の修復促進を目的に導入されていますが、実施する医療機関は限られているため、事前に対応の可否や症状が適応するかを確認することが重要です。
以下の記事では、肩関節の治療法について詳しく解説しています。
保存療法(薬物療法・注射・リハビリテーション)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 目的 | 症状の軽減と生活の質の向上 |
| 方法 | 消炎鎮痛薬や湿布、ステロイド注射による痛み・炎症の緩和 |
| リハビリの役割 | 肩甲骨周囲筋の柔軟性と筋力の維持・強化、肩関節のバランス改善 |
| 適応 | 部分断裂、高齢者、持病による手術リスクが高い方 |
| 特徴 | 手術に比べ身体への負担が少なく開始しやすい方法 |
| 注意点 | 腱板断裂そのものは自然治癒せず、定期的な経過観察が必要 |
保存療法は、手術を行わずに症状を和らげ、日常生活を維持する方法です。薬物療法で炎症や痛みを抑え、リハビリで肩の筋力・柔軟性を回復させて関節の安定性を高めます。
保存療法は、手術のリスクが高い高齢者や部分断裂の方、持病のある患者に適しており、身体への負担が少ないことが特徴です。ただし、腱板断裂は自然に修復されないため、症状が落ち着いた後も定期的な診察と経過観察が必要です。
以下の記事では、肩腱板断裂の痛みを和らげる方法を詳しく解説しています。
手術療法(関節鏡手術・縫合術など)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 確実な再固定 | 関節鏡を用いて断裂した腱板を元の骨に縫い付けることで自然な形に修復可能 |
| 低侵襲 | 小さな切開で行うため体への負担や術後の痛みが少ない方法 |
| 症状進行の抑制 | 断裂拡大や筋萎縮・脂肪変性の進行を防ぐ効果 |
| 機能回復の促進 | 回復期間が比較的短く早期リハビリ開始が可能な利点 |
| 適応の柔軟性 | 年齢・断裂の程度・生活環境に応じた治療方針の選択 |
保存療法で症状が改善しない場合や、断裂が大きく日常生活に支障がある場合、さらに活動性が高く早期の機能回復を希望する方には手術が検討されます。
現在主流の関節鏡手術は、小さな切開から関節鏡を挿入し、モニターで内部を確認しながら損傷した腱板を修復する方法です。身体への負担が比較的少なく、回復が早い点が特徴です。
腱板縫合術では、断裂した腱板を骨に縫い付けて固定し、断裂の程度に応じて方法を選択します。術後は腱板が骨に癒着するまで安静が必要で、その後のリハビリテーションが機能回復に重要な役割を果たします。
以下の記事では、肩腱板断裂の手術と入院期間について詳しく解説しています。
再生医療
再生医療は損傷した腱板の修復や再生を促進します。幹細胞治療は、患者自身の脂肪などから幹細胞を採取・培養し、断裂部位へ注射で投与する方法です。
幹細胞は損傷部位で修復を促し、注射で行えるため負担が少なく、手術困難例や保存療法無効例に適します。幹細胞やPRP療法は炎症を抑えつつ腱組織を修復し、痛み軽減や可動域改善、断裂進行防止に寄与します。
ただし、再生医療は実施している医療機関が限られており、適応には事前の相談や診察が必要です。投与後は適切なリハビリを併用することで、肩の機能回復がより効果的に進みます。
当院「リペアセルクリニック」では、腱板断裂に対する再生医療の症例を紹介しています。ぜひご確認いただき、再生医療も治療法の一つとしてご検討ください。
腱板断裂の予防法
| 予防法 | 詳細 |
|---|---|
| 肩の柔軟性&筋力維持 | 肩甲骨や肩周囲筋の柔軟性と筋力の維持・強化による肩関節の安定化 |
| 姿勢・使い方の見直し | 胸を張り肩甲骨を適切な位置に保つ、正しい姿勢と肩への負担を減らす動作の習慣化 |
| オーバーユース回避 | 肩の過剰使用を避けることによる筋肉や腱への負担軽減 |
| 生活管理と違和感への早期対応 | 肩の違和感や痛みの早期発見・専門医受診と適切なケアによる悪化防止 |
腱板断裂を予防するためには、肩甲骨や肩周囲の筋肉の柔軟性と筋力を維持・強化して肩関節の安定性を高めることが重要です。
胸を張り、肩甲骨を正しい位置に保つ、肩を過剰に使わず休養を取り、違和感があれば早期に受診して悪化を防ぎます。
以下の記事では、腱板断裂を放置するリスクを詳しく解説しています。
肩の柔軟性&筋力維持
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 肩や肩甲骨の連動性維持 | 肩関節と肩甲骨の動きのバランスを保ち腱板への負担を軽減 |
| 可動域の維持 | 動きの制限による摩擦や腱の摩耗の防止 |
| インナーマッスル強化 | 腱板筋群を中心に肩関節の安定性を高め負荷を分散 |
| 全体バランスの改善 | 偏った動きや代償動作の防止による怪我リスク低減 |
| 日常・スポーツ時の負担軽減 | 正しい肩の動きによる過度な使用からの保護 |
腱板断裂を予防するには、肩の柔軟性と筋力の維持が欠かせません。肩関節は肩甲骨と連動して動くため、柔軟性が落ちると動きのバランスが崩れ、腱板に負担が集中します。その結果、可動域が狭まり摩擦が増えて損傷を招く恐れがあります。
日常的なストレッチで柔軟性を保つことは、こうした負担の軽減に有効です。さらに、腱板を構成するインナーマッスルや周囲の筋力を維持・強化すると、肩関節の安定性が高まり、運動時や荷物を持つ際にも腱板への負荷を分散できます。柔軟性と筋力をバランスよく整えることで、スポーツや日常生活での無理な動きが減り、怪我や断裂のリスクが低下します。とくに肩を酷使する方は、予防のために日常的なストレッチと筋力トレーニングを継続することが重要です。
以下の記事では、右肩や左肩がズキズキと痛い症状について詳しく解説しています。
姿勢・使い方の見直し
肩甲骨や胸椎の位置と可動性を適切に保つことは、肩関節の動きを整え、腱板への負担を減らします。猫背や巻き肩では肩甲骨が前傾し、可動域が狭くなって筋肉や腱板が骨にこすれやすくなり、摩耗や断裂のリスクが高まります。
正しい姿勢を保ち肩甲骨を適正位置に維持すれば、摩擦と負荷の軽減が可能です。また、日常生活やスポーツでは腕の使い方も見直し、腕を高く上げすぎたり同じ姿勢を長時間続けることを避けます。重い物を持つ際は腕だけでなく体全体を使い、肩関節の安定性を保つことが腱板損傷の予防につながります。
オーバーユース回避
| 予防ポイント | 理由 |
|---|---|
| 肩の使いすぎの回避 | 繰り返し動作による腱板への微細損傷の蓄積 |
| 適切な休息の確保 | 腱板の自然修復を促すための負荷軽減 |
| 正しいフォーム・作業姿勢の習得 | 肩関節への不要なストレスの軽減 |
| 負担の分散 | 肩のみで行わず、体幹や下半身も活用 |
| 痛みや違和感時の使用中止 | 傷の進行防止 |
腱板断裂は、肩の筋肉と骨をつなぐ腱板が損傷する疾患です。野球やテニスなどのスポーツや重い物を扱う仕事で肩を繰り返し酷使すると、腱板に小さな損傷が蓄積します。腱板は血流が乏しく修復力が弱いため、休息を取らずに使い続けると回復が追いつかず、摩耗や断裂が進行します。
予防には、肩の使用を適度に制限して休養を確保し、動作や姿勢を見直して負担を軽減することが重要です。また、体の他の部位を活用して負担を分散し、痛みや違和感があれば早めに使用を中止することが推奨されます。これらの対策によって、腱板断裂の発症や悪化を防ぐことができます。
以下の記事では、腱板断裂(腱板損傷)でやってはいけないことを詳しく解説しています。
生活管理と違和感への早期対応
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 肩への過度な負担回避 | 重労働やスポーツでの繰り返し負荷を避け、肩の筋力・柔軟性を維持 |
| 早期受診の重要性 | 違和感や動作制限を感じた段階で専門医を受診し画像検査で診断 |
| 進行予防による負担軽減 | 症状の進行抑制による手術回避や機能障害予防 |
| 全身状態の改善 | 血糖値管理や禁煙による腱の健康維持 |
| 無理な使用の回避 | 違和感がある場合の安静による損傷拡大防止 |
腱板断裂を予防するには、日常生活で肩への負担を減らし、症状への早期対応を徹底することが重要です。重労働やスポーツでの反復動作、無理な姿勢や動作は腱板損傷のリスクを高めます。
普段から肩周囲の筋力と柔軟性を保ち、過度な使用を避けることが予防の基本です。肩に違和感や動きの制限を感じた場合は、症状が軽くても早めに医療機関を受診し、MRIや超音波検査によって診断を受けます。
早期に保存療法やリハビリを開始すれば断裂の進行を防ぎ、手術を回避できる可能性が高まります。また、糖尿病や喫煙(文献2)は腱の健康を損なうため、生活習慣の改善も重要です。違和感がある時は無理な動作を控え、安静を保つことが損傷拡大の防止につながります。
以下の記事では、腱板断裂(損傷)における超音波(エコー)検査について詳しく解説しています。
腱板断裂と似ている症状
| 似ている症状 | 詳細 |
|---|---|
| 肩関節の炎症・拘縮(五十肩・肩関節周囲炎・石灰沈着性腱板炎) | 肩関節周囲の炎症や拘縮による痛みと可動域制限。腕が上がりづらく動作時の痛みやこわばりが特徴 |
| 関節や骨の変性(変形性肩関節症・インピンジメント症候群) | 肩関節の軟骨や骨の変性による運動時の痛み、インピンジメントは腱板が骨に挟まることで生じる痛み |
| 腱や周囲組織の障害(上腕二頭筋長頭腱炎) | 上腕二頭筋の腱の炎症で、肩の前方の疼痛や動作時痛、押すと痛みが出ることが多い |
| 首からくる症状(頚椎症性神経根症など) | 首の神経圧迫に伴う放散痛やしびれ、腕の筋力低下、肩の動かしにくさ。首の動作で症状が誘発されることも |
腱板断裂と症状が似ている疾患はいくつか存在します。肩関節の炎症や拘縮を伴う五十肩(肩関節周囲炎)や石灰沈着性腱板炎では、肩の強い痛みや可動域の制限、腕の上げにくさ、こわばりが見られます。変形性肩関節症やインピンジメント症候群では、軟骨や骨の変性や腱板の挟み込みによって動作時の痛みが生じます。
上腕二頭筋長頭腱炎は、肩の前方に限局した痛みや押したときの圧痛、動作時痛が特徴です。さらに、頚椎症性神経根症など首からくる症状では、肩から腕にかけての放散痛やしびれ、筋力低下があり、首の動きで症状が誘発されることもあります。これらは腱板断裂と症状が似ているため、正確な診断には医師による診察と画像検査が欠かせません。
肩関節の炎症・拘縮(五十肩(肩関節周囲炎)・石灰沈着性腱板炎)
| 項目 | 腱板断裂 | 五十肩(肩関節周囲炎) | 石灰沈着性腱板炎 |
|---|---|---|---|
| 主な症状 | 肩の痛み、可動域制限、日常動作の困難、夜間痛 | 慢性的な痛み・力が入りにくい | 肩全体の広い痛みと動きの硬さと急な激痛や腫れ |
| 原因 | 腱板腱の断裂 | 肩関節周囲の炎症と拘縮 | 腱板へのカルシウム沈着 |
| 痛みの特徴 | 特定動作や夜間で強く出やすい | 夜間痛が強く、徐々に拘縮へ進行 | 発作的な強い痛みと寛解期 |
| 可動域制限 | 外転・外旋がとくに制限 | 全方向で強く制限 | 発作時は動かしにくい |
| 経過 | 自然治癒は稀で、放置すると悪化しやすい | 数年で自然回復傾向 | 数日〜数週間の発作後軽快しやすい |
| 主な治療 | 保存療法または手術 | 保存療法主体 | 薬物・注射・石灰除去(手術は稀) |
| 主な共通症状 | 肩の痛み、可動域制限、日常動作の困難、夜間痛 | ||
腱板断裂、五十肩(肩関節周囲炎)、石灰沈着性腱板炎はいずれも肩の痛みと可動域制限を伴いますが、原因や経過が異なります。五十肩は関節全体の炎症と拘縮により全方向の動きが制限され、数年かけて自然回復することが多い疾患です。
腱板断裂は肩の腱が部分的または完全に切れ、特定動作で力が入らず自然治癒はほぼありません。石灰沈着性腱板炎は腱板にカルシウムが沈着し、急激な激痛発作を起こしますが多くは自然軽快します。症状が似ていても治療法は異なるため、正確な診断には医師による診察とMRIや超音波検査が重要です。
以下の記事では、五十肩(肩関節周囲炎)と石灰沈着性腱板炎の症状について詳しく解説しています。
【関連記事】
石灰沈着性腱板炎の原因とは?症状や痛みが続く際の治療法を紹介
関節や骨の変性(変形性肩関節症・インピンジメント症候群)
| 項目 | 腱板断裂 | 変形性肩関節症 | インピンジメント症候群 |
|---|---|---|---|
| 主な症状 | 肩の痛み、可動域制限、日常動作の困難、夜間痛 (途中で力が入らないことも) | 肩の痛み、可動域制限、関節変形、慢性痛 | 肩の痛み、特定動作や挙上で強まる痛み、可動域制限 |
| 原因 | 腱板腱の断裂 | 長年の摩耗や軟部組織損傷で関節軟骨のすり減り・骨変形 | 腱板の摩擦や圧迫 |
| 症状の特徴 | 肩から腕にかけて広がる・断裂部周辺 | 関節内部が中心、動作時や負荷時に増す痛み | 肩前面、動作中に鋭い痛み |
| 可動域制限 | 外転・外旋などに強く制限 | 全方向で強く制限 | 特定動作(挙上など)で制限 |
| 経過 | 保存療法で経過観察も多い | 進行性で慢性化しやすい | 保存療法で多くが改善傾向がある |
| 主な治療 | 保存療法または手術 | 保存療法中心だが症状で手術選択 | 保存療法、重症時は手術 |
| 主な共通症状 | 肩の痛み、可動域制限、日常動作の困難、夜間痛 | ||
腱板断裂と関節や骨の変性によって起こる疾患(変形性肩関節症やインピンジメント症候群)は、どちらも肩の痛みや動かしにくさを伴い、症状が似ているため混同されやすい疾患です。
腱板断裂は肩の腱が部分的または完全に切れて特定動作で力が入らず、夜間痛が出やすいのが特徴です。変形性肩関節症は軟骨の摩耗や骨変形で肩全体の動きが制限され、進行すると関節音を伴います。
インピンジメント症候群は腕を上げる際に腱板が骨に挟まれ炎症を起こし、特定の角度で痛みや引っかかり感が生じます。原因と治療は異なり、腱板断裂は保存療法や手術、変形性肩関節症は保存療法を基本に進行例で人工関節手術、インピンジメント症候群は保存療法が中心です。診断にはMRIやレントゲンなどの画像検査と専門医の診察が必要です。
以下の記事では、インピンジメント症候群について詳しく解説しています。
腱や周囲組織の障害(上腕二頭筋長頭腱炎)
| 項目 | 腱板断裂 | 上腕二頭筋長頭腱炎 |
|---|---|---|
| 主な症状 | 肩の痛み、可動域制限、日常動作の困難、夜間痛 | 肩前面の痛み、可動域制限、日常動作の困難、夜間痛 |
| 原因 | 腱板腱(棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋)の断裂 | 上腕二頭筋長頭腱の摩擦や炎症 |
| 症状の特徴 | 特定動作で力が入らない、肩の上・外側の痛み | 肩前面、結節間溝付近の痛みや圧痛 |
| 可動域制限 | 外転・外旋の制限 | 肘の曲げや前腕の回内外で痛み増強 |
| 経過 | 自然治癒しにくく進行することあり | 安静や保存療法で多くは改善 |
| 主な治療 | 保存療法または手術療法 | 保存療法(安静、薬物、リハビリ) |
| 合併の可能性 | 発症により上腕二頭筋長頭腱炎を伴うことあり | 腱板断裂を伴うことあり |
| 主な共通症状 | 40歳以上の中高年に多い傾向、動作時や夜間に強まる肩前面や周囲の痛み、動かしにくさや筋力低下、スポーツや肉体労働による肩の反復使用による負担 | |
腱板断裂と上腕二頭筋長頭腱炎は肩の痛みや動きの制限を引き起こしますが、原因や特徴に違いがあります。共通点として、肩の痛みや筋力低下、とくに40歳以上に多く、スポーツや肉体労働がリスク要因です。
腱板断裂はインナーマッスルの腱が断裂し、外転や外旋で痛みが生じます。一方、上腕二頭筋長頭腱炎は炎症により腕を曲げる動作で痛みが生じます。診断にはMRIや超音波検査が使用され、症状がひどい場合は手術が必要です。治療法としては、保存療法と手術が選択肢となります。
以下の記事では、腱や周囲組織の障害について詳しく解説しています。
【関連記事】
腱板損傷と断裂の違いは?症状の進行や治療法について現役医師が解説
首からくる症状(頚椎症性神経根症など)
| 項目 | 腱板断裂 | 頚椎症性神経根症 |
|---|---|---|
| 主な症状 | 肩や腕の痛みやしびれ、動かしにくさや筋力低下、夜間痛 | 肩の痛み、とくに動作時の痛みと可動域制限、夜間痛 首から肩・腕・手にかけての痛みやしびれ、感覚鈍麻、筋力低下 |
| 原因 | 肩の腱板(棘上筋など)の部分または完全断裂 | 頚椎や椎間板の変性による神経根の圧迫 |
| 症状の特徴 | 腕を特定角度まで上げると痛みや力が入らなくなる(ドロップアーム) | 首の動きや姿勢で悪化する放散痛・しびれ、片側の筋力低下 |
| 痛みの範囲 | 肩関節周囲の局所痛、動作に伴う痛み | 首から肩・腕・手・指先までの放散痛やしびれ |
| 可動域制限 | 特定の肩の動きで強く制限 | 首の動きで痛み増悪、上肢の動作制限 |
| 診断方法 | 肩のMRIや超音波検査で腱板の損傷確認 | 頚椎X線・MRIで変性や神経圧迫を確認 |
| 主な治療 | 保存療法(安静・薬物・リハビリ)、必要に応じ手術療法 | 薬物療法、神経根ブロック、まれに手術 |
| 主な共通症状 | 肩や腕の痛みやしびれ、動かしにくさや筋力低下、夜間痛 | |
腱板断裂と頚椎症性神経根症は、肩や腕の痛みやしびれを引き起こしますが、原因や症状に違いがあります。共通点として、肩や腕の痛み、筋力低下、とくに夜間痛が見られ、腱板断裂は肩のインナーマッスルの腱が切れ、特定の動作で痛みが強くなります。
頚椎症性神経根症は首の骨の変形による神経圧迫で痛みやしびれが広がり、頚椎のX線・MRIで確認し、早期に医師の診察を受けることが重要です。
以下の記事では、頚椎症性神経根症について詳しく解説しています。
腱板断裂でお悩みなら当院へご相談ください
腱板断裂は、加齢やスポーツ、肉体労働により腱板が損傷または断裂し、肩の痛みや腕が上がらない原因となります。適切な治療を継続することで改善が期待できますが、症状が改善しない場合は手術が必要となることもあります。
腱板断裂の症状にお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。当院では、腱板断裂で損傷した組織の回復を促す治療法である再生医療を提案しています。再生医療は、手術に比べてリスクが少なく、断裂部分に直接アプローチできる治療法として近年注目されています。
ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。
\無料オンライン診断実施中!/
参考文献