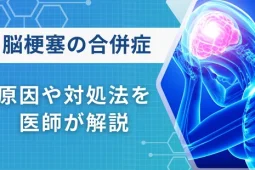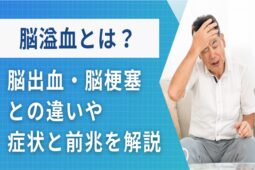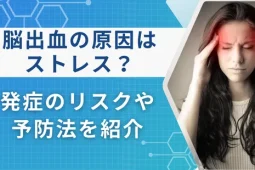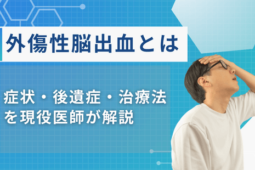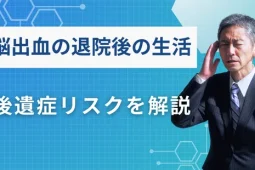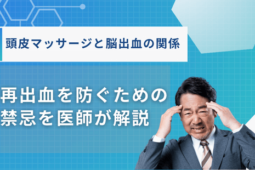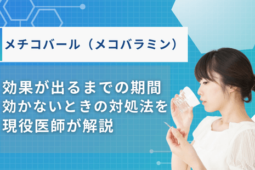- 脳卒中
- 頭部
- 脳出血
【医師監修】脳出血とは|症状・種類・原因を詳しく解説
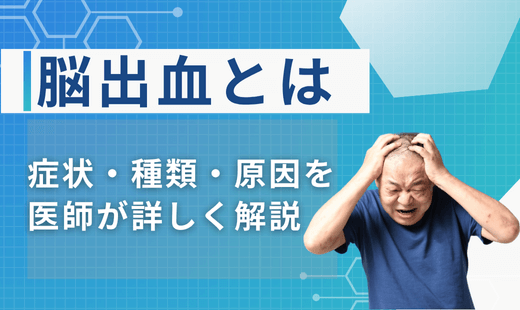
「ある日突然、激しい頭痛や吐き気に襲われた」
「片側が麻痺するような感覚や、言葉がうまく話せない」
これらは脳出血のサインの可能性が高く、脳の血管が破れて出血し、脳細胞を損傷・死滅させる疾患です。短時間で命や生活に重大な影響を及ぼします。
飲酒や喫煙、高血圧、糖尿病といった生活習慣や持病があれば、若年でも脳出血を発症する危険があります。脳出血は年齢を問わず起こるため、予防が欠かせません。
本記事では、脳出血について現役医師が詳しく解説します。
- 脳出血の症状
- 脳出血の種類
- 脳出血の原因
- 脳出血の治療法
- 脳出血の予防法
記事の最後には、脳出血についてよくある質問をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。
脳出血について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。
脳出血とは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な原因 | 長期間続く高血圧による血管の脆弱化。加齢による脳アミロイド血管症。脳動静脈奇形などの血管異常 |
| 他の脳卒中との違い | 脳出血は脳卒中の一種で、脳実質内の出血を指し、くも膜下出血(脳表面の隙間の出血)や脳梗塞(血管の詰まり)とは異なる |
| 出血で起きること | 血腫形成による脳細胞の圧迫。麻痺・言語障害・意識障害の発症。部位と出血量による症状の違い。血腫吸収後も残る神経障害の可能性 |
| 早期治療の理由 | 発症後48時間以内に進行する脳浮腫。再出血や脳圧上昇による生命危機。血圧管理・外科的処置・全身管理の必要性 |
| 主な症状 | 片側の麻痺・しびれ。言語障害。意識障害。吐き気・嘔吐。激しい頭痛 |
| 対応の重要性 | 急性期の対応が予後を左右。再出血や浮腫悪化時は緊急処置の必要性 |
| 予防と再発防止 | 高血圧管理。生活習慣改善。血管異常の検査。医師による定期的なフォロー |
(文献1)
脳出血は、脳内の細い血管が破れて出血し、血液が脳組織を直接傷つけたり、血腫(けっしゅ)となって周囲を圧迫し、脳組織を損傷する疾患です。意識障害、手足の麻痺、言語障害などの重い症状が突然現れることがあります。
脳の血管は非常に細く、高血圧などで慢性的な負担がかかると血管壁が脆くなり、破れやすくなります。出血は脳全体の圧力を高めて血流を妨げ、生命に関わる危険な状態を引き起こし得ます。急な頭痛、意識の変化、麻痺などが現れた場合は、一刻を争うため直ちに救急要請が必要です。
以下の記事では、脳梗塞と脳出血の合併症について詳しく解説しています。
脳出血の症状
| 症状 | 詳細 |
|---|---|
| 片麻痺・顔面のゆがみ | 手足の力が入らなくなる現象。顔半分の筋肉のゆがみ。片側だけ口角が下がる状態 |
| 言語障害(話す・理解) | 思ったことを言葉にできない状態。会話や文字の理解困難。意思疎通の困難 |
| 視覚・平衡感覚の異常 | 視野が欠ける現象。一部が見えなくなる状態。物が二重に見える現象。ふらつきや歩行困難 |
| 頭痛・吐き気・意識障害 | 突然の激しい頭痛。吐き気や嘔吐の発現。意識がもうろうとする状態。反応が鈍くなる現象 |
脳出血では、出血の部位や程度により多様な症状が突然現れます。代表的なのは片麻痺や顔面のゆがみで、口角が片方だけ下がることもあります。
言葉が出にくい、相手の話や文字が理解しづらいといった言語障害に加え、視野の一部が欠ける、物が二重に見えるなどの視覚異常や、平衡感覚の異常によるふらつき・歩行困難も特徴です。
さらに、突然の激しい頭痛、吐き気や嘔吐、意識の混濁、反応の鈍化などが起こることもあり、これらの症状が現れた場合は直ちに医療機関を受診する必要があります。
以下の記事では、脳出血の前兆を詳しく解説しています。
片麻痺・顔面のゆがみ
| 症状 | 詳細 |
|---|---|
| 片麻痺(かたまひ) | 脳の片側が出血で障害されると、反対側の手足の動きが悪くなる現象。力が入らない、動かせない、物を落としやすくなる状態 |
| 顔面のゆがみ | 顔の筋肉を動かす神経が障害され、片側の筋肉がうまく動かなくなる状態。笑ったときに口角が片側だけ下がる、まぶたが閉じにくい左右差 |
| 重要性 | いずれも脳出血の可能性が高い危険なサインで、突然出た場合は直ちに救急車を呼び医療機関を受診する必要性 |
脳出血が運動をつかさどる脳の部分に起こると、身体の片側が急に動かしにくくなり、腕や足に力が入らず物を落とすこともあります。
顔面神経にも障害が及ぶと、笑ったときに口角が一方だけ下がる、まぶたが閉じにくいなどの左右差が出ます。発症した場合は直ちに救急車を呼ぶことが重要です。
以下の記事では、脳出血の前兆として現れる手足のしびれについて詳しく解説しています。
【関連記事】
手足のしびれの原因となる病気の症状や予防法を解説!前兆も紹介
言語障害(話す・理解)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 言葉が話せなくなる理由 | 脳の左側にある言語中枢の出血による機能障害 |
| 主な症状 | 思ったことを言葉にできない発語障害。相手の言葉の意味がわからない理解障害 |
| 危険なサインの理由 | 脳の重要領域の障害を示す重大な兆候で、早急な治療が必要 |
| 対応の必要性 | 突然の発語困難や理解困難が出た場合は、脳出血や脳梗塞の可能性があり直ちに受診が必要 |
脳の言語中枢が出血で損なわれると、言葉を話す・理解する機能に障害が生じ、言葉が出ない、入れ替わる、理解しづらいなどの症状が現れます。口や舌の動きが悪くなり発音が不明瞭になることもあり、失語症や構音障害と呼ばれます。
これらは本人が気づきにくく、周囲の早期発見が重要です。突然の発症は脳出血の可能性が高く、速やかに医療機関を受診する必要があります。
視覚・平衡感覚の異常
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 視覚の異常 | 脳の後頭葉や視覚信号の経路への障害による視野狭窄や見えにくさ。目そのものの異常ではなく、脳の視覚処理の問題 |
| 平衡感覚の異常 | 小脳や脳幹の損傷による急なめまい、ふらつき、歩行時のバランス障害、方向感覚の喪失 |
| 重要性 | 突然の視覚や平衡感覚の異常は脳への深刻な障害のサインであり、緊急受診が必要 |
脳の視覚中枢や平衡感覚をつかさどる部位に出血が起こると、視界が欠ける、二重に見える、ふらつくなどの症状が現れます。歩行が不安定になり、立ち上がった際に倒れそうになることもあります。
視覚障害やめまいは一時的に治まる場合もありますが、脳出血は進行する恐れがあるため、軽視は禁物です。とくに、これまでにない視覚の異常やバランスの崩れは、早急な診断が必要な危険信号です。
頭痛・吐き気・意識障害
| 症状 | 詳細 |
|---|---|
| 激しい頭痛 | 脳の血管破裂による脳を覆う膜や血管への強い刺激。普段と異なる突然の強烈な痛み |
| 吐き気・嘔吐 | 脳圧の上昇による脳幹の嘔吐中枢刺激。身体からの危険信号としての反応 |
| 意識障害 | 血液や腫れによる脳の重要部位圧迫、意識がぼんやりする状態、重症の場合は意識消失の可能性 |
脳出血によって脳内の出血が増えると、頭蓋内の圧力が急激に上昇し、強い頭痛・吐き気・嘔吐などが起こります。これは、硬い頭蓋骨の中で血液が増えて脳が圧迫されるためです。
出血範囲が広くなると脳幹や全体へのむくみ(脳浮腫)により、意識がもうろうとしたり呼びかけに反応できなくなることもあり、命に関わる緊急事態となります。このような症状が急に現れた場合には、一刻も早く救急車を呼び、迅速な治療を受けることが非常に重要です。
以下の記事では、吐き気を伴う頭痛について詳しく解説しています。
脳出血の種類
| 種類 | 詳細 |
|---|---|
| 被殻出血 | 大脳基底核の一部である被殻での出血。主に高血圧が原因。反対側の手足の麻痺や感覚障害、言語障害が起こることが多い |
| 視床出血 | 感覚情報の中継を行う視床での出血。反対側の感覚障害や麻痺、意識障害を伴うことが多い |
| 皮質下出血 | 脳の表面近く、皮質直下の白質での出血。一部運動障害や感覚障害、視覚や言語の障害が現れる場合がある |
| 小脳出血 | 運動のバランスを司る小脳での出血。めまいや歩行困難、吐き気などが強く現れることが多い |
| 橋出血 | 生命維持に重要な脳幹の一部である橋での出血。四肢麻痺や重度の意識障害、呼吸不全など重篤な症状が出やすい |
脳出血は、出血する部位によって症状や重症度が異なります。被殻出血は、大脳深部の被殻に起こる脳出血で、高血圧が原因となることが多い病態です。視床出血は感覚の中継を行う視床で発生し、片側の感覚障害や麻痺、意識障害を伴うことが多くあります。
皮質下出血は脳の皮質下白質で起こり、運動・感覚・視覚・言語など多様な障害を引き起こす可能性があります。小脳出血はバランス機能を担う小脳で発生し、めまいや歩行困難、吐き気が顕著に現れることがあります。橋出血は脳幹の一部である橋で発症し、四肢麻痺や重度の意識障害、呼吸不全など重篤な症状を引き起こしやすく、とくに注意が必要です。
被殻出血
被殻出血は、脳の深部にある被殻で起こる脳出血で、手足の動きや感覚に関わる重要な部位が障害されます。脳出血のうち、約40~50%は被殻出血であり、脳出血全体の中で最も多くを占めています。被殻は脳の深部に位置し、手足の運動や感覚をつかさどる重要な部位です。
このため、被殻で出血が起こると、反対側の手足の麻痺やしびれが現れます。多くは高血圧が背景にあり、発症は急激です。言葉のもつれや視野の欠けを伴うこともあります。
さらに重症化すると意識障害に進行することがあるため、早期の診断と適切な血圧管理が不可欠です。日本国内の統計でも、視床出血(約30%)、小脳・脳幹・皮質下出血(いずれも約10%前後)と比べて圧倒的に頻度が高いことが示されています
視床出血
視床出血は、脳の深部にある視床で起こる出血です。視床は、手足や顔の感覚情報を脳の各部に中継し、意識の維持にも関わる重要な部位です。主な原因は長期の高血圧による細い血管(穿通枝)の破裂で、突然の頭痛、嘔吐、意識の低下、片側の手足のしびれや麻痺といった症状が急に現れます。
視床出血は感覚・運動・意識・眼球運動など多彩な症状を伴い、視覚異常や瞳孔反応の変化、言語障害、高次脳機能障害、慢性的な強い痛み(視床痛)が現れ、出血が大きい場合は運動障害が悪化します。
治療は血圧や脳の腫れを抑える保存療法が中心で、早期診断とリハビリが回復が重要です。
以下の記事では、視床出血について詳しく解説しています。
【関連記事】
手足のしびれの原因となる病気の症状や予防法を解説!前兆も紹介
【保存版】視床出血の主な症状はなに?原因や治療法・予後について現役医師が解説
皮質下出血
皮質下出血は、脳の表面に近い大脳皮質の直下で起こる脳出血です。高血圧が原因となることは少なく、若年者では脳動静脈奇形や海綿状血管腫、高齢者ではアミロイドアンギオパチーなどの血管異常が多くみられます。
症状は突然の激しい頭痛や吐き気、嘔吐に始まり、意識障害、片側の手足の麻痺、言語障害、てんかん発作などが出ます。数時間以内に症状が進行することもあり、予後は出血の大きさや原因に左右されます。
診断はCTなどで行い、大きな出血や重症例では手術が検討されますが、多くは薬物療法や経過観察が中心です。早期受診と原因に応じた治療が不可欠です。
小脳出血
小脳出血は、頭の後ろにある小脳で起こる脳出血です。小脳は体のバランスや運動の調整を担い、出血すると後頭部の激しい痛み、強いめまいやふらつき、吐き気、歩行障害、構音障害などが現れ、急速に悪化することがあります。
原因は高血圧が最も多く、血管奇形や頭部外傷も関与します。出血が大きいと脳幹を圧迫し命に関わるため、治療は血圧管理や脳浮腫の抑制が中心であり、必要に応じて手術が必要です。早期受診と適切な治療が予後を左右します。
橋出血
橋出血は、脳幹の一部である「橋」に発生する脳出血です。橋は呼吸や心拍の調整、感覚や運動の伝達など、生命維持に欠かせない機能を担っています。主な原因は長期の高血圧で、血管壁が弱くなり破れることで発症します。血管奇形や外傷、血液疾患が原因となるケースもあります。
症状は急速に進行し、激しい頭痛や嘔吐、意識障害、四肢麻痺、顔面のしびれや運動障害、呼吸困難、言語障害、めまい、眼球運動異常などが現れ、橋は重要な神経が集中する部位のため重症化しやすく、手術が困難な場合も多くあります。
治療は血圧や呼吸の管理が中心で、早期発見と迅速な対応が予後を左右するため、発症時は直ちに医療機関での治療が必要です。
以下の記事では、橋出血について詳しく解説しています。
【関連記事】
橋出血とは?症状・原因・治療法を現役医師がわかりやすく解説!
橋出血の初期症状は意外と身近な痛み?!死亡率や予防法も現役医師が解説
脳幹出血は回復の見込みある?治療や時期別のリハビリ内容も解説
脳出血の原因
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 高血圧性出血 | 持続する高血圧による脳内小動脈の血管壁破綻。血圧の過度な上昇による血管の破裂 |
| 血管異常(奇形・アミロイド) | 先天的な脳動静脈奇形や海綿状血管腫などの血管奇形。高齢者に多いアミロイド血管症による血管の脆弱化 |
| 薬剤・出血傾向を伴う血液の病気 | 抗凝固薬や抗血小板薬の服用による出血傾向。血液疾患による止血障害や血液成分異常 |
| 脳梗塞からの出血性転化 | 脳梗塞後に血管の浸食や血流再開で出血を伴うこと。脳組織の壊死に血管破綻が加わる状態 |
| 頭部の外傷 | 交通事故や転倒などの頭部への直接的な強い衝撃による脳内出血。とくに高齢者で転倒リスクが高い |
脳出血の原因は多岐にわたります。中でも代表的なのは、持続する高血圧による脳内小動脈の破綻です。ほかにも、先天的な脳動静脈奇形や海綿状血管腫、高齢者に多いアミロイド血管症などの血管異常、抗凝固薬・抗血小板薬の服用や血液疾患による出血傾向、脳梗塞後の血管破綻による出血性転化、交通事故や転倒といった頭部外傷などがあります。
これらの要因は脳の重要な部位に急激な出血を引き起こし、命に関わる重篤な症状へとつながる可能性があります。突然の頭痛、麻痺、言語障害、意識の変化などの症状が出た場合は、脳出血の可能性があるため直ちに医療機関を受診することが重要です。
高血圧性出血
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 血圧の慢性的上昇 | 小さな脳血管の壁への持続的な負担。血管壁の弾力低下と脆弱化 |
| 微小動脈瘤の形成 | 弱った血管にできる小さなコブ。血管の一部が膨らみ、破裂リスクの増加 |
| 急激な血圧上昇 | 強いストレスや激しい運動、寒冷刺激による急な負担。もろい血管の破裂誘発 |
| 高血圧症の頻度 | 多くの人が持つ慢性疾患。目立たないうちに脳血管障害の進行 |
| 脳出血の発症機序 | 血管壁の脆弱化と微小動脈瘤の破裂による脳出血 |
| 予防のポイント | 血圧の治療・生活習慣改善による脳血管の保護。血圧管理の重要性 |
脳出血は、脳内の細い血管が破れて血液がたまり、脳を圧迫する病気です。そのうち約6割から9割は高血圧が原因とされています。
慢性的に高血圧が続くと脳の細い動脈が硬く脆くなり、血圧が急に上がったときに破れやすくなります。とくに寒暖差、過度の飲酒、強いストレスは発症のきっかけになります。高血圧性出血は脳出血全体の多くを占めるため、日頃から血圧を適切に管理することが最も重要な予防策です。
血管異常(奇形・アミロイド)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 血管奇形の種類 | 脳動静脈奇形や海綿状血管腫などの先天性または後天性の血管構造異常 |
| アミロイド血管症 | 高齢者の脳血管壁にアミロイド蛋白が沈着し脆弱化する状態 |
| 出血のきっかけ | 弱くなった血管の血圧変動や外的刺激による破裂 |
| 若年者での特徴 | 高血圧がなくても血管奇形が原因で発症する脳出血 |
| 高齢者での特徴 | アミロイド血管症が原因となる脳出血 |
| 重要性 | 高血圧以外の独立した脳出血原因としての臨床的意義 |
血管異常には、若年層にも見られる脳動静脈奇形や海綿状血管腫などの血管奇形と、高齢者に多いアミロイド血管症があります。血管奇形は生まれつき構造が弱く、血圧の急変や軽い刺激でも破れやすく、若年層の脳出血の原因です。
アミロイド血管症は血管壁に異常なたんぱく質が沈着し、もろくなった血管から出血を招きます。これらは高血圧の有無に関係なく発症しやすく、とくに若年層と高齢者の脳出血で重要な原因です。
予防には、定期的な健康診断や脳ドックで早期発見し、生活習慣を改善することが重要です。海綿状血管腫は無症状のことも多いため、症状が現れたら速やかに受診することが、命を守り再出血や重症化を防ぎます。
異常血管と診断された場合は、専門医による経過観察や必要に応じた治療が推奨されます。脳出血は突然発症し、対応の遅れが命や後遺症に直結するため、少しでも異変を感じたら直ちに受診することが大切です。
薬剤・出血傾向を伴う血液の病気
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 出血傾向の仕組み | 血液凝固機能の低下による止血力の低下 |
| 薬剤による影響 | 抗凝固薬(ワルファリン・DOACなど)や抗血小板薬(アスピリンなど)による血液凝固抑制 |
| 薬剤の目的 | 血栓予防のための血のかたまり形成抑制 |
| 薬剤の副作用 | 脳内の細い血管からの出血リスク上昇 |
| 血液の病気による影響 | 血小板減少や凝固異常による全身的な出血しやすさ |
| 高血圧性出血との違い | 血管壁の脆弱化ではなく、血液そのものの止血不全 |
| 注意点 | 定期的な検査と医師の指示遵守による出血リスク管理 |
抗凝固薬(ワルファリン・DOACなど)や抗血小板薬(アスピリンなど)は、血液の凝固を抑えることで血栓予防に有効です。しかし、これらの薬剤は脳内の細い血管からの出血リスクを高める可能性があります。
また、血友病や白血病などの血液疾患では、血小板減少や凝固機能の異常により全身で出血しやすくなります。これらのケースにおける脳出血は、血管壁の脆弱化ではなく、止血機能の低下によって発症する点が特徴です。服薬中または血液疾患の既往がある方は、定期的な血液検査や診察を受け、医師の指示を厳守することが重要です。
脳梗塞からの出血性転化
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 出血性転化とは | 脳梗塞で詰まった血管が再び開通した際、損傷した血管や脳組織から血液が漏れ出す状態 |
| 原因となる仕組み | 血流遮断による血管壁・脳組織の脆弱化と、再開通による血流再流入 |
| リスクを高める要因 | 広範囲の脳梗塞、高血糖、抗血栓薬の使用 |
| 起こりやすい時期 | 脳梗塞発症後の治療中や経過観察期間 |
| 主な影響 | 脳圧上昇や脳損傷の拡大による症状の急激な悪化 |
| 予防・対策の重要性 | 出血性転化リスクの管理、早期発見と適切な治療 |
出血性転化とは、脳梗塞で詰まった血管が再び開いた際に、損傷した血管や脳組織から血液が漏れ、脳出血を起こす状態です。脳梗塞では、血流が途絶えた部分の脳細胞が酸素や栄養を失い壊死します。
長時間の血流不足により血管壁や脳組織は脆くなり、治療や自然回復で血流が戻ると出血が発生しやすくなります。梗塞範囲が広い場合や高血糖、抗血栓薬の使用はリスクを高めます。出血が起こると脳の圧迫や損傷が加わり、症状が急激に悪化するため、治療中や経過観察中は早期発見と慎重な管理が欠かせません。
以下の記事では、脳梗塞の症状について詳しく解説しています。
頭部の外傷
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 原因 | 交通事故、転倒、スポーツ中の衝突などによる頭部への強い衝撃 |
| 発症の仕組み | 脳の内部や周囲の血管損傷による出血 |
| 主な種類 | 脳内出血、硬膜外血腫、硬膜下血腫 |
| 症状 | 意識障害、手足の麻痺、言語障害、激しい頭痛、嘔吐 |
| 症状発現の特徴 | 外傷直後または数時間〜数日後の症状悪化 |
| 検査方法 | CTやMRIによる画像検査 |
| 治療方法 | 薬物療法、外科的血腫除去術 |
| 受診の重要性 | 頭部を強打した際の早期受診による重症化予防 |
頭部に強い衝撃が加わると、脳の血管が損傷し、脳内やその周囲で出血(外傷性脳出血)が起こることがあります。主な原因は交通事故、転倒、スポーツ中の衝突などです。出血部位によっては、脳内出血、硬膜外血腫、硬膜下血腫などに分類されます。
血液が脳を圧迫すると、意識障害、手足の麻痺、言語障害、激しい頭痛や嘔吐などの症状が現れます。発症は受傷直後とは限らず、数時間から数日後に出ることもあります。
とくに高齢者や抗凝固薬を服用している方は、軽い衝撃でも出血の危険があるため、頭を打った場合は症状がなくても早急に医療機関で検査を受けることが重要です。治療は血腫の大きさや症状に応じて薬物療法または手術が行われ、早期診断と治療が予後を左右します。
以下の記事では、頭部の外傷で発症する外傷性脳出血について詳しく解説します。
脳出血の治療法
| 治療法 | 詳細 |
|---|---|
| 保存療法 | 出血の広がり抑制と状態の安定化。血圧管理や脳圧コントロール |
| 薬物療法 | 降圧剤による血圧低下。脳浮腫を軽減する薬剤の使用 |
| リハビリテーション | 運動機能や言語機能の回復訓練。日常生活動作(ADL)の自立支援 |
| 手術療法 | 血腫除去や圧迫軽減のための開頭手術、内視鏡下血腫除去術 |
| 再生医療 | 脳組織の再生促進を目指す先進治療。臨床応用段階の研究・実施 |
脳出血の治療は、出血の規模や症状、患者様の全身状態に応じて選択されます。軽症時は安静と血圧管理を行い、必要に応じて薬物で脳浮腫や血圧を調整します。麻痺や言語障害があれば早期にリハビリを開始します。
血腫が大きい場合や脳を強く圧迫している場合は、手術での除去が必要です。また、再生医療は損傷した脳組織の機能回復を目指す新しい選択肢です。ただし、治療法によっては合併症や再出血のリスクもあるため、必ず医師の判断のもと適切な方法を選ぶことが大切です。
保存療法
| 項目 | 詳細 |
| 血圧管理(降圧療法) | 降圧薬による血圧コントロール。収縮期140mmHg未満または平均血圧130mmHg未満の維持 |
| 脳浮腫の抑制 | 浸透圧利尿薬(高張グリセロール・マンニトール)による脳圧の低下維持 |
| 全身管理と合併症予防 | 酸素投与や循環管理による低酸素・低血圧予防。感染対策や深部静脈血栓症予防 |
| 栄養・水分補給と休養確保 | 点滴や経管栄養による栄養・水分補給と十分な安静の確保 |
(文献2)
保存療法は、脳出血のうち出血量が少なく、脳や神経への圧迫が軽度な場合に選択される治療法です。全身状態が手術に耐えられない患者や高齢者、出血部位が深く手術が困難な症例にも適用されます。治療は安静を保ち、血圧を適切に管理することが基本です。
具体的には収縮期140mmHg未満、または平均血圧130mmHg未満を目標とします。(文献2)
降圧薬により再出血や細小血管への負担を軽減し、脳浮腫がみられる場合は高張グリセロールやマンニトールなどの浸透圧利尿薬を用いて脳圧を低下させます。点滴や経管栄養で水分・栄養を補給し、感染症や深部静脈血栓症の予防も並行して行います。
定期的な画像検査で経過を確認し、出血の自然吸収を促す、侵襲性が低くリスクの少ない治療法として、多くの患者にとって有力な選択肢です。
薬物療法
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 血圧の管理 | 降圧剤(カルシウム拮抗薬・硝酸薬など)による血圧コントロール |
| 止血剤の投与 | トラネキサム酸等の止血剤による出血拡大の防止 |
| 脳浮腫の抑制 | マンニトールや高張グリセロールによる脳内のむくみ軽減 |
| 抗凝固薬中和の対応 | ワルファリンやDOACの効果を中和する薬剤の投与 |
| 合併症の予防 | 発作や感染症などの予防薬の使用 |
薬物療法は、脳出血治療において重要な役割を果たします。主な目的は、血圧の適切なコントロールと脳浮腫(脳の腫れ)の軽減です。降圧薬を用いて血圧を安定させることで再出血のリスクを低減し、さらにグリセロール(高張グリセロール液)などの脳圧降下薬で脳圧の上昇を抑えます。
また、けいれん発作の恐れがある場合には、抗てんかん薬を予防的に使用します。薬物療法は、手術が困難な症例や軽症例で有効です。症状の悪化防止と全身状態の安定化に寄与します。加えて、継続的な血圧管理や合併症予防の観点からも欠かせない治療手段です。
リハビリテーション
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 理学療法 | 筋力回復、バランス改善、歩行訓練による身体機能の向上 |
| 作業療法 | 食事、着替え、排泄など日常生活動作の練習による生活自立支援 |
| 言語療法 | 発話・理解能力や嚥下機能の改善訓練によるコミュニケーション能力向上 |
| 認知療法 | 記憶力、注意力など脳の働きの改善訓練 |
脳出血の回復には、発症後できるだけ早い時期(通常24〜48時間以内)からのリハビリ開始が重要です。早期にリハビリを行うことで、運動機能や日常生活能力(ADL)の回復が促されます。
これは脳の神経可塑性を刺激し、新たな神経回路の再構築を助けるためです。リハビリは寝返りや起き上がり、座位保持などの基礎動作から始まり、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が連携して段階的に進めます。継続訓練により、運動機能、言語機能、嚥下機能を改善し、日常生活の自立と社会復帰を支援します。
手術療法
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 手術の目的 | 血腫除去による脳圧の軽減と脳損傷の予防 |
| 有効な理由 | 脳の圧迫解消による症状の悪化防止 |
| 適応となる状況 | 大量出血、急激な脳圧上昇、小脳出血による脳幹圧迫、一定以上の血腫での意識障害 |
| 期待される効果 | 意識障害や麻痺の進行防止と生命予後の改善 |
| 重要性 | 早期血腫除去による生命救助と回復促進 |
脳出血の手術療法は、血腫が大きく脳を強く圧迫している場合や、意識障害を伴い生命に危険が及ぶ場合に行われます。目的は、血腫を除去して脳の圧迫を軽減し、脳損傷の進行を防ぐことです。
主な方法には、頭蓋骨を約10cm開けて直接血腫を取り除く開頭血腫除去術、頭蓋骨に約1.5cmの小孔を開けて内視鏡で吸引・除去する内視鏡的血腫除去術、髄液の流れが障害され水頭症を起こした場合に管で体外へ排出する脳室ドレナージがあります。
手術方法の選択は、出血部位や量、全身状態を基に脳神経外科医が慎重に判断します。血腫除去後も、再出血予防のための血圧管理、脳浮腫対策、リハビリテーションなどの継続的治療が不可欠です。
再生医療
再生医療は、脳出血で損傷した脳細胞や血管を幹細胞で修復し、後遺症の改善や再発予防を目指す治療法です。
患者自身の骨髄・脂肪・歯髄から採取した幹細胞を体外で増殖させ、注射などで損傷部位に戻すことで、神経や血管の再生や炎症の抑制が期待されます。これにより、麻痺・言語障害・しびれなどの症状軽減が見込まれます。
リハビリテーションと併用することで効果が高まる可能性があり、早期の開始が望ましいとされています。
当院「リペアセルクリニック」では脳出血に対する再生医療の症例を紹介しているので、ぜひご確認ください。
脳出血の予防法
| 予防法 | 詳細 |
|---|---|
| 血圧・生活・嗜好の改善 | 塩分控えめの食事、適度な運動、禁煙、節度ある飲酒、ストレス管理 |
| 慢性疾患・薬剤使用の見直し | 高血圧や糖尿病、脂質異常症の適切な管理。医師による薬剤調整や定期検査 |
| 若年・再発時の血管精密検査 | 血管奇形やアミロイド血管症などの精密検査。再発リスクの評価と対策 |
脳出血の予防には、まず血圧管理を含めた生活習慣の改善が重要です。塩分を控えた食事、適度な運動、禁煙、節度ある飲酒、ストレスの軽減は血管への負担を減らします。高血圧、糖尿病、脂質異常症といった慢性疾患は、医師の指導のもと適切に管理し、薬剤の調整や定期検査を行います。
若年発症や再発例では、血管奇形やアミロイド血管症などを早期に発見するための精密検査を実施し、再発リスクを評価・対策します。こうした予防法を行っても改善が見られない場合や、体調に不安がある場合は、早めに医療機関を受診し、医師の診断と治療を受けることが大切です。
以下の記事では、脳出血の再発率と再発防止につながる行動を詳しく解説しています。
血圧・生活・嗜好の改善
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 高血圧管理 | 定期的な血圧測定と医師の指示に従った治療。薬物療法と生活習慣管理の継続 |
| 減塩と食事の見直し | 塩分摂取量の制限。バランスの良い食事内容への改善 |
| 適度な運動 | 毎日のウォーキングや週150分以上の有酸素運動の継続 |
| 禁煙・節酒 | タバコ・過度な飲酒の制限。血管への負担軽 |
| ストレス管理 | 十分な休養や趣味時間の確保。心身のリフレッシュ |
| 体重管理・糖尿病コントロール | 適正体重の維持と糖尿病・生活習慣病の管理 |
脳出血の最大の原因は高血圧であり、日頃からの血圧管理が不可欠です。塩分を控えたバランスの良い食事や適度な運動を心がけ、喫煙や過度な飲酒は避けましょう。これらの習慣は血管への負担を減らし、脳出血のリスク低下につながります。
規則正しい生活やストレスの軽減も血圧安定に有効です。とくに脳出血の既往がある方は、より厳格な血圧管理(130/80mmHg未満を目安)が推奨されます。継続した血圧管理と生活改善により、再発や新たな発症を防ぎやすくなります。
以下の記事では、高血圧の予防について詳しく解説しています。
慢性疾患・薬剤使用の見直し
脳出血のリスクは、高血圧に加え、糖尿病、脂質異常症、心疾患、腎疾患、血液疾患などの慢性疾患によっても高まります。これらは血管を脆弱にし、発症を招きやすくするため、継続的な管理が不可欠です。
抗凝固薬や抗血小板薬などの一部の治療薬は、管理が不十分だと出血リスクを増やす可能性があるため、定期的な診察や血液検査で病状と薬剤の効果・副作用を確認し、必要に応じて治療を見直すことが重要です。
薬剤の中止や変更は必ず医師・薬剤師と相談し、自己判断は避けましょう。生活習慣の改善と薬剤管理を含む慢性疾患の適切なコントロールが、脳血管の健康維持と脳出血予防につながります。
若年・再発時の血管精密検査
| 検査名 | 詳細 |
|---|---|
| MRI/MRA(磁気共鳴画像検査・血管造影検査) | 脳の組織や血管の状態確認。血管の狭窄、動脈瘤、血管奇形の有無を評価 |
| 頸動脈超音波検査(エコー) | 首の動脈の血流測定と動脈硬化の評価。脳への血流状態の確認 |
| 血管造影検査(必要に応じて) | カテーテルと造影剤による詳細な血管形状の評価。治療計画立案の補助 |
脳出血は高齢者に多く発症しますが、若年での発症や再発が疑われる場合には、脳動静脈奇形(AVM)や未破裂脳動脈瘤などの血管構造異常が隠れていることがあります。これらを放置すると再出血の危険性が高まるため、早期発見と症状の管理、必要に応じた外科的治療が重要です。
再発時には初回と異なる原因や血管の変化が生じている可能性があり、再評価としての精密検査が有効です。血管の詳細な状態を把握することで、発症リスクを正確に評価し、適切な治療や予防策を講じることができます。若年発症や再発例では、再発予防のため脳血管の精密検査が推奨されます。
脳出血が疑われる方は早急に医療機関を受診しよう
脳出血は時間の経過とともに脳への損傷が広がり、命や生活に深刻な影響を及ぼす危険性が高まります。
片側の手足が急に動かしにくい、言葉が出にくい、視界の一部が欠ける、強い頭の違和感や吐き気がある場合は、症状が軽くても急速に進行する可能性があるため、自己判断せずに迷わず救急要請してください。早期の診断と治療開始が後遺症を減らすために重要です。
脳出血の症状が改善しない、後遺症にお悩みの方は当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。当院では、脳出血による後遺症に直接アプローチできる再生医療を、治療の選択肢のひとつとしてご提案しています。
また当院では、現在も後遺症や症状でお困りの方の思いや生活上の不安に耳を傾けながら、状況に合わせた治療計画を一緒に考えてまいります。
ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。
\無料オンライン診断実施中!/
脳出血に関するよくある質問
脳出血の後遺症にはどのような症状があるのでしょうか?
脳出血後には、半身の麻痺や手足のしびれといった運動・感覚障害、言葉が出にくくなる失語や構音障害、記憶力や注意力の低下などの認知機能障害、嚥下障害、視野欠損や視力低下などの視覚障害がみられることがあります。
これらの症状は出血部位や範囲によって異なりますが、多くの場合、急性期から1年後もなんらかの後遺症が出るケースもあります。ただし、適切なリハビリテーションや継続的な医療支援によって、症状が改善する可能性も十分にあります。
以下の記事では、脳出血の後遺症について詳しく解説しています。
脳出血は若い人も発症する病気ですか?
若年層(18〜49歳)でも脳出血は発症する可能性があり、実際にこの年代が脳出血全体の約30%を占めるとの報告があります。(文献3)
日本における45歳未満の年間発症率は、平均で人口10万人あたり52.4人(95%信頼区間:35.7~69.2)とされ、高齢者に比べると頻度は低いものの、若年層でも発症が報告されています。(文献4)
発症の背景には、高血圧や血管異常、外傷、薬剤使用などがあり、とくに血管奇形や遺伝的要因は若年層における重要な原因とされています。
脳出血の入院期間はどのくらいですか?
一般的な入院期間の目安は以下のとおりですが、これはあくまで統計上の平均であり、実際の期間は年齢、症状の程度、合併症の有無、離床の進み具合などによって大きく異なります。厚生労働省の統計では、平均入院期間は77.4日と報告されています。(文献5)
以下の記事では、脳出血の入院期間について詳しく解説しています。
脳出血の退院後の生活は?
脳出血の再発予防には、毎日の血圧測定と降圧薬の適切な服用、減塩・栄養バランスの取れた食事、禁煙、節酒、適度な運動、規則正しい生活によるストレス軽減が重要です。
さらに、定期通院やリハビリを継続し、自宅でも訓練を行いながら症状の変化を医師に報告し、転倒防止のための住環境整備や介助者との連携を行うことで、再発リスクを減らし生活の質を保てます。
以下の記事では、脳出血の退院後の生活について詳しく解説しています。
脳出血の既往歴がありますが頭皮マッサージを受けても大丈夫でしょうか?
脳出血の既往がある方が頭皮マッサージを受ける際は、発症直後の急性期(24〜48時間以内)は再出血の危険が高いため、強い圧迫や刺激を避ける必要があります。
血圧が安定していても過度な力は脳や血管に負担をかけるため、優しい力加減で行うことが重要です。発熱、頭痛、めまいなど体調不良がある場合は施術を控え、施術前には医師に相談してください。
施術中に違和感や不調を感じたら直ちに中止し、医師の許可と適切な力加減のもとで強い刺激は避けましょう。
以下の記事では、頭皮マッサージと脳出血の関係性について詳しく解説しています。
家族が脳出血になってしまったときにできることはありますか?
脳出血からの回復には、ご家族の適切な支援が欠かせません。病気や治療内容、予想される後遺症を正しく理解し、リハビリ、日常生活の介助を行いましょう。精神的な寄り添いや励ましは、患者さんの意欲を高める重要な要素です。
介護保険や各種福祉サービスを活用して負担を軽減し、ご家族自身の健康管理にも配慮が必要です。医療スタッフと情報を共有しながら、患者さんとともに回復への道を歩んでいくことが大切です。
以下の記事では、脳出血後の介護ケアについて詳しく解説しています。
参考文献
脳卒中患者に対する発症後48 時間以内の起立と定義した早期離床導入の効果|J-STAGE
Epidemiology of intracerebral hemorrhage: A systematic review and meta-analysis|frontiers